第23回目 午前2時のアレクシア・エコーズ
プロフィール

名前
アレクシア・エコーズ
愛称
アレクシア
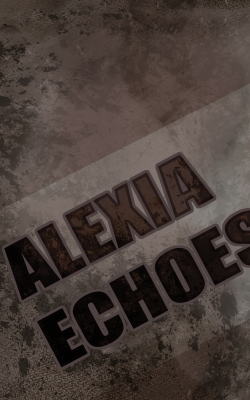 |  |
| 経歴 赤毛の女。 本職は技師。 平和主義。 感情が乗らない抑揚の乏しい声。 最近、男を拾った。 祝福と、傷跡。 機体名『サイレント・リップルス』。 ウミネコを模したグレムリン。 *プロフ絵はへたのさんから頂きました。 | |
僚機プロフィール

名前
コール=ターナー
愛称
コール
 | 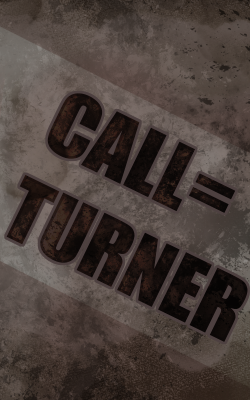 |
| 経歴 半身機械。 オートメイション。 拾われ。 グレムリンテイマー。 未来。 ※アイコン、プロフ絵はへたの先生に描いて貰いましあた!!!滅茶苦茶カッコいい!!!!!!【僚機詳細】 | |
◆日誌
いつかの未来。どこかの世界。
度重なる戦乱が遺した爪痕は深かった。
けれど、それでも人々は生き、世界は続いている。
そういうことだった。
カランカラン、とドアベルが鳴る。
「いらっしゃいませ。お一人様ですか?」
「後から友達が来るんですけど、先に入ってても大丈夫ですか?」
「大丈夫ですよ。空いてるとこならどこでも」
静かの海のとある小島に、そのコーヒーショップ『海月』はあった。
店員にしては愛想の乏しい赤毛の女――アレクシアが、客の少女に店の奥を示す。大きな窓から、透き通った海が見えている。
「おすすめはテラスですね」
「じゃあそこで!」
「メニューお持ちしますね。ごゆっくりどうぞ」
見晴らしを気に入ったらしい少女は、長い銀髪を揺らしてテラス席まで歩いていった。
店員の女は、キッチンカウンターでグラスにお冷を注ぎながら、奥にいるコールに声を掛ける。
「お客さん一人。後からもう一人来るって」
「わかった」
「二人ともパフェじゃないかなあ」
若い女性がここに来る理由の大半はパフェだ。経験則から当たりを付けて、アレクシアはそう言った。
一方でコールは、首を捻る。
「パフェか。ここはパフェ屋ではないんだが」
「パフェのが映えるからなー。まあ売上も出るし……」
最近流行りのSNS、Rustagramは『海月』ももちろん運用している。客商売において宣伝は重要だ。
開設当初から暫し、鳴かず飛ばずの状態だったが、先日の投稿――コール考案、秋の新作パフェ――が、ピグマリオン・マウソレウム所属のアイドルに紹介され、"バズった"。静かの海という、グレムリンの補給所くらいしかない僻地にあるため客が殺到することはなかったが、最近はじわじわと客足が伸びている。店の売り上げだけで暮らしていけそうな目途も立ちつつあり、たまに請け負っているグレムリンテイマーとしてのバイトも必要なくなりそうだ。
バズりが一過性ではない、と思える理由もあった。
「あと、おいしいし」
うちのパフェは見た目だけではなく、味も良い。それはアレクシアも、にこにこしながら徹底的にコールに料理を叩き込んだシリヤも、太鼓判を押すところだ。
コールは深く頷いた。
「確かにパフェはうまい」
「じゃ、よろしく」
「了解した、雇い主さん」
コールの呼び方は相変わらずだ。しかもそれが、今は本当なのだから、笑えるような、笑えないような心地になる。
『海月』の経営者はアレクシアだ。アッシュラッツを潰した際にアレクシアの、いわゆる"過払金"をどさくさ紛れでそれ以上にふんだくったカイルの手柄と言えよう。そのお陰でこの店はオープンできていて、カイルには永年コーヒー無料券が進呈されている。
ステンレスのトレイにメニュー、クラゲ型のコースターとお冷を載せて、アレクシアは厨房から出た。
カランカラン、とドアベルが新たな来客を告げる。
「いらっしゃいませ」
いつかの未来。どこかの世界。
今日も『海月』は営業中だ。
度重なる戦乱が遺した爪痕は深かった。
けれど、それでも人々は生き、世界は続いている。
そういうことだった。
カランカラン、とドアベルが鳴る。
「いらっしゃいませ。お一人様ですか?」
「後から友達が来るんですけど、先に入ってても大丈夫ですか?」
「大丈夫ですよ。空いてるとこならどこでも」
静かの海のとある小島に、そのコーヒーショップ『海月』はあった。
店員にしては愛想の乏しい赤毛の女――アレクシアが、客の少女に店の奥を示す。大きな窓から、透き通った海が見えている。
「おすすめはテラスですね」
「じゃあそこで!」
「メニューお持ちしますね。ごゆっくりどうぞ」
見晴らしを気に入ったらしい少女は、長い銀髪を揺らしてテラス席まで歩いていった。
店員の女は、キッチンカウンターでグラスにお冷を注ぎながら、奥にいるコールに声を掛ける。
「お客さん一人。後からもう一人来るって」
「わかった」
「二人ともパフェじゃないかなあ」
若い女性がここに来る理由の大半はパフェだ。経験則から当たりを付けて、アレクシアはそう言った。
一方でコールは、首を捻る。
「パフェか。ここはパフェ屋ではないんだが」
「パフェのが映えるからなー。まあ売上も出るし……」
最近流行りのSNS、Rustagramは『海月』ももちろん運用している。客商売において宣伝は重要だ。
開設当初から暫し、鳴かず飛ばずの状態だったが、先日の投稿――コール考案、秋の新作パフェ――が、ピグマリオン・マウソレウム所属のアイドルに紹介され、"バズった"。静かの海という、グレムリンの補給所くらいしかない僻地にあるため客が殺到することはなかったが、最近はじわじわと客足が伸びている。店の売り上げだけで暮らしていけそうな目途も立ちつつあり、たまに請け負っているグレムリンテイマーとしてのバイトも必要なくなりそうだ。
バズりが一過性ではない、と思える理由もあった。
「あと、おいしいし」
うちのパフェは見た目だけではなく、味も良い。それはアレクシアも、にこにこしながら徹底的にコールに料理を叩き込んだシリヤも、太鼓判を押すところだ。
コールは深く頷いた。
「確かにパフェはうまい」
「じゃ、よろしく」
「了解した、雇い主さん」
コールの呼び方は相変わらずだ。しかもそれが、今は本当なのだから、笑えるような、笑えないような心地になる。
『海月』の経営者はアレクシアだ。アッシュラッツを潰した際にアレクシアの、いわゆる"過払金"をどさくさ紛れでそれ以上にふんだくったカイルの手柄と言えよう。そのお陰でこの店はオープンできていて、カイルには永年コーヒー無料券が進呈されている。
ステンレスのトレイにメニュー、クラゲ型のコースターとお冷を載せて、アレクシアは厨房から出た。
カランカラン、とドアベルが新たな来客を告げる。
「いらっしゃいませ」
いつかの未来。どこかの世界。
今日も『海月』は営業中だ。
◆23回更新の日記ログ
未識別機動体の侵攻と『ベルーガ』の深刻な人材不足により、エンジニアからテイマーへの暫定的鞍替えが決まったアレクシアは、「せめて10日は時間が欲しい」と頑として主張した。いきなり乗って戦えと言われても無理だ、コロッセオ・レガシィには適当に誤魔化せ、こちらの戦力と未識別機動体の情報が錯綜している中で出撃するなんて無謀すぎる、など。
声を荒げるようなことはなかったにせよ、逆にアレクシアの淡々とした、主張を譲る気は一切ないという態度にさすがのカイルも折れて――正確には、見兼ねた他の乗組員に一丸となって説得された結果――要望通りの猶予が与えられた。
10日は、機体と心の準備をするには短い時間だった。侵攻を防ぐには長すぎる期間だが、そんなのは知ったことではない。こちらはこれから命を張るのだ。多少は都合を振り回したっていいだろう。
テイマーに任命された翌々日。アレクシアは乗ることとなったグレムリン――『サイレント・リップルス』の試運転も兼ね、タワー港湾部の廃工場が連なる区画に来ていた。
この廃工場群は、数日前まではグレムリンの整備やパーツ生産工場として稼働していたものだ。未識別機動体の侵攻によって、今はこのザマである。
何だっけ。諸行無常? そんな単語が思い浮かんだ。レーダーで探知しながら、アレクシアは廃工場を進む。
プリセットされていた『サイレント・リップルス』は攻撃的な小型逆関節機体だったが、アレクシアはサポート型の機体に変えることを決めていた。できるだけ命のリスクを負いたくないからだ。
そのアセンブルをするには、あと一つレーダーが欲しい。『ベルーガ』にあるパーツでは規格が合わなかったため、こうして探しにきている。機能停止したグレムリンや工場からパーツを拝借しようという算段で、経費削減もできる一石二鳥の方法と言えた。ついでに、使えそうなパーツがあればバラして持ち帰り、小遣いにしても良い――主目的はどちらかというとそれである。
しかし、皆考えることは同じなのか目ぼしい収穫がない。そもそも、アレクシアの見立て以上にここは破壊が尽くされていた。
これ以上の探索は無駄だ。瓦礫の山も見飽きたことだし、見切りをつけて帰ろうとした時――レーダーにグレムリンの反応を捉えた。
「えー……と、こっちかな、と」
確認しながら、レバーを引く。こんな調子で大丈夫か? と思う反面、『サイレント・リップルス』はアレクシアの言うことを素直に聞いた。
辿り着いたのは、半壊した廃工場だ。
大きな穴が空いたトタン屋根から、日が射している。その先に、ほとんどスクラップ状態のグレムリンがあった。
屋根を突き抜けて落ちてきたのか。そう思いながら、アレクシアは『サイレント・リップルス』をボロボロのグレムリンに寄せた。
レーダーを見る。生体反応なし。グレムリンが動く気配もなし。
動いてないならゴミと一緒だ。つまり拾った物勝ちである。『サイレント・リップルス』のアームは、大きな粗大ゴミの操縦棺をこじ開けた。
「……はあ?」
アレクシアは怪訝な声を上げた。
棺の中に、男がいた。
銀髪の男。目は閉じられていて、動かない。死んでる? いや、そんな風には見えない。何なら今、微かに身じろいだ。気絶しているのか? 確かに生体反応はなかったはずなのに、なんで?
もう一度、レーダーでスキャンを行う。生体反応なし。結果は変わらなくて、アレクシアは眉を顰める。
取れる方法はいくつかあった。
一つ目、見なかったことにすること。
二つ目、この男を操縦棺から放り出してグレムリンだけ回収すること。
……仮に死んでいたとしても、それはなんだか寝覚めが悪くなるような気がした。
三つ目、この男ごとグレムリンを回収して、手当てをすること。
アレクシアは狭い操縦棺の中で無理やり足を組んで、ヘッドレストに頭を預けた。
「……めんどくさー……」
気怠げな呟き。
それから、溜息。
体勢を直し、アレクシアはレバーを引いた。
かくして、彼と彼女は"また"出会う。
アレクシア・エコーズが拾ったコール=ターナーをなし崩し的に修理をして、借金返済のため僚機として戦場に出ることになるのは、ほんの少し先の話だ。
声を荒げるようなことはなかったにせよ、逆にアレクシアの淡々とした、主張を譲る気は一切ないという態度にさすがのカイルも折れて――正確には、見兼ねた他の乗組員に一丸となって説得された結果――要望通りの猶予が与えられた。
10日は、機体と心の準備をするには短い時間だった。侵攻を防ぐには長すぎる期間だが、そんなのは知ったことではない。こちらはこれから命を張るのだ。多少は都合を振り回したっていいだろう。
テイマーに任命された翌々日。アレクシアは乗ることとなったグレムリン――『サイレント・リップルス』の試運転も兼ね、タワー港湾部の廃工場が連なる区画に来ていた。
この廃工場群は、数日前まではグレムリンの整備やパーツ生産工場として稼働していたものだ。未識別機動体の侵攻によって、今はこのザマである。
何だっけ。諸行無常? そんな単語が思い浮かんだ。レーダーで探知しながら、アレクシアは廃工場を進む。
プリセットされていた『サイレント・リップルス』は攻撃的な小型逆関節機体だったが、アレクシアはサポート型の機体に変えることを決めていた。できるだけ命のリスクを負いたくないからだ。
そのアセンブルをするには、あと一つレーダーが欲しい。『ベルーガ』にあるパーツでは規格が合わなかったため、こうして探しにきている。機能停止したグレムリンや工場からパーツを拝借しようという算段で、経費削減もできる一石二鳥の方法と言えた。ついでに、使えそうなパーツがあればバラして持ち帰り、小遣いにしても良い――主目的はどちらかというとそれである。
しかし、皆考えることは同じなのか目ぼしい収穫がない。そもそも、アレクシアの見立て以上にここは破壊が尽くされていた。
これ以上の探索は無駄だ。瓦礫の山も見飽きたことだし、見切りをつけて帰ろうとした時――レーダーにグレムリンの反応を捉えた。
「えー……と、こっちかな、と」
確認しながら、レバーを引く。こんな調子で大丈夫か? と思う反面、『サイレント・リップルス』はアレクシアの言うことを素直に聞いた。
辿り着いたのは、半壊した廃工場だ。
大きな穴が空いたトタン屋根から、日が射している。その先に、ほとんどスクラップ状態のグレムリンがあった。
屋根を突き抜けて落ちてきたのか。そう思いながら、アレクシアは『サイレント・リップルス』をボロボロのグレムリンに寄せた。
レーダーを見る。生体反応なし。グレムリンが動く気配もなし。
動いてないならゴミと一緒だ。つまり拾った物勝ちである。『サイレント・リップルス』のアームは、大きな粗大ゴミの操縦棺をこじ開けた。
「……はあ?」
アレクシアは怪訝な声を上げた。
棺の中に、男がいた。
銀髪の男。目は閉じられていて、動かない。死んでる? いや、そんな風には見えない。何なら今、微かに身じろいだ。気絶しているのか? 確かに生体反応はなかったはずなのに、なんで?
もう一度、レーダーでスキャンを行う。生体反応なし。結果は変わらなくて、アレクシアは眉を顰める。
取れる方法はいくつかあった。
一つ目、見なかったことにすること。
二つ目、この男を操縦棺から放り出してグレムリンだけ回収すること。
……仮に死んでいたとしても、それはなんだか寝覚めが悪くなるような気がした。
三つ目、この男ごとグレムリンを回収して、手当てをすること。
アレクシアは狭い操縦棺の中で無理やり足を組んで、ヘッドレストに頭を預けた。
「……めんどくさー……」
気怠げな呟き。
それから、溜息。
体勢を直し、アレクシアはレバーを引いた。
かくして、彼と彼女は"また"出会う。
アレクシア・エコーズが拾ったコール=ターナーをなし崩し的に修理をして、借金返済のため僚機として戦場に出ることになるのは、ほんの少し先の話だ。
◆22回更新の日記ログ
最後の戦いになるのだろう。
それがこの零錆戦線のものか、"この世界"のものか、虚空領域のものかは分からない。
すべてはタワーでの戦いに懸かっている。
『サイレント・リップルス』と『クレオソート』は数多くのグレムリンと同様に、タワー内部に侵入していた。
全世界を巻き込んだこの事態だ。コロッセオ・レガシィ、ひいては『ベルーガ』が持つタワー防衛の役割も、優先順位において勝らなかった。
「つっても、お前は何かと理由を付けて行かないと思ってたんだがなあ」
「そのつもりだったんですけど」
アレクシアが作戦への参加を決めた時、カイルは意外そうに言った。
彼女自身もそうだ。自分がこの作戦に参加するとは思いもしなかった。きっと、今までだったら興味を示してない。
この世界は積極的に守るべきものではなかった。少なくとも、アレクシアにとっては。グレムリンテイマーになったのもどこまでも不可抗力であり、何なら今でも辞めたい。
けれども。この状況下において、アレクシアはグレムリンを動かせる、数少ない人間の一人だった。
そして今、この世界が亡くなることを、惜しく感じている。
「……まあ、やれることはやっておこうかと」
だからアレクシアは、タワーに行く。
正義感や義務感でもなく、この世界が続いてほしい思う、自分の勝手のために。
「死ぬんじゃねえぞ。エンジニア兼テイマー兼スカウトマン兼渉外担当に抜けられちゃ困る」
「しれっと仕事増やすの止めてください。お金貯まったら出ていくんで」
「ツレねえなァ」
「……クソブラック艦ですけど、多少の感謝はしてますよ」
「そりゃ何よりだ」
がはは、とカイルは豪快に笑っていた。
目的地は――決戦は近い。『サイレント・リップルス』は何の問題もなく、タワーを駆け登っている。
もしかしたら、話すのも最後になるのかもしれない、とふと思った。
操縦棺の中、アレクシアは『クレオソート』への通信チャネルを開いた。
「世界が終わるとか停まるとか、御大層なことになったもんだよね」
相変わらず気だるげに、あくまで雑談の態で。
辛気臭い会話をするつもりはなかった。そういうのはもう、いいかな、と思っている。
「あのグレムリンを破壊すればいいんだろうけど」
『間違いない』
スピーカーからの声は、コールがいつものように神妙な顔で頷いているのを想像させる。相変わらず生真面目な男だ。
やることは、いつもと変わらないと言えば変わらない、という訳だ。
アレクシアは話を続ける。
「そもそもさ。この世界は何度も繰り返してるとか言うじゃない。それ、コールくんは信じてる?」
『特に信じてはいない。繰り返す世界には面白みを感じない』
「私も信じてないけど」
この世界は、滅びの直前で何度もループしているらしい。といってもアレクシアにはその実感がなく、眉唾物――だった。今から倒しに行こうとしているグレムリンの、不可思議な力を見るまでは。
全てを停められるなら、世界をループさせることもグレムリンにはできるのかもしれない。
「繰り返し、やり直しってわけじゃん。今までのことがなかったことになるわけでしょ? 最悪だ」
『確かに最悪だ』
そうなると、アレクシアの懸念は"やり直し"だった。
せっかく、自由になれたのに――色んな人のお陰で。
だから世界の繰り返しについて、今は信じていないというより、信じたくなかった。
ザザ、とスピーカーの音が揺れる。
『クレオソート』から返答。
『だが、そうなった場合はまた同じように自由になるだけだ。そんなに気にすることはない』
「……そ、っか」
惚けたような表情を、一瞬。
当然のように彼は言った。
はは、とおかしそうにアレクシアは笑う。
「そうね。うん。その通りだ」
その感覚は不意に訪れた。
同じ言葉を、いつかの昔に聞いたことがある。
「じゃ、まあ……"次"があったら、またよろしく」
やっぱりループしてるのかな、世界。
なんかムカつくな。
でも、いいか。
何とかなるでしょ、きっと。
一人じゃないみたいだしさ。
アレクシアは、タワー上層目掛けて『サイレント・リップルス』を走らせた。
それがこの零錆戦線のものか、"この世界"のものか、虚空領域のものかは分からない。
すべてはタワーでの戦いに懸かっている。
『サイレント・リップルス』と『クレオソート』は数多くのグレムリンと同様に、タワー内部に侵入していた。
全世界を巻き込んだこの事態だ。コロッセオ・レガシィ、ひいては『ベルーガ』が持つタワー防衛の役割も、優先順位において勝らなかった。
「つっても、お前は何かと理由を付けて行かないと思ってたんだがなあ」
「そのつもりだったんですけど」
アレクシアが作戦への参加を決めた時、カイルは意外そうに言った。
彼女自身もそうだ。自分がこの作戦に参加するとは思いもしなかった。きっと、今までだったら興味を示してない。
この世界は積極的に守るべきものではなかった。少なくとも、アレクシアにとっては。グレムリンテイマーになったのもどこまでも不可抗力であり、何なら今でも辞めたい。
けれども。この状況下において、アレクシアはグレムリンを動かせる、数少ない人間の一人だった。
そして今、この世界が亡くなることを、惜しく感じている。
「……まあ、やれることはやっておこうかと」
だからアレクシアは、タワーに行く。
正義感や義務感でもなく、この世界が続いてほしい思う、自分の勝手のために。
「死ぬんじゃねえぞ。エンジニア兼テイマー兼スカウトマン兼渉外担当に抜けられちゃ困る」
「しれっと仕事増やすの止めてください。お金貯まったら出ていくんで」
「ツレねえなァ」
「……クソブラック艦ですけど、多少の感謝はしてますよ」
「そりゃ何よりだ」
がはは、とカイルは豪快に笑っていた。
目的地は――決戦は近い。『サイレント・リップルス』は何の問題もなく、タワーを駆け登っている。
もしかしたら、話すのも最後になるのかもしれない、とふと思った。
操縦棺の中、アレクシアは『クレオソート』への通信チャネルを開いた。
「世界が終わるとか停まるとか、御大層なことになったもんだよね」
相変わらず気だるげに、あくまで雑談の態で。
辛気臭い会話をするつもりはなかった。そういうのはもう、いいかな、と思っている。
「あのグレムリンを破壊すればいいんだろうけど」
『間違いない』
スピーカーからの声は、コールがいつものように神妙な顔で頷いているのを想像させる。相変わらず生真面目な男だ。
やることは、いつもと変わらないと言えば変わらない、という訳だ。
アレクシアは話を続ける。
「そもそもさ。この世界は何度も繰り返してるとか言うじゃない。それ、コールくんは信じてる?」
『特に信じてはいない。繰り返す世界には面白みを感じない』
「私も信じてないけど」
この世界は、滅びの直前で何度もループしているらしい。といってもアレクシアにはその実感がなく、眉唾物――だった。今から倒しに行こうとしているグレムリンの、不可思議な力を見るまでは。
全てを停められるなら、世界をループさせることもグレムリンにはできるのかもしれない。
「繰り返し、やり直しってわけじゃん。今までのことがなかったことになるわけでしょ? 最悪だ」
『確かに最悪だ』
そうなると、アレクシアの懸念は"やり直し"だった。
せっかく、自由になれたのに――色んな人のお陰で。
だから世界の繰り返しについて、今は信じていないというより、信じたくなかった。
ザザ、とスピーカーの音が揺れる。
『クレオソート』から返答。
『だが、そうなった場合はまた同じように自由になるだけだ。そんなに気にすることはない』
「……そ、っか」
惚けたような表情を、一瞬。
当然のように彼は言った。
はは、とおかしそうにアレクシアは笑う。
「そうね。うん。その通りだ」
その感覚は不意に訪れた。
同じ言葉を、いつかの昔に聞いたことがある。
「じゃ、まあ……"次"があったら、またよろしく」
やっぱりループしてるのかな、世界。
なんかムカつくな。
でも、いいか。
何とかなるでしょ、きっと。
一人じゃないみたいだしさ。
アレクシアは、タワー上層目掛けて『サイレント・リップルス』を走らせた。
◆21回更新の日記ログ
その未識別グレムリン――いや、『トゥルー・ブルー』を見た時に思ったのは、ああ、セラは本当に死んじゃったんだな、だった。
表示された索敵情報はその思いを確信に変えた。生体反応、なし。
通信チャネルから聞こえる声は、懐かしいそれ。けれど、壊れたラジオのように同じことをずっと繰り返していた。
アレクシアはセラフィンの死体を見たわけではない。彼が乗っていた『トゥルー・ブルー』は錆の海に沈んでそのまま見つからなかった、と聞いている。実際、それは間違いないだろうし――セラフィンが生きていると思ったことはなかった。
生きているなら、きっと彼は私のことを置いていかない。
"幽霊"との遭遇は、その死に確かな実感を与えただけだった。
本当に、本当に死んじゃったんだな。
セラ。セラフィン。ごめんね。私と会ったばっかりに。本当にごめん。
でも私、あなたに会えてよかった。あなたのお陰で人になれた。
あなたの分までちゃんと生きるよ。
青い空だって、きっといつか見てみせるから。
だから、ごめんね。ありがとう。
さよなら。
照準を合わせる。間違いのないように。
私の手で送らせて。
弾丸がひとつ。
戦場に静けさが戻った。
表示された索敵情報はその思いを確信に変えた。生体反応、なし。
通信チャネルから聞こえる声は、懐かしいそれ。けれど、壊れたラジオのように同じことをずっと繰り返していた。
アレクシアはセラフィンの死体を見たわけではない。彼が乗っていた『トゥルー・ブルー』は錆の海に沈んでそのまま見つからなかった、と聞いている。実際、それは間違いないだろうし――セラフィンが生きていると思ったことはなかった。
生きているなら、きっと彼は私のことを置いていかない。
"幽霊"との遭遇は、その死に確かな実感を与えただけだった。
本当に、本当に死んじゃったんだな。
セラ。セラフィン。ごめんね。私と会ったばっかりに。本当にごめん。
でも私、あなたに会えてよかった。あなたのお陰で人になれた。
あなたの分までちゃんと生きるよ。
青い空だって、きっといつか見てみせるから。
だから、ごめんね。ありがとう。
さよなら。
照準を合わせる。間違いのないように。
私の手で送らせて。
弾丸がひとつ。
戦場に静けさが戻った。
◆20回更新の日記ログ
*今回の日誌*
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/6d2fd124-6d4b-4beb-bc4c-67ffe10d757a/e0cde4ab45fa0ce4aed7c67afa0c1686
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/6d2fd124-6d4b-4beb-bc4c-67ffe10d757a/e0cde4ab45fa0ce4aed7c67afa0c1686
◆19回更新の日記ログ
*今回の日誌*
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/e09d562d-f68c-4c8b-9abd-2cd7713369da/e7ce47f54c84f38ada1230d70e4b4edb
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/e09d562d-f68c-4c8b-9abd-2cd7713369da/e7ce47f54c84f38ada1230d70e4b4edb
◆18回更新の日記ログ
*今回の日誌*
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/c7ebfff9-680d-4884-b5fe-d6873f9b2009/14aa85cc662666ed8293bcec22e59b8d
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/c7ebfff9-680d-4884-b5fe-d6873f9b2009/14aa85cc662666ed8293bcec22e59b8d
◆17回更新の日記ログ
*今回の日誌*
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/8992300f-2f56-4a9f-9bf6-c2b666a00e22/137bc07abc1f0a7a2ef92636b564f94b
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/8992300f-2f56-4a9f-9bf6-c2b666a00e22/137bc07abc1f0a7a2ef92636b564f94b
◆16回更新の日記ログ
「で、本部行きを阻止するって、何か案とかあるの」
「とりあえず破壊しよう」
「破壊」
「破壊は得意だ」
「……その調子でコーヒーショップなんて大丈夫?」
「コーヒーショップはコーヒー豆を破壊する仕事だろう」
「そうかなあ……」
破壊する、と言いながらコーヒー豆を挽くコールを想像してみる。どう考えても繁盛しなさそうな店だ。
現実問題として、"破壊"は選択肢に挙がらないわけではない。グレムリンという力が、アレクシアとコールにはある。
しかし、何をどう破壊するのか。たとえばウェイブ一人をどうにかしたとして、それで解決する問題なのか。先の灰塵戦争でアッシュラッツのグレムリンも多くが機能停止したとはいえ、相手の戦力は如何ほどか。曲がりなりにも三大勢力から出資を受けている企業に派手に喧嘩を売って、その後の生活は大丈夫なのか。不透明なことが多すぎる。
仮に、それらの懸念を全てクリアにしたとしても、ウェイブだけを狙い撃つのはきっと難しい。アッシュラッツは最悪な企業だが、それでも、無駄な犠牲を出すのは、アレクシアにとって気が引けることだった。
そうして自分一人が自由になったとして、セラフィンに顔向けできないように思えた。彼もまた、こんなクソみたいな世界の中で、そういう理想を語るひとだった――コールのように。
アレクシアだって生きるためにグレムリンを、そのテイマーを斃している。今更何を言っているんだ、という話でもあるが、それでも、広範囲の破壊はできるだけ避けたい。人間らしく在るなら、きっとそうすべきだ。
他の選択肢には、"借金の返済"がある。一番の正攻法に思えるし、アレクシアもこれを目指していた。が、正直なところ、金を払い切ってもすんなり辞めさせてくれるとは考え辛かった。何より、この方法を取るには時間も金も無い。状況は逼迫している。
ああでもない、こうでもないと二人は話を続けたが、やがて案も出尽くした。ふう、とアレクシアは疲れを滲ませた息を吐く。
「今日はこのくらいにしとこうか。一回、落ち着いて考えてみる」
「分かった。俺も何か考えておこう」
コールは頷き、席を立った。アレクシアもそれに倣って、二人して会議室を出る。
「コールくん」
「何だ?」
呼ばれて振り返ったコールは、いつもと変わらない、涼しい顔をしている。
少し間を置いて、アレクシアは首を横に振る。
「や、何でもない」
「そうか。それじゃ、また明日」
「うん」
コールはそのまま歩いていった。恐らく自室に戻るのだろう。
会議室の扉にもたれながら、アレクシアはその背を見ている。
あんなことを言っておいて。手を差し伸べておいて。
拍子抜けするくらい、あまりにいつも通りだ。
「……何なのさ」
アレクシアは釈然としない様子で呟いた。
もしかすると本当にただの仕事のように思っていて、コールにとってはどうってことのない話なのかもしれない。
拾って、僚機を組んで、気づけばもう随分経つのに、彼のことはよく分からない。
けれど――あの未来に進もうとする真っ直ぐな姿勢には、感心する。
そのせいだろうか。特に名案が出たわけでもないのに、心強く思うのは。
コールのことは分からない。
分からなくたって、確かにアレクシアは救われている。
それが分かっていればいいのだろう。
異動の話を聞いてからずっと頭が靄がかった心地だったが、今はすっきりと晴れていた。
その夜は、久しぶりによく眠れた。
次の日、コールとの話し合いの前にアレクシアが向かったのはダストデッキだった。
とりあえず、自分のタイムリミットを知りたくて、艦長室の扉を叩く。
「あ、エコーズさん!」
ドアを開けたのはシリヤだった。何でシリヤが? 目を瞬かせるアレクシアに対し、彼女はぱっと笑う。その後ろでは、「おー、入れ入れ」と執務机に座ったカイルが手招きしている。
アレクシアは二人を見比べて言った。
「取り込み中なら出直しますけど」
「いや、お前にも関係ある話だ。丁度良かった」
シリヤもうんうん頷いて、道を空けるようカイルの前に移動した。
アレクシアが扉を閉めて部屋に入ると、カイルは、「早速だが」と話を切り出した。
「今から話すことは極秘事項だ。いいな?」
「はあ、どうぞ」
極秘事項? 一体何を話してたんだ? アレクシアは僅かに眉を寄せた。
「ジャンク財団のことは把握してるな」
「そりゃ、もちろん」
今、ジャンク財団のことを知らないテイマーはいないだろう。大々的に行われた宣戦布告の後から、グレイヴネットには恐ろしい量の広告が流れている。世相に疎く、ニュースなどに触れていないとしても、マーケットに繋がるグレイヴネットはテイマーの必需品だ。必ず目にしていると言っていい。
ここからが本題だ、と言わんばかりに、カイルは声を潜めた。
「奴らの資金ルートは謎だが、いくつかの企業と繋がりがあることが分かった。その内の一つが"ネズミ"だ」
「……アッシュラッツが?」
それは、つまり――アレクシアの考えがまとまり切る前に、シリヤが言葉を続ける。
「そのアッシュラッツに、料理長……じゃないや、元料理長が潜入捜査してくれてます」
「あの人、そういう感じの人だったの?」
元料理長は、この間いきなりベルーガを辞めた、と聞いている。シリヤの上長に相応しく、いつも柔和な笑みを浮かべていた彼は、ただただ蒸発したとばかり思っていたのだが。
シリヤは悪戯がバレた子どものような、少し困った笑みを見せた。
「それで、アッシュラッツとジャンク財団の幹部同士の会合の日が分かりました。そこを強襲します。ずばり……ネズミの丸焼き作戦です!」
「やるのは可能な限りの生捕りだがな。色々吐かせにゃならん」
「下準備は大事ですしね」
「ネズミのローストってのもあんまり美味くなさそうだが……三大勢力のお偉方は相当お怒りだ。同じタイミングでガサ入れして、解体に追い込むつもりだぜ」
そう。この作戦が成功すれば、アッシュラッツは無くなる、ということだ。
青天の霹靂とでも言うべき事態を呑み込むのでいっぱいだった。そんな様子のアレクシアに、「エコーズ」とカイルが声を掛ける。
「この作戦に、何でベルーガが選ばれたと思う?」
どうしてこのブラッククソ艦が? 見当も付かなくて、首を横に振る。
「一つは、曲がりなりにもコロッセオ・レガシィ直属の戦力だから。ま、三大勢力外のうちが介入した方が後腐れがねえってわけだな。
もう一つは……保有するグレムリン戦力を買われたんだよ。すごいもんだぜ、今やユニオンとしちゃ虚空領域最大規模なんだからな。
……それを集めてきたのは誰だ?」
慣れないグレムリンに乗り、グレイヴネットのアクセス権を駆使して地道に勧誘を行ったのは、紛れもなくアレクシアだ。
心音がうるさかった。肯定も否定もできないまま、カイルは続ける。
「クソみたいな境遇でも、腐らず努力した成果だろう。俺はお前さんの事情を全部知ってるわけじゃないが……ネズミなんざに囚われず、自由になってもいいんじゃないか」
そもそも、アッシュラッツ・ファクトリーの人間であるアレクシアにこの作戦を伝えるべきではないだろう。それをこうして伝えられているのは信頼と――きっと、心配の表れだった。シリヤも、「そうすべきですよ!」と言わんばかりに頷いている。
「ま、できりゃァ今後も船に居てほしいもんだが。頼りにしてるんだぜ、お前さんのことは」
「……それは期待しないでください」
やっとのことで絞り出された言葉に、カイルとシリヤが目を丸くする。
「再就職先の当てはあるんで」
微かに見えた未来に、心臓が鳴っていた。
「とりあえず破壊しよう」
「破壊」
「破壊は得意だ」
「……その調子でコーヒーショップなんて大丈夫?」
「コーヒーショップはコーヒー豆を破壊する仕事だろう」
「そうかなあ……」
破壊する、と言いながらコーヒー豆を挽くコールを想像してみる。どう考えても繁盛しなさそうな店だ。
現実問題として、"破壊"は選択肢に挙がらないわけではない。グレムリンという力が、アレクシアとコールにはある。
しかし、何をどう破壊するのか。たとえばウェイブ一人をどうにかしたとして、それで解決する問題なのか。先の灰塵戦争でアッシュラッツのグレムリンも多くが機能停止したとはいえ、相手の戦力は如何ほどか。曲がりなりにも三大勢力から出資を受けている企業に派手に喧嘩を売って、その後の生活は大丈夫なのか。不透明なことが多すぎる。
仮に、それらの懸念を全てクリアにしたとしても、ウェイブだけを狙い撃つのはきっと難しい。アッシュラッツは最悪な企業だが、それでも、無駄な犠牲を出すのは、アレクシアにとって気が引けることだった。
そうして自分一人が自由になったとして、セラフィンに顔向けできないように思えた。彼もまた、こんなクソみたいな世界の中で、そういう理想を語るひとだった――コールのように。
アレクシアだって生きるためにグレムリンを、そのテイマーを斃している。今更何を言っているんだ、という話でもあるが、それでも、広範囲の破壊はできるだけ避けたい。人間らしく在るなら、きっとそうすべきだ。
他の選択肢には、"借金の返済"がある。一番の正攻法に思えるし、アレクシアもこれを目指していた。が、正直なところ、金を払い切ってもすんなり辞めさせてくれるとは考え辛かった。何より、この方法を取るには時間も金も無い。状況は逼迫している。
ああでもない、こうでもないと二人は話を続けたが、やがて案も出尽くした。ふう、とアレクシアは疲れを滲ませた息を吐く。
「今日はこのくらいにしとこうか。一回、落ち着いて考えてみる」
「分かった。俺も何か考えておこう」
コールは頷き、席を立った。アレクシアもそれに倣って、二人して会議室を出る。
「コールくん」
「何だ?」
呼ばれて振り返ったコールは、いつもと変わらない、涼しい顔をしている。
少し間を置いて、アレクシアは首を横に振る。
「や、何でもない」
「そうか。それじゃ、また明日」
「うん」
コールはそのまま歩いていった。恐らく自室に戻るのだろう。
会議室の扉にもたれながら、アレクシアはその背を見ている。
あんなことを言っておいて。手を差し伸べておいて。
拍子抜けするくらい、あまりにいつも通りだ。
「……何なのさ」
アレクシアは釈然としない様子で呟いた。
もしかすると本当にただの仕事のように思っていて、コールにとってはどうってことのない話なのかもしれない。
拾って、僚機を組んで、気づけばもう随分経つのに、彼のことはよく分からない。
けれど――あの未来に進もうとする真っ直ぐな姿勢には、感心する。
そのせいだろうか。特に名案が出たわけでもないのに、心強く思うのは。
コールのことは分からない。
分からなくたって、確かにアレクシアは救われている。
それが分かっていればいいのだろう。
異動の話を聞いてからずっと頭が靄がかった心地だったが、今はすっきりと晴れていた。
その夜は、久しぶりによく眠れた。
次の日、コールとの話し合いの前にアレクシアが向かったのはダストデッキだった。
とりあえず、自分のタイムリミットを知りたくて、艦長室の扉を叩く。
「あ、エコーズさん!」
ドアを開けたのはシリヤだった。何でシリヤが? 目を瞬かせるアレクシアに対し、彼女はぱっと笑う。その後ろでは、「おー、入れ入れ」と執務机に座ったカイルが手招きしている。
アレクシアは二人を見比べて言った。
「取り込み中なら出直しますけど」
「いや、お前にも関係ある話だ。丁度良かった」
シリヤもうんうん頷いて、道を空けるようカイルの前に移動した。
アレクシアが扉を閉めて部屋に入ると、カイルは、「早速だが」と話を切り出した。
「今から話すことは極秘事項だ。いいな?」
「はあ、どうぞ」
極秘事項? 一体何を話してたんだ? アレクシアは僅かに眉を寄せた。
「ジャンク財団のことは把握してるな」
「そりゃ、もちろん」
今、ジャンク財団のことを知らないテイマーはいないだろう。大々的に行われた宣戦布告の後から、グレイヴネットには恐ろしい量の広告が流れている。世相に疎く、ニュースなどに触れていないとしても、マーケットに繋がるグレイヴネットはテイマーの必需品だ。必ず目にしていると言っていい。
ここからが本題だ、と言わんばかりに、カイルは声を潜めた。
「奴らの資金ルートは謎だが、いくつかの企業と繋がりがあることが分かった。その内の一つが"ネズミ"だ」
「……アッシュラッツが?」
それは、つまり――アレクシアの考えがまとまり切る前に、シリヤが言葉を続ける。
「そのアッシュラッツに、料理長……じゃないや、元料理長が潜入捜査してくれてます」
「あの人、そういう感じの人だったの?」
元料理長は、この間いきなりベルーガを辞めた、と聞いている。シリヤの上長に相応しく、いつも柔和な笑みを浮かべていた彼は、ただただ蒸発したとばかり思っていたのだが。
シリヤは悪戯がバレた子どものような、少し困った笑みを見せた。
「それで、アッシュラッツとジャンク財団の幹部同士の会合の日が分かりました。そこを強襲します。ずばり……ネズミの丸焼き作戦です!」
「やるのは可能な限りの生捕りだがな。色々吐かせにゃならん」
「下準備は大事ですしね」
「ネズミのローストってのもあんまり美味くなさそうだが……三大勢力のお偉方は相当お怒りだ。同じタイミングでガサ入れして、解体に追い込むつもりだぜ」
そう。この作戦が成功すれば、アッシュラッツは無くなる、ということだ。
青天の霹靂とでも言うべき事態を呑み込むのでいっぱいだった。そんな様子のアレクシアに、「エコーズ」とカイルが声を掛ける。
「この作戦に、何でベルーガが選ばれたと思う?」
どうしてこのブラッククソ艦が? 見当も付かなくて、首を横に振る。
「一つは、曲がりなりにもコロッセオ・レガシィ直属の戦力だから。ま、三大勢力外のうちが介入した方が後腐れがねえってわけだな。
もう一つは……保有するグレムリン戦力を買われたんだよ。すごいもんだぜ、今やユニオンとしちゃ虚空領域最大規模なんだからな。
……それを集めてきたのは誰だ?」
慣れないグレムリンに乗り、グレイヴネットのアクセス権を駆使して地道に勧誘を行ったのは、紛れもなくアレクシアだ。
心音がうるさかった。肯定も否定もできないまま、カイルは続ける。
「クソみたいな境遇でも、腐らず努力した成果だろう。俺はお前さんの事情を全部知ってるわけじゃないが……ネズミなんざに囚われず、自由になってもいいんじゃないか」
そもそも、アッシュラッツ・ファクトリーの人間であるアレクシアにこの作戦を伝えるべきではないだろう。それをこうして伝えられているのは信頼と――きっと、心配の表れだった。シリヤも、「そうすべきですよ!」と言わんばかりに頷いている。
「ま、できりゃァ今後も船に居てほしいもんだが。頼りにしてるんだぜ、お前さんのことは」
「……それは期待しないでください」
やっとのことで絞り出された言葉に、カイルとシリヤが目を丸くする。
「再就職先の当てはあるんで」
微かに見えた未来に、心臓が鳴っていた。
◆15回更新の日記ログ
*今回の日誌*
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/c6cac0dd-56e4-4560-b2cc-e986cc05bf0e/eee1b04013c4985066c36283250fd4a3
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/c6cac0dd-56e4-4560-b2cc-e986cc05bf0e/eee1b04013c4985066c36283250fd4a3
◆14回更新の日記ログ
*今回の日誌*
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/ae2dce6d-78f7-4f7b-8686-527f4d7ebff1/53c12890f3d4bad455115ce486d6c627
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/ae2dce6d-78f7-4f7b-8686-527f4d7ebff1/53c12890f3d4bad455115ce486d6c627
◆13回更新の日記ログ
グレイヴネット上でのジャンク財団の宣戦布告から一夜明け、【ベルーガ】では艦長カイルから今後の方針が発表された。
「曲がりなりにも俺らの所属は【コロッセオ・レガシィ】だ。
コロッセオ・レガシィの役目は何だ? タワーの守護だな。
何もジャンク財団を野放しにしろって話じゃねぇが、俺たちはそっちに回ることになった。お上からのご要望でな。
ってことで、タワーを航路に取るぞ」
ジャンク財団の代表と名乗る人物はこう言っていた。「未識別機動体を、すでに掌握し、制御している」と。
未識別機動体の侵攻により、今、虚空領域は滅茶苦茶になっている。その発端も、ジャンク財団によるものなのだろうか。
と、そこまで考えて、アレクシアは思考を打ち切る。よく分からないことだらけだ。これ以上考えても無駄だろう。
艦長室の扉をノックする。「入れ」と部屋の中から聞こえて、ドアノブを回す。
「あー……エコーズ。伝え辛いんだが」
【ベルーガ】全体の連絡の後、カイルに呼び出されていた。
そしてそのカイルは今、アレクシアの前で酷く苦々しい顔をしている。座っている革張りの防錆高級ソファが、似合わないことこの上ない。
こういう時は悪い話に決まっている。努めて、アレクシアは無感情に言った。
「また役職でも増えるんで?」
「ネズミの方から連絡があってな」
「……気ぃ遣ってもらわなくてもいいんで。簡潔に伝えてくれますか」
「俺が気ィ遣ってんだぜ。有難く受け取れよ」
なおもカイルは躊躇した様子で、歯切れ悪く、こう言った。
「アレクシア・エコーズは【ベルーガ】付グレムリンテイマーから、【アッシュラッツ・ファクトリー】本部、ウェイブ・クローヴィンケル付秘書への速やかな異動を命じる、だと」
「……」
そうか。そう来るのか。そこまで、するのか。
頭だけは妙に冷静にその事実を理解していたが、アレクシアは何も言えなかった。ぐつぐつと煮立つ感情を、言葉にすることができない。
カイルは珍しく、慮るようにアレクシアを窺う。
「一応、栄転だと思うんだが」
栄転。これが?
ふ、と自嘲のような息が漏れた。それで、ようやく呼吸を思い出したような心地になる。心臓がどくどく鳴っていることに気が付く。
言葉を。何か言わないと。
「……面白くない冗談ですね」
「エコーズ、大丈夫なのか?
なんつーか、あいつおかしいだろ。
この前押しかけてきたのだってよ……仕事の範疇を越えて、お前さんに執着してる」
「……」
そうだ。あのウェイブという男は、おかしい。そんなことは言われなくても知っている。
あの時からずっとそうだ。ずっと変わらない。
アレクシアはずっと、ウェイブの掌の上で、ただただ弄ばれている。
そういうことなのだろう。
黙りこくるアレクシアを見兼ねて、カイルは首を横に振った。
「……いや、いい。悪いな。エコーズ、今日はもう休め。いいな。艦長命令だ。
とりあえず、ギリギリまで引き伸ばすからよ。俺もあいつは気に食わねーんだ。
何かあったら言えや。ここにいる間は【ベルーガ】の一員だ」
聞こえる声がどうにも遠く感じる。聞き返す気も起きない。
きっともう関係のなくなることだから。
アレクシアは曖昧に頷いて、艦長室を出た。
「え、エコーズさん? 大丈夫ですか?」
名前を呼ばれて、一拍遅れて振り返る。
第二甲板まで下りてきたアレクシアに声をかけたのは、シリヤだった。
グレムリンエンジニア、兼料理長――副料理長だったが、最近料理長が辞めたので格上げさせられた――、兼食料班主任である彼女は、グレムリンドックのある第二甲板でもよく見かけるが、大量の整備機材を抱え、見るからに忙しそうにも関わらず、足を止めてぎょっとした表情でアレクシアを見ている。
「シリヤ」
「あいや、あの……」
シリヤはアレクシアの顔をまじまじと見て、心配の色をより強めた。
「顔色が酷くて。どうかしました?」
「……んー。はは。過労かもね。
ちょっと、疲れたんでしょ。うん。それだけだよ」
アレクシアは力なく手を振って、ふらりとグレムリンドックの奥に入っていく。
シリヤは何も言えずに、その背を見送ることしかできなかった。
グレムリンドックを通り抜けると、船員や機材の喧騒がだんだん小さくなる。代わりに聞こえるのは艦の機械的で規則的な駆動音だ。
第二甲板奥の多目的倉庫。アレクシアのいつもの喫煙所。
何度も開けた扉が、やけに重たく感じられた。腕だけではなく体全体で、ようやく押し開ける。電気も付けずに、エアフィルターの下に立つ。背中を冷たい壁にもたれかけるが、すぐ、ずるずると頽れるように座り込んだ。煙草を吸いにきたはずだったが、そんな気にもなれない。
しばらく、アレクシアは膝に顔を埋めていた。
ごう、ごう、とエアフィルターの中の換気扇が回る音だけが響く。
「……やだな……」
掻き消されてしまいそうな、か細い声だった。
実際、それは誰にも届かない。
あの男のところに行くのは本当に、本当に嫌だった。いっそ死んだほうがマシにさえ思える。
それでも。
アレクシアは生きていなくてはいけない。
約束したからだ。
蹲る。目を閉じる。
意識が、思い出の中へと沈んでいく。
「曲がりなりにも俺らの所属は【コロッセオ・レガシィ】だ。
コロッセオ・レガシィの役目は何だ? タワーの守護だな。
何もジャンク財団を野放しにしろって話じゃねぇが、俺たちはそっちに回ることになった。お上からのご要望でな。
ってことで、タワーを航路に取るぞ」
ジャンク財団の代表と名乗る人物はこう言っていた。「未識別機動体を、すでに掌握し、制御している」と。
未識別機動体の侵攻により、今、虚空領域は滅茶苦茶になっている。その発端も、ジャンク財団によるものなのだろうか。
と、そこまで考えて、アレクシアは思考を打ち切る。よく分からないことだらけだ。これ以上考えても無駄だろう。
艦長室の扉をノックする。「入れ」と部屋の中から聞こえて、ドアノブを回す。
「あー……エコーズ。伝え辛いんだが」
【ベルーガ】全体の連絡の後、カイルに呼び出されていた。
そしてそのカイルは今、アレクシアの前で酷く苦々しい顔をしている。座っている革張りの防錆高級ソファが、似合わないことこの上ない。
こういう時は悪い話に決まっている。努めて、アレクシアは無感情に言った。
「また役職でも増えるんで?」
「ネズミの方から連絡があってな」
「……気ぃ遣ってもらわなくてもいいんで。簡潔に伝えてくれますか」
「俺が気ィ遣ってんだぜ。有難く受け取れよ」
なおもカイルは躊躇した様子で、歯切れ悪く、こう言った。
「アレクシア・エコーズは【ベルーガ】付グレムリンテイマーから、【アッシュラッツ・ファクトリー】本部、ウェイブ・クローヴィンケル付秘書への速やかな異動を命じる、だと」
「……」
そうか。そう来るのか。そこまで、するのか。
頭だけは妙に冷静にその事実を理解していたが、アレクシアは何も言えなかった。ぐつぐつと煮立つ感情を、言葉にすることができない。
カイルは珍しく、慮るようにアレクシアを窺う。
「一応、栄転だと思うんだが」
栄転。これが?
ふ、と自嘲のような息が漏れた。それで、ようやく呼吸を思い出したような心地になる。心臓がどくどく鳴っていることに気が付く。
言葉を。何か言わないと。
「……面白くない冗談ですね」
「エコーズ、大丈夫なのか?
なんつーか、あいつおかしいだろ。
この前押しかけてきたのだってよ……仕事の範疇を越えて、お前さんに執着してる」
「……」
そうだ。あのウェイブという男は、おかしい。そんなことは言われなくても知っている。
あの時からずっとそうだ。ずっと変わらない。
アレクシアはずっと、ウェイブの掌の上で、ただただ弄ばれている。
そういうことなのだろう。
黙りこくるアレクシアを見兼ねて、カイルは首を横に振った。
「……いや、いい。悪いな。エコーズ、今日はもう休め。いいな。艦長命令だ。
とりあえず、ギリギリまで引き伸ばすからよ。俺もあいつは気に食わねーんだ。
何かあったら言えや。ここにいる間は【ベルーガ】の一員だ」
聞こえる声がどうにも遠く感じる。聞き返す気も起きない。
きっともう関係のなくなることだから。
アレクシアは曖昧に頷いて、艦長室を出た。
「え、エコーズさん? 大丈夫ですか?」
名前を呼ばれて、一拍遅れて振り返る。
第二甲板まで下りてきたアレクシアに声をかけたのは、シリヤだった。
グレムリンエンジニア、兼料理長――副料理長だったが、最近料理長が辞めたので格上げさせられた――、兼食料班主任である彼女は、グレムリンドックのある第二甲板でもよく見かけるが、大量の整備機材を抱え、見るからに忙しそうにも関わらず、足を止めてぎょっとした表情でアレクシアを見ている。
「シリヤ」
「あいや、あの……」
シリヤはアレクシアの顔をまじまじと見て、心配の色をより強めた。
「顔色が酷くて。どうかしました?」
「……んー。はは。過労かもね。
ちょっと、疲れたんでしょ。うん。それだけだよ」
アレクシアは力なく手を振って、ふらりとグレムリンドックの奥に入っていく。
シリヤは何も言えずに、その背を見送ることしかできなかった。
グレムリンドックを通り抜けると、船員や機材の喧騒がだんだん小さくなる。代わりに聞こえるのは艦の機械的で規則的な駆動音だ。
第二甲板奥の多目的倉庫。アレクシアのいつもの喫煙所。
何度も開けた扉が、やけに重たく感じられた。腕だけではなく体全体で、ようやく押し開ける。電気も付けずに、エアフィルターの下に立つ。背中を冷たい壁にもたれかけるが、すぐ、ずるずると頽れるように座り込んだ。煙草を吸いにきたはずだったが、そんな気にもなれない。
しばらく、アレクシアは膝に顔を埋めていた。
ごう、ごう、とエアフィルターの中の換気扇が回る音だけが響く。
「……やだな……」
掻き消されてしまいそうな、か細い声だった。
実際、それは誰にも届かない。
あの男のところに行くのは本当に、本当に嫌だった。いっそ死んだほうがマシにさえ思える。
それでも。
アレクシアは生きていなくてはいけない。
約束したからだ。
蹲る。目を閉じる。
意識が、思い出の中へと沈んでいく。
◆12回更新の日記ログ
「そろそろ借金完済だけど、コール君はどうするの」
いつものように戦闘を終えた後、アレクシアがコールにそう問いかけた。
沈黙が流れる。
「そうなのか?」
「え? そうだけど?」
「初耳だ」
「嘘でしょ」
信じられない。アレクシアの顔にはその6文字が張り付いていた。
自分の借金の額を忘れるなんてこと、ある?
「……まあ、いいけど。とりあえずほら、返済のためにここで働いてたわけじゃない。違うとこ行くなら早めに教えてね。こっちにも色々と都合があるから」
「わかった」
と、いつもと同じ無表情で、コールは頷いた。
***
そんな会話をしてから、暫く。
ジャンク財団掃討作戦が計画されているという噂もあるが、ひとまず【ベルーガ】は通常運行だった。未確認機を見つければ破壊し、グレムリンテイマーが襲撃してきたらこれも破壊する。錆の海での破壊に明け暮れる日々。
「雇い主さん。この前の話だが」
アレクシアが食堂で食事――本日のメニューはドロの光の柱風――をしていると、そう言ってコールが正面の席に座ってきた。コールはドロと、コンブレッドがどっさり載ったトレーを机の上に置く。
相変わらずよく食べるなあと思いつつ、アレクシアは食事の手を取りコールに視線を向けた。
「あー、どうするかって話?」
「そうだ」
ついに来たか。
見切り発車で僚機探しとけばよかったな。せめて次の戦闘まではいてほしいところだけど……
「差し当たってここに残ろうと思う」
「……あ、そうなの?」
珍しく、アレクシアは驚いたように目を瞠った。
コールが【ベルーガ】に残る。それは予想だにしていないことだ。
「そりゃまあ……」
嬉しいよ、と言葉が過る。
いや。これは違う。
視線を揺らして、アレクシアはこう言った。
「艦としては助かるけど」
回答をしたからここからは雑談気分なのか、コールはコンブレッドに手を付け始めている。「とりあえず資金調達を目標にしよう」と言いつつ、食べ盛りの子どものようにもりもりと食べている。
「コーヒーショップの?」
「そうだ」
以前、アレクシアはコールに聞いたことがある。コーヒーショップを開くことが将来の夢だ、と。
まさか、本気でそう思っているとは。
「……コールくん、本気なんだ? 完済に気づいてなかったのに、経営なんてできる?」
「やってみなければわからない」
「まあ……いいんじゃない。やりたいことがあるのはさ」
「雇い主さんは何がやりたいんだ?」
「うん? ……私?」
「ああ」
コーヒーショップの会話をした時。冗談のつもりで、「店を開いたら、飲みに行ってあげようか」と言った。コーヒーはそこまで好きではないが、コールが店を開くなら、そうしてもいいと思ったのは確かだ。
その返事に、コールは言ったのだ。「雇い主さんも一緒にやるか? コーヒー屋。そしたら、わざわざ飲みに来る必要も無い」と。
アレクシアは、それを断っていた。分かり難い冗談は止めた方が良い。コーヒーにも詳しくないし、愛想も悪い。接客業には向いていない。私には無理だ。そうして、やれない理由を並び立てた。
「……やりたいこと……」
やりたいこと、なんて無かった。
やれないことが分かっているから、そんなことは考えたことがない。いや、考えないようにしてきた。
「やりたくない、ことなら、たくさんある」
だからアレクシアにはこう言うことしかできない。コールみたいに、やりたいことなんて語れなかった。
「グレムリンテイマーとか。戦うこととか。エンジニアも慣れてるってだけで、別にやりたいことではないし」
「辞めるという選択肢はないのか?」
コールは不思議そうにしている。
「……そうできたらいいけどねえ」
アレクシアはふっと笑った。自嘲めいたそれは、困ったような苦笑いに変わる。
「もし辞めれたら、雇ってくれる? コールくん」
「ああ。構わない」
「そりゃ心強いや」
あーあ。どっかの企業みたいに爆発しないかな、アッシュラッツも。
そんなことを思いながら、食事と他愛のない話が続く。
***
ジリリリリ、と旧式の着信音を模した音が鳴る。
カイルはアンティーク調の通信機の受話器を取った。
「こちら【ベルーガ】艦長室。……ああ? クローヴィンケル殿?」
電話先の相手に、思わず眉を顰める。
「どうしたんですかい、お忙しいでしょうに……はあ?」
声がどんどん険しくなる。
「いやいや、ちょっと待ってもらえますか、そんな急に? 有り得ねえ。今抜けられたら困りますよ。契約違反でしょう……ああ!? いやだから、ちょっ、おい!? ……あァー、クソ!」
ガチャンと受話器を荒く置き、カイルはその先を、忌々しげに睨んだ。
いつものように戦闘を終えた後、アレクシアがコールにそう問いかけた。
沈黙が流れる。
「そうなのか?」
「え? そうだけど?」
「初耳だ」
「嘘でしょ」
信じられない。アレクシアの顔にはその6文字が張り付いていた。
自分の借金の額を忘れるなんてこと、ある?
「……まあ、いいけど。とりあえずほら、返済のためにここで働いてたわけじゃない。違うとこ行くなら早めに教えてね。こっちにも色々と都合があるから」
「わかった」
と、いつもと同じ無表情で、コールは頷いた。
***
そんな会話をしてから、暫く。
ジャンク財団掃討作戦が計画されているという噂もあるが、ひとまず【ベルーガ】は通常運行だった。未確認機を見つければ破壊し、グレムリンテイマーが襲撃してきたらこれも破壊する。錆の海での破壊に明け暮れる日々。
「雇い主さん。この前の話だが」
アレクシアが食堂で食事――本日のメニューはドロの光の柱風――をしていると、そう言ってコールが正面の席に座ってきた。コールはドロと、コンブレッドがどっさり載ったトレーを机の上に置く。
相変わらずよく食べるなあと思いつつ、アレクシアは食事の手を取りコールに視線を向けた。
「あー、どうするかって話?」
「そうだ」
ついに来たか。
見切り発車で僚機探しとけばよかったな。せめて次の戦闘まではいてほしいところだけど……
「差し当たってここに残ろうと思う」
「……あ、そうなの?」
珍しく、アレクシアは驚いたように目を瞠った。
コールが【ベルーガ】に残る。それは予想だにしていないことだ。
「そりゃまあ……」
嬉しいよ、と言葉が過る。
いや。これは違う。
視線を揺らして、アレクシアはこう言った。
「艦としては助かるけど」
回答をしたからここからは雑談気分なのか、コールはコンブレッドに手を付け始めている。「とりあえず資金調達を目標にしよう」と言いつつ、食べ盛りの子どものようにもりもりと食べている。
「コーヒーショップの?」
「そうだ」
以前、アレクシアはコールに聞いたことがある。コーヒーショップを開くことが将来の夢だ、と。
まさか、本気でそう思っているとは。
「……コールくん、本気なんだ? 完済に気づいてなかったのに、経営なんてできる?」
「やってみなければわからない」
「まあ……いいんじゃない。やりたいことがあるのはさ」
「雇い主さんは何がやりたいんだ?」
「うん? ……私?」
「ああ」
コーヒーショップの会話をした時。冗談のつもりで、「店を開いたら、飲みに行ってあげようか」と言った。コーヒーはそこまで好きではないが、コールが店を開くなら、そうしてもいいと思ったのは確かだ。
その返事に、コールは言ったのだ。「雇い主さんも一緒にやるか? コーヒー屋。そしたら、わざわざ飲みに来る必要も無い」と。
アレクシアは、それを断っていた。分かり難い冗談は止めた方が良い。コーヒーにも詳しくないし、愛想も悪い。接客業には向いていない。私には無理だ。そうして、やれない理由を並び立てた。
「……やりたいこと……」
やりたいこと、なんて無かった。
やれないことが分かっているから、そんなことは考えたことがない。いや、考えないようにしてきた。
「やりたくない、ことなら、たくさんある」
だからアレクシアにはこう言うことしかできない。コールみたいに、やりたいことなんて語れなかった。
「グレムリンテイマーとか。戦うこととか。エンジニアも慣れてるってだけで、別にやりたいことではないし」
「辞めるという選択肢はないのか?」
コールは不思議そうにしている。
「……そうできたらいいけどねえ」
アレクシアはふっと笑った。自嘲めいたそれは、困ったような苦笑いに変わる。
「もし辞めれたら、雇ってくれる? コールくん」
「ああ。構わない」
「そりゃ心強いや」
あーあ。どっかの企業みたいに爆発しないかな、アッシュラッツも。
そんなことを思いながら、食事と他愛のない話が続く。
***
ジリリリリ、と旧式の着信音を模した音が鳴る。
カイルはアンティーク調の通信機の受話器を取った。
「こちら【ベルーガ】艦長室。……ああ? クローヴィンケル殿?」
電話先の相手に、思わず眉を顰める。
「どうしたんですかい、お忙しいでしょうに……はあ?」
声がどんどん険しくなる。
「いやいや、ちょっと待ってもらえますか、そんな急に? 有り得ねえ。今抜けられたら困りますよ。契約違反でしょう……ああ!? いやだから、ちょっ、おい!? ……あァー、クソ!」
ガチャンと受話器を荒く置き、カイルはその先を、忌々しげに睨んだ。
◆11回更新の日記ログ
*今回の日記*
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/ecabd90b-e623-46b4-b96f-9b1b995d8f6a/c47509f1ff2b9de061423ff7dacef510
https://www.evernote.com/shard/s232/sh/ecabd90b-e623-46b4-b96f-9b1b995d8f6a/c47509f1ff2b9de061423ff7dacef510
◆10回更新の日記ログ
ニュースが慌ただしく駆け巡る。刻一刻と変わる世界の情勢が報じられる。
アレクシアはそれをどこか他人事のように聞いていた。グレムリンに乗って戦っているのだから、言ってしまえば前線にいるのだが、それでも自分事に思うのは難しかった。先の巨大未識別融合体との戦いだって、アレクシアはコンテナ狙いのジャンクテイマーと戦ってばかりで、結局相対することはなかった。
世界が終わるとか、ループしているとか、急に言われても実感が湧かない。神秘工廠『ゼラ』に行けと言われたが、雇われの身だ。カイルの許可が出るだろうか? それは怪しい。
自分の世界は手の届く範囲だけで、それより向こうの出来事は透明の膜で隔てられている。観測することはできるが、触れることはできない。そんな余裕も無い。――まあ、触れられるとしても、そうしない可能性が高いのだが。アレクシアは平和主義を自称している。厄介事は御免だった。平穏であればあるほど好ましい。
そこまで聞き流して、アレクシアはベッドサイドに置かれたラジオのスイッチを切る。金を掛けずに気を紛らわせることができるラジオは好きだったが、考え事をする時には向いていない。
入れ替わりで電子タブレットを手に取るとベッドに寝転び直し、それをしげしげと眺める。
アレクシアにとって、目下の自分事はこちらの方だった。
(相変わらずだな)
表示されているのはベルーガからの給与明細だった。
額面としては、企業やユニオン勤めのテイマーの相場より少し低いくらいだ。それに、この時世に給与が出るだけマシと言えなくもない。
問題はその下に書かれている、『仲介料』と『返済』の欄だ。
『仲介料』で給与の約半分、『返済』でその更に半分が差し引かれており、結果的にアレクシアの手元には4分の1ほどしか残らない。
アレクシアは、アッシュラッツ・ファクトリーに所属し、ベルーガへ配属されている。仕事は全てアッシュラッツから割り振られていて、『仲介料』はそういうことだ。
稼ぎの半分も持っていくのは暴利だ。正当ではない。もちろんアレクシアもそう思っている。それでもアッシュラッツを辞められないのは、『返済』の方にあった。
物心がついた時には、アレクシアはすでにアッシュラッツの管理下にあった。
孤児なのか、売られたのかは分からない。ずっと、"そういうもの"だと思っていたから、知ろうとも思わなかった。アッシュラッツから教えられるものが全てだった。
けれどあの日、あの時、知ってしまったのだ。外の世界のことを。目を逸らし続けていた、自分の置かれた状況を。向き合わざるを得なくなってしまった。
アッシュラッツを辞めたいと言ったアレクシアに請求されたのは、それまでの生活費、教育費、その他諸々を含んだ多額の身請け金。すぐに払えるものでは到底なく、分割で返し始めたのは17歳の頃だ。完済の目途は立たないまま、もう7年も経ってしまった。
電子タブレットを枕際に放って、アレクシアは目を閉じた。
(……そういえば、コールくんの借金はもうなくなるのか)
コールのアレクシアへの借金――激しく損壊した『クレオソート』と、コール自身の修理代。いくらかはベルーガが負担しているが、おおよそはアレクシアが持っていた。
返済に追われる自分が返済を迫るのもなんだか滑稽な話だった。というか、心情的にはとても嫌だった。アッシュラッツと同じようになってしまった、そんな心地。それでも金は必要だった。仕方がない。利子はほとんど請求していないから、それでゆるしてほしい。
借金を返済すれば、ベルーガで働く理由はなくなる。
その時、コールはどうするのだろう。
彼の腕ならもっと待遇の良い艦に乗れるだろうし、ヴォイド・テイマーとして一人でやっていくことだって不可能ではない。ベルーガの待遇、特に食事には常々不満を持っているし、残る可能性は極めて低いだろう。
そうしたら、アレクシアは僚機を探さなくてはならない。今更テイマーを下りることは難しそうだし、一人で戦場に出られるほど実力はなかった。
この状況下で新しい僚機は見つかるのか。見つかったとして、うまくやっていけるのか。食事はこだわるタイプだろうか。卓球に興味を示したりするだろうか。
そこまで考えて、アレクシアは気づいた。
最初こそコールを拾ったのは間違いだったと思っていたが、今ではそう思っていないらしい。
溜息。
コールがいなくなる。
それは少し、面倒臭いな、と思った。
アレクシアはそれをどこか他人事のように聞いていた。グレムリンに乗って戦っているのだから、言ってしまえば前線にいるのだが、それでも自分事に思うのは難しかった。先の巨大未識別融合体との戦いだって、アレクシアはコンテナ狙いのジャンクテイマーと戦ってばかりで、結局相対することはなかった。
世界が終わるとか、ループしているとか、急に言われても実感が湧かない。神秘工廠『ゼラ』に行けと言われたが、雇われの身だ。カイルの許可が出るだろうか? それは怪しい。
自分の世界は手の届く範囲だけで、それより向こうの出来事は透明の膜で隔てられている。観測することはできるが、触れることはできない。そんな余裕も無い。――まあ、触れられるとしても、そうしない可能性が高いのだが。アレクシアは平和主義を自称している。厄介事は御免だった。平穏であればあるほど好ましい。
本日のニュースです
犠牲は大きく、多くの都市や船が焼かれました
その損害は計り知れません
復興には100年とも1000年とも言われています
戦火の傷跡は大きく、我々はいま試されています
そこまで聞き流して、アレクシアはベッドサイドに置かれたラジオのスイッチを切る。金を掛けずに気を紛らわせることができるラジオは好きだったが、考え事をする時には向いていない。
入れ替わりで電子タブレットを手に取るとベッドに寝転び直し、それをしげしげと眺める。
アレクシアにとって、目下の自分事はこちらの方だった。
(相変わらずだな)
表示されているのはベルーガからの給与明細だった。
額面としては、企業やユニオン勤めのテイマーの相場より少し低いくらいだ。それに、この時世に給与が出るだけマシと言えなくもない。
問題はその下に書かれている、『仲介料』と『返済』の欄だ。
『仲介料』で給与の約半分、『返済』でその更に半分が差し引かれており、結果的にアレクシアの手元には4分の1ほどしか残らない。
アレクシアは、アッシュラッツ・ファクトリーに所属し、ベルーガへ配属されている。仕事は全てアッシュラッツから割り振られていて、『仲介料』はそういうことだ。
稼ぎの半分も持っていくのは暴利だ。正当ではない。もちろんアレクシアもそう思っている。それでもアッシュラッツを辞められないのは、『返済』の方にあった。
物心がついた時には、アレクシアはすでにアッシュラッツの管理下にあった。
孤児なのか、売られたのかは分からない。ずっと、"そういうもの"だと思っていたから、知ろうとも思わなかった。アッシュラッツから教えられるものが全てだった。
けれどあの日、あの時、知ってしまったのだ。外の世界のことを。目を逸らし続けていた、自分の置かれた状況を。向き合わざるを得なくなってしまった。
アッシュラッツを辞めたいと言ったアレクシアに請求されたのは、それまでの生活費、教育費、その他諸々を含んだ多額の身請け金。すぐに払えるものでは到底なく、分割で返し始めたのは17歳の頃だ。完済の目途は立たないまま、もう7年も経ってしまった。
電子タブレットを枕際に放って、アレクシアは目を閉じた。
(……そういえば、コールくんの借金はもうなくなるのか)
コールのアレクシアへの借金――激しく損壊した『クレオソート』と、コール自身の修理代。いくらかはベルーガが負担しているが、おおよそはアレクシアが持っていた。
返済に追われる自分が返済を迫るのもなんだか滑稽な話だった。というか、心情的にはとても嫌だった。アッシュラッツと同じようになってしまった、そんな心地。それでも金は必要だった。仕方がない。利子はほとんど請求していないから、それでゆるしてほしい。
借金を返済すれば、ベルーガで働く理由はなくなる。
その時、コールはどうするのだろう。
彼の腕ならもっと待遇の良い艦に乗れるだろうし、ヴォイド・テイマーとして一人でやっていくことだって不可能ではない。ベルーガの待遇、特に食事には常々不満を持っているし、残る可能性は極めて低いだろう。
そうしたら、アレクシアは僚機を探さなくてはならない。今更テイマーを下りることは難しそうだし、一人で戦場に出られるほど実力はなかった。
この状況下で新しい僚機は見つかるのか。見つかったとして、うまくやっていけるのか。食事はこだわるタイプだろうか。卓球に興味を示したりするだろうか。
そこまで考えて、アレクシアは気づいた。
最初こそコールを拾ったのは間違いだったと思っていたが、今ではそう思っていないらしい。
溜息。
コールがいなくなる。
それは少し、面倒臭いな、と思った。
◆9回更新の日記ログ
あらすじ:
ペンギン諸島に来たベルーガ一行は、艦長カイルの「温泉に入りてえ~!」という気紛れによりボロ温泉旅館に泊まることになった!
ガコン、と重みのある物が落ちる音。
アレクシアは自動販売機の取り出し口から、瓶に入ったコーヒー牛乳を掴み上げた。
"ゆ"と書かれた赤い暖簾をくぐり、脱衣所から待合室に出る。女湯と男湯に面した待合室には背の低い机と椅子が並び、壁際には自動販売機と、年季の入ったマッサージチェアが鎮座していた。
その待合室の真ん中で。
「……え、何? どしたの?」
コールが姿勢良く立ち、腰に手を当て堂々とコーヒー牛乳を飲んでいる。
なぜこんなところで。そんなに堂々と。アレクシアが思わず声を掛けると、「コーヒー牛乳を飲んでいる」とコールは事もなげに答えた。
「温泉でコーヒー牛乳を飲むときは、腰に手を当ててグッと飲むように言われた。それも瓶で……だ」
「コールくん、もうちょい人を疑うことを覚えた方がいいよ。特に艦長の言うことは」
カイル、というかベルーガの乗組員はコールのことを気に入っていた。彼の知識は妙に偏っている。その無い部分のことは嘘や冗談でも簡単に真に受け、すくすく吸収するから面白がられているのだ。
コールは、「そうなのか?」と眉を顰めた。アレクシアは近くの椅子に腰掛け、コーヒー牛乳の蓋を開けながら頷いた。
「そ。半分くらいは適当なこと言ってると思った方がいい。……いや、今回の場合は間違ってるわけでもないけどさあ。何だろ。別にほら、好きに飲んだらいいじゃん。そういう決まりがあるわけでもないし」
「決まりがあるわけではないのか」
「決まりではないねえ」
それを実証するように、アレクシアは椅子に座ってコーヒー牛乳を飲む。コールは、「なるほど」と一つ頷いた。
「次はビールを飲んでみるつもりだ。温泉といえばビールも間違いなのか?」
「それは合ってる。ペンギン諸島の特産じゃなかったっけ? いんじゃない、せっかくだし」
ペンギン諸島の名物、それはペンギンと温泉とビールだ。さっきまで入っていた露天風呂でも、ペンギンが寒さをものともせず歩き回っていた。ビールについては、食道楽のシリヤがうきうきと語っていたのを覚えている。
「満喫してるねえ、温泉」
コールは相変わらずの無表情だが、随分楽しんでいるように見えて――それを、どちらかというと好ましく思いながらアレクシアは言った。
しかし、コールは首を横に振る。
「満喫というほどではないが。温泉には入っていないし」
「そうなの? ……って、あー、そっか。無理か」
すぐに納得した様子でコールの義手をしげしげと見遣った。防水加工はされているだろうが、さすがに温泉では錆びそうだ。簡単に取り外しができるタイプでもないようだし、これでは難しい。
そう考えたところで、ふと、この旅館に来た時のことを思い出す。
「外に足湯なかったっけ? そっちならコールくんでもいけるんじゃない。それこそせっかくなんだし、行ってきたら」
確か、旅館のすぐ外に足湯があったはずだ。待合室から旅館の入り口に続く廊下を指さした。
「足湯。それならば入れるかもしれない」
「温泉に来て入らないのもね」
旅館はボロいが、温泉は温泉だ。入らないのはもったいない。
コールと一緒に廊下を渡る。アレクシアは足湯に興味がなかったが、単純に進行方向が同じだった。右手のガラス窓からは和風作りの庭が見える。こういうのをワビサビと言うんだったか。
「あれは」
「ん?」
不意にコールが立ち止まる。少し遅れてアレクシアも歩を止めると、そこは卓球コーナーの前だった。廊下の左手はいくつかの部屋と繋がっていて、他にも漫画コーナーや休憩室がある。
コールの視線は、卓球台にじっと向けられていた。
「あれが噂の卓球か」
「あー……かな? 卓球。よく知らないけど」
「温泉といえば卓球らしい。どうやら、ピンポンダマという物を打ち合って競うスポーツらしいが」
コールは卓球台に近づく。なんか行っちゃったよ。好奇心の塊か? 仕方なく、アレクシアも後を追う。
コールは早速、備え付けのピンポン球とラケットを手に持って眺めている。アレクシアも実物を見るのは初めてだ。
「ふーん、これがねえ……」
「試しにやってみようか」
「え? やるの?」
コールはアレクシアにラケットを差し出した。つい勢いに押されて受け取るのだが、
「……どうやって?」
「わからない」
ルールを知る者が――この場に居ないのである!!
アレクシアはふと、ラケットの色が裏表で違うことに気づいた。なんだこれは。裏表の概念があるのか? 続いて、台を見る。真ん中に張られたネットで二手に仕切られているようだ。
コールもラケットと球を手に持ったまま暫く黙り込んでいたが、やがて頷いた。
「やってみるか」
「まあ、いいけどさ……え、こっちに立てばいいんだよね? なんか仕切りあるし」
「仕切り……そういう見方もあるか」
卓球台の仕切りによって、陣地が分けられているのでは? そう当たりをつけ、アレクシアはコールの反対側に立った。ネットを挟んで、二人が向かい合う。
コールはボールを高く投げ、ラケットを振るった。
ブンッ!!
スカッ。
「……もう一回やったら」
「そうしよう」
コールは落ちた球を拾い、元の位置に戻った。同じように構え、球を高く投げる。ラケットを振ると今度は球を捉えた――が、台には入らず、アレクシアを通り越して飛んでいってしまった。
「思ったより難しいな」
アレクシアは球を拾い上げ、所定の位置に立つ。随分苦戦しているようだが、そんなに難しいのだろうか?
ボールをトス。ラケットを振る。スカッ。
「……難しいね。小さくない? ボール。あと、なんか軽いし」
「ああ、意外とコントロールが難しい。見た目より繊細な競技だ」
「うーん」
台上に転がったボールを回収、トス、空振り。
「……コールくん、どうぞ」
諦めて球を素手で投げた。コン、コンコン……ピンポン玉が台を跳ねる、独特な音が響く。
コールは手前に来たそれを掬い上げ、再び構えた。球を高く投げ、ラケットを振り――今度は上手くいった。アレクシア目掛けて打球が飛ぶ。
ものすごい速さで。
「うわっ」
思わず避けるも、球が頬を掠めた。コンッ! と壁に当たった球が跳ね返り、床を転がる。
球とラケット、それからコールを見比べて、
「あっぶな……ちょっと待って、これこういうゲームなの? 危なくない?」
「わからない」
「少なくとも人にぶつけるのは違うと思う」
「そうか」
そんなスポーツは嫌だ。憮然としたアレクシアに対し、コールは腕を組んで考え込む。
と、そこに別の客が卓球コーナーに入ってきた。雑談を交わしながら自然な流れで空いている卓球台の前に立ち、これまた自然に卓球を楽しみ始めた。
あれこそ正しい卓球作法では? 二人はその客を暫く眺めていた。「なるほど」とコールが呟き、「ほら」とアレクシアが言った。ぶつけてないじゃん。
「やっとこの仕切りの意味がわかってきた。なら、あまり力を入れ過ぎても駄目ということか」
「相手の陣地にバウンドさせて入れないと駄目っぽくない? そのまますっ飛ばしたらミスになりそう」
「そして……最初の打球は自分の陣地に入れてから」
とりあえず、実践あるのみ。コールは球を高く投げ、狙いを定めてラケットを振った。コンと球が自分の陣地で跳ね、相手の陣地で跳ねる。
アレクシアが構えた。この球を相手の陣地に返せばいい。
えいっ。
スカッ。
「……」
トスした球を打てなかった人間が、打ち入れられて跳ねる球を打ち返せるわけがなかった。
球を拾う、トス、また空振り。
「……何かコツとかある?」
「ボールをよく見る」
「見てたよ」
「ラケットを正確に振る」
「振ったし」
「力加減を間違えない」
「そもそも当たらないんだよね」
アレクシアは眉を顰める。
「全部やってるつもりなんだけどな~……」
ただの遊びだが、このまま打てないのも癪だった。また球をトスする。落ちてくるそれをよく見て、ラケットを丁寧に振って、
「あ」
当たった。コンッ、コン……コールの陣地に球が入る。
「ボールをよく見る。ラケットを正確に振る。力加減を間違えない」
コールは空中の球の芯を捉えるよう、ラケットをまっすぐ振った。コンッと小気味いい音を立て、アレクシアへの返球に成功する。
「えー、ボール……ラケット……」
返ってくるのが早い。ええいままよ。勢いでラケットを振るとなんとか返ったが、球はネットギリギリを通る返し辛い一打となった。
コールは咄嗟に手を伸ばす。寸でのところでラケットに当たったが、球は明後日の方に飛んでいってしまった。
「そういうやり方もあるのか。やるな、雇い主さん」
「え? あー……うん。狙った」
「意外とこういうスポーツをやるのも悪くない」
コールはそう言って、またサーブをする。
「……まあ、悪くはないね」
卓球コーナーには、暫くラリーの音が響いていた。
ペンギン諸島に来たベルーガ一行は、艦長カイルの「温泉に入りてえ~!」という気紛れによりボロ温泉旅館に泊まることになった!
ガコン、と重みのある物が落ちる音。
アレクシアは自動販売機の取り出し口から、瓶に入ったコーヒー牛乳を掴み上げた。
"ゆ"と書かれた赤い暖簾をくぐり、脱衣所から待合室に出る。女湯と男湯に面した待合室には背の低い机と椅子が並び、壁際には自動販売機と、年季の入ったマッサージチェアが鎮座していた。
その待合室の真ん中で。
「……え、何? どしたの?」
コールが姿勢良く立ち、腰に手を当て堂々とコーヒー牛乳を飲んでいる。
なぜこんなところで。そんなに堂々と。アレクシアが思わず声を掛けると、「コーヒー牛乳を飲んでいる」とコールは事もなげに答えた。
「温泉でコーヒー牛乳を飲むときは、腰に手を当ててグッと飲むように言われた。それも瓶で……だ」
「コールくん、もうちょい人を疑うことを覚えた方がいいよ。特に艦長の言うことは」
カイル、というかベルーガの乗組員はコールのことを気に入っていた。彼の知識は妙に偏っている。その無い部分のことは嘘や冗談でも簡単に真に受け、すくすく吸収するから面白がられているのだ。
コールは、「そうなのか?」と眉を顰めた。アレクシアは近くの椅子に腰掛け、コーヒー牛乳の蓋を開けながら頷いた。
「そ。半分くらいは適当なこと言ってると思った方がいい。……いや、今回の場合は間違ってるわけでもないけどさあ。何だろ。別にほら、好きに飲んだらいいじゃん。そういう決まりがあるわけでもないし」
「決まりがあるわけではないのか」
「決まりではないねえ」
それを実証するように、アレクシアは椅子に座ってコーヒー牛乳を飲む。コールは、「なるほど」と一つ頷いた。
「次はビールを飲んでみるつもりだ。温泉といえばビールも間違いなのか?」
「それは合ってる。ペンギン諸島の特産じゃなかったっけ? いんじゃない、せっかくだし」
ペンギン諸島の名物、それはペンギンと温泉とビールだ。さっきまで入っていた露天風呂でも、ペンギンが寒さをものともせず歩き回っていた。ビールについては、食道楽のシリヤがうきうきと語っていたのを覚えている。
「満喫してるねえ、温泉」
コールは相変わらずの無表情だが、随分楽しんでいるように見えて――それを、どちらかというと好ましく思いながらアレクシアは言った。
しかし、コールは首を横に振る。
「満喫というほどではないが。温泉には入っていないし」
「そうなの? ……って、あー、そっか。無理か」
すぐに納得した様子でコールの義手をしげしげと見遣った。防水加工はされているだろうが、さすがに温泉では錆びそうだ。簡単に取り外しができるタイプでもないようだし、これでは難しい。
そう考えたところで、ふと、この旅館に来た時のことを思い出す。
「外に足湯なかったっけ? そっちならコールくんでもいけるんじゃない。それこそせっかくなんだし、行ってきたら」
確か、旅館のすぐ外に足湯があったはずだ。待合室から旅館の入り口に続く廊下を指さした。
「足湯。それならば入れるかもしれない」
「温泉に来て入らないのもね」
旅館はボロいが、温泉は温泉だ。入らないのはもったいない。
コールと一緒に廊下を渡る。アレクシアは足湯に興味がなかったが、単純に進行方向が同じだった。右手のガラス窓からは和風作りの庭が見える。こういうのをワビサビと言うんだったか。
「あれは」
「ん?」
不意にコールが立ち止まる。少し遅れてアレクシアも歩を止めると、そこは卓球コーナーの前だった。廊下の左手はいくつかの部屋と繋がっていて、他にも漫画コーナーや休憩室がある。
コールの視線は、卓球台にじっと向けられていた。
「あれが噂の卓球か」
「あー……かな? 卓球。よく知らないけど」
「温泉といえば卓球らしい。どうやら、ピンポンダマという物を打ち合って競うスポーツらしいが」
コールは卓球台に近づく。なんか行っちゃったよ。好奇心の塊か? 仕方なく、アレクシアも後を追う。
コールは早速、備え付けのピンポン球とラケットを手に持って眺めている。アレクシアも実物を見るのは初めてだ。
「ふーん、これがねえ……」
「試しにやってみようか」
「え? やるの?」
コールはアレクシアにラケットを差し出した。つい勢いに押されて受け取るのだが、
「……どうやって?」
「わからない」
ルールを知る者が――この場に居ないのである!!
アレクシアはふと、ラケットの色が裏表で違うことに気づいた。なんだこれは。裏表の概念があるのか? 続いて、台を見る。真ん中に張られたネットで二手に仕切られているようだ。
コールもラケットと球を手に持ったまま暫く黙り込んでいたが、やがて頷いた。
「やってみるか」
「まあ、いいけどさ……え、こっちに立てばいいんだよね? なんか仕切りあるし」
「仕切り……そういう見方もあるか」
卓球台の仕切りによって、陣地が分けられているのでは? そう当たりをつけ、アレクシアはコールの反対側に立った。ネットを挟んで、二人が向かい合う。
コールはボールを高く投げ、ラケットを振るった。
ブンッ!!
スカッ。
「……もう一回やったら」
「そうしよう」
コールは落ちた球を拾い、元の位置に戻った。同じように構え、球を高く投げる。ラケットを振ると今度は球を捉えた――が、台には入らず、アレクシアを通り越して飛んでいってしまった。
「思ったより難しいな」
アレクシアは球を拾い上げ、所定の位置に立つ。随分苦戦しているようだが、そんなに難しいのだろうか?
ボールをトス。ラケットを振る。スカッ。
「……難しいね。小さくない? ボール。あと、なんか軽いし」
「ああ、意外とコントロールが難しい。見た目より繊細な競技だ」
「うーん」
台上に転がったボールを回収、トス、空振り。
「……コールくん、どうぞ」
諦めて球を素手で投げた。コン、コンコン……ピンポン玉が台を跳ねる、独特な音が響く。
コールは手前に来たそれを掬い上げ、再び構えた。球を高く投げ、ラケットを振り――今度は上手くいった。アレクシア目掛けて打球が飛ぶ。
ものすごい速さで。
「うわっ」
思わず避けるも、球が頬を掠めた。コンッ! と壁に当たった球が跳ね返り、床を転がる。
球とラケット、それからコールを見比べて、
「あっぶな……ちょっと待って、これこういうゲームなの? 危なくない?」
「わからない」
「少なくとも人にぶつけるのは違うと思う」
「そうか」
そんなスポーツは嫌だ。憮然としたアレクシアに対し、コールは腕を組んで考え込む。
と、そこに別の客が卓球コーナーに入ってきた。雑談を交わしながら自然な流れで空いている卓球台の前に立ち、これまた自然に卓球を楽しみ始めた。
あれこそ正しい卓球作法では? 二人はその客を暫く眺めていた。「なるほど」とコールが呟き、「ほら」とアレクシアが言った。ぶつけてないじゃん。
「やっとこの仕切りの意味がわかってきた。なら、あまり力を入れ過ぎても駄目ということか」
「相手の陣地にバウンドさせて入れないと駄目っぽくない? そのまますっ飛ばしたらミスになりそう」
「そして……最初の打球は自分の陣地に入れてから」
とりあえず、実践あるのみ。コールは球を高く投げ、狙いを定めてラケットを振った。コンと球が自分の陣地で跳ね、相手の陣地で跳ねる。
アレクシアが構えた。この球を相手の陣地に返せばいい。
えいっ。
スカッ。
「……」
トスした球を打てなかった人間が、打ち入れられて跳ねる球を打ち返せるわけがなかった。
球を拾う、トス、また空振り。
「……何かコツとかある?」
「ボールをよく見る」
「見てたよ」
「ラケットを正確に振る」
「振ったし」
「力加減を間違えない」
「そもそも当たらないんだよね」
アレクシアは眉を顰める。
「全部やってるつもりなんだけどな~……」
ただの遊びだが、このまま打てないのも癪だった。また球をトスする。落ちてくるそれをよく見て、ラケットを丁寧に振って、
「あ」
当たった。コンッ、コン……コールの陣地に球が入る。
「ボールをよく見る。ラケットを正確に振る。力加減を間違えない」
コールは空中の球の芯を捉えるよう、ラケットをまっすぐ振った。コンッと小気味いい音を立て、アレクシアへの返球に成功する。
「えー、ボール……ラケット……」
返ってくるのが早い。ええいままよ。勢いでラケットを振るとなんとか返ったが、球はネットギリギリを通る返し辛い一打となった。
コールは咄嗟に手を伸ばす。寸でのところでラケットに当たったが、球は明後日の方に飛んでいってしまった。
「そういうやり方もあるのか。やるな、雇い主さん」
「え? あー……うん。狙った」
「意外とこういうスポーツをやるのも悪くない」
コールはそう言って、またサーブをする。
「……まあ、悪くはないね」
卓球コーナーには、暫くラリーの音が響いていた。
◆8回更新の日記ログ
ウェイブが部屋を去ってから、ぎこちない沈黙が部屋を覆う。
暫くして、アレクシアは傷跡を庇うようおずおずと口を開いた。
「ごめん。ありがとう……」
立ち上がった状態のまま、コールはアレクシアへと振り返る。その表情は闖入者に相対する前と変わらない、いつもの無表情だ。
「今のは誰なんだ?」
「……」
コールの当然の問いに、アレクシアは口籠もった。彼女ももともと口数が多い方ではないが、黙り込むというのも稀なことだ。
「聞かない方がいいか」
「……いや、まあ、隠すことでもないんだけど」
とはいえ、さすがに説明しないのも何だ。歯切れが悪いながらも、アレクシアは言葉を選びながらぽつぽつと話し出す。
「私は……正確に言うと、ベルーガの所属じゃない。アッシュラッツ・ファクトリーっていう、グレムリンワーカーを派遣する組織があって、そこの所属」
【アッシュラッツ・ファクトリー】は、グレムリンテイマーやエンジニアなどを養成している組織だ。三大勢力から出資を受けて成り立っており、灰色の名を冠するに相応しい――実態はというと、【ベルーガ】が白く見えるくらいには限りなくブラックに近いのだが。
「で、今のが……まあ、上司みたいなもん」
そして先の男、ウェイブ・クローヴィンケルはアレクシアの管理者だ。アレクシアの他にも【アッシュラッツ・ファクトリー】から"商品"を与えられ、管理している。アレクシアを【ベルーガ】に寄越したのはウェイブだ。その関係で、艦長のカイルもウェイブとは面識がある。カイルの立場からすると、ウェイブからアレクシアを借りている形となるのだ。
本当は今日、アレクシアはウェイブから呼び出しを受けていた。特に何も言われなかったから、カイルが体よく断ってくれていたとばかり思ったのだが――とまで考えて、アレクシアは顔を歪ませる。
「嫌いなの、あの人」
感情に乏しい彼女にしては珍しく、明確な嫌悪感を持って、吐き捨てるように言った。
「私たちのこと、ただの道具としか思ってないから、嫌い」
恐らく。カイルはウェイブに、アレクシアは体調が悪くて面談に行けないと伝えている。
それを聞いて、わざわざ様子を見に来たのだろう。決して見舞いなんてものではなく、ただただ面白がり、嗜虐心を満たして、何なら祝福でもするために。
あの男は本当に趣味が悪い。壊された"商品"をアレクシアは何人も見てきた。それこそ、人間をただの道具――いや、ネズミくらいにしか思っていないのだ。
「そうか」
コールは少し考えるような素振りを見せ、真面目な顔――いつもの無表情を好意的解釈しているせいかもしれないが――でこう言った。
「要注意人物ってことか」
「……まあ、そういうこと。さすがに艦まで来ることは早々ないだろうけど。暇じゃないだろうに、何やってんだか」
コールの、ある種単純明快な解にアレクシアの表情から険が取れる。要注意人物。確かにそうだ。
「見つけたら今みたいに適当に追い払ってよ」
「分かった」
「いい返事だね」
「ありがとう」
コールの返事は妙に律儀なところがある。こうやって礼を言うだとか。それが一層、彼をよく分からなくしていた。
思考が逸れる。さっきの、嫌な男の顔がだんだんぼやけていく。どことなく安心感を覚えて、入れ替わりのように眠気がやってくる。
「ごめん。ちょっと疲れたから寝る」
「ああ。お大事に」
コールはそう言い、部屋から出ていった。オートロックが掛かって、部屋にはアレクシア一人。
毛布を被って、目を閉じる。眠気が緩やかに意識を遠のかせる。
「……ありがとね、コールくん」
アレクシアは、夢うつつにそう呟いた。
暫くして、アレクシアは傷跡を庇うようおずおずと口を開いた。
「ごめん。ありがとう……」
立ち上がった状態のまま、コールはアレクシアへと振り返る。その表情は闖入者に相対する前と変わらない、いつもの無表情だ。
「今のは誰なんだ?」
「……」
コールの当然の問いに、アレクシアは口籠もった。彼女ももともと口数が多い方ではないが、黙り込むというのも稀なことだ。
「聞かない方がいいか」
「……いや、まあ、隠すことでもないんだけど」
とはいえ、さすがに説明しないのも何だ。歯切れが悪いながらも、アレクシアは言葉を選びながらぽつぽつと話し出す。
「私は……正確に言うと、ベルーガの所属じゃない。アッシュラッツ・ファクトリーっていう、グレムリンワーカーを派遣する組織があって、そこの所属」
【アッシュラッツ・ファクトリー】は、グレムリンテイマーやエンジニアなどを養成している組織だ。三大勢力から出資を受けて成り立っており、灰色の名を冠するに相応しい――実態はというと、【ベルーガ】が白く見えるくらいには限りなくブラックに近いのだが。
「で、今のが……まあ、上司みたいなもん」
そして先の男、ウェイブ・クローヴィンケルはアレクシアの管理者だ。アレクシアの他にも【アッシュラッツ・ファクトリー】から"商品"を与えられ、管理している。アレクシアを【ベルーガ】に寄越したのはウェイブだ。その関係で、艦長のカイルもウェイブとは面識がある。カイルの立場からすると、ウェイブからアレクシアを借りている形となるのだ。
本当は今日、アレクシアはウェイブから呼び出しを受けていた。特に何も言われなかったから、カイルが体よく断ってくれていたとばかり思ったのだが――とまで考えて、アレクシアは顔を歪ませる。
「嫌いなの、あの人」
感情に乏しい彼女にしては珍しく、明確な嫌悪感を持って、吐き捨てるように言った。
「私たちのこと、ただの道具としか思ってないから、嫌い」
恐らく。カイルはウェイブに、アレクシアは体調が悪くて面談に行けないと伝えている。
それを聞いて、わざわざ様子を見に来たのだろう。決して見舞いなんてものではなく、ただただ面白がり、嗜虐心を満たして、何なら祝福でもするために。
あの男は本当に趣味が悪い。壊された"商品"をアレクシアは何人も見てきた。それこそ、人間をただの道具――いや、ネズミくらいにしか思っていないのだ。
「そうか」
コールは少し考えるような素振りを見せ、真面目な顔――いつもの無表情を好意的解釈しているせいかもしれないが――でこう言った。
「要注意人物ってことか」
「……まあ、そういうこと。さすがに艦まで来ることは早々ないだろうけど。暇じゃないだろうに、何やってんだか」
コールの、ある種単純明快な解にアレクシアの表情から険が取れる。要注意人物。確かにそうだ。
「見つけたら今みたいに適当に追い払ってよ」
「分かった」
「いい返事だね」
「ありがとう」
コールの返事は妙に律儀なところがある。こうやって礼を言うだとか。それが一層、彼をよく分からなくしていた。
思考が逸れる。さっきの、嫌な男の顔がだんだんぼやけていく。どことなく安心感を覚えて、入れ替わりのように眠気がやってくる。
「ごめん。ちょっと疲れたから寝る」
「ああ。お大事に」
コールはそう言い、部屋から出ていった。オートロックが掛かって、部屋にはアレクシア一人。
毛布を被って、目を閉じる。眠気が緩やかに意識を遠のかせる。
「……ありがとね、コールくん」
アレクシアは、夢うつつにそう呟いた。
◆7回更新の日記ログ
空を見上げている。
「本当の空は青いんだぜ」
そう聞いた時は、何を言っているんだ、空は赤いものだろうと鼻で笑ったものだった。
けれど、今見上げている空は塵どころか雲一つなく晴れ晴れと青く、その下に広がる海もまた吸い込まれそうなほど青い。
こんな世界があるとは思いもしなかった。
「来てよかっただろ」
隣に立つ少年が誇らしげに笑った。
その顔を見て、薄らと抱いていた違和感が確かなものとなる。
ああ、これは夢だ。
なんてむごい。
「……あー……」
狭い部屋に、寝起きで掠れた呻き声が弱々しく響く。体調が悪いのに夢見まで悪く、心身ともに最悪だ。
勘弁してほしい。そう思いながら、ベッドの中で目を覚ましたアレクシアは、身体を丸めるように体勢を変えた。
ここのところの無理が祟ってか、彼女は体調を崩していた。が、もちろんそれですぐ休めるほどベルーガの人員は潤沢ではなく、昨日も微熱を気のせいとして働いていた。いつもならそれでもどうにかなるのだが、今朝起きたらびっくりするほどの高熱があり、さすがに療養することとなった。『サイレント・リップルス』のフレーム換装の他、タワー寄港に伴う仕事が山積みだったが、その辺はどうにかしてくれるらしい。
寝直し、目覚めた今もまだ身体が熱く、怠く、しんどい。喉も乾いたが耐えきれない程ではなく、起き上がる方が億劫なのでそのまま毛布を被り直した。なるべく何も考えないようにして、目を瞑り、耐えるように時間が過ぎるのを待つ。
暫くそうしていたら、コンコンとドアをノックする音がした――が、聞き間違いということにして無視を決め込む。
コンコン。
コンコンコン。
コンコンコンコン。
観念して、のろのろと布団から這い出る。
いったい誰だこんな時に。当然着替える元気はなく、寝間着のままドアを開けた。
「……どしたの」
「見舞いにきた」
紙袋を小脇に抱えたコールは、常と変わらない無表情でそう言った。
見舞いにきた。アレクシアはその言葉を、熱っぽい頭でじわじわと咀嚼する。寝込んでいる自分を、コールくんが、見舞いにきた。らしい。……いや、見舞い? コールくんが?
「えー……と、はあ、どうぞ」
「お邪魔します」
「散らかってますが……」
意外だ。そんなタイプだったのか。そう思いつつ、アレクシアは部屋の奥のベッドに座り、コールは壁際の机の前にある椅子に座らせる。艦の中の居住スペースの広さはたかが知れていて、人間が二人入るとそれなりに圧迫感がある。
コールは机上に紙袋を置き、
「見舞いの品を持ってきた」
と、中からりんごと紙皿、そしてナイフを取り出した。
アレクシアは目を瞬かせ、「りんごだ」と呟いた。コールは、もっともらしく頷いた。
「病人にはりんごと決まっている」
「よく買うお金あったね」
「ベルーガの買い出し分から持ってきた」
「横領じゃん」
「そうなのか?」
「多分。……まあいっか」
このブラック艦のブラック労働で体調を崩したことは間違いないのだから、そのくらい問題ないだろう。コールもまったく気にしていないようだし、そういうことにする。
コールはりんごとナイフをそれぞれ手に持ちながら、「体調は?」と尋ねた。
「まだ熱っぽいけど、朝よりはマシ」
「それは良かった」
りんごのへたをくり抜き、八等分。種の部分も切り落とす。皮は剥かないのかな、とアレクシアが思った矢先、コールは皮と身の間にナイフを入れ、浮かせた皮に三角の切れ込みを入れた。
あっという間に、いわゆる、うさぎりんごが出来上がる。
「どうぞ」
「……ありがと」
アレクシアは八羽のうさぎりんごが乗せられた皿を受け取る。何でこの形にしたんだろう。いささか躊躇った後、一番手前のうさぎの尻から齧った。
瑞々しい果実から甘味と、微かな酸味が口の中に広がる。
「おいしい」
ぽつんとアレクシアは呟いた。
そういえば、りんごは好きだった。すっかり忘れていたが、そうだ。昔は好んで食べていた。
いや、忘れていたというか――思い出さないようにしていた。
さっきの夢といい、りんごといい、今日はそういう日なのかもしれない。半ば諦めるような気持ちになりつつ、それを表には出さないで、アレクシアはりんごからコールに視線を移した。
「コールくんは食べないの」
「食べない」
「りんご嫌い?」
「いや、好きだ」
「じゃあ食べなよ」
コールは少し間を置いてから、「わかった」と答えた。皿に手を伸ばして、一羽が丸ごと口の中に放り込まれる。
「なんで遠慮したのさ」
「病人じゃないから」
「……変なの」
コールは食べることが好きだ、とアレクシアは思っている。少なくとも、こだわりが強いは間違いない。それなのに、病人じゃないからという理由で遠慮をした様がどうにもおかしくて、少しだけ表情が緩む。
それから、タワーでの補給の話やら、艦の様子やらの話をコールから聞きつつ、二人でりんごを食べた。
アレクシアが最後の一羽に手を伸ばした、ちょうどその時だった。
コンコン、とまたドアをノックする音。コールの視線がアレクシアに向いて、彼女は首を横に振った。心当たりがない。
急かすようなノックの音が続く。
立ち上がろうとしたアレクシアを片手で制して、コールが入り口に向かい、ドアを開ける。
「……おや、ここはアレクシアの部屋と聞いたのですが。貴方は?」
そこには、作り物めいて見える程に整った相貌の男がいた。
ベルーガの乗組員ではない。コールは僅かに眉を寄せる。
「どちら様ですか?」
「これは失敬」
男はコールを見下ろし、口の両端を持ち上げて綺麗に笑みを作った。
「ウェイブ・クローヴィンケルといいます。アレクシアに用事が。……ああ、奥にいるんですね」
ウェイブと名乗る男は扉を広く引いて、コールに構わず部屋の中に入った。コールは押されるような形で部屋の奥に行って、ベッドに座ったままのアレクシアの前に立つ格好になる。
それを見たウェイブはコールに、あくまでにこやかに言った。
「彼女と二人で話したいので、少し席を外してくれませんか」
コールは、そこで初めてアレクシアを見た。
今まで見たことのない、ひどく狼狽した表情をしている。
「どうする?」
そう訊くも、返事はない。考えあぐねたコールがひとまずウェイブに向き直ると、ぐいと後ろから引っ張られた。俯きがちで表情は窺いづらく、今なお言葉もないが、「行かないで」と言わんばかりにアレクシアがシャツの背中側を掴んでいる。
その様子を見て、コールはウェイブに言った。
「体調が悪いから無理だ。熱がある」
ウェイブは表情を変えずに、話しているコールではなくアレクシアへ目を向ける。
なめるように視線を這わせて、それから、おかしそうに笑った。
「わかりました、出直しましょう」
すっと身を引いて、部屋を出る。扉を閉める間際、彼は笑顔で言った。
「また連絡しますよ、アレクシア」
その言葉は、いやにじとりと響いた。
「本当の空は青いんだぜ」
そう聞いた時は、何を言っているんだ、空は赤いものだろうと鼻で笑ったものだった。
けれど、今見上げている空は塵どころか雲一つなく晴れ晴れと青く、その下に広がる海もまた吸い込まれそうなほど青い。
こんな世界があるとは思いもしなかった。
「来てよかっただろ」
隣に立つ少年が誇らしげに笑った。
その顔を見て、薄らと抱いていた違和感が確かなものとなる。
ああ、これは夢だ。
なんてむごい。
「……あー……」
狭い部屋に、寝起きで掠れた呻き声が弱々しく響く。体調が悪いのに夢見まで悪く、心身ともに最悪だ。
勘弁してほしい。そう思いながら、ベッドの中で目を覚ましたアレクシアは、身体を丸めるように体勢を変えた。
ここのところの無理が祟ってか、彼女は体調を崩していた。が、もちろんそれですぐ休めるほどベルーガの人員は潤沢ではなく、昨日も微熱を気のせいとして働いていた。いつもならそれでもどうにかなるのだが、今朝起きたらびっくりするほどの高熱があり、さすがに療養することとなった。『サイレント・リップルス』のフレーム換装の他、タワー寄港に伴う仕事が山積みだったが、その辺はどうにかしてくれるらしい。
寝直し、目覚めた今もまだ身体が熱く、怠く、しんどい。喉も乾いたが耐えきれない程ではなく、起き上がる方が億劫なのでそのまま毛布を被り直した。なるべく何も考えないようにして、目を瞑り、耐えるように時間が過ぎるのを待つ。
暫くそうしていたら、コンコンとドアをノックする音がした――が、聞き間違いということにして無視を決め込む。
コンコン。
コンコンコン。
コンコンコンコン。
観念して、のろのろと布団から這い出る。
いったい誰だこんな時に。当然着替える元気はなく、寝間着のままドアを開けた。
「……どしたの」
「見舞いにきた」
紙袋を小脇に抱えたコールは、常と変わらない無表情でそう言った。
見舞いにきた。アレクシアはその言葉を、熱っぽい頭でじわじわと咀嚼する。寝込んでいる自分を、コールくんが、見舞いにきた。らしい。……いや、見舞い? コールくんが?
「えー……と、はあ、どうぞ」
「お邪魔します」
「散らかってますが……」
意外だ。そんなタイプだったのか。そう思いつつ、アレクシアは部屋の奥のベッドに座り、コールは壁際の机の前にある椅子に座らせる。艦の中の居住スペースの広さはたかが知れていて、人間が二人入るとそれなりに圧迫感がある。
コールは机上に紙袋を置き、
「見舞いの品を持ってきた」
と、中からりんごと紙皿、そしてナイフを取り出した。
アレクシアは目を瞬かせ、「りんごだ」と呟いた。コールは、もっともらしく頷いた。
「病人にはりんごと決まっている」
「よく買うお金あったね」
「ベルーガの買い出し分から持ってきた」
「横領じゃん」
「そうなのか?」
「多分。……まあいっか」
このブラック艦のブラック労働で体調を崩したことは間違いないのだから、そのくらい問題ないだろう。コールもまったく気にしていないようだし、そういうことにする。
コールはりんごとナイフをそれぞれ手に持ちながら、「体調は?」と尋ねた。
「まだ熱っぽいけど、朝よりはマシ」
「それは良かった」
りんごのへたをくり抜き、八等分。種の部分も切り落とす。皮は剥かないのかな、とアレクシアが思った矢先、コールは皮と身の間にナイフを入れ、浮かせた皮に三角の切れ込みを入れた。
あっという間に、いわゆる、うさぎりんごが出来上がる。
「どうぞ」
「……ありがと」
アレクシアは八羽のうさぎりんごが乗せられた皿を受け取る。何でこの形にしたんだろう。いささか躊躇った後、一番手前のうさぎの尻から齧った。
瑞々しい果実から甘味と、微かな酸味が口の中に広がる。
「おいしい」
ぽつんとアレクシアは呟いた。
そういえば、りんごは好きだった。すっかり忘れていたが、そうだ。昔は好んで食べていた。
いや、忘れていたというか――思い出さないようにしていた。
さっきの夢といい、りんごといい、今日はそういう日なのかもしれない。半ば諦めるような気持ちになりつつ、それを表には出さないで、アレクシアはりんごからコールに視線を移した。
「コールくんは食べないの」
「食べない」
「りんご嫌い?」
「いや、好きだ」
「じゃあ食べなよ」
コールは少し間を置いてから、「わかった」と答えた。皿に手を伸ばして、一羽が丸ごと口の中に放り込まれる。
「なんで遠慮したのさ」
「病人じゃないから」
「……変なの」
コールは食べることが好きだ、とアレクシアは思っている。少なくとも、こだわりが強いは間違いない。それなのに、病人じゃないからという理由で遠慮をした様がどうにもおかしくて、少しだけ表情が緩む。
それから、タワーでの補給の話やら、艦の様子やらの話をコールから聞きつつ、二人でりんごを食べた。
アレクシアが最後の一羽に手を伸ばした、ちょうどその時だった。
コンコン、とまたドアをノックする音。コールの視線がアレクシアに向いて、彼女は首を横に振った。心当たりがない。
急かすようなノックの音が続く。
立ち上がろうとしたアレクシアを片手で制して、コールが入り口に向かい、ドアを開ける。
「……おや、ここはアレクシアの部屋と聞いたのですが。貴方は?」
そこには、作り物めいて見える程に整った相貌の男がいた。
ベルーガの乗組員ではない。コールは僅かに眉を寄せる。
「どちら様ですか?」
「これは失敬」
男はコールを見下ろし、口の両端を持ち上げて綺麗に笑みを作った。
「ウェイブ・クローヴィンケルといいます。アレクシアに用事が。……ああ、奥にいるんですね」
ウェイブと名乗る男は扉を広く引いて、コールに構わず部屋の中に入った。コールは押されるような形で部屋の奥に行って、ベッドに座ったままのアレクシアの前に立つ格好になる。
それを見たウェイブはコールに、あくまでにこやかに言った。
「彼女と二人で話したいので、少し席を外してくれませんか」
コールは、そこで初めてアレクシアを見た。
今まで見たことのない、ひどく狼狽した表情をしている。
「どうする?」
そう訊くも、返事はない。考えあぐねたコールがひとまずウェイブに向き直ると、ぐいと後ろから引っ張られた。俯きがちで表情は窺いづらく、今なお言葉もないが、「行かないで」と言わんばかりにアレクシアがシャツの背中側を掴んでいる。
その様子を見て、コールはウェイブに言った。
「体調が悪いから無理だ。熱がある」
ウェイブは表情を変えずに、話しているコールではなくアレクシアへ目を向ける。
なめるように視線を這わせて、それから、おかしそうに笑った。
「わかりました、出直しましょう」
すっと身を引いて、部屋を出る。扉を閉める間際、彼は笑顔で言った。
「また連絡しますよ、アレクシア」
その言葉は、いやにじとりと響いた。
◆6回更新の日記ログ
「はい、割増賃金」
珍しく、コールが驚いたような表情でこちらを見てくる。
アレクシアは丸テーブルの上、ちょうどコールの座る正面にバイオコーヒー入りのマグカップを置いた。談話室に彼がいるのを見かけて、わざわざ食堂で淹れてきたものだ。
「奢りか」
「そ」
流れでコールの斜め前に座りながら、アレクシアは続けて言う。
「まあ、今回の件は感謝してるんだよ。私のせいじゃないとはいえ、コールくんに負担かけてるのは事実なんだから」
『クレオソート』とアサルト・フレームの相性は良かったらしい。新フレームでの初めての戦闘は、つつがなく終わっていた。
心配事の96%は実際に起こらない、と聞いたことがある。アレクシアの心配も杞憂に終わったわけだ。『サイレント・リップルス』の方は最低限の働きはしたものの戦果は上がらず、グレイヴネットのテイマーランキングには掠りもしなくなったが、それは彼女にとって些事だ。むしろ、今回のランキングには『ナイトフライヤー』やベルゼリア、イライアといった最近ユニオンに加入した面々の名前が多く載っていて、スカウトマンとしての手腕に我ながら感心したくらいだ。
そうやって少し気分を良くしたものだから、今回くらいは労ってもいいかな、と思った結果がこのバイオコーヒーだった。コールは知らない――にしても察してそうだが、アレクシアが人に奢るというのは珍しい。虚空領域に晴れ間が覗くくらいの希少さがある。
コールは受け取ったマグカップを少し眺めてから、口を付けた。表情こそ変わらないが不味くはなかったようで、そのまま二口目。
「やはりコーヒーは美味い」
「好きなんだ」
「嫌いじゃない」
「そりゃ良かった」
コールは自分のことをあまり話さない。アレクシアも人のことは言えないが、彼について知っていることは金がないこと、テイマーとしてはそれなりに働くこと、文句と屁理屈が多いこと、黙っていれば顔は悪くないこと、そのくらいだ。コーヒーが好きなのは今知った。知らなかったのに持ってきたのは、飲まないなら自分が飲めばいいと思っていたからだ。
コールはマグカップをテーブルに置いた。先の戦闘の件に話が戻る。
「新フレームとどう付き合っていくかはこれから考えるとして、戦えないことはなさそうだ」
「だね。でもレーダーが使えないのはやっぱり痛いなー。私はフレームを戻すけど、コールくんは?」
真紅工廠【スルト】での一件に責任を感じたシリヤの迅速で懸命な調べによると、タワー港湾区でラスト・フレームに戻せるらしい。ついでに、アレクシアの機体に合いそうなフレーム――ストレイキャット・フレームが青花工廠【アネモネ】で作られているという情報を得たので、当面の目的地はそこだ。悪鬼巡洋艦【ベルーガ】は今、虚空領域の北へ向かっている。
コールは、アレクシアの問いかけに首を横に振った。
「とりあえず、俺はこのままで行こうと思う」
「そっちは悪くなさそうだったしね。いいんじゃない」
コールが強くなればアレクシアは楽になる。願ってもないことだ。この調子でどんどん強くなってほしい。
そんなことを考えていたら、
『アレクシア・エコーズ。アレクシア・エコーズ。至急艦長室まで。繰り返す。アレクシア・エコーズ……』
自分を呼ぶ、艦内放送が流れる。
コールはアレクシアをちらと見た。
「何かトラブルか?」
「かも。……あーはいはい、今行きますよって」
繰り返される呼び出しに、取り繕う素振りすらなくアレクシアはかったるそうに腰を上げた。ひらひらと手を振って、そのまま談話室を出る。
ベルーガは全体的に雑だ。呼び出しにしたって、『エコーズ! ちょっと艦長室まで来い!』とか、『ターナー、今日の掃除当番はお前だ忘れてんな! 速やかに取り掛かれ!』とか、普段はそういう感じだ。
だから、カイルが妙に堅苦しい呼び方をする時は、ほとんどの場合が悪い報せだった。
***
ノックもおざなりに、アレクシアは艦長室の扉を開く。
中ではカイルが、私財を投げ打ったらしい高級ソファに座って彼女を待っていた。
「何ですか。優秀なテイマーをスカウトした表彰でもしてくれるんで?」
「"鼠"からだ」
その単語を聞いた途端、アレクシアの表情が険しくなる。
「……この前しましたよね、定期連絡」
「それがなあ。先方がどうしても話したいだと」
カイルもカイルで顔を顰めながら、机上にあるレトロな電話型の音声通信用グレイヴネット回線を指した。なお、これも私財投資の一環らしい。
彼に文句を垂れても仕方がないことを分かっていて、しかしそれで気分が乗るわけもなく、アレクシアは渋々と言った態で受話器を上げた。
「先日の報告に不備でもありました?」
『いや、そんなことは。何でもタワーに寄るらしいじゃないか。直接顔を合わせておきたいと思ってね』
「……私のグレムリンのフレーム換装のためです。自由にできる時間は少ないので、難しいと思いますが」
『ハワードには君の予定を空けるよう言っておいた』
「……」
カイルへの根回しは済んでいるらしい。逃げ道はとうに塞がれていた。ちらりと彼を横目で見ると、両手を上げている。お手上げのポーズだ。
電話をかけてきた相手は、尚も続けて言う。
『商品の状態を把握しておくのは管理者として当然の責務だろう? そして、君の責務は私の命令に応じることだ』
「……分かりました。日時はメールで頂けますか。これで用件は終わりですか?」
『ああ。それでは、楽しみにしているよ』
そこで音声が途切れた。
アレクシアは受話器を元に戻して、
「……最ッ悪だな……」
つい、低く言葉が漏れ出る。
カイルもいるがそんなことに構ってはいられなかった。胸に渦巻く嫌悪感を少しでも吐き出したかった。
「……艦長。煙草ありますか」
「待ってな」
カイルは暫く戸棚の中を探して、くしゃくしゃになった箱とポケットライターをアレクシアへと差し出した。
「ほれ」
「給料から引いといてください」
「奢りだ」
「……ありがとうございます」
アレクシアはカイルに頭を下げて、俯きがちに艦長室を後にした。
第二甲板、グレムリンドック奥の多目的倉庫。あまり人も訪れない場所で、煙草を吸う時は大体ここに来る。
エアフィルターの下で、壁にもたれながら粗末な葉巻を口に加えた。ライターで火を点ける。点かない。湿気ているのだろう。よくあることだが、苛立ちを覚える。もう一度フリント・ホイールを強く押し込む……薄暗い倉庫の中で、頼りない橙色が灯った。ようやく葉巻の先端がちりちりと熱を帯び、奇妙な色の煙が漂う。
息を大きく吸い込んで、大きく吐いた。
背中を壁に這わせるように、ずるずるとしゃがみ込む。
「……最悪。最悪、さいあく」
言葉にすれば、いくらか無くなってはくれないだろうか。無駄な足掻きだと分かっていながら、言わずにはいられなかった。
――例えばの話。フィルタースーツを着ずにダスト・デッキに出る。
そうすると即死だ。
いっそタワーに着く前に死んでやろうか、と考える。
でも、それはできない。一時の衝動に身を任せてはいけない。アレクシアはよく知っている。
今日もまた、勝利したのは理性だ。もう一度吐き出した煙は、抵抗にすらならなかった。
珍しく、コールが驚いたような表情でこちらを見てくる。
アレクシアは丸テーブルの上、ちょうどコールの座る正面にバイオコーヒー入りのマグカップを置いた。談話室に彼がいるのを見かけて、わざわざ食堂で淹れてきたものだ。
「奢りか」
「そ」
流れでコールの斜め前に座りながら、アレクシアは続けて言う。
「まあ、今回の件は感謝してるんだよ。私のせいじゃないとはいえ、コールくんに負担かけてるのは事実なんだから」
『クレオソート』とアサルト・フレームの相性は良かったらしい。新フレームでの初めての戦闘は、つつがなく終わっていた。
心配事の96%は実際に起こらない、と聞いたことがある。アレクシアの心配も杞憂に終わったわけだ。『サイレント・リップルス』の方は最低限の働きはしたものの戦果は上がらず、グレイヴネットのテイマーランキングには掠りもしなくなったが、それは彼女にとって些事だ。むしろ、今回のランキングには『ナイトフライヤー』やベルゼリア、イライアといった最近ユニオンに加入した面々の名前が多く載っていて、スカウトマンとしての手腕に我ながら感心したくらいだ。
そうやって少し気分を良くしたものだから、今回くらいは労ってもいいかな、と思った結果がこのバイオコーヒーだった。コールは知らない――にしても察してそうだが、アレクシアが人に奢るというのは珍しい。虚空領域に晴れ間が覗くくらいの希少さがある。
コールは受け取ったマグカップを少し眺めてから、口を付けた。表情こそ変わらないが不味くはなかったようで、そのまま二口目。
「やはりコーヒーは美味い」
「好きなんだ」
「嫌いじゃない」
「そりゃ良かった」
コールは自分のことをあまり話さない。アレクシアも人のことは言えないが、彼について知っていることは金がないこと、テイマーとしてはそれなりに働くこと、文句と屁理屈が多いこと、黙っていれば顔は悪くないこと、そのくらいだ。コーヒーが好きなのは今知った。知らなかったのに持ってきたのは、飲まないなら自分が飲めばいいと思っていたからだ。
コールはマグカップをテーブルに置いた。先の戦闘の件に話が戻る。
「新フレームとどう付き合っていくかはこれから考えるとして、戦えないことはなさそうだ」
「だね。でもレーダーが使えないのはやっぱり痛いなー。私はフレームを戻すけど、コールくんは?」
真紅工廠【スルト】での一件に責任を感じたシリヤの迅速で懸命な調べによると、タワー港湾区でラスト・フレームに戻せるらしい。ついでに、アレクシアの機体に合いそうなフレーム――ストレイキャット・フレームが青花工廠【アネモネ】で作られているという情報を得たので、当面の目的地はそこだ。悪鬼巡洋艦【ベルーガ】は今、虚空領域の北へ向かっている。
コールは、アレクシアの問いかけに首を横に振った。
「とりあえず、俺はこのままで行こうと思う」
「そっちは悪くなさそうだったしね。いいんじゃない」
コールが強くなればアレクシアは楽になる。願ってもないことだ。この調子でどんどん強くなってほしい。
そんなことを考えていたら、
『アレクシア・エコーズ。アレクシア・エコーズ。至急艦長室まで。繰り返す。アレクシア・エコーズ……』
自分を呼ぶ、艦内放送が流れる。
コールはアレクシアをちらと見た。
「何かトラブルか?」
「かも。……あーはいはい、今行きますよって」
繰り返される呼び出しに、取り繕う素振りすらなくアレクシアはかったるそうに腰を上げた。ひらひらと手を振って、そのまま談話室を出る。
ベルーガは全体的に雑だ。呼び出しにしたって、『エコーズ! ちょっと艦長室まで来い!』とか、『ターナー、今日の掃除当番はお前だ忘れてんな! 速やかに取り掛かれ!』とか、普段はそういう感じだ。
だから、カイルが妙に堅苦しい呼び方をする時は、ほとんどの場合が悪い報せだった。
***
ノックもおざなりに、アレクシアは艦長室の扉を開く。
中ではカイルが、私財を投げ打ったらしい高級ソファに座って彼女を待っていた。
「何ですか。優秀なテイマーをスカウトした表彰でもしてくれるんで?」
「"鼠"からだ」
その単語を聞いた途端、アレクシアの表情が険しくなる。
「……この前しましたよね、定期連絡」
「それがなあ。先方がどうしても話したいだと」
カイルもカイルで顔を顰めながら、机上にあるレトロな電話型の音声通信用グレイヴネット回線を指した。なお、これも私財投資の一環らしい。
彼に文句を垂れても仕方がないことを分かっていて、しかしそれで気分が乗るわけもなく、アレクシアは渋々と言った態で受話器を上げた。
「先日の報告に不備でもありました?」
『いや、そんなことは。何でもタワーに寄るらしいじゃないか。直接顔を合わせておきたいと思ってね』
「……私のグレムリンのフレーム換装のためです。自由にできる時間は少ないので、難しいと思いますが」
『ハワードには君の予定を空けるよう言っておいた』
「……」
カイルへの根回しは済んでいるらしい。逃げ道はとうに塞がれていた。ちらりと彼を横目で見ると、両手を上げている。お手上げのポーズだ。
電話をかけてきた相手は、尚も続けて言う。
『商品の状態を把握しておくのは管理者として当然の責務だろう? そして、君の責務は私の命令に応じることだ』
「……分かりました。日時はメールで頂けますか。これで用件は終わりですか?」
『ああ。それでは、楽しみにしているよ』
そこで音声が途切れた。
アレクシアは受話器を元に戻して、
「……最ッ悪だな……」
つい、低く言葉が漏れ出る。
カイルもいるがそんなことに構ってはいられなかった。胸に渦巻く嫌悪感を少しでも吐き出したかった。
「……艦長。煙草ありますか」
「待ってな」
カイルは暫く戸棚の中を探して、くしゃくしゃになった箱とポケットライターをアレクシアへと差し出した。
「ほれ」
「給料から引いといてください」
「奢りだ」
「……ありがとうございます」
アレクシアはカイルに頭を下げて、俯きがちに艦長室を後にした。
第二甲板、グレムリンドック奥の多目的倉庫。あまり人も訪れない場所で、煙草を吸う時は大体ここに来る。
エアフィルターの下で、壁にもたれながら粗末な葉巻を口に加えた。ライターで火を点ける。点かない。湿気ているのだろう。よくあることだが、苛立ちを覚える。もう一度フリント・ホイールを強く押し込む……薄暗い倉庫の中で、頼りない橙色が灯った。ようやく葉巻の先端がちりちりと熱を帯び、奇妙な色の煙が漂う。
息を大きく吸い込んで、大きく吐いた。
背中を壁に這わせるように、ずるずるとしゃがみ込む。
「……最悪。最悪、さいあく」
言葉にすれば、いくらか無くなってはくれないだろうか。無駄な足掻きだと分かっていながら、言わずにはいられなかった。
――例えばの話。フィルタースーツを着ずにダスト・デッキに出る。
そうすると即死だ。
いっそタワーに着く前に死んでやろうか、と考える。
でも、それはできない。一時の衝動に身を任せてはいけない。アレクシアはよく知っている。
今日もまた、勝利したのは理性だ。もう一度吐き出した煙は、抵抗にすらならなかった。
◆5回更新の日記ログ
どうしてコール=ターナーを拾ったか。
そう聞かれると困る。
明確な理由はない。強いて言うなら、あの廃工場でコールを見つけた時、このまま見捨てたら寝覚めが悪くなりそうな気がした。
それに、いつ滅ぶとも知れない世界なのだから、少しくらいは善いことをしてもいいか、と思った。
どちらにせよ気分の問題だった。
そして今もなお、意外と世界は滅びず、その気まぐれのツケを支払っている。
視界を覆う粉塵。
それを切り裂くように、一筋の光が閃いた。
(やればできるじゃん)
ヒートストリングの高熱線が、中量格闘機『金砕棒』を両断した。『クレオソート』は一瞥もせず、ブースターを吹かして次の獲物へ狙いを定める。
繰り返すが、アレクシアはグレムリンエンジニアだ。支援ならまだしも、戦闘能力自体を期待されても困る。今日みたいに本業のコールが張り切るべきだし、景気よく敵機を墜としていく様を見ると少しは拾った甲斐を感じるものだ。
「……だぁから、あっち狙ってくれないかなー」
つんざくようなアラート音が操縦棺内に響いた。レーダーが『サイレント・リップルス』に接近する敵機を捉え、アレクシアはレバーを引いて機体を急旋回させる。
左方に掃海艇『みずすまし』。即座にレーダーをセットし、小型粒子銃の照準を合わせ――ファイア。瞬く間に高エネルギー粒子が炸裂し、エネルギー機構を損傷した『みずすまし』が赤い海に沈む。
今ので最後らしい。レーダーが周囲に敵機を検出していないことを確認して、アレクシアは息を吐く。
今日もまたグレムリンを動かせてしまった。普通に考えて、素人が少し触ったくらいの機械を動かせるわけがない。空母や巡洋艦だって一夕一朝で操縦技術は身につかないだろう。
しかし、グレムリンは違うと聞いたことがある。
人がグレムリンを動かすのではなく、グレムリンが人を導くのだ、と。
(誰から聞いたんだったかな)
遠い記憶だ。確か、「そんなことあるわけないでしょ」と適当に返事をして取り合わなかった気がする。
その時はそんなことを一切信じていなかったが、現にアレクシアは『サイレント・リップルス』を動かせてしまっている。
この機体がアレクシアを導いているのなら、
「……一体どこに導かれるのやら」
当然、答えはない。グレムリンは話さない。
独り言だけが操縦棺に零れ落ちた。
***
南南西海域・赤の海での戦闘を終えた悪鬼巡洋艦【ベルーガ】は、真紅工廠【スルト】に寄港していた。
スルトは海面に建つ巨大な城の中にある、真紅連理系のグレムリン工廠だ。ここでアサルト・フレーム――より攻撃的なグレムリンのフレームを増産しているという話を聞きつけ、ベルーガは針路をとっていた。
新フレームだけではなく、もちろんスルトのグレムリン関連設備は巡洋艦のそれよりも良い。一部を除いて、この機会にベルーガのグレムリンをまとめてメンテナンスに出すことになっている。ちなみに機体の相性を鑑みた結果、フレームの換装はコールの『クレオソート』だけ行う予定だ。
「搬入任せていい?」
「大丈夫です! 久々の陸地ですし、エコーズさんもターナーさんもゆっくりしてください」
アレクシアよりいくらか年若い女性は、短い金髪を揺らして笑顔でそう言った。彼女、シリヤ・マキはベルーガのグレムリンエンジニア、兼副料理長、兼食料班主任だ。例に漏れず人員不足の煽りを受け、最近は機関士補助にも就いているらしい。
少しおっちょこちょいなところもあるが、仕事に間違いはない。それにこの愛想の良さ。とても真似ができる気がせず、アレクシアは密かに感心していた。まあ、そうなりたいとは思わないのだが。
いつもながらにこやかなシリヤのお言葉に甘えて、アレクシアは『サイレント・リップルス』のスルトへの搬入を任せることにした。
「ありがと。じゃあよろしく。
私は城下町でご飯でも食べてこようと思うけど、コールくんは?」
グレムリン搬入の件でドックまで一緒に来ていたコールに聞くと、彼は首を横に振った。
「俺はベルーガで待機する」
「そっか。メンテが終わる頃には戻るから、また後でね」
ひらりと手を振って、アレクシアはドックを後にした。
ベルーガのタラップを降り、向かう先は赤の海城の城下町だ。
降り立った途端、見渡す限り赤、赤、赤。海も家も道路も赤。悪趣味を通り越して潔い町だ。何度目かの寄港でアレクシアは慣れつつあったが、最初に来た時は赤さで胸焼けがしそうなくらいだった。それでも最初のうちは眩しくて、目を慣らすよう瞬かせる。
(ジェリィちゃんでも誘えばよかったかな)
アレクシアの目当ては、城下町の一角にある食堂だ。そこの虚空赤魚のオイル煮は割とおいしい。別にコールと一緒に行きたかったわけではないが、珍しく誰かと一緒に行っても良いような気分だった。ここのところベルーガにも人が増え、食事の時間がにぎやかになったせいだろうか。
ジェリィはつい最近ベルーガに加入した少女だ。見た目は可愛らしい少女だが、どうも人間ではないらしい。アレクシアは詳しいことを知らなかった。しかし食事はでき、「うまいもん食えばちゃんとテンションは上がります」とのことだったので誘っても良かったかもしれない。
同じくベルーガに加わったメンバーと言えば、ネレとベルゼリアがいる。前者は今は北東方面にいて、誘うのは物理的に不可能――仮に誘ったら軽い調子で来そうな気はする。後者は静かな方が好きと言っていたので、誘っても来なかったかもしれない。
(……いや、でも。あんまり良くないな、これは)
自分がベルーガに勧誘したせいか、一人ひとりのことを把握できてしまっていた。
しかし所詮はユニオンを通した付き合いであり、いざという時には見捨てる必要性も出てくる。状況が変われば銃口を突き合わせることだってあるだろう。
変に情やら思い入れを抱くのは悪手だ。まだそこまでのことを考えているわけではないが、今のうちから改めて自覚しておくことは必要であると思えた。
アレクシアはベルーガを振り返らず、一人で赤い町を歩いていく。
***
「……はあ? どういうこと?」
「す、すみませんすみません、私にもどういうことかさっぱりで」
夕方。ベルーガのドックで眉間に皺を寄せるアレクシア、腰を深く折って平謝りするシリヤ。
遅れてドックに入ってきたコールが、訝しそうに問いかけてくる。
「どうしたんだ? 雇い主さん」
「いや、それが……」
「ああああの、エコーズさんは悪くなくてぇ、私が、私がですね……」
酷く慌てたシリヤ曰く。
どうにも、『クレオソート』だけではなく『サイレント・リップルス』までアサルト・フレームに換装されてしまったらしい。「あの赤いお嬢さんにはこの赤いアサルト・フレームこそが相応しい」と赤の海特有の赤色崇拝理論により、『サイレント・リップルス』が返ってきた頃にはすでに後の祭りだった。
『サイレント・リップルス』の肝はレーダーだ。しかし、アサルト・フレームにはレーダーを載せる機構がない。これはかなりの問題だった。
指で眉間の皺をほぐし、努めて冷静に、アレクシアはシリヤに再度確認する。
「戻せないんだよね?」
「無理、とバッサリ切り捨てられました……艦長にも言ってもらったんですけど、全然ダメでぇ……」
「……なら仕方がない」
ベルーガ艦長のカイルが出ても無理なら、自分が何を言っても無駄だろう。カイルはいつもは大雑把だが、こういう時はきちんと言うタイプのはずだ。
起こったことはどうしようもない。今考えるべきは、レーダーを外したアセンブルだ。
「積めるのがレーダーからエンジンになったんだよね? 『サイレント・リップルス』が積んでるのと同じ規格のエンジンを見繕って手配してくれるかな。戦闘はそれでどうにかするから。
それと、タワーの方でフレームが戻せるか調べておいて」
「はっ、はいぃ、本当にすみません……」
「いいよ、私も確認不足だった。赤の海のイカレ具合をなめてたなー……それよりほら、手ぇ動かして」
「はいっ!」
アレクシアの言に押されるようにシリヤは勢いよく敬礼し、更に勢いよくドックを出ていった。
一転して、ドック内が静かになる。
アレクシアは『サイレント・リップルス』を、そして横目でコールを見た。
「……ってことなんだって。はあ。クソだなー」
「意外と怒らないんだな」
「怒って元に戻るならいくらでも怒るけど。艦長が出ても無駄なら仕方がないよ」
しげしげと『サイレント・リップルス』を上から下まで眺める。見た目はあまり変わっていないように見えるが、違うらしい。シリヤもいなくなったことで、さすがに溜息が漏れた。
「今からじゃ機体の組み替えも間に合わないし、間に合っても私に動かせる気がしないからなー……コールくんには負担をかけるね。悪いけど、頼める?」
「やるべき仕事はやる。嫌なことでも。それが仕事というものだ」
また屁理屈か文句を言われるかと思ったが、存外に素直な返事だ。アレクシアは驚いて目を瞬かせ、コールを見た。いつもと同じ、何を考えているか分かり辛い無表情。
さすがにここでどうこう言われたら、アレクシアの堪忍袋がもつ気がしなかった。いま吐いた息は、安堵のそれだ。
「良い返事じゃない。割増賃金は艦長に請求しといてね」
「分かった」
それにしても、次の戦闘は大丈夫だろうか。
アレクシアの胸中にはじわりと不安が広がっていた。
そう聞かれると困る。
明確な理由はない。強いて言うなら、あの廃工場でコールを見つけた時、このまま見捨てたら寝覚めが悪くなりそうな気がした。
それに、いつ滅ぶとも知れない世界なのだから、少しくらいは善いことをしてもいいか、と思った。
どちらにせよ気分の問題だった。
そして今もなお、意外と世界は滅びず、その気まぐれのツケを支払っている。
視界を覆う粉塵。
それを切り裂くように、一筋の光が閃いた。
(やればできるじゃん)
ヒートストリングの高熱線が、中量格闘機『金砕棒』を両断した。『クレオソート』は一瞥もせず、ブースターを吹かして次の獲物へ狙いを定める。
繰り返すが、アレクシアはグレムリンエンジニアだ。支援ならまだしも、戦闘能力自体を期待されても困る。今日みたいに本業のコールが張り切るべきだし、景気よく敵機を墜としていく様を見ると少しは拾った甲斐を感じるものだ。
「……だぁから、あっち狙ってくれないかなー」
つんざくようなアラート音が操縦棺内に響いた。レーダーが『サイレント・リップルス』に接近する敵機を捉え、アレクシアはレバーを引いて機体を急旋回させる。
左方に掃海艇『みずすまし』。即座にレーダーをセットし、小型粒子銃の照準を合わせ――ファイア。瞬く間に高エネルギー粒子が炸裂し、エネルギー機構を損傷した『みずすまし』が赤い海に沈む。
今ので最後らしい。レーダーが周囲に敵機を検出していないことを確認して、アレクシアは息を吐く。
今日もまたグレムリンを動かせてしまった。普通に考えて、素人が少し触ったくらいの機械を動かせるわけがない。空母や巡洋艦だって一夕一朝で操縦技術は身につかないだろう。
しかし、グレムリンは違うと聞いたことがある。
人がグレムリンを動かすのではなく、グレムリンが人を導くのだ、と。
(誰から聞いたんだったかな)
遠い記憶だ。確か、「そんなことあるわけないでしょ」と適当に返事をして取り合わなかった気がする。
その時はそんなことを一切信じていなかったが、現にアレクシアは『サイレント・リップルス』を動かせてしまっている。
この機体がアレクシアを導いているのなら、
「……一体どこに導かれるのやら」
当然、答えはない。グレムリンは話さない。
独り言だけが操縦棺に零れ落ちた。
***
南南西海域・赤の海での戦闘を終えた悪鬼巡洋艦【ベルーガ】は、真紅工廠【スルト】に寄港していた。
スルトは海面に建つ巨大な城の中にある、真紅連理系のグレムリン工廠だ。ここでアサルト・フレーム――より攻撃的なグレムリンのフレームを増産しているという話を聞きつけ、ベルーガは針路をとっていた。
新フレームだけではなく、もちろんスルトのグレムリン関連設備は巡洋艦のそれよりも良い。一部を除いて、この機会にベルーガのグレムリンをまとめてメンテナンスに出すことになっている。ちなみに機体の相性を鑑みた結果、フレームの換装はコールの『クレオソート』だけ行う予定だ。
「搬入任せていい?」
「大丈夫です! 久々の陸地ですし、エコーズさんもターナーさんもゆっくりしてください」
アレクシアよりいくらか年若い女性は、短い金髪を揺らして笑顔でそう言った。彼女、シリヤ・マキはベルーガのグレムリンエンジニア、兼副料理長、兼食料班主任だ。例に漏れず人員不足の煽りを受け、最近は機関士補助にも就いているらしい。
少しおっちょこちょいなところもあるが、仕事に間違いはない。それにこの愛想の良さ。とても真似ができる気がせず、アレクシアは密かに感心していた。まあ、そうなりたいとは思わないのだが。
いつもながらにこやかなシリヤのお言葉に甘えて、アレクシアは『サイレント・リップルス』のスルトへの搬入を任せることにした。
「ありがと。じゃあよろしく。
私は城下町でご飯でも食べてこようと思うけど、コールくんは?」
グレムリン搬入の件でドックまで一緒に来ていたコールに聞くと、彼は首を横に振った。
「俺はベルーガで待機する」
「そっか。メンテが終わる頃には戻るから、また後でね」
ひらりと手を振って、アレクシアはドックを後にした。
ベルーガのタラップを降り、向かう先は赤の海城の城下町だ。
降り立った途端、見渡す限り赤、赤、赤。海も家も道路も赤。悪趣味を通り越して潔い町だ。何度目かの寄港でアレクシアは慣れつつあったが、最初に来た時は赤さで胸焼けがしそうなくらいだった。それでも最初のうちは眩しくて、目を慣らすよう瞬かせる。
(ジェリィちゃんでも誘えばよかったかな)
アレクシアの目当ては、城下町の一角にある食堂だ。そこの虚空赤魚のオイル煮は割とおいしい。別にコールと一緒に行きたかったわけではないが、珍しく誰かと一緒に行っても良いような気分だった。ここのところベルーガにも人が増え、食事の時間がにぎやかになったせいだろうか。
ジェリィはつい最近ベルーガに加入した少女だ。見た目は可愛らしい少女だが、どうも人間ではないらしい。アレクシアは詳しいことを知らなかった。しかし食事はでき、「うまいもん食えばちゃんとテンションは上がります」とのことだったので誘っても良かったかもしれない。
同じくベルーガに加わったメンバーと言えば、ネレとベルゼリアがいる。前者は今は北東方面にいて、誘うのは物理的に不可能――仮に誘ったら軽い調子で来そうな気はする。後者は静かな方が好きと言っていたので、誘っても来なかったかもしれない。
(……いや、でも。あんまり良くないな、これは)
自分がベルーガに勧誘したせいか、一人ひとりのことを把握できてしまっていた。
しかし所詮はユニオンを通した付き合いであり、いざという時には見捨てる必要性も出てくる。状況が変われば銃口を突き合わせることだってあるだろう。
変に情やら思い入れを抱くのは悪手だ。まだそこまでのことを考えているわけではないが、今のうちから改めて自覚しておくことは必要であると思えた。
アレクシアはベルーガを振り返らず、一人で赤い町を歩いていく。
***
「……はあ? どういうこと?」
「す、すみませんすみません、私にもどういうことかさっぱりで」
夕方。ベルーガのドックで眉間に皺を寄せるアレクシア、腰を深く折って平謝りするシリヤ。
遅れてドックに入ってきたコールが、訝しそうに問いかけてくる。
「どうしたんだ? 雇い主さん」
「いや、それが……」
「ああああの、エコーズさんは悪くなくてぇ、私が、私がですね……」
酷く慌てたシリヤ曰く。
どうにも、『クレオソート』だけではなく『サイレント・リップルス』までアサルト・フレームに換装されてしまったらしい。「あの赤いお嬢さんにはこの赤いアサルト・フレームこそが相応しい」と赤の海特有の赤色崇拝理論により、『サイレント・リップルス』が返ってきた頃にはすでに後の祭りだった。
『サイレント・リップルス』の肝はレーダーだ。しかし、アサルト・フレームにはレーダーを載せる機構がない。これはかなりの問題だった。
指で眉間の皺をほぐし、努めて冷静に、アレクシアはシリヤに再度確認する。
「戻せないんだよね?」
「無理、とバッサリ切り捨てられました……艦長にも言ってもらったんですけど、全然ダメでぇ……」
「……なら仕方がない」
ベルーガ艦長のカイルが出ても無理なら、自分が何を言っても無駄だろう。カイルはいつもは大雑把だが、こういう時はきちんと言うタイプのはずだ。
起こったことはどうしようもない。今考えるべきは、レーダーを外したアセンブルだ。
「積めるのがレーダーからエンジンになったんだよね? 『サイレント・リップルス』が積んでるのと同じ規格のエンジンを見繕って手配してくれるかな。戦闘はそれでどうにかするから。
それと、タワーの方でフレームが戻せるか調べておいて」
「はっ、はいぃ、本当にすみません……」
「いいよ、私も確認不足だった。赤の海のイカレ具合をなめてたなー……それよりほら、手ぇ動かして」
「はいっ!」
アレクシアの言に押されるようにシリヤは勢いよく敬礼し、更に勢いよくドックを出ていった。
一転して、ドック内が静かになる。
アレクシアは『サイレント・リップルス』を、そして横目でコールを見た。
「……ってことなんだって。はあ。クソだなー」
「意外と怒らないんだな」
「怒って元に戻るならいくらでも怒るけど。艦長が出ても無駄なら仕方がないよ」
しげしげと『サイレント・リップルス』を上から下まで眺める。見た目はあまり変わっていないように見えるが、違うらしい。シリヤもいなくなったことで、さすがに溜息が漏れた。
「今からじゃ機体の組み替えも間に合わないし、間に合っても私に動かせる気がしないからなー……コールくんには負担をかけるね。悪いけど、頼める?」
「やるべき仕事はやる。嫌なことでも。それが仕事というものだ」
また屁理屈か文句を言われるかと思ったが、存外に素直な返事だ。アレクシアは驚いて目を瞬かせ、コールを見た。いつもと同じ、何を考えているか分かり辛い無表情。
さすがにここでどうこう言われたら、アレクシアの堪忍袋がもつ気がしなかった。いま吐いた息は、安堵のそれだ。
「良い返事じゃない。割増賃金は艦長に請求しといてね」
「分かった」
それにしても、次の戦闘は大丈夫だろうか。
アレクシアの胸中にはじわりと不安が広がっていた。
◆4回更新の日記ログ
「いや、しかし本当に集めてくるとはなあ!」
豪快な笑い声が、狭い部屋に響く。
立派な黒革張りのソファに、恰幅の良い大男がどっしりと構えていた。彼は機嫌が良さそうに、手に持った電子タブレットに表示されたリストと、これもまた立派な執務デスクを挟んで目の前に立つアレクシアを見比べる。
悪鬼巡洋艦【ベルーガ】艦長であるカイルは、アレクシアをグレムリンエンジニアからテイマーに転向させるだけでは飽き足らなかった。「グレイヴネットのアクセス権持ってるんだから、ついでにテイマーも集めてきてくれ!」と無茶振りしたのが約10日前。
無茶振られたアレクシアが、投げやりな気持ちで広域通信やランキングを参考にユニオン勧誘のメッセージを送ったら――意外や意外。数名のテイマーがベルーガに集っていた。
正直なところ、彼女としてもこんなにテイマーが集まるのは予想外だった。こんな薄給で飯がマズいクソ船に来ちゃって大丈夫なんだろうか、この人たち。今のご時世なら他のユニオンでも変わらないのかねえ。と、ユニオン加入の連絡を受けた際に思ったが、もちろんベルーガの労働環境のブラック部分については話していない。心配するようでいて、彼女も彼女でやり方があくどいのだ。評判なんて少し調べたら出てくるし、その辺は自己責任ってことで。私は知らない。そんな風に決め込んでいる。
「営業のセンスがあるな、エコーズには」
「艦長の営業力が低すぎるんじゃないですか」
成果を盾に、アレクシアは皮肉っぽくそう返した。そもそも、カイルが最初からテイマーを確保できてさえいれば、自分がグレムリンに乗る必要はなかったのだ。いくら物事全般の興味が薄い彼女でも皮肉くらいは言いたくなる。まあ、この雑な男にそんなものは一切通用しないのだが。
カイルはわざとらしく、ふっさりと髭の生えた顎をさすった。
「あの時はほら、どこもかしこも滅茶苦茶だっただろ。世の中が落ち着いてきてる証拠じゃねぇか?」
「全然しませんけどね、落ち着いてる感じ」
「はっは、細かいこたぁ気にすんな! エンジニア業もテイマー業も営業も優秀優秀。立派な乗組員だねえ。
報酬は現物支給でいいんだよな?」
アレクシアは頷いた。
嫌々ながらもそれなりに営業に励んだ理由が、報酬だ。一人の勧誘成功につき、現金もしくは等価の現物支給。彼女は後者としてラジオを要求していた。私物のそれを修理しながら騙し騙し使っていたが、いい加減に限界が来ている。
「そうしてください。現金貰ってああだこうだ言われるのも嫌なんで」
その返事を聞くと、カイルは憐れむように眉を顰めた。
「お前さんも面倒な身の上だよなあ」
「同情するなら給料上げてくれます?」
「そりゃ無理だ」
「はあ。ラジオはちゃんとしてくださいね」
これ以上ここに居る必要はないと言わんばかりに、アレクシアは踵を返して艦長室から出ていった。
薄暗い通路には丸い窓が嵌められていて、ダストデッキの様子が見える。今日の天気はもちろん粉塵。変わり映えのない景色だ。
ダストデッキの約三分の一は艦長室と操舵室兼海図室、残りはグレムリン発着場で構成されている。アレクシアは艦長室に際した階段を下りてグレムリンドッグのある第二甲板へ、更に下って居住スペースや食堂のある第三甲板まで移動した。
しかしまあ、こんなボロ船でも人が集まるもんだな。案外私には営業の才能があるのかもしれない。見切りを付けてフェアギスマインニヒトにでも入る? まあ、無理だけど――艦内の様子を見てそんなことを考えながら、通路を歩き、"C"という掠れかけのアルファベットプレートが取り付けられた会議室の扉を開く。
「あれ。早いじゃん」
「雇い主さんが遅い」
「野暮用でね。まあまあ、始めようよ」
そう言いながら、アレクシアは椅子に腰かける。机の向こう側には、コールがすでに座っていた。ちなみに、"雇い主さん"という呼ばれ方はアレクシアの本意ではないが、何度言ってもそう呼んでくるので最近は諦めている。
今日は、二人で次の戦場に向けてのミーティングをすることになっていた。アレクシアが遅刻した格好だが、欠片も気にした様子を見せずに会議室備え付けのパソコンを操作する。
「……と言っても、ベルーガの針路は決まってるし。未識別機動体もほとんど戦ったことがある機体だし。
今日はあんまり話すことないな」
掃海艇『みずすまし』、狙撃機『マインゴーシュ』――パソコンから壁掛けスクリーンに投影された敵データは、見覚えのあるものが多かった。初めて相対する機体もあるが、『サイレント・リップルス』の索敵によって各種兵器の種は割れている。戦果を狙うならともかく、普通に倒すだけなら脅威とは言えない。
コールも同じ見解のようで、すぐにスクリーンから目を離した。
「じゃあ、これで解散か」
「お互いのアセンのチェックだけして終わりでいいんじゃない。……あ、でも」
アレクシアは端末を操作して、南西海域【星の海】での戦闘解析データを呼び出した。これは先週、二人が出撃した戦場だ。
「コールくんさあ、仕事してなくない?」
「仕事ならしているだろう」
「いや、私の方が働いてない? ってこと。ほら」
『クレオソート』、敵機撃墜数5。
『サイレント・リップルス』、敵機撃墜数6。
アレクシアの方が1機多く墜としていた。ちなみに、前々回の戦闘ではもっと差が開いている。
しかし、いきなりこんなに働けるなんて私は才能の塊なんじゃないか? 全くもって嬉しくない才能にアレクシアは苦々しい気持ちになりながら、スクリーンを指してコールに言った。
「コールくんが攻撃。私がサポート。そのはずじゃなかったっけ」
「そんな気もする」
「気がするじゃなくてそうだよ」
最初の取り決めでそうなったはずだ。この期に及んで白ばっくれるとは。アレクシアは呆れ気味に
目を細めた。
対するコールは、表情を変えずに首を捻る。
「脳に栄養が行っていないのかもしれない。やはり食事が悪いせいか……給料も低いし。猫缶しか拾わないし」
「墜とされて借金持ちになった自分を恨みなよ。あと最後のは関係ないし。次はもっと張り切ってほしいな」
「給料分は頑張ろう」
「それでよろしく」
そんな実のない話を切り上げ、アセンブルの確認に移る。
『クレオソート』はヒートストリングを中心とした二脚の攻撃型機体、『サイレント・リップルス』はレーダーでのサポートを重視した逆関節の機体。お互い特に問題は見受けられず、ミーティングはあっさりと終わった。
パソコンとスクリーンの片付けをしながら、アレクシアはふと、最近よく見るグレイヴネットのニュースを思い出した。
「そういえば、戦場で死んだはずの傭兵を見ただって。コールくんも聞いた?」
「ああ」
「幻覚でも見てんのかね。それとも幽霊か」
死者の戦場での目撃情報が、ここのところ相次いでいた。その事象自体にアレクシアの興味はあまりそそられなかったが、戦場に関係することでもあるのでそのまま話を続ける。
「死んだ知り合いが化けて出てきたらどうする?」
「破壊する」
情緒ゼロの即答に、さすがのアレクシアも片付けの手を止めて沈黙する。
「……破壊するんだ」
「その方が話が早い」
「話すらしてないじゃん」
「じゃあ雇い主さんはどうするんだ」
そう聞かれて、考え込む。
別に、死んだ人間に未練はなかった。聞きたいことも言いたいこともない。
となると。
「破壊かな」
「正解だ」
「過去は振り返らないタイプだからね」
「素晴らしい」
「……でもコールくんと同じなのはなんかヤだな。選択を間違えてる気がする」
それに、直近の選択らしいものと言えば――アレクシアはコールを見遣り、呟く。
「拾ったの、間違いだったかなあ」
「何か言ったか?」
「何でもないよ」
金がなく、食事に文句を言い、屁理屈が多く、素直じゃなくて面倒臭い年下の男の僚機。
彼を助けたことは間違いと言い切ることこそしないが、正解とも言えない気がする。
……いや、やっぱり正解ではないな。もっとベターな選択肢があったに違いない。
自分の判断について自信をなくしながら、アレクシアは談話室を後にした。
豪快な笑い声が、狭い部屋に響く。
立派な黒革張りのソファに、恰幅の良い大男がどっしりと構えていた。彼は機嫌が良さそうに、手に持った電子タブレットに表示されたリストと、これもまた立派な執務デスクを挟んで目の前に立つアレクシアを見比べる。
悪鬼巡洋艦【ベルーガ】艦長であるカイルは、アレクシアをグレムリンエンジニアからテイマーに転向させるだけでは飽き足らなかった。「グレイヴネットのアクセス権持ってるんだから、ついでにテイマーも集めてきてくれ!」と無茶振りしたのが約10日前。
無茶振られたアレクシアが、投げやりな気持ちで広域通信やランキングを参考にユニオン勧誘のメッセージを送ったら――意外や意外。数名のテイマーがベルーガに集っていた。
正直なところ、彼女としてもこんなにテイマーが集まるのは予想外だった。こんな薄給で飯がマズいクソ船に来ちゃって大丈夫なんだろうか、この人たち。今のご時世なら他のユニオンでも変わらないのかねえ。と、ユニオン加入の連絡を受けた際に思ったが、もちろんベルーガの労働環境のブラック部分については話していない。心配するようでいて、彼女も彼女でやり方があくどいのだ。評判なんて少し調べたら出てくるし、その辺は自己責任ってことで。私は知らない。そんな風に決め込んでいる。
「営業のセンスがあるな、エコーズには」
「艦長の営業力が低すぎるんじゃないですか」
成果を盾に、アレクシアは皮肉っぽくそう返した。そもそも、カイルが最初からテイマーを確保できてさえいれば、自分がグレムリンに乗る必要はなかったのだ。いくら物事全般の興味が薄い彼女でも皮肉くらいは言いたくなる。まあ、この雑な男にそんなものは一切通用しないのだが。
カイルはわざとらしく、ふっさりと髭の生えた顎をさすった。
「あの時はほら、どこもかしこも滅茶苦茶だっただろ。世の中が落ち着いてきてる証拠じゃねぇか?」
「全然しませんけどね、落ち着いてる感じ」
「はっは、細かいこたぁ気にすんな! エンジニア業もテイマー業も営業も優秀優秀。立派な乗組員だねえ。
報酬は現物支給でいいんだよな?」
アレクシアは頷いた。
嫌々ながらもそれなりに営業に励んだ理由が、報酬だ。一人の勧誘成功につき、現金もしくは等価の現物支給。彼女は後者としてラジオを要求していた。私物のそれを修理しながら騙し騙し使っていたが、いい加減に限界が来ている。
「そうしてください。現金貰ってああだこうだ言われるのも嫌なんで」
その返事を聞くと、カイルは憐れむように眉を顰めた。
「お前さんも面倒な身の上だよなあ」
「同情するなら給料上げてくれます?」
「そりゃ無理だ」
「はあ。ラジオはちゃんとしてくださいね」
これ以上ここに居る必要はないと言わんばかりに、アレクシアは踵を返して艦長室から出ていった。
薄暗い通路には丸い窓が嵌められていて、ダストデッキの様子が見える。今日の天気はもちろん粉塵。変わり映えのない景色だ。
ダストデッキの約三分の一は艦長室と操舵室兼海図室、残りはグレムリン発着場で構成されている。アレクシアは艦長室に際した階段を下りてグレムリンドッグのある第二甲板へ、更に下って居住スペースや食堂のある第三甲板まで移動した。
しかしまあ、こんなボロ船でも人が集まるもんだな。案外私には営業の才能があるのかもしれない。見切りを付けてフェアギスマインニヒトにでも入る? まあ、無理だけど――艦内の様子を見てそんなことを考えながら、通路を歩き、"C"という掠れかけのアルファベットプレートが取り付けられた会議室の扉を開く。
「あれ。早いじゃん」
「雇い主さんが遅い」
「野暮用でね。まあまあ、始めようよ」
そう言いながら、アレクシアは椅子に腰かける。机の向こう側には、コールがすでに座っていた。ちなみに、"雇い主さん"という呼ばれ方はアレクシアの本意ではないが、何度言ってもそう呼んでくるので最近は諦めている。
今日は、二人で次の戦場に向けてのミーティングをすることになっていた。アレクシアが遅刻した格好だが、欠片も気にした様子を見せずに会議室備え付けのパソコンを操作する。
「……と言っても、ベルーガの針路は決まってるし。未識別機動体もほとんど戦ったことがある機体だし。
今日はあんまり話すことないな」
掃海艇『みずすまし』、狙撃機『マインゴーシュ』――パソコンから壁掛けスクリーンに投影された敵データは、見覚えのあるものが多かった。初めて相対する機体もあるが、『サイレント・リップルス』の索敵によって各種兵器の種は割れている。戦果を狙うならともかく、普通に倒すだけなら脅威とは言えない。
コールも同じ見解のようで、すぐにスクリーンから目を離した。
「じゃあ、これで解散か」
「お互いのアセンのチェックだけして終わりでいいんじゃない。……あ、でも」
アレクシアは端末を操作して、南西海域【星の海】での戦闘解析データを呼び出した。これは先週、二人が出撃した戦場だ。
「コールくんさあ、仕事してなくない?」
「仕事ならしているだろう」
「いや、私の方が働いてない? ってこと。ほら」
『クレオソート』、敵機撃墜数5。
『サイレント・リップルス』、敵機撃墜数6。
アレクシアの方が1機多く墜としていた。ちなみに、前々回の戦闘ではもっと差が開いている。
しかし、いきなりこんなに働けるなんて私は才能の塊なんじゃないか? 全くもって嬉しくない才能にアレクシアは苦々しい気持ちになりながら、スクリーンを指してコールに言った。
「コールくんが攻撃。私がサポート。そのはずじゃなかったっけ」
「そんな気もする」
「気がするじゃなくてそうだよ」
最初の取り決めでそうなったはずだ。この期に及んで白ばっくれるとは。アレクシアは呆れ気味に
目を細めた。
対するコールは、表情を変えずに首を捻る。
「脳に栄養が行っていないのかもしれない。やはり食事が悪いせいか……給料も低いし。猫缶しか拾わないし」
「墜とされて借金持ちになった自分を恨みなよ。あと最後のは関係ないし。次はもっと張り切ってほしいな」
「給料分は頑張ろう」
「それでよろしく」
そんな実のない話を切り上げ、アセンブルの確認に移る。
『クレオソート』はヒートストリングを中心とした二脚の攻撃型機体、『サイレント・リップルス』はレーダーでのサポートを重視した逆関節の機体。お互い特に問題は見受けられず、ミーティングはあっさりと終わった。
パソコンとスクリーンの片付けをしながら、アレクシアはふと、最近よく見るグレイヴネットのニュースを思い出した。
「そういえば、戦場で死んだはずの傭兵を見ただって。コールくんも聞いた?」
「ああ」
「幻覚でも見てんのかね。それとも幽霊か」
死者の戦場での目撃情報が、ここのところ相次いでいた。その事象自体にアレクシアの興味はあまりそそられなかったが、戦場に関係することでもあるのでそのまま話を続ける。
「死んだ知り合いが化けて出てきたらどうする?」
「破壊する」
情緒ゼロの即答に、さすがのアレクシアも片付けの手を止めて沈黙する。
「……破壊するんだ」
「その方が話が早い」
「話すらしてないじゃん」
「じゃあ雇い主さんはどうするんだ」
そう聞かれて、考え込む。
別に、死んだ人間に未練はなかった。聞きたいことも言いたいこともない。
となると。
「破壊かな」
「正解だ」
「過去は振り返らないタイプだからね」
「素晴らしい」
「……でもコールくんと同じなのはなんかヤだな。選択を間違えてる気がする」
それに、直近の選択らしいものと言えば――アレクシアはコールを見遣り、呟く。
「拾ったの、間違いだったかなあ」
「何か言ったか?」
「何でもないよ」
金がなく、食事に文句を言い、屁理屈が多く、素直じゃなくて面倒臭い年下の男の僚機。
彼を助けたことは間違いと言い切ることこそしないが、正解とも言えない気がする。
……いや、やっぱり正解ではないな。もっとベターな選択肢があったに違いない。
自分の判断について自信をなくしながら、アレクシアは談話室を後にした。
◆3回更新の日記ログ
錆びた海を、一隻の船が南へと航行する。
悪鬼巡洋艦【ベルーガ】。空母船団【コロッセオ・レガシィ】所属の船だ。
といっても、下請けのそのまた下請けに位置する弱小船で、御自慢の潤沢な資源の恩恵はほとんど受けていない。船体にこびり付く、落とし切れていない赤錆がそれをよく物語っている。
ベルーガに属するグレムリン及びグレムリン・テイマーは、先の灰燼戦争で多くが死ぬか機能停止に陥った。
この世界全体が甚大な被害を受けているから、それを回避できなかったのは責められることではない。しかし、だからと言って未識別機動体の侵攻と、それを迎え撃つ仕事は待ってくれなかった。
運良く(もしくは、悪く)グレイヴネットは正常に稼働している。それを経由したコロッセオ・レガシィからの出撃命令を聞き流しながら、ベルーガ艦長のカイル・ハワードは考えた。
人手が足りない。足りなさすぎる。駄目元で縦横の繋がりからテイマーの増員を要請したが、もちろんどこも応えない。
さて、どうするか。
考えはすぐにまとまった。――緊急事態だし、とりあえず乗組員を片っ端からグレムリンに乗せてみるか!
グレムリンの機能停止の原因が機体とテイマーのどちらにあるのかすら分からない状態だ。経験は問わない。動かせるだけ御の字。そいつはグレムリンに選ばれたってことだ。こんな状況なんだし、嫌でもみんな協力せざるを得ないだろう。
このカイルという男は、非常に大雑把な性格をしていた。そして、言い出したら聞かない。
他に打てる手がないのも事実で、艦長号令の下、乗組員は渋々とグレムリンの操縦棺に交代で入っていった。
そして――カイルの言葉を借りるなら、”選ばれた”のがアレクシア・エコーズだった。
「……はあ。こんなもんかな」
ベルーガ内第三グレムリンドッグは、小型機の整備用ドッグだ。外装と同じく内装も古く、あちこちの塗装は剥がれ、埃っぽい照明は気紛れに明滅する。
ウミネコの形を模したグレムリン――『サイレント・リップルス』の整備をしていたアレクシアは、作業の手を止めて息を吐いた。もう直すところもないし、装甲もピカピカに磨いた。こんなところだろう。
ドタバタのグレムリン総試乗から一週間。初めての戦場に出てから半日。整備を終えて5秒。
アレクシアは凝り固まった身体をほぐすように伸びてから、慣れた手付きで年季の入った整備器具を片付け始める。
意外にも、『サイレント・リップルス』は大した被弾もなくベルーガへ帰投した。
もともとグレムリン・エンジニアをしていたから、テスト運行や輸送程度の操縦はしたことがあった。全くの未経験者ではないが、それにしても初の戦闘で上手く行きすぎだ。テイマーの才能があったなんて楽観的に考えることはできず、何だか空恐ろしさを感じる。”選ばれた”という言葉も、今となってはオカルティックに聞こえた。
整備の後始末を粗方終え、アレクシアは『サイレント・リップルス』の横に置いてあったパイプ椅子に身を預ける。ぎしり。椅子の軋む音がした。
ここでこう、背もたれが折れて背中から行って、背骨でも折ったら御役御免かなあ。でもそれは痛いし嫌だなあ。脳がぼんやりと現実逃避を始める。
大変な一週間だった。ただでさえ滅びかけの世界が未知の敵に占領され、グレムリンに乗り、戦って、整備もして。当たり前のように疲れている。
アレクシアは椅子にもたれたまま、天井を仰いで目を閉じた。照明の明滅が瞼越しに角膜を刺激する。休憩に適した姿勢でも環境でもないが、部屋に戻るのも億劫だった。
どうなるんだろなー、これから。それに、あっちの件だって……。
「雇い主さん」
聞こえた声にうとうとした思考が打ち切られた。上体を起こし、座ったまま視線を遣る。
そこには整備器具を持つ銀髪の青年がいた。頭に装着した黒いヘッドギアが影を差して見え辛いが、チカチカと光るライトブルーの瞳がこちらを向いている。
「その雇い主って言うの止めてくれる? 雇ってないし」
「じゃあ取り立て屋さん」
「余計に人聞きが悪い。で、もう終わったの」
アレクシアの問いかけに、青年は顎を引いて応えた。
「どこに置けばいい」
「そこ開けて。種類別に並べておいて」
雑に指をさした方向に、工具箱があった。青年はそれに従って、黙々と整備器具を片付けていく。機械化手術を受けたらしい左手に外皮はなく、金属がぶつかる音が静かに響く。
ヘッドギアと同じような色合いのサバイバルベストに覆われたその背を見ながら、アレクシアは言った。
「『クレオソート』はどう?」
「そっちは問題ない。問題は船にある」
整備器具をしまい終えた青年は、アレクシアの方を振り向いた。眉間には皺が寄っている。
「と言いますと?」
「飯がマズい。具材がマズい」
「えー? 普通じゃん。コーンミール」
「前の仕事ではもっとマシなものが出た」
「食べ盛りだねえ」
「せめてコンブレッドにしてくれ」
「半分機械なんだし、食事も半分じゃダメなの」
「味は二倍で頼む」
「……って言ってもねえ。君、立場分かってる?」
アレクシアは呆れたように目を細め、青年を見上げる。
「食事のランク上げたらますます返済が遠のくよ、コールくん」
コール=ターナーという青年は、アレクシアの怒涛の一週間の構成要因の一つだった。
ひょんなきっかけからコールを拾い、彼のグレムリン『クレオソート』を修理したまではよかった。修理費を請求したら、「金がない」と言い出すので、返済代わりにコールはアレクシアの僚機として働いている。
ちょうど僚機の当てがなかったから都合が良かったが、それはそれ、これはこれだ。さっさと金を返せ。アレクシアはそう思っていた。
一方のコールは、債務者の身分を全く気にしないかのように不遜な物言いを続ける。
「長期計画で返す」
「どっちか死んでそうだね、それ」
「その時はその時だろう」
「踏み倒し反対」
「生きている内の仕事はちゃんとする。マシな食事さえあれば」
「はいはい……戦場でサボられても困る。料理長に言っとくよ。
手元に残るお金、ほとんどなくなるけど文句は言わないよーに」
「分かった」
コールの返事を最後まで聞かないで、アレクシアは立ち上がった。食事ランクを上げることによる完済までの期間のズレを計算しながら、ドッグを後にする。
世界が滅亡の危機に瀕する状況で金、金と言うのも滑稽な話だという自覚はあった。
しかし、もし世界が平和になり、元通りになったとしたら――アレクシアには金が必要だった。
悪鬼巡洋艦【ベルーガ】。空母船団【コロッセオ・レガシィ】所属の船だ。
といっても、下請けのそのまた下請けに位置する弱小船で、御自慢の潤沢な資源の恩恵はほとんど受けていない。船体にこびり付く、落とし切れていない赤錆がそれをよく物語っている。
ベルーガに属するグレムリン及びグレムリン・テイマーは、先の灰燼戦争で多くが死ぬか機能停止に陥った。
この世界全体が甚大な被害を受けているから、それを回避できなかったのは責められることではない。しかし、だからと言って未識別機動体の侵攻と、それを迎え撃つ仕事は待ってくれなかった。
運良く(もしくは、悪く)グレイヴネットは正常に稼働している。それを経由したコロッセオ・レガシィからの出撃命令を聞き流しながら、ベルーガ艦長のカイル・ハワードは考えた。
人手が足りない。足りなさすぎる。駄目元で縦横の繋がりからテイマーの増員を要請したが、もちろんどこも応えない。
さて、どうするか。
考えはすぐにまとまった。――緊急事態だし、とりあえず乗組員を片っ端からグレムリンに乗せてみるか!
グレムリンの機能停止の原因が機体とテイマーのどちらにあるのかすら分からない状態だ。経験は問わない。動かせるだけ御の字。そいつはグレムリンに選ばれたってことだ。こんな状況なんだし、嫌でもみんな協力せざるを得ないだろう。
このカイルという男は、非常に大雑把な性格をしていた。そして、言い出したら聞かない。
他に打てる手がないのも事実で、艦長号令の下、乗組員は渋々とグレムリンの操縦棺に交代で入っていった。
そして――カイルの言葉を借りるなら、”選ばれた”のがアレクシア・エコーズだった。
「……はあ。こんなもんかな」
ベルーガ内第三グレムリンドッグは、小型機の整備用ドッグだ。外装と同じく内装も古く、あちこちの塗装は剥がれ、埃っぽい照明は気紛れに明滅する。
ウミネコの形を模したグレムリン――『サイレント・リップルス』の整備をしていたアレクシアは、作業の手を止めて息を吐いた。もう直すところもないし、装甲もピカピカに磨いた。こんなところだろう。
ドタバタのグレムリン総試乗から一週間。初めての戦場に出てから半日。整備を終えて5秒。
アレクシアは凝り固まった身体をほぐすように伸びてから、慣れた手付きで年季の入った整備器具を片付け始める。
意外にも、『サイレント・リップルス』は大した被弾もなくベルーガへ帰投した。
もともとグレムリン・エンジニアをしていたから、テスト運行や輸送程度の操縦はしたことがあった。全くの未経験者ではないが、それにしても初の戦闘で上手く行きすぎだ。テイマーの才能があったなんて楽観的に考えることはできず、何だか空恐ろしさを感じる。”選ばれた”という言葉も、今となってはオカルティックに聞こえた。
整備の後始末を粗方終え、アレクシアは『サイレント・リップルス』の横に置いてあったパイプ椅子に身を預ける。ぎしり。椅子の軋む音がした。
ここでこう、背もたれが折れて背中から行って、背骨でも折ったら御役御免かなあ。でもそれは痛いし嫌だなあ。脳がぼんやりと現実逃避を始める。
大変な一週間だった。ただでさえ滅びかけの世界が未知の敵に占領され、グレムリンに乗り、戦って、整備もして。当たり前のように疲れている。
アレクシアは椅子にもたれたまま、天井を仰いで目を閉じた。照明の明滅が瞼越しに角膜を刺激する。休憩に適した姿勢でも環境でもないが、部屋に戻るのも億劫だった。
どうなるんだろなー、これから。それに、あっちの件だって……。
「雇い主さん」
聞こえた声にうとうとした思考が打ち切られた。上体を起こし、座ったまま視線を遣る。
そこには整備器具を持つ銀髪の青年がいた。頭に装着した黒いヘッドギアが影を差して見え辛いが、チカチカと光るライトブルーの瞳がこちらを向いている。
「その雇い主って言うの止めてくれる? 雇ってないし」
「じゃあ取り立て屋さん」
「余計に人聞きが悪い。で、もう終わったの」
アレクシアの問いかけに、青年は顎を引いて応えた。
「どこに置けばいい」
「そこ開けて。種類別に並べておいて」
雑に指をさした方向に、工具箱があった。青年はそれに従って、黙々と整備器具を片付けていく。機械化手術を受けたらしい左手に外皮はなく、金属がぶつかる音が静かに響く。
ヘッドギアと同じような色合いのサバイバルベストに覆われたその背を見ながら、アレクシアは言った。
「『クレオソート』はどう?」
「そっちは問題ない。問題は船にある」
整備器具をしまい終えた青年は、アレクシアの方を振り向いた。眉間には皺が寄っている。
「と言いますと?」
「飯がマズい。具材がマズい」
「えー? 普通じゃん。コーンミール」
「前の仕事ではもっとマシなものが出た」
「食べ盛りだねえ」
「せめてコンブレッドにしてくれ」
「半分機械なんだし、食事も半分じゃダメなの」
「味は二倍で頼む」
「……って言ってもねえ。君、立場分かってる?」
アレクシアは呆れたように目を細め、青年を見上げる。
「食事のランク上げたらますます返済が遠のくよ、コールくん」
コール=ターナーという青年は、アレクシアの怒涛の一週間の構成要因の一つだった。
ひょんなきっかけからコールを拾い、彼のグレムリン『クレオソート』を修理したまではよかった。修理費を請求したら、「金がない」と言い出すので、返済代わりにコールはアレクシアの僚機として働いている。
ちょうど僚機の当てがなかったから都合が良かったが、それはそれ、これはこれだ。さっさと金を返せ。アレクシアはそう思っていた。
一方のコールは、債務者の身分を全く気にしないかのように不遜な物言いを続ける。
「長期計画で返す」
「どっちか死んでそうだね、それ」
「その時はその時だろう」
「踏み倒し反対」
「生きている内の仕事はちゃんとする。マシな食事さえあれば」
「はいはい……戦場でサボられても困る。料理長に言っとくよ。
手元に残るお金、ほとんどなくなるけど文句は言わないよーに」
「分かった」
コールの返事を最後まで聞かないで、アレクシアは立ち上がった。食事ランクを上げることによる完済までの期間のズレを計算しながら、ドッグを後にする。
世界が滅亡の危機に瀕する状況で金、金と言うのも滑稽な話だという自覚はあった。
しかし、もし世界が平和になり、元通りになったとしたら――アレクシアには金が必要だった。
◆2回更新の日記ログ
コール君からクレームがあった。
食事がまずいとのこと。
……。
半分機械だからアレでもいけるかと思ったけど、無理かー。
めんどくさいなー。
てゆーか修理代払ってもらってないのに食事にケチ付けてくること、ある?
図々しくない? 賄いが出るだけマシと思いな?
やれやれ。
食事がまずいとのこと。
……。
半分機械だからアレでもいけるかと思ったけど、無理かー。
めんどくさいなー。
てゆーか修理代払ってもらってないのに食事にケチ付けてくること、ある?
図々しくない? 賄いが出るだけマシと思いな?
やれやれ。
◆アセンブル
◆僚機と合言葉
コール=ターナーとバディを結成した!!
次回フェアギスマインニヒトに協賛し、参戦します
「こちらの商品はいかがかな? いまなら入荷、絶賛未定!!」
(c) 霧のひと