第23回目 午前2時のアザミネ・トウハ
プロフィール

名前
アザミネ・トウハ
愛称
アザミネ
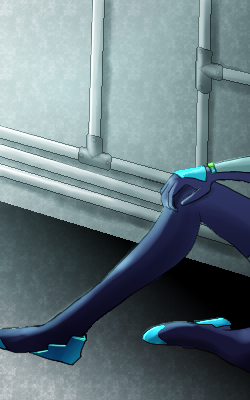 |  |
| 経歴 氏名:アザミネ・トウハ 性別:男性 年齢:15 生年:2006/06/09 身長:178cm 体重:75kg 色覚:正常 視力:B(インプラントによる矯正値) 疾病:粉塵性軽度内臓障害(新生体化処置により寛解状態) 備考:新生体化処置箇所、およびインプラント処理箇所、来歴に関する別紙資料あり 搭乗グレムリン登録名『サーシオネ』(テイマーズ・ケイジ登録番号XXXX-XX-XX) 現搭乗グレムリン仮名『フォールスビーク』 各種制御識適性: 第一種《未来》:微弱 第二種《傷跡》:微弱 第三種《連環》:好適 第四種《希望》:平均 第五種《祝福》:好適 以上は蒼花師団テイマー養成施設「アルテア・スクール」内部資料より。 | |
◆日誌
それを俺は暴風と錯覚した。埃を手で払うように無造作で局地的な、だがそれ故に何の容赦もない、鋼の集合体であるはずのグレムリンさえ塵のように容易く吹き飛ばす不可視の波を。
その加速に危うく吹っ飛びかける意識を引き戻したのは痛覚。規定量を超えた衝撃を察知した棺内エアバッグは淡々と作動して、システム通りに俺をぶん殴る勢いで膨張する。
何が起きている。その手掛かりを探して巡らす視線が捉えたのは未だ生きていたカメラ映像。その中にはっきりと映る、遠ざかってなお変わりがないほど巨大な。そしてグレムリンでありながら人の形すら捨て去った四つ腕の機体《ヴォイドジェネシス》。
そいつは変わらず悠然と立っていた。タワーの内部へ侵入し集合したグレムリンのすべてを、まるで機体と螺子のような体格差で見下ろし相手取りながら。
あの場に戻らなくてはいけなかった。何をされたとしても。あれもまた壊さなければ未来はないと言うのなら、やることなんか一つだった。
気絶しかけてなお手の中にある出力レバー。それを倒せばホーネット・フレームの加速は慣性を振り切って、また俺をあそこへ連れて行くだろう。
しかし鳴り響いた棺内アラートは、俺のその期待を木っ端微塵にぶち壊すものだった。動作チェックでしか聞いたことがなくとも聞き違うはずもない特別警報。
それは破壊されてはいけない箇所が破壊し尽くされていることの通告。つまりは、撃墜が迫る証。つい一秒前まで傷一つなかったこの機体に。
背筋が凍りついたのはその方法がわからなかったからじゃない。思い当たってしまうからこそ、それを覆せないこともまた理解できてしまう。
第四種制御識《希望》の極致、無傷の機体を何の前触れもなく即座に破壊し得る力。意力撃滅と呼ばれるそれは、俺だってこの3週間余りに散々振るってきたものだ。
そして知っているからこそ、法則と、これから起きることもまた予測できる。思念を振るうトリガーとなる敵意は、具体性を伴っていなければならない。
カメラの視野へと飛び込んでくるこの幾条もの粒子砲の光のように。
真っ白に潰れた視界の中で感じるのは前後から挟み込むような衝撃と耳をつんざく破砕音。その後に吹き抜けてきた風は、紛うことなく本物だった。
グレムリンの中でも最も頑丈なはずの操縦棺さえ割り砕くほどの波状攻撃が中のテイマーを無事で済ますはずもない。側頭部、片腕、脚、腹もいくらか。
だがただの一息で苦しいのはそれだけのせいじゃない。呼吸器が中から焼け付くようなその嫌な感覚は、間違いなく粉塵入りの空気を吸った時のそれだ。
追い打ちをかけるように、内臓が捩れそうな感覚とともに下へ下へと急速に身を引く重力。そして見上げれば逆光に浮かぶ、長い嘴を備えた頭のシルエット。
そのすべてを突きつけられれば、否が応でも理解せざるを得なかった。
グレムリン一機分の質量、それを玩具のように吹き飛ばす加速度、そして止めの死体撃ちが、どんな兵器よりも乱雑にタワーの壁をブチ抜いて。
そして『フォールスビーク』というグレムリンを、パーツ以下の鉄クズへと破壊し尽くしたのだと。
『こんなのは勝負じゃないよ』
支え一つない虚空を限りなく落下しながら脳裏をよぎるのは、まだ聞いて30分と経っていないはずの、だがあまりにも遠い台詞。
《ヴォイドステイシス》。タワー上層に鎮座していた、この事態の元凶だったはずのもの。
世界すべてを停滞させる不滅のグレムリン。《傷跡》の制御識の化身。そいつは蓋を開けてみれば、ただのお育ちのいいガキそのものだった。
無敵の座を捨ててむざむざ相手の土俵に上がってくる。一方的でない『勝負』がしたいから。そんな真似はそういう奴にしかできない。自分が死ぬなんて露ほども思ったことがない奴にしか。
それは確かに不死だった奴にしかできない隙で、だからこそ存分に付け入れた。大仰な呼び名に見合うだけの化け物を、破壊し得た。
だが《ヴォイドジェネシス》にそれはない。あれは間違いなく死を知った人間で、死を撒き散らして何の呵責もない大人だ。そういう奴がやるのは対等な勝負なんかじゃなく、ただ一つ、今成されていることに他ならない。
一方的で抵抗しようのない、蹂躙。
『この世界には、シミュレーションとか、勝手な予測とか、想像とか……全部超えたような何かが待っている。
それこそが、未来なんだって、思います」
『死にゆく世界へ手向ける花』、『グレイヴキーパー』、そんな名を名乗ったきり現れなくなった夢の中の女、フヌ。
現実世界で聞いたただ一つの声は、シミュレーションデータに紛れ込まされていたそんな台詞で。だがそれだって、こんなことに引っ掛けるために遺したものじゃなかったろう。
その声は希望に満ちていた。この世界をぶっ潰すものとの仮想戦の場に響くには場違いすぎる、穏やかで期待に満ちた声。
不意に化け物がもう一体現れて息の根を止めてくるような、そして今目の前で起きているような想像の超え方なんか、それを録った時には微塵も浮かんじゃいなかったに違いない。
『未来は人間の視界に捉えるには巨大すぎる』
アンタだってそうだろ、教官。《未来》の制御識の予測ってものは本当にアテにならないってことが、今となっちゃ身に染みて理解できる。
だがそれが当たってくれていた方が万倍よかった。あのスモークの中のグレムリンたちの世界。訳の分からない、だが一応ああした形で知っちゃいる世界が訪れてくれた方がずっと。
こんな。
こんな、目に映しきれないほどの空が、知らない色に塗り変えられていく世界より。
それは夕暮れ、あるいは夜明けに似ていた。空は端から徐々に塗り変わって、境界線が音もなく動いていく。
今はもちろん見慣れた黒と赤でそれが成される時間じゃあない。だが実際、見上げる空は間違いなく蠢いていた。時計に従ったにしてはあまりにも忙しなく。
見慣れた赤色はみるみるうちに面積を失って、代わりに空を覆っていくのは、奇妙な、例えようもない、この世のものとは思えない。
見たこともない、いちめんの青。
青花のエンブレムなら腐るほど見てきた。それに限らなくたって、三大勢力の名前になるほどありふれた原色なんか数え切れないほど使われている。なのにそのどれとも違う。
そこには何もないのに、確かに色があって、透き通っている。
名前は知っている。だがそう呼んでいいのかも、同じ色と当てはめられるのかも分からない、どうしようもない異物。
湧き上がるのは拒否感。それが見慣れた空に我が物顔で陣取って、ぐるりと俺の全周を取り囲んでいくことへの。
こんなことができる可能性なんか一つしかない。そしてそんなことは、あの《ヴォイドステイシス》を見てなきゃ思いつきやしなかったろう。
あの《傷跡》の化身のように、意力撃滅を無造作に振るった《ヴォイドジェネシス》が第四種制御識《希望》の化身だったとしたなら。
その力は戦場においては不可視の銃弾で、無限の力を持つ兵器だ。だが戦場を離れたその本質は違う。
それは望んだことを起こす、世界を望みの方へ変えていく力だと。アルテアではそう言っていて、四種持ちの連中と後でゲラゲラ笑っていた。それが本当ならどんなによかったかと。
それが真実だったとしたら。そしてあの化け物が、その力を無限に拡張したとしたら。
思い当たるような望みは嫌になるほど聞かされてきた。今じゃ見ることもできない青い空。思うまま外に出られる粉塵のない空気。今と比べりゃずっと平和だったとかいう世界。
その頃へ帰りたがる人間なんて腐るほどいて、だがその誰も時計の針なんか戻せやしなかったから、飽きもせずに繰り返されるその話を聞かされるばかりだった。
今となっちゃそれは『聞かされるだけで済んでいた』と言う方がよっぽど正しい。誰もそのための力を持っていなかったという方が。
今じゃあその懐古趣味な、しかし圧倒的多数の望みとやらはあの化け物に組み込まれて、こうして世界を丸ごとくるむ現実に成り果てた。
ああ、こんなことをやらかそうって奴が誰だか知らないが、てめえの眼中に俺達なんぞ入っちゃいないんだろうよ。粉塵の下に生まれ赤い空とともに育ち、その中で戦ってしか生きられない人間のことなんざ。
そんな奴は吐いて捨てるほどいた。だがてめえほど思い上がった奴は初めてだ。
思い上がった、それ以外にどう呼べばいい。てめえの意識と見聞と視界になかったものをそのままいよいよ無かったことにして上から塗り潰す。ただ純粋に続いていくこの先が欲しかった人間がいると気づいてさえいない、その、傲慢!!
「クソがあああああああああああああああああッ!!!!」
煮えくり返る感情を剥き出しにした、喉の裂けるような絶叫。中空へ目標もなく振り上げた拳。だがそれに、空気を震わせてついでに内臓を痛めつける以上の効果はない。
思念ならこれまでのいつよりも宿っているだろう。だがそれに何の力がある。
粉塵の代わりについに世界を覆い尽くしたあの抜けるような空、あの化け物の思念の前に。
振りかざした腕は、目の前で勢いのままあらぬ方向へ曲がっていた。激昂が遮断していたその激痛に気が付いた時、背に何かがようやく触れる。
瞬間、全身をしたたかに打つ痺れるような衝撃と轟音。息を吐き切った肺が反射的に吸い込んだのは、周囲のすべてを満たす海水。
吸い込まれるように落ちた意識が向かう瞼の内側の闇。そこが世界にただ一つ遺された、あの青色のない場所だった。
その加速に危うく吹っ飛びかける意識を引き戻したのは痛覚。規定量を超えた衝撃を察知した棺内エアバッグは淡々と作動して、システム通りに俺をぶん殴る勢いで膨張する。
何が起きている。その手掛かりを探して巡らす視線が捉えたのは未だ生きていたカメラ映像。その中にはっきりと映る、遠ざかってなお変わりがないほど巨大な。そしてグレムリンでありながら人の形すら捨て去った四つ腕の機体《ヴォイドジェネシス》。
そいつは変わらず悠然と立っていた。タワーの内部へ侵入し集合したグレムリンのすべてを、まるで機体と螺子のような体格差で見下ろし相手取りながら。
あの場に戻らなくてはいけなかった。何をされたとしても。あれもまた壊さなければ未来はないと言うのなら、やることなんか一つだった。
気絶しかけてなお手の中にある出力レバー。それを倒せばホーネット・フレームの加速は慣性を振り切って、また俺をあそこへ連れて行くだろう。
しかし鳴り響いた棺内アラートは、俺のその期待を木っ端微塵にぶち壊すものだった。動作チェックでしか聞いたことがなくとも聞き違うはずもない特別警報。
それは破壊されてはいけない箇所が破壊し尽くされていることの通告。つまりは、撃墜が迫る証。つい一秒前まで傷一つなかったこの機体に。
背筋が凍りついたのはその方法がわからなかったからじゃない。思い当たってしまうからこそ、それを覆せないこともまた理解できてしまう。
第四種制御識《希望》の極致、無傷の機体を何の前触れもなく即座に破壊し得る力。意力撃滅と呼ばれるそれは、俺だってこの3週間余りに散々振るってきたものだ。
そして知っているからこそ、法則と、これから起きることもまた予測できる。思念を振るうトリガーとなる敵意は、具体性を伴っていなければならない。
カメラの視野へと飛び込んでくるこの幾条もの粒子砲の光のように。
真っ白に潰れた視界の中で感じるのは前後から挟み込むような衝撃と耳をつんざく破砕音。その後に吹き抜けてきた風は、紛うことなく本物だった。
グレムリンの中でも最も頑丈なはずの操縦棺さえ割り砕くほどの波状攻撃が中のテイマーを無事で済ますはずもない。側頭部、片腕、脚、腹もいくらか。
だがただの一息で苦しいのはそれだけのせいじゃない。呼吸器が中から焼け付くようなその嫌な感覚は、間違いなく粉塵入りの空気を吸った時のそれだ。
追い打ちをかけるように、内臓が捩れそうな感覚とともに下へ下へと急速に身を引く重力。そして見上げれば逆光に浮かぶ、長い嘴を備えた頭のシルエット。
そのすべてを突きつけられれば、否が応でも理解せざるを得なかった。
グレムリン一機分の質量、それを玩具のように吹き飛ばす加速度、そして止めの死体撃ちが、どんな兵器よりも乱雑にタワーの壁をブチ抜いて。
そして『フォールスビーク』というグレムリンを、パーツ以下の鉄クズへと破壊し尽くしたのだと。
『こんなのは勝負じゃないよ』
支え一つない虚空を限りなく落下しながら脳裏をよぎるのは、まだ聞いて30分と経っていないはずの、だがあまりにも遠い台詞。
《ヴォイドステイシス》。タワー上層に鎮座していた、この事態の元凶だったはずのもの。
世界すべてを停滞させる不滅のグレムリン。《傷跡》の制御識の化身。そいつは蓋を開けてみれば、ただのお育ちのいいガキそのものだった。
無敵の座を捨ててむざむざ相手の土俵に上がってくる。一方的でない『勝負』がしたいから。そんな真似はそういう奴にしかできない。自分が死ぬなんて露ほども思ったことがない奴にしか。
それは確かに不死だった奴にしかできない隙で、だからこそ存分に付け入れた。大仰な呼び名に見合うだけの化け物を、破壊し得た。
だが《ヴォイドジェネシス》にそれはない。あれは間違いなく死を知った人間で、死を撒き散らして何の呵責もない大人だ。そういう奴がやるのは対等な勝負なんかじゃなく、ただ一つ、今成されていることに他ならない。
一方的で抵抗しようのない、蹂躙。
『この世界には、シミュレーションとか、勝手な予測とか、想像とか……全部超えたような何かが待っている。
それこそが、未来なんだって、思います」
『死にゆく世界へ手向ける花』、『グレイヴキーパー』、そんな名を名乗ったきり現れなくなった夢の中の女、フヌ。
現実世界で聞いたただ一つの声は、シミュレーションデータに紛れ込まされていたそんな台詞で。だがそれだって、こんなことに引っ掛けるために遺したものじゃなかったろう。
その声は希望に満ちていた。この世界をぶっ潰すものとの仮想戦の場に響くには場違いすぎる、穏やかで期待に満ちた声。
不意に化け物がもう一体現れて息の根を止めてくるような、そして今目の前で起きているような想像の超え方なんか、それを録った時には微塵も浮かんじゃいなかったに違いない。
『未来は人間の視界に捉えるには巨大すぎる』
アンタだってそうだろ、教官。《未来》の制御識の予測ってものは本当にアテにならないってことが、今となっちゃ身に染みて理解できる。
だがそれが当たってくれていた方が万倍よかった。あのスモークの中のグレムリンたちの世界。訳の分からない、だが一応ああした形で知っちゃいる世界が訪れてくれた方がずっと。
こんな。
こんな、目に映しきれないほどの空が、知らない色に塗り変えられていく世界より。
それは夕暮れ、あるいは夜明けに似ていた。空は端から徐々に塗り変わって、境界線が音もなく動いていく。
今はもちろん見慣れた黒と赤でそれが成される時間じゃあない。だが実際、見上げる空は間違いなく蠢いていた。時計に従ったにしてはあまりにも忙しなく。
見慣れた赤色はみるみるうちに面積を失って、代わりに空を覆っていくのは、奇妙な、例えようもない、この世のものとは思えない。
見たこともない、いちめんの青。
青花のエンブレムなら腐るほど見てきた。それに限らなくたって、三大勢力の名前になるほどありふれた原色なんか数え切れないほど使われている。なのにそのどれとも違う。
そこには何もないのに、確かに色があって、透き通っている。
名前は知っている。だがそう呼んでいいのかも、同じ色と当てはめられるのかも分からない、どうしようもない異物。
湧き上がるのは拒否感。それが見慣れた空に我が物顔で陣取って、ぐるりと俺の全周を取り囲んでいくことへの。
こんなことができる可能性なんか一つしかない。そしてそんなことは、あの《ヴォイドステイシス》を見てなきゃ思いつきやしなかったろう。
あの《傷跡》の化身のように、意力撃滅を無造作に振るった《ヴォイドジェネシス》が第四種制御識《希望》の化身だったとしたなら。
その力は戦場においては不可視の銃弾で、無限の力を持つ兵器だ。だが戦場を離れたその本質は違う。
それは望んだことを起こす、世界を望みの方へ変えていく力だと。アルテアではそう言っていて、四種持ちの連中と後でゲラゲラ笑っていた。それが本当ならどんなによかったかと。
それが真実だったとしたら。そしてあの化け物が、その力を無限に拡張したとしたら。
思い当たるような望みは嫌になるほど聞かされてきた。今じゃ見ることもできない青い空。思うまま外に出られる粉塵のない空気。今と比べりゃずっと平和だったとかいう世界。
その頃へ帰りたがる人間なんて腐るほどいて、だがその誰も時計の針なんか戻せやしなかったから、飽きもせずに繰り返されるその話を聞かされるばかりだった。
今となっちゃそれは『聞かされるだけで済んでいた』と言う方がよっぽど正しい。誰もそのための力を持っていなかったという方が。
今じゃあその懐古趣味な、しかし圧倒的多数の望みとやらはあの化け物に組み込まれて、こうして世界を丸ごとくるむ現実に成り果てた。
ああ、こんなことをやらかそうって奴が誰だか知らないが、てめえの眼中に俺達なんぞ入っちゃいないんだろうよ。粉塵の下に生まれ赤い空とともに育ち、その中で戦ってしか生きられない人間のことなんざ。
そんな奴は吐いて捨てるほどいた。だがてめえほど思い上がった奴は初めてだ。
思い上がった、それ以外にどう呼べばいい。てめえの意識と見聞と視界になかったものをそのままいよいよ無かったことにして上から塗り潰す。ただ純粋に続いていくこの先が欲しかった人間がいると気づいてさえいない、その、傲慢!!
「クソがあああああああああああああああああッ!!!!」
煮えくり返る感情を剥き出しにした、喉の裂けるような絶叫。中空へ目標もなく振り上げた拳。だがそれに、空気を震わせてついでに内臓を痛めつける以上の効果はない。
思念ならこれまでのいつよりも宿っているだろう。だがそれに何の力がある。
粉塵の代わりについに世界を覆い尽くしたあの抜けるような空、あの化け物の思念の前に。
振りかざした腕は、目の前で勢いのままあらぬ方向へ曲がっていた。激昂が遮断していたその激痛に気が付いた時、背に何かがようやく触れる。
瞬間、全身をしたたかに打つ痺れるような衝撃と轟音。息を吐き切った肺が反射的に吸い込んだのは、周囲のすべてを満たす海水。
吸い込まれるように落ちた意識が向かう瞼の内側の闇。そこが世界にただ一つ遺された、あの青色のない場所だった。
◆23回更新の日記ログ
日記:
https://privatter.net/p/9330627
*どうして文字数制限の倍もあるんですか? 終わらなかったから……*
https://privatter.net/p/9330627
*どうして文字数制限の倍もあるんですか? 終わらなかったから……*
◆22回更新の日記ログ
掴みかかった側とかかられた側。二人の影が重なれば、元より大きすぎる図体は倍に膨れ上がったようだった。
襟元を掴むのは生身近接戦闘および生徒指導教官。自分と一二を争う体格の持ち主の視線と怒号を至近で浴びてなお、男の顔に一切の動揺はない。
第三種制御識《連環》指導教官、アルテア一の鉄面皮はこの場でも揺らいじゃいなかった。
「あんなものに手ェ出すなんざ青花の名折れに決まってるだろうが!! その意味、分からねェなんざ言わせねェぞ……!!」
「その『あんなもの』がこの船に積まれていることをどう考える、ラーズイ教官。
この件に関する緘口令がいつまで保つかも、元より今保っているのかも分からない状態だ。不信が全生徒へ伝播するより早く手を打たなくてはならない。
それを考えれば、精神干渉および記憶そのものの改変は即効性と確実性の双方を確保する手段と」
在んのかよ。仮にも青花の船に。そんなモンが。
心中の呟きがもし肉声として出たなら、そいつはさぞかし酷く引き攣った絞り出すような音になっていたことだろう。
いくらなんだってそこまで酷いとは思っちゃいなかった。そいつは青花が後生大事にしてやまない自由とやらの最大にして最悪の敵で、使ったことがあるなんざ公言しようモンならゴミを見る目を向けられる程度じゃ済まないものだ。
この場の全員、それを知らないはずもないのに。
その思考と、そして続いていた話を中断させたのはラーズイが振るった拳だった。凍りついたように固まっていた周囲がようやく動き出し、大の男数人が群がって無理矢理に二人を引き離す。
殴られた側はといえば懲りた様子の一つもなく、赤く腫れ上がった痕に手を当てながら遠ざかる大柄な影を眺めていた。
「どうせもうあの女に使った後だろうに」
「あれはそうした敵対者への最終手段として用意されたものだ。決して青花の同胞の心を曲げるためにあるものじゃない。
それにもし許可が出るのなら、これだけ頭を悩ませて子供たちの相手をしていることそのものが無意味にならないかい」
声をかけたのは第一種《未来》担当、つまりこの光景の記憶者自身。
「子供達へもまた最終手段となり得るのではないか、また現状はそれを選択肢として考慮すべき事態ではないかと言っている」
「その提案が出るのももっともだね。だが、僕も反対を表明しておこう。ラーズイ教官ほど荒っぽい形ではないにしても」
「まったく肩身が狭いな。囲まれた気分だ」
「分かっていただろうに。
だがその中で、少数派であろうことに臆せず提案を行ってくれた君に敬意を評するよ。後でビエチル教官の世話になるといい」
「現状、保健室は可能な限りのリソースを生徒のメンタルケアへ充てるべきだ。
自分もまた、装置が必要なくなるのならその方が良いと強く思っていることは理解してもらいたい」
「……それを初めに言っておけば、こんなことにはならなかったんじゃあ」
眉を下げた小柄な女、第二種《傷跡》指導教官が小さな声で割って入るのを聞いても、第三種指導教官の仏頂面は変わらない。
その目は細められたまま、違いないと同調する第一種教官の方へ向く。
「その点は確かに自分の不行き届きだ。だが今は未来の話に少しでも時間を割きたい。
……反対派だというなら聞いておきたい、ブラウ教官。
これを看過したことで生徒の離反および青花のグレムリンに関係する技術流出が発生した場合、どう対処する」
「それが発生しないように、またあれにも頼らないように、他のあらゆる手を尽くした前提、ということで構わないかい」
「無論」
「ならば僕は、それが彼らの自由の下の選択だと考える。与えられた情報の元、自分の意志に基づいて判断した結果だと。
つまりその時点で『対処』はすべて済んでおり、それは失敗に終わった。その結果として挙げられた問題が発生している、という見方だね」
「答えになっていない。
それに、元とする情報そのものを歪められたうえでの選択を『意志に基づいた判断』と呼べるのか」
「その歪みを矯正するあらゆる努力を尽くしてなお通じないのなら、それは彼ら自身があちらを信じる方を選んだということだろう。
それに基づいて彼らが新たな所属を得るなら、それが彼らの生き延び方で、自由を行使した結果だ」
聞いている鬼教官の眉が、そこでようやく動いた。その怒りとも呆れともつかない顔は、俺たちが唯一知っているあいつの表情らしい表情だ。小さく開けた口から漏れる、深い溜息までがセット。
「理想主義者の同僚を持つと苦労する」
「それが許されるのが師団であるべきだ、と思っているだけだよ」
そういうところだよ。そう言いたげに睨めつける目が、思わぬところから伸びた手に振り返る。
巌の巨体の隣に座るとなお小さく見える第二種教官の女が、震える指で小さく肩を叩いていた。
「……そこまで思い切ったことは言えませんし、はっきりとした対案を持っているわけでもないんですが。
私も、ブラウ教官に賛同します」
続けろとばかり注がれる目一つにさえ小さく肩を跳ねさせて悲鳴を飲み込み、しかし合わせる視線は決然としている。
似合わない顔だと思った。あの女、こんな面なんてできたのか。
「歪められた情報のみによって判断するのは意志とは呼べない。それは正しいと思います。
ですが……彼らの耳に入る情報や選択肢を一番歪めて制限しているのは、私たち自身じゃないでしょうか。
船を降りる自由もなく本人の嗜好や興味とも関係なく、幼い頃から軍事訓練をさせる。私たちがしているのは間違いなく、彼らの人生への最も強い束縛です。
そんな私たちが、あのやり口を責められるんでしょうか。これ以上私たちの都合で、記憶や心まで歪めていいんでしょうか。
だから、できれば、私は彼らに自分で選んで欲しいんです。説明を尽くした上、証拠を示し尽くした上で、納得して」
「それはもっともな指摘だ。我々は養育者としては厳格で、狭量だろう。それも非常に。だがその代わりに、彼らの命だけは守ることができる。
青花グレムリンの機密を握る彼らが青花に不信を抱き離反すれば、口封じを考える者は必ず出るだろう。
一度は師団の手で救ったものを、同胞の手でむざむざ散らす。実に無意味だ。それだけは避けたい」
その言葉は的確に一番の泣き所を突いたんだろう。
ものも言えなくなってすっかりいつものように縮こまった女から、ブラウ教官が選手交代とばかり言葉を引き継ぐ。
「大事な指摘をありがとう、ニフ教官。そう、僕たちは彼らの命を握って、今既に自由を制限している。
だがそれがいつまで続く? 送り出した一期生たちのように、彼らもいずれ出ていく身だ。その先を僕らが管理することは難しい。
青花の倫理を冒してここで彼らを守っても、次もそうしてやれるわけじゃない。
それを考えれば、僕らが教えるべきはただ、自由と命はいつだって天秤にかかるということ――」
自由と、命。
先から出ていたその二つがそうして並べられた時に、目の前の風景のすべてが爆ぜるように崩れ落ちた。
ふざけるな、どんな兵器よりも強い思念の業怒に一瞬にして焼き尽くされて。
それが天秤にかけられる意味なんか知りすぎるほど知っている。どちらもが。どちらもが当たり前にあったなら、皆あんなことにはならなかったのに。
それを身で教えるのがおまえたちのやり方だった。あの場でどんなに議論を尽くしているようでも、俺は行き着いたところを知っている。
口封じをする側になったのはお前たちだ、さもなきゃお前たちは俺たちの頭まで弄るつもりだっただと、どっちにしろお前たちは天秤から俺たちを下ろす気なんかなかったんだ。
そう叫び続けてすべてを遠ざけた場には、もう何一つ残っていなくて。
『――フォグストラクト・ワン、第一試合! いま開始です!!』
その虚空に響いてきたのはあまりに場違いな、悩みの欠片も感じられない声。
振り向くように意識を向ければずっと遠くにあったその光景の方から勝手にこちらへ近づいてきて、真っ白な点のようだったその中にあるものが次第にはっきりと見えてくる。
立ち込める白く色濃い煙の中へ消えてはまた現れるいくつもの人型。
時には互いが交錯する一瞬に手の武器を振るい、轟音とともに銃弾を放つ。二本の足があれどステップもなければ走ることもない、気嚢とブースターで制御された飛翔の動きは見間違いようもなく。
(……グレムリン?)
だがそれにしちゃどうも可笑しい。どれもこれも見たことのないシルエットのパーツ、各自が見せるのはあり得ないほどの急加速に異常な頑丈性。それにこれほどの数の機体が飛ぶ場所が屋内のはずがない。
何より、こんなにも。
『ここで冬橋選手が被撃墜!
あまりにも早い退場に会場も動揺を隠せない! チーム・レッドはこの数の不利をここからどうカバーするか!?」
こんなにも明るい戦闘が、あってたまるか。
そう吐き捨てたところで、お望み通りとばかりその光景は消えていく。
不意に空から垂れこめた、粉塵よりなお濃いどろりとした赤色に塗り潰されて。
襟元を掴むのは生身近接戦闘および生徒指導教官。自分と一二を争う体格の持ち主の視線と怒号を至近で浴びてなお、男の顔に一切の動揺はない。
第三種制御識《連環》指導教官、アルテア一の鉄面皮はこの場でも揺らいじゃいなかった。
「あんなものに手ェ出すなんざ青花の名折れに決まってるだろうが!! その意味、分からねェなんざ言わせねェぞ……!!」
「その『あんなもの』がこの船に積まれていることをどう考える、ラーズイ教官。
この件に関する緘口令がいつまで保つかも、元より今保っているのかも分からない状態だ。不信が全生徒へ伝播するより早く手を打たなくてはならない。
それを考えれば、精神干渉および記憶そのものの改変は即効性と確実性の双方を確保する手段と」
在んのかよ。仮にも青花の船に。そんなモンが。
心中の呟きがもし肉声として出たなら、そいつはさぞかし酷く引き攣った絞り出すような音になっていたことだろう。
いくらなんだってそこまで酷いとは思っちゃいなかった。そいつは青花が後生大事にしてやまない自由とやらの最大にして最悪の敵で、使ったことがあるなんざ公言しようモンならゴミを見る目を向けられる程度じゃ済まないものだ。
この場の全員、それを知らないはずもないのに。
その思考と、そして続いていた話を中断させたのはラーズイが振るった拳だった。凍りついたように固まっていた周囲がようやく動き出し、大の男数人が群がって無理矢理に二人を引き離す。
殴られた側はといえば懲りた様子の一つもなく、赤く腫れ上がった痕に手を当てながら遠ざかる大柄な影を眺めていた。
「どうせもうあの女に使った後だろうに」
「あれはそうした敵対者への最終手段として用意されたものだ。決して青花の同胞の心を曲げるためにあるものじゃない。
それにもし許可が出るのなら、これだけ頭を悩ませて子供たちの相手をしていることそのものが無意味にならないかい」
声をかけたのは第一種《未来》担当、つまりこの光景の記憶者自身。
「子供達へもまた最終手段となり得るのではないか、また現状はそれを選択肢として考慮すべき事態ではないかと言っている」
「その提案が出るのももっともだね。だが、僕も反対を表明しておこう。ラーズイ教官ほど荒っぽい形ではないにしても」
「まったく肩身が狭いな。囲まれた気分だ」
「分かっていただろうに。
だがその中で、少数派であろうことに臆せず提案を行ってくれた君に敬意を評するよ。後でビエチル教官の世話になるといい」
「現状、保健室は可能な限りのリソースを生徒のメンタルケアへ充てるべきだ。
自分もまた、装置が必要なくなるのならその方が良いと強く思っていることは理解してもらいたい」
「……それを初めに言っておけば、こんなことにはならなかったんじゃあ」
眉を下げた小柄な女、第二種《傷跡》指導教官が小さな声で割って入るのを聞いても、第三種指導教官の仏頂面は変わらない。
その目は細められたまま、違いないと同調する第一種教官の方へ向く。
「その点は確かに自分の不行き届きだ。だが今は未来の話に少しでも時間を割きたい。
……反対派だというなら聞いておきたい、ブラウ教官。
これを看過したことで生徒の離反および青花のグレムリンに関係する技術流出が発生した場合、どう対処する」
「それが発生しないように、またあれにも頼らないように、他のあらゆる手を尽くした前提、ということで構わないかい」
「無論」
「ならば僕は、それが彼らの自由の下の選択だと考える。与えられた情報の元、自分の意志に基づいて判断した結果だと。
つまりその時点で『対処』はすべて済んでおり、それは失敗に終わった。その結果として挙げられた問題が発生している、という見方だね」
「答えになっていない。
それに、元とする情報そのものを歪められたうえでの選択を『意志に基づいた判断』と呼べるのか」
「その歪みを矯正するあらゆる努力を尽くしてなお通じないのなら、それは彼ら自身があちらを信じる方を選んだということだろう。
それに基づいて彼らが新たな所属を得るなら、それが彼らの生き延び方で、自由を行使した結果だ」
聞いている鬼教官の眉が、そこでようやく動いた。その怒りとも呆れともつかない顔は、俺たちが唯一知っているあいつの表情らしい表情だ。小さく開けた口から漏れる、深い溜息までがセット。
「理想主義者の同僚を持つと苦労する」
「それが許されるのが師団であるべきだ、と思っているだけだよ」
そういうところだよ。そう言いたげに睨めつける目が、思わぬところから伸びた手に振り返る。
巌の巨体の隣に座るとなお小さく見える第二種教官の女が、震える指で小さく肩を叩いていた。
「……そこまで思い切ったことは言えませんし、はっきりとした対案を持っているわけでもないんですが。
私も、ブラウ教官に賛同します」
続けろとばかり注がれる目一つにさえ小さく肩を跳ねさせて悲鳴を飲み込み、しかし合わせる視線は決然としている。
似合わない顔だと思った。あの女、こんな面なんてできたのか。
「歪められた情報のみによって判断するのは意志とは呼べない。それは正しいと思います。
ですが……彼らの耳に入る情報や選択肢を一番歪めて制限しているのは、私たち自身じゃないでしょうか。
船を降りる自由もなく本人の嗜好や興味とも関係なく、幼い頃から軍事訓練をさせる。私たちがしているのは間違いなく、彼らの人生への最も強い束縛です。
そんな私たちが、あのやり口を責められるんでしょうか。これ以上私たちの都合で、記憶や心まで歪めていいんでしょうか。
だから、できれば、私は彼らに自分で選んで欲しいんです。説明を尽くした上、証拠を示し尽くした上で、納得して」
「それはもっともな指摘だ。我々は養育者としては厳格で、狭量だろう。それも非常に。だがその代わりに、彼らの命だけは守ることができる。
青花グレムリンの機密を握る彼らが青花に不信を抱き離反すれば、口封じを考える者は必ず出るだろう。
一度は師団の手で救ったものを、同胞の手でむざむざ散らす。実に無意味だ。それだけは避けたい」
その言葉は的確に一番の泣き所を突いたんだろう。
ものも言えなくなってすっかりいつものように縮こまった女から、ブラウ教官が選手交代とばかり言葉を引き継ぐ。
「大事な指摘をありがとう、ニフ教官。そう、僕たちは彼らの命を握って、今既に自由を制限している。
だがそれがいつまで続く? 送り出した一期生たちのように、彼らもいずれ出ていく身だ。その先を僕らが管理することは難しい。
青花の倫理を冒してここで彼らを守っても、次もそうしてやれるわけじゃない。
それを考えれば、僕らが教えるべきはただ、自由と命はいつだって天秤にかかるということ――」
自由と、命。
先から出ていたその二つがそうして並べられた時に、目の前の風景のすべてが爆ぜるように崩れ落ちた。
ふざけるな、どんな兵器よりも強い思念の業怒に一瞬にして焼き尽くされて。
それが天秤にかけられる意味なんか知りすぎるほど知っている。どちらもが。どちらもが当たり前にあったなら、皆あんなことにはならなかったのに。
それを身で教えるのがおまえたちのやり方だった。あの場でどんなに議論を尽くしているようでも、俺は行き着いたところを知っている。
口封じをする側になったのはお前たちだ、さもなきゃお前たちは俺たちの頭まで弄るつもりだっただと、どっちにしろお前たちは天秤から俺たちを下ろす気なんかなかったんだ。
そう叫び続けてすべてを遠ざけた場には、もう何一つ残っていなくて。
『――フォグストラクト・ワン、第一試合! いま開始です!!』
その虚空に響いてきたのはあまりに場違いな、悩みの欠片も感じられない声。
振り向くように意識を向ければずっと遠くにあったその光景の方から勝手にこちらへ近づいてきて、真っ白な点のようだったその中にあるものが次第にはっきりと見えてくる。
立ち込める白く色濃い煙の中へ消えてはまた現れるいくつもの人型。
時には互いが交錯する一瞬に手の武器を振るい、轟音とともに銃弾を放つ。二本の足があれどステップもなければ走ることもない、気嚢とブースターで制御された飛翔の動きは見間違いようもなく。
(……グレムリン?)
だがそれにしちゃどうも可笑しい。どれもこれも見たことのないシルエットのパーツ、各自が見せるのはあり得ないほどの急加速に異常な頑丈性。それにこれほどの数の機体が飛ぶ場所が屋内のはずがない。
何より、こんなにも。
『ここで冬橋選手が被撃墜!
あまりにも早い退場に会場も動揺を隠せない! チーム・レッドはこの数の不利をここからどうカバーするか!?」
こんなにも明るい戦闘が、あってたまるか。
そう吐き捨てたところで、お望み通りとばかりその光景は消えていく。
不意に空から垂れこめた、粉塵よりなお濃いどろりとした赤色に塗り潰されて。
◆21回更新の日記ログ
違う。見たいのはこんな個人の話じゃあない。
そう意識すれば今まで見ていた面接室の風景もまた急激に遠ざかる。それとともに視界に飛び込む、数多見える記憶のイメージ。その中からさっきのように、求めるものを探して向かう先を決めていく。
アルテアに関わった個人としての記憶は、おそらく必要ない。アルテアという組織そのものの話を。
そう望んで再び音もなく駆け、そうして辿り着く一つの光景。
演壇の上には白髪の爺。骨と皮みたいな見てくれからは想像できないような声で、口角泡飛ばして居並んだ聴衆へ叫んでいる。
そいつが誰だか知らないが、聞く側は雁首揃えて規律正しくその話に耳を傾けていた。随分と見慣れた軍隊式の整列で、その割には統制に欠けた好き好きの服装で。
『――グレムリンという新たな、そしてすべてを過去とする兵力に対し!
真紅連理はその統制によって才ある子供をその意志に関わらず取り立て、悪鬼のシートへ座らせるだろう!
翡翠経典はその技術によって才ある子供を創り出し、あの悪鬼のコックピットへ収めるだろう!
翻って青花師団はどうか。我々には強制力はなく、また科学力もない。
だが我々には理想がある。そのために撒く種と、それが咲かす美しい花。その結実によって生まれた過去よりの結晶がある!
この計画もまた、新たに青花の土に撒かれる種子の一つだ!
今、未来は混沌としている。日に日に濃度を増し、青空を遮るあの憎き粉塵のように。
その新時代において、我々が三大勢力の一角として存在感を保ち続けるために。師団成立以来幾度も迎えた時代の転換期、その一つに今まさに直面していることを認め、次の百年に青花師団を続けてゆくために。
そして次代を担う一人でも多くの子供たちに教育と帰属とを与え、光の当たる場で生かすためにこの計画はある!!
この明日をも知れぬ世で治安は急速に悪化し、その犠牲が増え続けていることは知っての通りだ。一刻も早く、この闇に救いの糸を垂らさねばならない!!」
そのご高説は間違いなく、もうしばらく長々と続く予定だっただろう。興奮のあまりにか爺が言葉を切って胸を押さえることがなければ。
壇上の奥に控えていた取り巻きらしい若いのが慌てて立ち上がり、様子を見て声をかけ肩を貸す。
よろめきながら退出する爺を送るように湧き上がった拍手も、その姿が見えなくなればあっという間にまばらになった。入れ替わるように部屋を満たすのはそこここで交わされるざわめき。
「治安のためだって言うなら、浮浪児をどうにかしたいだけじゃないのかね」
「闇上がりの傭兵……彼らほどの実力者はそもそも養成できるものなんでしょうか」
「これで散々バカにされた福祉も少しはマシになるといいんだけどな」
「しかし、あの調子ではパトロン殿もいつまで保つことだかな。次代が手を引くと言い出した時にも行き先くらいは斡旋してほしいものだが」
それを耳に入れながら、若き教官の目は未だ無人の演壇に向いていた。
そろそろ潮時か。これ以上留まって、何かしらの収穫があるとは思えない。
だが着実に望む光景には近づいていた。組織としてのアルテアのお題目。お綺麗で長ったらしいそれは当然外向きのものだろうが、先ほど見た光景よりはよほど求めた通りのものだ。
それを見られたのはやり方を分かってきたってことなのか、それとも単なる偶然なのか。
それを思考によって確かめるほど悠長には構えていられない。必要なのは再度の、そして更に的を絞った試行。
そう結論付ける間にも足は止めない。行き過ぎていく光景はどんどんと見覚えのあるものが多くなっていく。
幾度も通った教練船の昇降口。こいつにとっては同僚の、別の教官の顔。その近くへ浮かんだ風景は講義中だろう。机に一面居並んだガキどもの姿。その中には俺もいた。
だんだん時期は、俺の知る頃へと近づいてきている。
その中で探るとしたら。そう考えられる時間も長くはない。けれど、ぱっと思いつくものはある。
真っ暗な布団の中で語られた外のこと。見る影もないほどひどい顔になったルームメイト。あのことを、教官たちだって知らないはずはない。ああなるまであいつを閉じ込め問い詰めたのは、他ならぬ船の教官たちなのだから。
教えろ。答えろ。
お前たちから見て、あれはどう見えていた。
「終わったぞ」
その声は、部屋のほとんど全員を一斉に振り向かせた割には随分と覇気のないものだった。
時季としてはいつ頃なのか、席のほとんどすべてが埋まった職員室の入口でそれを告げた男は射撃指導教官だ。その表情は声色と同じくひどく固い。一度たりとも見たことがないほどに。
「真紅の差し金だ。あの女は金を積まれただけのフリーランスに過ぎないようだが。
うまく丸め込んで、生徒を引き抜けりゃ万々歳だったんだろうな」
『女』。生徒を引き抜こうとした女。そしてアルテア中の教官にこれほどの注目を向けられる女。
背筋に冷たいものが走る。そんな奴は一人しか浮かばない。
どことも分からない『家』に、級友を連れて行こうとした狂った女。確かにあいつは、引き離された時教官たちに『連れていかれた』と言っていた。
差し金。差し金? あいつは誰かが差し向けていた? 俺たちを狙って?
そんなはずはない。だって。その先は続かない。今見ているのは間違いなく記憶そのもののはずだ。そのどこに誤魔化しようがある。俺たちと違って、嘘を教えられるはずもない人間の見たものに。
その動揺はこの場の誰にも伝わることはない。元より俺は、これを聞いているはずの人間じゃない。
「後は何らかの形で接触できりゃいいって状態までお膳立てされてたそうだ。あの脱走自体には関与してない。あれは単純なこっちの見落としってこったな。
相も変わらず目の敵にされてるらしい。嗅ぎつけてくる程度には」
静まり返った部屋にその言葉が響けば、それとともに男の纏う重々しい空気までもが同時に室内へ広がっていくようだった。
吸い込んだそれに気が逸って堪らないのだろう。それに口々に音を乗せて、各人が好き勝手に意見だか感想だかを吐き出す。
「真実に嘘を混ぜるあの手口、背後に何かなければ実行できるまいと思っていたが。やはり……」
「それなら航路ももう割れてると考えた方がいいでしょうね。再考が必要でしょう、寄港先候補と青花船団の移動予定リストを」
「船団合流の際のチェックも更に厳重にしなきゃだよね。寄る回数自体減らした方がいいかも」
「やっと第一期生を送り出したところだって言うのに。いつだって前途多難でしたが最大級ですよ」
「このタイミングってのに嫌な予感がするんだよなあ。まさか漏洩源は……」
てんでまとまりなく話したいだけ続くかと思われたその声は、予想に反して徐々に減っていく。
いや、喋っていた連中が自主的にその口を少しずつ閉じていた。室内に意見表明としておずおずと掲げられた手に気づいた者から。
「すみません、これは、子供達には……特に、当事者の彼らにはどう伝えるべきなのでしょう。
聴取の限り、彼らはあちらの話を信じている可能性が高いんですよね。可能な限り速やかにこれを伝えて、こちらを信用してもらい直さなければ」
ひときわ小さなその手は見慣れたものだ。第二種《傷跡》担当教官、俺たちにすら舐められっぱなしだった気も体も小さい女。
その声の後を隣の男が継ぐ。棺に収まることが不思議なほどの岩じみた巨躯に、散々見慣れた無表情のいかつい顔、その見てくれ通りのアルテアきっての鬼教官。第三種《連環》担当。
「今から信用が得られる可能性は低いと言わざるを得ない。子供たちが奴の話を信じ込んだ時点で、既に向こうの仕掛けは成功していると言っていい。
生徒を手に入れることは、向こうにとってはおまけ程度だろう」
「説明をしたところで意味はないと?」
「必要とは思っている。だが」
再び反論のために開こうとした女の口を音もなく閉じたのは、持ち主に似て堂々たる存在感を放ちながら高々と掲げられた男の腕。
「論議を提案する。
『誠実な説明』に効果がなかった際の第二案、および可能ならば第三案を今のうちに決定しておきたい。
特に、装置の使用を是とするかについて」
その提案を耳にしてさっと青ざめた女の顔は、あっという間に隠れて見えなくなった。
装置。その単語が聞こえるや否やほとんど反射的な速度で席を立って挙げられた手の主へ掴みかかった、同じくらいの巨漢の陰に。
そう意識すれば今まで見ていた面接室の風景もまた急激に遠ざかる。それとともに視界に飛び込む、数多見える記憶のイメージ。その中からさっきのように、求めるものを探して向かう先を決めていく。
アルテアに関わった個人としての記憶は、おそらく必要ない。アルテアという組織そのものの話を。
そう望んで再び音もなく駆け、そうして辿り着く一つの光景。
演壇の上には白髪の爺。骨と皮みたいな見てくれからは想像できないような声で、口角泡飛ばして居並んだ聴衆へ叫んでいる。
そいつが誰だか知らないが、聞く側は雁首揃えて規律正しくその話に耳を傾けていた。随分と見慣れた軍隊式の整列で、その割には統制に欠けた好き好きの服装で。
『――グレムリンという新たな、そしてすべてを過去とする兵力に対し!
真紅連理はその統制によって才ある子供をその意志に関わらず取り立て、悪鬼のシートへ座らせるだろう!
翡翠経典はその技術によって才ある子供を創り出し、あの悪鬼のコックピットへ収めるだろう!
翻って青花師団はどうか。我々には強制力はなく、また科学力もない。
だが我々には理想がある。そのために撒く種と、それが咲かす美しい花。その結実によって生まれた過去よりの結晶がある!
この計画もまた、新たに青花の土に撒かれる種子の一つだ!
今、未来は混沌としている。日に日に濃度を増し、青空を遮るあの憎き粉塵のように。
その新時代において、我々が三大勢力の一角として存在感を保ち続けるために。師団成立以来幾度も迎えた時代の転換期、その一つに今まさに直面していることを認め、次の百年に青花師団を続けてゆくために。
そして次代を担う一人でも多くの子供たちに教育と帰属とを与え、光の当たる場で生かすためにこの計画はある!!
この明日をも知れぬ世で治安は急速に悪化し、その犠牲が増え続けていることは知っての通りだ。一刻も早く、この闇に救いの糸を垂らさねばならない!!」
そのご高説は間違いなく、もうしばらく長々と続く予定だっただろう。興奮のあまりにか爺が言葉を切って胸を押さえることがなければ。
壇上の奥に控えていた取り巻きらしい若いのが慌てて立ち上がり、様子を見て声をかけ肩を貸す。
よろめきながら退出する爺を送るように湧き上がった拍手も、その姿が見えなくなればあっという間にまばらになった。入れ替わるように部屋を満たすのはそこここで交わされるざわめき。
「治安のためだって言うなら、浮浪児をどうにかしたいだけじゃないのかね」
「闇上がりの傭兵……彼らほどの実力者はそもそも養成できるものなんでしょうか」
「これで散々バカにされた福祉も少しはマシになるといいんだけどな」
「しかし、あの調子ではパトロン殿もいつまで保つことだかな。次代が手を引くと言い出した時にも行き先くらいは斡旋してほしいものだが」
それを耳に入れながら、若き教官の目は未だ無人の演壇に向いていた。
そろそろ潮時か。これ以上留まって、何かしらの収穫があるとは思えない。
だが着実に望む光景には近づいていた。組織としてのアルテアのお題目。お綺麗で長ったらしいそれは当然外向きのものだろうが、先ほど見た光景よりはよほど求めた通りのものだ。
それを見られたのはやり方を分かってきたってことなのか、それとも単なる偶然なのか。
それを思考によって確かめるほど悠長には構えていられない。必要なのは再度の、そして更に的を絞った試行。
そう結論付ける間にも足は止めない。行き過ぎていく光景はどんどんと見覚えのあるものが多くなっていく。
幾度も通った教練船の昇降口。こいつにとっては同僚の、別の教官の顔。その近くへ浮かんだ風景は講義中だろう。机に一面居並んだガキどもの姿。その中には俺もいた。
だんだん時期は、俺の知る頃へと近づいてきている。
その中で探るとしたら。そう考えられる時間も長くはない。けれど、ぱっと思いつくものはある。
真っ暗な布団の中で語られた外のこと。見る影もないほどひどい顔になったルームメイト。あのことを、教官たちだって知らないはずはない。ああなるまであいつを閉じ込め問い詰めたのは、他ならぬ船の教官たちなのだから。
教えろ。答えろ。
お前たちから見て、あれはどう見えていた。
「終わったぞ」
その声は、部屋のほとんど全員を一斉に振り向かせた割には随分と覇気のないものだった。
時季としてはいつ頃なのか、席のほとんどすべてが埋まった職員室の入口でそれを告げた男は射撃指導教官だ。その表情は声色と同じくひどく固い。一度たりとも見たことがないほどに。
「真紅の差し金だ。あの女は金を積まれただけのフリーランスに過ぎないようだが。
うまく丸め込んで、生徒を引き抜けりゃ万々歳だったんだろうな」
『女』。生徒を引き抜こうとした女。そしてアルテア中の教官にこれほどの注目を向けられる女。
背筋に冷たいものが走る。そんな奴は一人しか浮かばない。
どことも分からない『家』に、級友を連れて行こうとした狂った女。確かにあいつは、引き離された時教官たちに『連れていかれた』と言っていた。
差し金。差し金? あいつは誰かが差し向けていた? 俺たちを狙って?
そんなはずはない。だって。その先は続かない。今見ているのは間違いなく記憶そのもののはずだ。そのどこに誤魔化しようがある。俺たちと違って、嘘を教えられるはずもない人間の見たものに。
その動揺はこの場の誰にも伝わることはない。元より俺は、これを聞いているはずの人間じゃない。
「後は何らかの形で接触できりゃいいって状態までお膳立てされてたそうだ。あの脱走自体には関与してない。あれは単純なこっちの見落としってこったな。
相も変わらず目の敵にされてるらしい。嗅ぎつけてくる程度には」
静まり返った部屋にその言葉が響けば、それとともに男の纏う重々しい空気までもが同時に室内へ広がっていくようだった。
吸い込んだそれに気が逸って堪らないのだろう。それに口々に音を乗せて、各人が好き勝手に意見だか感想だかを吐き出す。
「真実に嘘を混ぜるあの手口、背後に何かなければ実行できるまいと思っていたが。やはり……」
「それなら航路ももう割れてると考えた方がいいでしょうね。再考が必要でしょう、寄港先候補と青花船団の移動予定リストを」
「船団合流の際のチェックも更に厳重にしなきゃだよね。寄る回数自体減らした方がいいかも」
「やっと第一期生を送り出したところだって言うのに。いつだって前途多難でしたが最大級ですよ」
「このタイミングってのに嫌な予感がするんだよなあ。まさか漏洩源は……」
てんでまとまりなく話したいだけ続くかと思われたその声は、予想に反して徐々に減っていく。
いや、喋っていた連中が自主的にその口を少しずつ閉じていた。室内に意見表明としておずおずと掲げられた手に気づいた者から。
「すみません、これは、子供達には……特に、当事者の彼らにはどう伝えるべきなのでしょう。
聴取の限り、彼らはあちらの話を信じている可能性が高いんですよね。可能な限り速やかにこれを伝えて、こちらを信用してもらい直さなければ」
ひときわ小さなその手は見慣れたものだ。第二種《傷跡》担当教官、俺たちにすら舐められっぱなしだった気も体も小さい女。
その声の後を隣の男が継ぐ。棺に収まることが不思議なほどの岩じみた巨躯に、散々見慣れた無表情のいかつい顔、その見てくれ通りのアルテアきっての鬼教官。第三種《連環》担当。
「今から信用が得られる可能性は低いと言わざるを得ない。子供たちが奴の話を信じ込んだ時点で、既に向こうの仕掛けは成功していると言っていい。
生徒を手に入れることは、向こうにとってはおまけ程度だろう」
「説明をしたところで意味はないと?」
「必要とは思っている。だが」
再び反論のために開こうとした女の口を音もなく閉じたのは、持ち主に似て堂々たる存在感を放ちながら高々と掲げられた男の腕。
「論議を提案する。
『誠実な説明』に効果がなかった際の第二案、および可能ならば第三案を今のうちに決定しておきたい。
特に、装置の使用を是とするかについて」
その提案を耳にしてさっと青ざめた女の顔は、あっという間に隠れて見えなくなった。
装置。その単語が聞こえるや否やほとんど反射的な速度で席を立って挙げられた手の主へ掴みかかった、同じくらいの巨漢の陰に。
◆20回更新の日記ログ
「僕の知ってる店ではここのバイオチキンが一番本物に近いんだよ」
「本物、食ったことないスね」
「そうか、まあ予習には丁度いいだろう。試していきなさい」
自分で言い出しておきながら、心底馬鹿馬鹿しいという感想しか浮かんではこなかった。
この、高級ですよとひけらかしやしなくても分かる洒落た店。明らかにそこに望まれた客じゃあない、対塵スーツそのままの俺。それを何一つ気にかけず、ただそこに俺がいるということだけに奇妙に浮き足立った教官。
目の前に並ぶ鼻をつく香料がふんだんに使われた肉、けばげばしい合成緑に着色されたバイオビーンズ、そして泡を立てるビールもそう。
そして、ここに連れられてきた理由も。
「それじゃ」
「いきなり行くね。乾杯くらいはしたかったものだが」
「……あー、すんません」
「いや、構わないよ。君からお誘いが来ただけで嬉しいことだ」
「随分な評価、ありがとうございます」
「在学中の君は、こういうことからは一番遠い子だったと思っていたからね」
酒教えてくれませんか、なんて、旗艦で会ったあの日にねじ込まれた走り書きの連絡先をどうにか解読して、突然送り付けたそんな誘い文句。
検討を重ねてすらこれしか思いつけない自分も救いようのない馬鹿だなと思ったが、乗ってくるこいつは輪をかけて馬鹿だなと、先導するその背へ送る視線は自分でも分かるほど冷たかった。
本当にそんな能天気な理由で人を、それもこんな相手なんぞ呼び出しやしない。ただ今聞きたいことを聞き出せそうな相手などこれしかなく、今を逃せば機はないかもしれないという危機感、あるいは今以上の機なんてこれより後には来ないかもしれない、そういう期待感に急かされただけ。
もし、世界がこれ以上保たないとしたら。世界の不具合とやらが拡大し続けて、奮戦空しく俺たちは無だか死だかカタストロフィだかに放り込まれるとしたら?
その可能性は絵空事だと笑い飛ばすには大きくなりすぎた。あの綻びそのものの姿をした未識別として、目の前に形を取って現れるほどに。
「ノーコメントで。
……でも、覚えててもらえてんのは本当にありがたいですね」
「これでも教えた身だからね、教えた相手のことはできる限り覚えておきたいさ」
「昔の話ができる相手なんざそうそういないスからね、このご時世。
……アルテアも、もう無いんでしょう?」
「……ああ、なるほど、それでかい?」
「はい。最初聞いた時は耳を疑いましたよ」
そうして銃声も硝煙の匂いもエンジンの唸りもない場所から来る死を思った時。明日世界が滅びるとしたら、そんな現実味のない問いへの答えを本気で考える羽目になった時。
あまりにも答えはあっさりと出た。
真実が、知りたくなった。もはや存在もしない、いやそれさえも虚言でただ地下に潜ったのかもしれない、そう思わせる場所。アルテア・スクールのことが。
「それに、ここのところ変なことしかねえ。怪奇現象って騒いでたうちはまだマシだったんスね。
このタイミングで港湾部がこんな騒ぎになるなんざ思っても見ませんでしたよ」
「十二条光柱か。騒ぎになるのは僕も意外だったな。
長らく空にあるとはいえ、特段気にされていない存在に思っていたが」
今なら探りを入れたって、殺されるまでにいくらかは足掻ける。虚空領域の端から端までも行き交え、どこへ消えたかも悟らせないヴォイド・エレベータほど逃げ隠れに向いたものもない。それを通過して追走し得るグレムリンの所持者は、ジャンクどもが壊滅した今となってはごく少数だ。
それに第一、その手が俺に追いつくよりも前に世界の方がなくなるようなら死の未来に怯える方が馬鹿げている。
あるいはそれを超えて世界が残れば。あの未識別どもがいない時間の方が俺の死より先にやってくるのだとしたらそれで構わなかった。
それでもう、戦う目的は果たされる。
動かないグレムリンを解析する猶予を世界にもたらす。平和がほしいとただ言うよりもずっと具体性を持った、敵のない時間の使い道。
「俺も気にしたことなんざなかったですけど。
ま、こういう状況なら、ちょっとは俺が妙な真似をしたっておかしかないでしょう。昔話とか」
「未成年飲酒だとかな」
「見えます?」
「店員だって何も言わなかったろう。僕だってそれを咎めるつもりなら最初から乗りやしないさ。
それに、非行としては随分可愛いものじゃないか。今のテイマーができる範囲を考えればな」
あの別れ際の言葉からすれば、警戒を緩ませるために酒が飲みたいなんて話はなかなか効きそうに見えた。
こいつはきっと、自分を『よくしてくれそうな大人』だと信じさせたがっている。ならそれを演じてやるまでだ。
それに、世界が滅びる前にしておきたいことと言われて『生まれて初めて酒が飲んでみたい』なんてのは、いかにも考えなしそうで。だからこそ俗っぽくて、あり得そうな回答だった。
「その心の広さに乾杯といきたいですね、今からでもいいなら」
「もちろん構わないさ、それじゃ」
「…………乾杯」
だがアルテアでこいつがどういう立場にあったかを考えれば、警戒と工夫は重ねなければならない。
第一種制御識《未来》統御指導担当教官。すなわち予知能力者。それも指折りの。
グレムリンなしでそれがどういう現れ方をするのかはアルテアの同期、つまりこいつに指導を受けていた級友から聞いていた。俺の見るものによく似た映像、やたらによく当たる勘、そういうものだと。
だからある程度、何かが見えていること、こちらから仕掛けて知らず躱されることは予期しておかなければならない。
逆に言えば見えても分からない、仕掛けられたと分からなければ通る隙がある。
「肉はどうだい」
「……香料強いスね」
「人工ガーリックは慣れないか」
必死になって自然さを装うくだらない話の応酬。口に運ぶ培養肉の薬臭さを誤魔化すためにまぶされたそれ以上の臭気。ケーブル束でも噛むような繊維の感触。それを合成アルコールで流し込む様子に返ってくる小さな笑い声。
何もかも、しなくていいのならするわけもなかった。
その奥で少しずつ綻んでいく精神の扉が。
心へ入り込むための隙間が、少しずつ開いていくのが感じられるのでなければ。
気づかれるかもしれないのなら、何をされたかも分からないまますべてを知ってしまえばよかった。
第三種《連環》、精神連結。第五種《祝福》、限界突破。俺に備わる二つの制御識は、思いつけば誂えたようにそれに向いていると思えた。
ただずっと、誰にもそうしようと思ったことなどなかったというだけで。
かつての級友たちにそうして土足で踏み入る理由もなく、その後会った誰一人として踏み入りたくなるほどの興味もない。
だから俺の連環は、そこに割り入ってくる何かを捉えてばかりいた。それを静かに、いまひとりへ向ける。
脳裏に浮かべるイメージはそれこそ束ねられた繊維だ。解してどこへでもつなげることのできる柔軟なケーブルの束。それを細く細く解して、隙間を滑るように割り入らせていく。
まるで手慣れているかのような動きは、何にされているのかも知らない祝福の賜物とでも言うべきか。連環に比して扱うことの少ないそれも、求めればすぐに意志に応えた。
今食べている食い物の味。俺の顔のイメージ。行き過ぎた、そしてこれからの仕事。次々に見えるどうでもいいものを片端から通り過ぎていくのは、長い長い廊下を駆け抜けるのに似ていた。
アルテアの記憶を。あの場への、深い執着を伴う記憶を。
そう求めて脇目も振らず、偵察機じみて音もなく走り続ける。
その果てに辿り着くイメージの前で、ようやく、足を止めた。
見えるのは随分と立派な部屋、その部屋に見合う豪奢な椅子に座る壮年と、もう一人。
今になお面影を残した、随分と若い、教官。
『はい。正式な名前を得たのは軍籍に入ってからです。このお話をいただいて退官を。
血縁も家族もない人間は、適当だったのでしょう』
『同じ孤児を相手とするのは、辛くはないかね』
『いえ。むしろ、だからこそ力添えせねばと思います』
『この赤い空の下で。ろくに外へも出られない世界で。
オイルの浮いた水を啜らず生きられる人間が一人でも増えるなら、与するのにそれ以上の理由は必要ですか』
「本物、食ったことないスね」
「そうか、まあ予習には丁度いいだろう。試していきなさい」
自分で言い出しておきながら、心底馬鹿馬鹿しいという感想しか浮かんではこなかった。
この、高級ですよとひけらかしやしなくても分かる洒落た店。明らかにそこに望まれた客じゃあない、対塵スーツそのままの俺。それを何一つ気にかけず、ただそこに俺がいるということだけに奇妙に浮き足立った教官。
目の前に並ぶ鼻をつく香料がふんだんに使われた肉、けばげばしい合成緑に着色されたバイオビーンズ、そして泡を立てるビールもそう。
そして、ここに連れられてきた理由も。
「それじゃ」
「いきなり行くね。乾杯くらいはしたかったものだが」
「……あー、すんません」
「いや、構わないよ。君からお誘いが来ただけで嬉しいことだ」
「随分な評価、ありがとうございます」
「在学中の君は、こういうことからは一番遠い子だったと思っていたからね」
酒教えてくれませんか、なんて、旗艦で会ったあの日にねじ込まれた走り書きの連絡先をどうにか解読して、突然送り付けたそんな誘い文句。
検討を重ねてすらこれしか思いつけない自分も救いようのない馬鹿だなと思ったが、乗ってくるこいつは輪をかけて馬鹿だなと、先導するその背へ送る視線は自分でも分かるほど冷たかった。
本当にそんな能天気な理由で人を、それもこんな相手なんぞ呼び出しやしない。ただ今聞きたいことを聞き出せそうな相手などこれしかなく、今を逃せば機はないかもしれないという危機感、あるいは今以上の機なんてこれより後には来ないかもしれない、そういう期待感に急かされただけ。
もし、世界がこれ以上保たないとしたら。世界の不具合とやらが拡大し続けて、奮戦空しく俺たちは無だか死だかカタストロフィだかに放り込まれるとしたら?
その可能性は絵空事だと笑い飛ばすには大きくなりすぎた。あの綻びそのものの姿をした未識別として、目の前に形を取って現れるほどに。
「ノーコメントで。
……でも、覚えててもらえてんのは本当にありがたいですね」
「これでも教えた身だからね、教えた相手のことはできる限り覚えておきたいさ」
「昔の話ができる相手なんざそうそういないスからね、このご時世。
……アルテアも、もう無いんでしょう?」
「……ああ、なるほど、それでかい?」
「はい。最初聞いた時は耳を疑いましたよ」
そうして銃声も硝煙の匂いもエンジンの唸りもない場所から来る死を思った時。明日世界が滅びるとしたら、そんな現実味のない問いへの答えを本気で考える羽目になった時。
あまりにも答えはあっさりと出た。
真実が、知りたくなった。もはや存在もしない、いやそれさえも虚言でただ地下に潜ったのかもしれない、そう思わせる場所。アルテア・スクールのことが。
「それに、ここのところ変なことしかねえ。怪奇現象って騒いでたうちはまだマシだったんスね。
このタイミングで港湾部がこんな騒ぎになるなんざ思っても見ませんでしたよ」
「十二条光柱か。騒ぎになるのは僕も意外だったな。
長らく空にあるとはいえ、特段気にされていない存在に思っていたが」
今なら探りを入れたって、殺されるまでにいくらかは足掻ける。虚空領域の端から端までも行き交え、どこへ消えたかも悟らせないヴォイド・エレベータほど逃げ隠れに向いたものもない。それを通過して追走し得るグレムリンの所持者は、ジャンクどもが壊滅した今となってはごく少数だ。
それに第一、その手が俺に追いつくよりも前に世界の方がなくなるようなら死の未来に怯える方が馬鹿げている。
あるいはそれを超えて世界が残れば。あの未識別どもがいない時間の方が俺の死より先にやってくるのだとしたらそれで構わなかった。
それでもう、戦う目的は果たされる。
動かないグレムリンを解析する猶予を世界にもたらす。平和がほしいとただ言うよりもずっと具体性を持った、敵のない時間の使い道。
「俺も気にしたことなんざなかったですけど。
ま、こういう状況なら、ちょっとは俺が妙な真似をしたっておかしかないでしょう。昔話とか」
「未成年飲酒だとかな」
「見えます?」
「店員だって何も言わなかったろう。僕だってそれを咎めるつもりなら最初から乗りやしないさ。
それに、非行としては随分可愛いものじゃないか。今のテイマーができる範囲を考えればな」
あの別れ際の言葉からすれば、警戒を緩ませるために酒が飲みたいなんて話はなかなか効きそうに見えた。
こいつはきっと、自分を『よくしてくれそうな大人』だと信じさせたがっている。ならそれを演じてやるまでだ。
それに、世界が滅びる前にしておきたいことと言われて『生まれて初めて酒が飲んでみたい』なんてのは、いかにも考えなしそうで。だからこそ俗っぽくて、あり得そうな回答だった。
「その心の広さに乾杯といきたいですね、今からでもいいなら」
「もちろん構わないさ、それじゃ」
「…………乾杯」
だがアルテアでこいつがどういう立場にあったかを考えれば、警戒と工夫は重ねなければならない。
第一種制御識《未来》統御指導担当教官。すなわち予知能力者。それも指折りの。
グレムリンなしでそれがどういう現れ方をするのかはアルテアの同期、つまりこいつに指導を受けていた級友から聞いていた。俺の見るものによく似た映像、やたらによく当たる勘、そういうものだと。
だからある程度、何かが見えていること、こちらから仕掛けて知らず躱されることは予期しておかなければならない。
逆に言えば見えても分からない、仕掛けられたと分からなければ通る隙がある。
「肉はどうだい」
「……香料強いスね」
「人工ガーリックは慣れないか」
必死になって自然さを装うくだらない話の応酬。口に運ぶ培養肉の薬臭さを誤魔化すためにまぶされたそれ以上の臭気。ケーブル束でも噛むような繊維の感触。それを合成アルコールで流し込む様子に返ってくる小さな笑い声。
何もかも、しなくていいのならするわけもなかった。
その奥で少しずつ綻んでいく精神の扉が。
心へ入り込むための隙間が、少しずつ開いていくのが感じられるのでなければ。
気づかれるかもしれないのなら、何をされたかも分からないまますべてを知ってしまえばよかった。
第三種《連環》、精神連結。第五種《祝福》、限界突破。俺に備わる二つの制御識は、思いつけば誂えたようにそれに向いていると思えた。
ただずっと、誰にもそうしようと思ったことなどなかったというだけで。
かつての級友たちにそうして土足で踏み入る理由もなく、その後会った誰一人として踏み入りたくなるほどの興味もない。
だから俺の連環は、そこに割り入ってくる何かを捉えてばかりいた。それを静かに、いまひとりへ向ける。
脳裏に浮かべるイメージはそれこそ束ねられた繊維だ。解してどこへでもつなげることのできる柔軟なケーブルの束。それを細く細く解して、隙間を滑るように割り入らせていく。
まるで手慣れているかのような動きは、何にされているのかも知らない祝福の賜物とでも言うべきか。連環に比して扱うことの少ないそれも、求めればすぐに意志に応えた。
今食べている食い物の味。俺の顔のイメージ。行き過ぎた、そしてこれからの仕事。次々に見えるどうでもいいものを片端から通り過ぎていくのは、長い長い廊下を駆け抜けるのに似ていた。
アルテアの記憶を。あの場への、深い執着を伴う記憶を。
そう求めて脇目も振らず、偵察機じみて音もなく走り続ける。
その果てに辿り着くイメージの前で、ようやく、足を止めた。
見えるのは随分と立派な部屋、その部屋に見合う豪奢な椅子に座る壮年と、もう一人。
今になお面影を残した、随分と若い、教官。
『はい。正式な名前を得たのは軍籍に入ってからです。このお話をいただいて退官を。
血縁も家族もない人間は、適当だったのでしょう』
『同じ孤児を相手とするのは、辛くはないかね』
『いえ。むしろ、だからこそ力添えせねばと思います』
『この赤い空の下で。ろくに外へも出られない世界で。
オイルの浮いた水を啜らず生きられる人間が一人でも増えるなら、与するのにそれ以上の理由は必要ですか』
◆19回更新の日記ログ
『本日のニュースで……ッザザ……
各地で……々な怪奇現…ガガッ……が多発……
この放送もいつま……ザーッ……けられるか……』
つけた覚えもないラジオにそうして叩き起こされること自体が、まさしく言われた通りの怪奇現象だった。
まず確認するのは航行状態、問題なし。機体は指定通り自動でタワー近海へと南下し続けていて、敵影もない。
続けてラジオを確かめれば、間違いなく視聴プログラムは勝手に起動して放送を拾っている。つまり俺を起こしたこいつが、怪奇現象ではあれ夢か以前に見たような幻聴幻覚の類ではないことは保証された。
ホーネット・フレームにより増幅された連環制御識、それがどこからか呼び込むヴィジョンと異なることは。
見せられていたそれが怪奇現象とやらかどうかは知らないが、その声と光景は砂嵐まみれの放送よりもよっぽど鮮明だった。
今目前にあるすべてを上塗りして現れ、俺を暫しその中に捉える録画ビデオのような何かは。
『なんで捨てられたんだ? 役目を終えたからか?
つらくなければ教えてくれ、君の見た未来のシミュレーションってどんなものなんだ?』
『私の見た未来は、ありえない未来。
どう計算しても、ヴォイドステイシスの真永劫が破られるなどあるはずがないのに』
『ヴォイドステイシスは完全なるマシンだ。
唯一完全でないものがあるとするならば、ヴォイドステイシスには《心》がある。
ヴォイドステイシスの《思念》を――』
男はともかく女の方の声をどこで聞いたんだったか、そう記憶の中を探ってみれば、行き当たるのは夢の中。
見えた姿も語調も随分と違う。けれどその声質だけは妙に似通っていた。
『死にゆく世界に手向けた花』。幾度となく夢に出たくせ、最後にその名を伝えたきり姿を消した女のそれに。
『例の怪奇現象ですか? 私も遭遇しましたよ。
ラジオ放送の合間に入る囁き声や、聞いたことのない言葉で歌われる歌。おおむね報道通りのものですね。
節回しも全く耳馴染みのないものでした』
「空の方も何かあったんだったか。そっちは?」
『空……十二条光柱や空中葬列ですよね? 私はまだ見ていませんが、同僚の中には見た者がいますよ、それも複数人。
特に熱心な中には仕事の合間に光柱の明滅周期の計測を行っている者がいましたね。あれは神々の脈拍では、と仮説を立てたそうで』
「フリーランサーってのは案外暇らしいな」
『まさか』
寝起きの棺に通話を繋いできたオペレータを捕まえれば、やはり知らないはずもない。これほどの人口が触れられるものとなれば、おそらくは制御識の共鳴の範囲を超えている。
つまり俺の見たのとは別物で、それは今に始まったことじゃない。『手向けた花』の名乗り、西の空へ走る光の夢。そして更に遡れば誰からかも分からない始まりの電話、語らずとも脳裏に蘇ったその先の言葉。
思えばこの戦いの間に絶えず見てきていた。連環が、あるいは他の何かが連れてきたとしか思えない、話す気になるより前に一笑される未来を予想する方がずっと容易いものは。
『それにしてもアザミネさん、こういう話に興味がおありだったんですか』
「別に。どこの局でもやってる割に、てんで縁がないんでね」
『そうですか。任務とグレムリン以外の話なんて珍しいなと』
「そっちこそ、その話しに来たんじゃねえの」
『今日は任務の依頼ではありませんよ。関連の話ではありますが』
『っていうと?』
『昨日の違法人身売買取引摘発作戦、無事に終了しました、というご報告に』
言われた文言を頭で三度反芻してから、聞こえよがしの溜息は意識的な部分が半分、残りは天然。
「律儀なこったな、直前で蹴った奴によ」
『参加を検討していただけたのは事実ですから。テイマーである以上優先順位がある、というのももっともです。
それに、随分気にしてらしたように思えましたので』
「ふうん。そう見えたかい」
はい、という肯定を聞き流しながら、断りの連絡を入れた時を思い返す。別に殊更平常とかけ離れたところはなかった――という判断がどれだけ正確なものか。
了解は取っていたとはいえ当日の朝という急場の通達、そして結局機体に問題がなければ行くという事前連絡をひっくり返した。そのどちらを取っても、まあ殊勝になるほうが普通の場面のはずだ。
それ以上の何かを分かるほど滲ませてしまっていたというなら、多少は悔しくそして情けない。
そんな内心ももちろん悟られることなどなく、オペレータは報告を続けていた。
『犯人チームのうち8名を拘束。2名は高速艇に乗り込み逃亡を図り、現在も追跡中。
ですが少なくとも子供達については、生命反応のあった全員を保護できました』
生命反応のあった。その注釈が何を意味するかなんざ今更確認するまでもない。ただ不幸な奴がいたというだけだ。
ただ残った側を幸運と呼べるかどうかを決めるのはこの先であって、今じゃないこともよく知っている。
「どうなんの、そいつら」
『もちろん親元へ返します……と言いたいところですが。
この状況では、まず今すぐ必要なのは親族が見つかるまで生き延びるための受け入れ先です』
「師団にゃ一番期待しちゃいけねえモンだな」
そう返せば落ちる沈黙は、その言葉を向こうだってはっきりと理解している証だ。
抱える人間の数ばかりは多いくせに、青花師団というものは『公的』とつくあらゆるものに大した興味がない。必要性こそあれ用意するだけ自由を奪う、特に小児への思想教育へ繋がることは避けなければならない。叫ばれているそんな言葉はどう聞いたって体のいい言い訳で、実質としては金もなければやりたがる人間もいないってだけだろう。
お得意の自主性ってものに期待したところで、得にもならないガキを好き好んで相手するような人間がそう多いわけもない。
『……返す言葉もありません。
氷獄と小群島の避難受け入れの限界は聞こえてきていますし、横道潮流と巨人の島はまだ復興着手の段階で施設そのものがありません。
頼みの綱になるのは民間ですが……こちらも、まずこの戦火の中で残っているかどうかからの調査になっているそうです。
担当はずっと嘆いていますよ、ここが残っていれば、と。フローリスト、ペルビアナ、プルンバーゴ……』
元から席の少ない中の椅子取りにさしたる希望もないだろう。脳裏に蘇るのは小群島で見た物盗りのガキども。
だがあいつらはこうして関係のない人間にも覚えられているだけまだマシなのかもしれなかった。誰の目にも触れないように育てられ、使われあるいは死んでいく奴だってこの世界には掃いて捨てるほどいる。
まさに今、摘発がなければ表の誰にも知られることのないまま『取引』されていったであろう子供の話をしているように。
そして俺がどこで、どんな風にして育ったかを思えば。
『――アルテア』
まさにその時、心中を読んだかのように挙げられたその名だけで、目を見開かせるには十分だった。
どういうことだ。あれは受け入れ先なんかとはほど遠い密売者どもの巣のはずだ。あれは消えたのか。あの死の眠りの16時間に。あるいはそれ以降に?
そのすべてを訊くために、それかただの驚きで発した最初の一声を上からかき消すのは最大音量で鳴り響く不協和音。俺を寝ていようが問答無用で叩き起こせる大きさの騒音は敵影感知のアラート、会敵の合図だ。
通信は自動シャットダウンし、映っていたオペレータの顔は瞬時に消え去る。届かなかった詰問の代わりに口を突いて出るのは抑えもしない罵声そのもの。
入れ替わるように立ち上がる戦闘プログラム、ローディングを始めるカメラ映像へ向ける視線が殺気立っているのが自分自身ですら分かった。だがこの場をさっさと切り抜けるには、ずっと続けてきた戦法は適しすぎているくらいだ。
全力で叩き落とせば五分と――
その気勢を一挙に、まさに海へ突き落としたように冷やしたのは、そのウィンドウの中へ映り込んだ異貌だ。薄らぎまた濃さを増す粉塵の中でさえ一目で分かるほどの。
それは海を往く砂嵐、あるいは音を頼りに描き出したイメージとしてのノイズ。敵機として、いや機械として製造されたものとは到底思えやしないそれが画面の中で群れを成していた。
真っ先に疑ったのはもちろんモニタやカメラ、映像関連機器の故障だ。だが隣の既存機は間違いなく昨日相手をしたのと同じ姿で映っている。敵機と判定された砂嵐の映るそのエリアへ来ようとも。
なら次の可能性はそれを敵影と判断した索敵関連の不調。開くのはテキストエリア、居並んだ敵機の内訳表記。
【かk機めut艦『veu・るージェ』】
そこにずらりと十行ばかり並んでいるのは不具合としか思えない羅列だった。眩暈を堪えながらも回す頭は止めない、その中で辿り着いた一つの回答。
それが元からそういうもの、どこかが狂ったものとして存在しているんだとしたら?
その可能性を思った時に浮かんだのはかつて幾度となく焼き尽くした、スクラップとなることを拒む機械。
そしてそれを含む未識別機動体が何と呼ばれたか。
あの連環の像に似た声をした『手向ける花』が、何を告げたか。
『この世界は致命的な不具合を抱えている』
それを思い浮かべながら文字列に目を滑らせていけば、その末尾にぞくりと怖気が走った。心臓でも掴まれるように。
正体不明。取り巻きどもとは格が違うと一目で分かる連中の枕詞。それに続く、今日の名。
『あなたは誰?』
それを直接連環の回路に割り込ませる形で告げられたのなんて、初めてだったから。
各地で……々な怪奇現…ガガッ……が多発……
この放送もいつま……ザーッ……けられるか……』
つけた覚えもないラジオにそうして叩き起こされること自体が、まさしく言われた通りの怪奇現象だった。
まず確認するのは航行状態、問題なし。機体は指定通り自動でタワー近海へと南下し続けていて、敵影もない。
続けてラジオを確かめれば、間違いなく視聴プログラムは勝手に起動して放送を拾っている。つまり俺を起こしたこいつが、怪奇現象ではあれ夢か以前に見たような幻聴幻覚の類ではないことは保証された。
ホーネット・フレームにより増幅された連環制御識、それがどこからか呼び込むヴィジョンと異なることは。
見せられていたそれが怪奇現象とやらかどうかは知らないが、その声と光景は砂嵐まみれの放送よりもよっぽど鮮明だった。
今目前にあるすべてを上塗りして現れ、俺を暫しその中に捉える録画ビデオのような何かは。
『なんで捨てられたんだ? 役目を終えたからか?
つらくなければ教えてくれ、君の見た未来のシミュレーションってどんなものなんだ?』
『私の見た未来は、ありえない未来。
どう計算しても、ヴォイドステイシスの真永劫が破られるなどあるはずがないのに』
『ヴォイドステイシスは完全なるマシンだ。
唯一完全でないものがあるとするならば、ヴォイドステイシスには《心》がある。
ヴォイドステイシスの《思念》を――』
男はともかく女の方の声をどこで聞いたんだったか、そう記憶の中を探ってみれば、行き当たるのは夢の中。
見えた姿も語調も随分と違う。けれどその声質だけは妙に似通っていた。
『死にゆく世界に手向けた花』。幾度となく夢に出たくせ、最後にその名を伝えたきり姿を消した女のそれに。
『例の怪奇現象ですか? 私も遭遇しましたよ。
ラジオ放送の合間に入る囁き声や、聞いたことのない言葉で歌われる歌。おおむね報道通りのものですね。
節回しも全く耳馴染みのないものでした』
「空の方も何かあったんだったか。そっちは?」
『空……十二条光柱や空中葬列ですよね? 私はまだ見ていませんが、同僚の中には見た者がいますよ、それも複数人。
特に熱心な中には仕事の合間に光柱の明滅周期の計測を行っている者がいましたね。あれは神々の脈拍では、と仮説を立てたそうで』
「フリーランサーってのは案外暇らしいな」
『まさか』
寝起きの棺に通話を繋いできたオペレータを捕まえれば、やはり知らないはずもない。これほどの人口が触れられるものとなれば、おそらくは制御識の共鳴の範囲を超えている。
つまり俺の見たのとは別物で、それは今に始まったことじゃない。『手向けた花』の名乗り、西の空へ走る光の夢。そして更に遡れば誰からかも分からない始まりの電話、語らずとも脳裏に蘇ったその先の言葉。
思えばこの戦いの間に絶えず見てきていた。連環が、あるいは他の何かが連れてきたとしか思えない、話す気になるより前に一笑される未来を予想する方がずっと容易いものは。
『それにしてもアザミネさん、こういう話に興味がおありだったんですか』
「別に。どこの局でもやってる割に、てんで縁がないんでね」
『そうですか。任務とグレムリン以外の話なんて珍しいなと』
「そっちこそ、その話しに来たんじゃねえの」
『今日は任務の依頼ではありませんよ。関連の話ではありますが』
『っていうと?』
『昨日の違法人身売買取引摘発作戦、無事に終了しました、というご報告に』
言われた文言を頭で三度反芻してから、聞こえよがしの溜息は意識的な部分が半分、残りは天然。
「律儀なこったな、直前で蹴った奴によ」
『参加を検討していただけたのは事実ですから。テイマーである以上優先順位がある、というのももっともです。
それに、随分気にしてらしたように思えましたので』
「ふうん。そう見えたかい」
はい、という肯定を聞き流しながら、断りの連絡を入れた時を思い返す。別に殊更平常とかけ離れたところはなかった――という判断がどれだけ正確なものか。
了解は取っていたとはいえ当日の朝という急場の通達、そして結局機体に問題がなければ行くという事前連絡をひっくり返した。そのどちらを取っても、まあ殊勝になるほうが普通の場面のはずだ。
それ以上の何かを分かるほど滲ませてしまっていたというなら、多少は悔しくそして情けない。
そんな内心ももちろん悟られることなどなく、オペレータは報告を続けていた。
『犯人チームのうち8名を拘束。2名は高速艇に乗り込み逃亡を図り、現在も追跡中。
ですが少なくとも子供達については、生命反応のあった全員を保護できました』
生命反応のあった。その注釈が何を意味するかなんざ今更確認するまでもない。ただ不幸な奴がいたというだけだ。
ただ残った側を幸運と呼べるかどうかを決めるのはこの先であって、今じゃないこともよく知っている。
「どうなんの、そいつら」
『もちろん親元へ返します……と言いたいところですが。
この状況では、まず今すぐ必要なのは親族が見つかるまで生き延びるための受け入れ先です』
「師団にゃ一番期待しちゃいけねえモンだな」
そう返せば落ちる沈黙は、その言葉を向こうだってはっきりと理解している証だ。
抱える人間の数ばかりは多いくせに、青花師団というものは『公的』とつくあらゆるものに大した興味がない。必要性こそあれ用意するだけ自由を奪う、特に小児への思想教育へ繋がることは避けなければならない。叫ばれているそんな言葉はどう聞いたって体のいい言い訳で、実質としては金もなければやりたがる人間もいないってだけだろう。
お得意の自主性ってものに期待したところで、得にもならないガキを好き好んで相手するような人間がそう多いわけもない。
『……返す言葉もありません。
氷獄と小群島の避難受け入れの限界は聞こえてきていますし、横道潮流と巨人の島はまだ復興着手の段階で施設そのものがありません。
頼みの綱になるのは民間ですが……こちらも、まずこの戦火の中で残っているかどうかからの調査になっているそうです。
担当はずっと嘆いていますよ、ここが残っていれば、と。フローリスト、ペルビアナ、プルンバーゴ……』
元から席の少ない中の椅子取りにさしたる希望もないだろう。脳裏に蘇るのは小群島で見た物盗りのガキども。
だがあいつらはこうして関係のない人間にも覚えられているだけまだマシなのかもしれなかった。誰の目にも触れないように育てられ、使われあるいは死んでいく奴だってこの世界には掃いて捨てるほどいる。
まさに今、摘発がなければ表の誰にも知られることのないまま『取引』されていったであろう子供の話をしているように。
そして俺がどこで、どんな風にして育ったかを思えば。
『――アルテア』
まさにその時、心中を読んだかのように挙げられたその名だけで、目を見開かせるには十分だった。
どういうことだ。あれは受け入れ先なんかとはほど遠い密売者どもの巣のはずだ。あれは消えたのか。あの死の眠りの16時間に。あるいはそれ以降に?
そのすべてを訊くために、それかただの驚きで発した最初の一声を上からかき消すのは最大音量で鳴り響く不協和音。俺を寝ていようが問答無用で叩き起こせる大きさの騒音は敵影感知のアラート、会敵の合図だ。
通信は自動シャットダウンし、映っていたオペレータの顔は瞬時に消え去る。届かなかった詰問の代わりに口を突いて出るのは抑えもしない罵声そのもの。
入れ替わるように立ち上がる戦闘プログラム、ローディングを始めるカメラ映像へ向ける視線が殺気立っているのが自分自身ですら分かった。だがこの場をさっさと切り抜けるには、ずっと続けてきた戦法は適しすぎているくらいだ。
全力で叩き落とせば五分と――
その気勢を一挙に、まさに海へ突き落としたように冷やしたのは、そのウィンドウの中へ映り込んだ異貌だ。薄らぎまた濃さを増す粉塵の中でさえ一目で分かるほどの。
それは海を往く砂嵐、あるいは音を頼りに描き出したイメージとしてのノイズ。敵機として、いや機械として製造されたものとは到底思えやしないそれが画面の中で群れを成していた。
真っ先に疑ったのはもちろんモニタやカメラ、映像関連機器の故障だ。だが隣の既存機は間違いなく昨日相手をしたのと同じ姿で映っている。敵機と判定された砂嵐の映るそのエリアへ来ようとも。
なら次の可能性はそれを敵影と判断した索敵関連の不調。開くのはテキストエリア、居並んだ敵機の内訳表記。
【かk機めut艦『veu・るージェ』】
そこにずらりと十行ばかり並んでいるのは不具合としか思えない羅列だった。眩暈を堪えながらも回す頭は止めない、その中で辿り着いた一つの回答。
それが元からそういうもの、どこかが狂ったものとして存在しているんだとしたら?
その可能性を思った時に浮かんだのはかつて幾度となく焼き尽くした、スクラップとなることを拒む機械。
そしてそれを含む未識別機動体が何と呼ばれたか。
あの連環の像に似た声をした『手向ける花』が、何を告げたか。
『この世界は致命的な不具合を抱えている』
それを思い浮かべながら文字列に目を滑らせていけば、その末尾にぞくりと怖気が走った。心臓でも掴まれるように。
正体不明。取り巻きどもとは格が違うと一目で分かる連中の枕詞。それに続く、今日の名。
『あなたは誰?』
それを直接連環の回路に割り込ませる形で告げられたのなんて、初めてだったから。
◆18回更新の日記ログ
「本当にこの動きをストレイキャット・フレームで?」
スクリーンから外れてこっちを向いたアネモネのエンジニアの視線は、その言葉が纏う雰囲気と同じく完全に詰問のそれだった。
映像そのものは3分もない。これまでの戦い方なら、それだけあれば十分だったからだ。
狙撃砲付属の精細思念捕捉装置で目を光らせ、撃ち抜き、それを起点にファントムハートを目一杯に吹かす。小兵どもを踏み潰しながら十分な加圧を行い、オールグリーンが出次第、拡散火球砲が放つ圧縮火球の熱波が敵機すべてを焼き尽くす。生き残りがいたとして、フレームに満ち満ちたエンジンの余剰出力で貫けばまず落とせないことはない。
どんな敵機が動くよりも早い、傷一つつけさせないための戦い。それはどう考えたって、ストレイキャットという哨戒機に向いた戦法じゃない。
結局のところそいつは無駄骨に過ぎなかった。そうしてまで持ち帰ったものを、完膚なきまでに拒絶された今となっては。
「ああ」
「火器系統不調の原因、よく分かりました。これからもあのまま戦うのなら、換装を強くお勧めしますよ」
口じゃそう言っちゃいるが、どう考えたってお勧めするなんてものじゃない。そんな体を取っただけの命令形。
だからこっちの対応だって口に出すまでもないものだ。肩をすくめて、よろしく、と一言。
不満そうに鼻を鳴らし、聞こえよがしに足音を立てて歩いていく姿を見送って、こちらにも向かう先があった。
巨体の立ち並ぶグレムリンハンガー。かつてとは比べ物にならないほどの人間が行き交うその通路を、人の流れに逆らってずっと奥へ。
前と同じように、『サーシオネ』への搭乗許可はあっさりと下りていた。前はそれが動くことへの祈るような期待故だったろうが、今や搭乗したところで動かないことは分かり切っている。状況が変わっての再試験、というほど何が動いたわけでもない。
ただ、好きにさせておけってだけだろう。それで気が済むなら構わないというだけの。
二週間のあいだ閉められたままの棺には埃が入る隙間もない。身を沈めたシートの感触は以前の訪問と何ら変わらず、そしてやはり『フォールスビーク』にどこか似ている。
そしてこれから、『フォールスビーク』はもっと似ていくことになる。ホーネット・フレーム、今搭乗しているこの抜け殻じみた機体の骸と同じ形態へ換装することで。
第三種《連環》、および第五種《祝福》好適。そんな奴に与えられた青花の機体は、第三種制御識適性を存分に生かす連動機。
闇の中で座ったまま腕を伸ばせば、探り当てるまでもなくロックされたままのレバーに行き当たる。軽く握ればそれだけで、モニタがある位置にかつての表示が重なって見えた。そしてこの機体が、どんな動きで戦場を駆けていたのかも。
装甲の一部を省いて軽量化されたボディが可能にする流れるような加速と、その速度でもって躱す弾丸。それが飛んできた方へ向ける四門の兵装スロット、そこに据えられた連動兵器を動かすたび戦場のすべてを幾度となく薙ぎ払う思念の波。
今だって昨日のことのように思い出せる、そして明日にも同じ動きをすることになるであろう、このグレムリン・フレームの戦い方。哨戒機が見つけ出した相手を、完膚なきまでに叩き潰すための。
だがただそれを思い出したいだけなら、座るべき座席はここでなんかあるはずがなかった。
頼るべきは確証の取れて、何より電源の入るシミュレータによる訓練と試行であって、不確かな記憶と電源すら点かないような棺じゃない。
『航空者』からの提供データを元にもたらされた新たなパーツ。思念研究によって拡張された新たな戦闘システム。『進化』し、意力撃滅をも漸減する思念障壁を備えた未識別。この二週間あまりでテイマーを、グレムリンを取り巻く環境も激変しているから猶更だ。
それを知りながら、どうして。
聞かれたなら、そう詰る誰もここにはいないからだ、と答えるだろう。
そう聞く奴だって初めからいるわけがないけれど。
腕はアームレストに載せたまま、手をレバーから離す。同じように脱力した首を引いて、後頭部を重力のままヘッドレストにもたせ掛ける。
見上げる天井が『棺』の呼び名に相応しく低いことは知っている。
そしてこれだけは、記憶と差異があるだろう。いつもこうして見ていた頃に比べれば、天井なんて今はずっと近くなっているはずだ。あらゆる動力から隔絶された真っ暗な世界では、はっきりと視認できないというだけで。
見つめるべきものは俺しかない。
未識別機動体の危機に晒された虚空領域で、今なお戦うことのできるグレムリンテイマー。
その立場に甘えに甘えた末に、何よりも優先するべき、数少ないすべてを共有できる相手をどうにもこっぴどく裏切ったガキしか。
いや。俺がどう思っていようが、向こうからはもう何を共有できることもないとでも見られているだろう。覗かせたあの本音は、おそらくそれを伝える最後通告でもあった。
もう俺にはそれに報いる何かも、もう一度縋るための手段さえも思いつかなかった。
テイマーとして戦う。平和を連れてくる。止まったグレムリンたちをもう一度動かす、その希望を叶える時間をもたらすために。自分が口走るなんて思わなかったそんな正しくて綺麗な回答を、これから俺は真顔で答える羽目になるだろう。心底そのつもりで。
だがそれは、その言葉が真実である証明になんかなりえない。仮に俺があのことに何ら心動かなかったとして、それでも戦い続けることには変わりないからだ。これまでただ、グレムリンがあるからというだけで戦ってきたのと同じように。
そして俺ともう関わらないとして、それは今やあいつにとってそこまでの痛手でもないだろう。
あいつにはもうアネモネで得た居場所がある。グレムリンを失いながらも、その知識をもって戦線に協力するテイマー。そういう背景とともに、あいつはもうあそこに受け入れられている。
それがある中なら、一人と縁を切るくらいはどうってことはない。例えその背景にある出自を誰も知らないとしても。子供の頃の秘密を共有する相手がいないとしても。
それを見ながら自分を振り返ってみれば、あるものなんてグレムリンひとつ。残りのすべては、テイマーという肩書があるから泊まることを許された寄港地みたいなものに過ぎない。
受け入れられる地も帰りたい場所も、守りたいと望んだものを信じてもらえるような信用もない。これまでもこれからも。
ただ、それを壊し続けることだけができる。なにひとつ作れも得られもしないくせに。
そんな自分のどうしようもない空っぽさに滲む涙に揺らぐものも、漏れる啜り泣きを聞くものもここには何もない。
記憶の通り棺の中にはこれまでと何ら変わらず、何もかもを受け入れる無言の闇だけがあった。
ガキ四人が二段ベッド二つと一緒に一部屋に押し込められた、プライバシーもクソもない集団生活。
依頼に応じてあらゆる船へ移り、宛がわれた客室を転々とする傭兵暮らし。
落ち着きという言葉とてんで縁のなかった人生の中で、唯一『いつもの』と呼んで、ひとりきりになれた場所には。
スクリーンから外れてこっちを向いたアネモネのエンジニアの視線は、その言葉が纏う雰囲気と同じく完全に詰問のそれだった。
映像そのものは3分もない。これまでの戦い方なら、それだけあれば十分だったからだ。
狙撃砲付属の精細思念捕捉装置で目を光らせ、撃ち抜き、それを起点にファントムハートを目一杯に吹かす。小兵どもを踏み潰しながら十分な加圧を行い、オールグリーンが出次第、拡散火球砲が放つ圧縮火球の熱波が敵機すべてを焼き尽くす。生き残りがいたとして、フレームに満ち満ちたエンジンの余剰出力で貫けばまず落とせないことはない。
どんな敵機が動くよりも早い、傷一つつけさせないための戦い。それはどう考えたって、ストレイキャットという哨戒機に向いた戦法じゃない。
結局のところそいつは無駄骨に過ぎなかった。そうしてまで持ち帰ったものを、完膚なきまでに拒絶された今となっては。
「ああ」
「火器系統不調の原因、よく分かりました。これからもあのまま戦うのなら、換装を強くお勧めしますよ」
口じゃそう言っちゃいるが、どう考えたってお勧めするなんてものじゃない。そんな体を取っただけの命令形。
だからこっちの対応だって口に出すまでもないものだ。肩をすくめて、よろしく、と一言。
不満そうに鼻を鳴らし、聞こえよがしに足音を立てて歩いていく姿を見送って、こちらにも向かう先があった。
巨体の立ち並ぶグレムリンハンガー。かつてとは比べ物にならないほどの人間が行き交うその通路を、人の流れに逆らってずっと奥へ。
前と同じように、『サーシオネ』への搭乗許可はあっさりと下りていた。前はそれが動くことへの祈るような期待故だったろうが、今や搭乗したところで動かないことは分かり切っている。状況が変わっての再試験、というほど何が動いたわけでもない。
ただ、好きにさせておけってだけだろう。それで気が済むなら構わないというだけの。
二週間のあいだ閉められたままの棺には埃が入る隙間もない。身を沈めたシートの感触は以前の訪問と何ら変わらず、そしてやはり『フォールスビーク』にどこか似ている。
そしてこれから、『フォールスビーク』はもっと似ていくことになる。ホーネット・フレーム、今搭乗しているこの抜け殻じみた機体の骸と同じ形態へ換装することで。
第三種《連環》、および第五種《祝福》好適。そんな奴に与えられた青花の機体は、第三種制御識適性を存分に生かす連動機。
闇の中で座ったまま腕を伸ばせば、探り当てるまでもなくロックされたままのレバーに行き当たる。軽く握ればそれだけで、モニタがある位置にかつての表示が重なって見えた。そしてこの機体が、どんな動きで戦場を駆けていたのかも。
装甲の一部を省いて軽量化されたボディが可能にする流れるような加速と、その速度でもって躱す弾丸。それが飛んできた方へ向ける四門の兵装スロット、そこに据えられた連動兵器を動かすたび戦場のすべてを幾度となく薙ぎ払う思念の波。
今だって昨日のことのように思い出せる、そして明日にも同じ動きをすることになるであろう、このグレムリン・フレームの戦い方。哨戒機が見つけ出した相手を、完膚なきまでに叩き潰すための。
だがただそれを思い出したいだけなら、座るべき座席はここでなんかあるはずがなかった。
頼るべきは確証の取れて、何より電源の入るシミュレータによる訓練と試行であって、不確かな記憶と電源すら点かないような棺じゃない。
『航空者』からの提供データを元にもたらされた新たなパーツ。思念研究によって拡張された新たな戦闘システム。『進化』し、意力撃滅をも漸減する思念障壁を備えた未識別。この二週間あまりでテイマーを、グレムリンを取り巻く環境も激変しているから猶更だ。
それを知りながら、どうして。
聞かれたなら、そう詰る誰もここにはいないからだ、と答えるだろう。
そう聞く奴だって初めからいるわけがないけれど。
腕はアームレストに載せたまま、手をレバーから離す。同じように脱力した首を引いて、後頭部を重力のままヘッドレストにもたせ掛ける。
見上げる天井が『棺』の呼び名に相応しく低いことは知っている。
そしてこれだけは、記憶と差異があるだろう。いつもこうして見ていた頃に比べれば、天井なんて今はずっと近くなっているはずだ。あらゆる動力から隔絶された真っ暗な世界では、はっきりと視認できないというだけで。
見つめるべきものは俺しかない。
未識別機動体の危機に晒された虚空領域で、今なお戦うことのできるグレムリンテイマー。
その立場に甘えに甘えた末に、何よりも優先するべき、数少ないすべてを共有できる相手をどうにもこっぴどく裏切ったガキしか。
いや。俺がどう思っていようが、向こうからはもう何を共有できることもないとでも見られているだろう。覗かせたあの本音は、おそらくそれを伝える最後通告でもあった。
もう俺にはそれに報いる何かも、もう一度縋るための手段さえも思いつかなかった。
テイマーとして戦う。平和を連れてくる。止まったグレムリンたちをもう一度動かす、その希望を叶える時間をもたらすために。自分が口走るなんて思わなかったそんな正しくて綺麗な回答を、これから俺は真顔で答える羽目になるだろう。心底そのつもりで。
だがそれは、その言葉が真実である証明になんかなりえない。仮に俺があのことに何ら心動かなかったとして、それでも戦い続けることには変わりないからだ。これまでただ、グレムリンがあるからというだけで戦ってきたのと同じように。
そして俺ともう関わらないとして、それは今やあいつにとってそこまでの痛手でもないだろう。
あいつにはもうアネモネで得た居場所がある。グレムリンを失いながらも、その知識をもって戦線に協力するテイマー。そういう背景とともに、あいつはもうあそこに受け入れられている。
それがある中なら、一人と縁を切るくらいはどうってことはない。例えその背景にある出自を誰も知らないとしても。子供の頃の秘密を共有する相手がいないとしても。
それを見ながら自分を振り返ってみれば、あるものなんてグレムリンひとつ。残りのすべては、テイマーという肩書があるから泊まることを許された寄港地みたいなものに過ぎない。
受け入れられる地も帰りたい場所も、守りたいと望んだものを信じてもらえるような信用もない。これまでもこれからも。
ただ、それを壊し続けることだけができる。なにひとつ作れも得られもしないくせに。
そんな自分のどうしようもない空っぽさに滲む涙に揺らぐものも、漏れる啜り泣きを聞くものもここには何もない。
記憶の通り棺の中にはこれまでと何ら変わらず、何もかもを受け入れる無言の闇だけがあった。
ガキ四人が二段ベッド二つと一緒に一部屋に押し込められた、プライバシーもクソもない集団生活。
依頼に応じてあらゆる船へ移り、宛がわれた客室を転々とする傭兵暮らし。
落ち着きという言葉とてんで縁のなかった人生の中で、唯一『いつもの』と呼んで、ひとりきりになれた場所には。
◆17回更新の日記ログ
硬い鉄板の上に腰を下ろせば、ようやっと周りをじっくり眺める余裕ができた。ここまでにちらっと見てきた通り壁も天井も明らかに急ごしらえ、そのくせ人間だけは溢れ返っている。
押し手が見えなくなるほど箱を満載した台車が大声を上げて通り抜け、許可もないだろうにダクト下を占拠して立ち並んだ屋台の客引きをかき消す。その後を汚れた服のガキどもが追って走り、つくりが適当な床に引っかかって案の定横転した台車の荷物拾いを手伝うふりしていくらか懐へせしめた。どっかの制服のおっさんが怒号を上げてそいつらを叱り飛ばしても、人波の隙間を縫って逃げる子供を追うにはその図体は大きすぎる。
鼻で笑いながら別の方へ目を向ければ、そこだけは粉塵避けにしっかり作られた窓から赤い空気に遠く霞んで見えるのは旗を掲げた人型のシルエット。こうして別の島からでも見えるほどに大きなグレムリン像は、領域解放記念とか言って作られたものらしい。一心にそいつを拝む連中に埋め尽くされた窓の周りだけが別の空間のように静かで、その周囲では着の身着のままの避難民が泥のように眠っていた。かろうじて持ち出せたらしい小さな荷を後生大事に抱えて。
「凄いだろ。ここ一週間くらいで一気にこの調子になったから、まだ全然……この通り、混沌としてるとしか言いようがない」
その声に、雑多を絵に描いたような光景から目を離して正面を向く。
テーブルとは名ばかりのかろうじて平坦にネジ止めされた板、その上に置かれた二杯のコーヒーを挟んで、困り顔のラトーが笑っていた。
「一月前の俺に小群島だっつっても信じねえよ、こんなの」
「何もなかったもんな、アネモネくらいしか」
「そうそ、師団どころか虚空領域一のクソ田舎」
そして、昨日の俺に言えばもっとだろう。
あの死に体の工廠を見た後の俺なら、こんなものは確かに実際目にしなければ信じなかったに違いない。
「……でも、アネモネがなかったらこんなことにはならなかったろうな」
そしてその工廠もまた『生き返った』としか言いようのない復活ぶりだった。
もちろん、あれほどの損害の傷跡を二週間程度で埋められるはずもない。しかしどうやったのかグレムリンの死体で埋め尽くされたハンガーにはいくらかの空きができて、人員も少ないとはいえ前の生気のなさに比べりゃ意気も働きも雲泥の違いだ。
「あの後もストレイキャットは随分出たよ。
これは、そのために寄ったグレムリンが戦ってくれた結果だ」
そもそも工廠が『死んでいる』って俺の見立てそのものが間違いだったのかもしれなかった。
工廠が死に絶えたのならそんな場所でどうして換装ができた。どうして後から後からテイマーがやってくる。どうしてグレムリンを診られる。
「にしたって、こんなことになるまで受け入れるこたねえだろうに。氷獄の旗艦も相当だったが比じゃねえぞ」
どうして気づけなかったんだか。漏れ出た苛立ちの矛先が不意に向いたのを、相対する目ははっきりと怒りをもって睨んできた。
「アザミネ」
「悪り」
「そんなこと言ったら放り出されるのはそっちだ。一番後から来たのはお前なんだからな」
そう一息に口に出して、ラトーは一度コーヒーで口を湿す。
「……でもお前がテイマーだってのが知れれば、まあ助かるかもしれない。それも、たった今飛んできたやつのって言えばさ。
こんな民間施設ができても、ここの核はやっぱり工廠だ。戦える、動けるグレムリンの支援施設」
知っているさ。さっきのあの翡翠みたいに像を拝む連中を見ても分かる。今のテイマーというものに、どれくらいの力があるのか。
そしてそれがどれくらいの物事を正当化できるか。
例え今この群衆の中に『フォールスビーク』の正当な持ち主がいたとして、その主張を一蹴できる程度にはあるだろう。
動くグレムリンを奪うなんてことは初めてじゃない。
だからお前を誘っているんだ、と口に出そうとして、――そこから出たのは音にならない息だけだ。
俺のものと同じ眼窩を横切る手術痕を持つ瞼が開いて、覗いた目はそれほどまで真っ直ぐに俺を射抜く。
「だからその一員として、僕はあの提案には絶対に頷けない。
工廠で機体を奪われたなんて話、一回でも起きたら二度とアネモネに人は寄り付かない。
噂がどんな速さで広まるか、この二週間で嫌って程わかったしね」
その声も語り口も、努めて声を潜めているのもあって一貫して静かだ。ただそこに煮えたぎるような怒りのあることは疑いようがない。
堰を切ったまま止まらない台詞はその証明として余りある。これまでずっと堪えてきたか、あるいは蓄えてきたものだ。
今すぐの話なわけがない。きっとあの通信で交わした言葉の間に挟まった不自然な沈黙のその時から。
「調整の要る機体が寄るのを中止するようなことも出るだろう。それが元で落ちるんなら、それは防げたはずの負けだ。
その機体が救えた人ごとみんな巻き込む戦力の喪失だ」
機銃のように吐き出され並べられるその論理は驚くほど正しい。教科書じみて。
グレムリンの一機は何人の人命を救えるか。自分が直接乗るのでなくても、アネモネにいることで間接的にどれほど影響できるか。今のこの状況を見ればそれもまた自明だ。
それを認識するほどに、ひどく視座のずれていることを自覚させられる。
瞬間のうちに幾度となく反芻してその言葉の中に感じ取る齟齬は、グレムリンから引き剥がされたラトーがアネモネという新しい居場所で見出した、操縦棺の中より遥かに広大な世界と、そこに生きる人間と、未来への眼に違いなかった。
「ならその分、お前が乗って取り返しゃいい!!
アレがいくら性能が落ちるって言ったって、できないとは言わせねえ。
お前だってテイマーだろうがよ!!」
張り上げた声もテーブルへ叩きつけた拳も勢いのまま立ち上がる体も、振り上げられた手に対する防御反応にこそ近かった。それは俺を打ちのめすと意識よりも前に魂が気づいていた。
その視座を得た一歩、操縦棺の外への一足、親しんだ相手の離れていく恐怖は意見の正しさなんかよりよほど強烈に俺を殺すと。
肺の中の空気を一息に吐き出しきって、呼吸は酷く荒かった。テーブルに置いたままの手は横倒しになったコーヒーと冷汗でじっとりと濡れている。転がったカップが床を叩く。怒号でこちらに気づいた野次馬が喧嘩を囃し立てる声が遠い。
「グレムリンから離れたら、死ぬ、アルテアのテイマーだろ」
その一つ一つにすっかり意気を失ってさえ、吐き出されるのは懸念のふりをして縛る小狡い台詞だ。
ガキめ。
頭の中を切り分けて住みついたすっかり冷静な自己が他人事じみてそう吐き捨てる。
ああそうだよ。
戻ってきてほしい。お前がいい。同じ場所にいてくれ。そんな感情論と俺だけの目線でしかものを言えねえガキだ。
「……何を言われたって、乗る気はないからな。僕だけの話じゃない。勢力レベルの話だってある。
青花の工廠で真紅の機体に何かあれば、絶対にこの後の火種になる。今は何ともなくてもだ」
そんな奴が頷いてもらえるわけもない。提示され続ける正しさが、向けられた情を明確に弾く。幾枚もの分厚い装甲板に似て。
「だけどな」
だから次がれたその言葉はその間から開いた銃眼に見えて、心は瞬時に身構える。そこから放たれる弾を見越して。
けれど同時に拭えない違和感。……だけど?
「グレムリンのあるお前が、今でも飛べるお前が羨ましくないって言ったら嘘になる」
その感覚を立証するように、隙間から覗いたのは銃身ではなく剥き出しの棺。世界から隔てられた小さな小さな個。
未だ座ったままこちらを見上げてくる視線への確かな既視感がそれを裏付ける。
そこにあるのはかつてアネモネで、乗機をなくした虚ろなテイマーが向けてきた目だ。
紛れもない、嫉妬を宿した。
「僕の他にも、機体が動かなくてエンジニアやってる奴はいるよ。そいつら全員きっとそうだ」
そうしてその瞳は一度瞼の裏に隠れる。
眉根を寄せたその表情は今までのものから離れて、また別のものに似通っていく。
あのグレムリン像に祈る連中に。
「だけど僕たちは、まだ、空を『完全に』奪われたわけじゃない。
僕らの支えたグレムリンは飛んでる。僕らはまだグレムリンの一部でいられる。それに。
……この戦いが終われば、僕らの機体を解析するだけの余裕ができる。僕らのグレムリンが動き出す可能性は、まだ、ゼロじゃないんだ」
それは自分にとっても祝福そのもののはずだった。この工廠で未だ眠る『サーシオネ』を、こいつが知らないわけもない。
だから、その言葉は、他ならぬ俺を説得するためのもののはずで。
しかしその一言一言を、ラトーは自分に言い聞かせているようにしか映らなかった。
「ラトー」
この期に及んで悟るのは、あまりにも遅すぎただろう。
あの呆れにも似た沈黙で、隔壁じみて張り巡らした正しさで、漏れ出させるまいとしていたものが何だったのか。
それに不用意にも穴を穿とうとした俺が、どれほど、馬鹿だったか。
あるいは今も、こうして話しているだけでその壁を軋ませ続けているのか。
既に他人のそれを奪ったグレムリンで飛び続ける奴が、こうして目の前にいるだけで。
「悪かった」
変わらず響き続ける絶え間ない周りの声、ひしめく生の立てる音に包まれて、目の前の相手は微動だにしない。
何もかも、分からなかった。掠れたその言葉が届いたのかどうかさえ。
押し手が見えなくなるほど箱を満載した台車が大声を上げて通り抜け、許可もないだろうにダクト下を占拠して立ち並んだ屋台の客引きをかき消す。その後を汚れた服のガキどもが追って走り、つくりが適当な床に引っかかって案の定横転した台車の荷物拾いを手伝うふりしていくらか懐へせしめた。どっかの制服のおっさんが怒号を上げてそいつらを叱り飛ばしても、人波の隙間を縫って逃げる子供を追うにはその図体は大きすぎる。
鼻で笑いながら別の方へ目を向ければ、そこだけは粉塵避けにしっかり作られた窓から赤い空気に遠く霞んで見えるのは旗を掲げた人型のシルエット。こうして別の島からでも見えるほどに大きなグレムリン像は、領域解放記念とか言って作られたものらしい。一心にそいつを拝む連中に埋め尽くされた窓の周りだけが別の空間のように静かで、その周囲では着の身着のままの避難民が泥のように眠っていた。かろうじて持ち出せたらしい小さな荷を後生大事に抱えて。
「凄いだろ。ここ一週間くらいで一気にこの調子になったから、まだ全然……この通り、混沌としてるとしか言いようがない」
その声に、雑多を絵に描いたような光景から目を離して正面を向く。
テーブルとは名ばかりのかろうじて平坦にネジ止めされた板、その上に置かれた二杯のコーヒーを挟んで、困り顔のラトーが笑っていた。
「一月前の俺に小群島だっつっても信じねえよ、こんなの」
「何もなかったもんな、アネモネくらいしか」
「そうそ、師団どころか虚空領域一のクソ田舎」
そして、昨日の俺に言えばもっとだろう。
あの死に体の工廠を見た後の俺なら、こんなものは確かに実際目にしなければ信じなかったに違いない。
「……でも、アネモネがなかったらこんなことにはならなかったろうな」
そしてその工廠もまた『生き返った』としか言いようのない復活ぶりだった。
もちろん、あれほどの損害の傷跡を二週間程度で埋められるはずもない。しかしどうやったのかグレムリンの死体で埋め尽くされたハンガーにはいくらかの空きができて、人員も少ないとはいえ前の生気のなさに比べりゃ意気も働きも雲泥の違いだ。
「あの後もストレイキャットは随分出たよ。
これは、そのために寄ったグレムリンが戦ってくれた結果だ」
そもそも工廠が『死んでいる』って俺の見立てそのものが間違いだったのかもしれなかった。
工廠が死に絶えたのならそんな場所でどうして換装ができた。どうして後から後からテイマーがやってくる。どうしてグレムリンを診られる。
「にしたって、こんなことになるまで受け入れるこたねえだろうに。氷獄の旗艦も相当だったが比じゃねえぞ」
どうして気づけなかったんだか。漏れ出た苛立ちの矛先が不意に向いたのを、相対する目ははっきりと怒りをもって睨んできた。
「アザミネ」
「悪り」
「そんなこと言ったら放り出されるのはそっちだ。一番後から来たのはお前なんだからな」
そう一息に口に出して、ラトーは一度コーヒーで口を湿す。
「……でもお前がテイマーだってのが知れれば、まあ助かるかもしれない。それも、たった今飛んできたやつのって言えばさ。
こんな民間施設ができても、ここの核はやっぱり工廠だ。戦える、動けるグレムリンの支援施設」
知っているさ。さっきのあの翡翠みたいに像を拝む連中を見ても分かる。今のテイマーというものに、どれくらいの力があるのか。
そしてそれがどれくらいの物事を正当化できるか。
例え今この群衆の中に『フォールスビーク』の正当な持ち主がいたとして、その主張を一蹴できる程度にはあるだろう。
動くグレムリンを奪うなんてことは初めてじゃない。
だからお前を誘っているんだ、と口に出そうとして、――そこから出たのは音にならない息だけだ。
俺のものと同じ眼窩を横切る手術痕を持つ瞼が開いて、覗いた目はそれほどまで真っ直ぐに俺を射抜く。
「だからその一員として、僕はあの提案には絶対に頷けない。
工廠で機体を奪われたなんて話、一回でも起きたら二度とアネモネに人は寄り付かない。
噂がどんな速さで広まるか、この二週間で嫌って程わかったしね」
その声も語り口も、努めて声を潜めているのもあって一貫して静かだ。ただそこに煮えたぎるような怒りのあることは疑いようがない。
堰を切ったまま止まらない台詞はその証明として余りある。これまでずっと堪えてきたか、あるいは蓄えてきたものだ。
今すぐの話なわけがない。きっとあの通信で交わした言葉の間に挟まった不自然な沈黙のその時から。
「調整の要る機体が寄るのを中止するようなことも出るだろう。それが元で落ちるんなら、それは防げたはずの負けだ。
その機体が救えた人ごとみんな巻き込む戦力の喪失だ」
機銃のように吐き出され並べられるその論理は驚くほど正しい。教科書じみて。
グレムリンの一機は何人の人命を救えるか。自分が直接乗るのでなくても、アネモネにいることで間接的にどれほど影響できるか。今のこの状況を見ればそれもまた自明だ。
それを認識するほどに、ひどく視座のずれていることを自覚させられる。
瞬間のうちに幾度となく反芻してその言葉の中に感じ取る齟齬は、グレムリンから引き剥がされたラトーがアネモネという新しい居場所で見出した、操縦棺の中より遥かに広大な世界と、そこに生きる人間と、未来への眼に違いなかった。
「ならその分、お前が乗って取り返しゃいい!!
アレがいくら性能が落ちるって言ったって、できないとは言わせねえ。
お前だってテイマーだろうがよ!!」
張り上げた声もテーブルへ叩きつけた拳も勢いのまま立ち上がる体も、振り上げられた手に対する防御反応にこそ近かった。それは俺を打ちのめすと意識よりも前に魂が気づいていた。
その視座を得た一歩、操縦棺の外への一足、親しんだ相手の離れていく恐怖は意見の正しさなんかよりよほど強烈に俺を殺すと。
肺の中の空気を一息に吐き出しきって、呼吸は酷く荒かった。テーブルに置いたままの手は横倒しになったコーヒーと冷汗でじっとりと濡れている。転がったカップが床を叩く。怒号でこちらに気づいた野次馬が喧嘩を囃し立てる声が遠い。
「グレムリンから離れたら、死ぬ、アルテアのテイマーだろ」
その一つ一つにすっかり意気を失ってさえ、吐き出されるのは懸念のふりをして縛る小狡い台詞だ。
ガキめ。
頭の中を切り分けて住みついたすっかり冷静な自己が他人事じみてそう吐き捨てる。
ああそうだよ。
戻ってきてほしい。お前がいい。同じ場所にいてくれ。そんな感情論と俺だけの目線でしかものを言えねえガキだ。
「……何を言われたって、乗る気はないからな。僕だけの話じゃない。勢力レベルの話だってある。
青花の工廠で真紅の機体に何かあれば、絶対にこの後の火種になる。今は何ともなくてもだ」
そんな奴が頷いてもらえるわけもない。提示され続ける正しさが、向けられた情を明確に弾く。幾枚もの分厚い装甲板に似て。
「だけどな」
だから次がれたその言葉はその間から開いた銃眼に見えて、心は瞬時に身構える。そこから放たれる弾を見越して。
けれど同時に拭えない違和感。……だけど?
「グレムリンのあるお前が、今でも飛べるお前が羨ましくないって言ったら嘘になる」
その感覚を立証するように、隙間から覗いたのは銃身ではなく剥き出しの棺。世界から隔てられた小さな小さな個。
未だ座ったままこちらを見上げてくる視線への確かな既視感がそれを裏付ける。
そこにあるのはかつてアネモネで、乗機をなくした虚ろなテイマーが向けてきた目だ。
紛れもない、嫉妬を宿した。
「僕の他にも、機体が動かなくてエンジニアやってる奴はいるよ。そいつら全員きっとそうだ」
そうしてその瞳は一度瞼の裏に隠れる。
眉根を寄せたその表情は今までのものから離れて、また別のものに似通っていく。
あのグレムリン像に祈る連中に。
「だけど僕たちは、まだ、空を『完全に』奪われたわけじゃない。
僕らの支えたグレムリンは飛んでる。僕らはまだグレムリンの一部でいられる。それに。
……この戦いが終われば、僕らの機体を解析するだけの余裕ができる。僕らのグレムリンが動き出す可能性は、まだ、ゼロじゃないんだ」
それは自分にとっても祝福そのもののはずだった。この工廠で未だ眠る『サーシオネ』を、こいつが知らないわけもない。
だから、その言葉は、他ならぬ俺を説得するためのもののはずで。
しかしその一言一言を、ラトーは自分に言い聞かせているようにしか映らなかった。
「ラトー」
この期に及んで悟るのは、あまりにも遅すぎただろう。
あの呆れにも似た沈黙で、隔壁じみて張り巡らした正しさで、漏れ出させるまいとしていたものが何だったのか。
それに不用意にも穴を穿とうとした俺が、どれほど、馬鹿だったか。
あるいは今も、こうして話しているだけでその壁を軋ませ続けているのか。
既に他人のそれを奪ったグレムリンで飛び続ける奴が、こうして目の前にいるだけで。
「悪かった」
変わらず響き続ける絶え間ない周りの声、ひしめく生の立てる音に包まれて、目の前の相手は微動だにしない。
何もかも、分からなかった。掠れたその言葉が届いたのかどうかさえ。
◆16回更新の日記ログ
『認証に成功。思念接続を開始……対流域を確保。ようこそ、グレイヴネットへ!!』
繰り返される通信エラーの後に響く、心待ちにしていた人工音声に顔を上げる。あのジャンク野郎どもも随分と面倒なことをしてくれたものだ。
立ち上げるのは多重暗号化された秘匿通話回線。発信先アドレスを打ち込み終えて最後のキーの一押しは、寸前で割り込んできた通常通話の受信許可を出してしまう。まだ発信元も何も見ていないうちから。
ようやく繋がったばかりの回線は未だ不安定らしかった。画面に大写しになる姿ははっきりしているくせに、聞こえてくる声は乱れノイズにまみれている。
「ザザッ――かった、繋がりま―ザッ―たね。
ハイド―ザザザーッ――リーランサーより、『フォールスビーク』アザミネ・トウハさ――ザーッ」
音がいくらか潰れたって分かるお決まりの通信文を耳に入れながら、改めて文字として表示し直した発信元は名乗り口上と同じ。
映るのも見慣れた顔だ。フリーランサーに身を置いた当初から変わらないいつもの窓口役。
「切っていいか? 用あるんでね、終わったらこっちから繋ぎ直す」
「待っ―ザーッ―さい、かなり人員の限られた作戦がありまして。話だけで―ザザザーッ――。
繋ぎ直すって言ったってこの―ザーッ――子です。それにせっ―ザッ―取っていただいたんですし」
取りたくて取ったんじゃねえよ。それに説明もろくに聞こえやしねえだろ。
食い下がるオペレータは反応を待たずもう話を次ぎ始めている。最悪このまま切られても構わないといった風に。
そこまで切羽詰まる何がある、その微かな興味が通話終了ボタンへ伸ばした指を止めさせた。
「フリーランサーでは現在、違法――ザザザーッ――取引の摘発――ザザッ―に協力可能な人員を探しています。
作―ザッー域は辺境海域、北西柱。決行は二日後――ザーッ――交戦可能性あり。
グレムリンな――ザザザ――による戦闘ではなく、目標船に乗り込んでの白兵戦任務となります。
決行期日までに作戦領域へ到達可能かつ、肉体的戦闘技術を習得し―ザッ―方として、アザミネさんに協力を要請したく――ザザザ」
ふうん。漏れたのは自分でも分かるほど興味のなさそうな音。
雑音に紛れた分を聞き飛ばしたって分かる。グレムリンに乗れる奴が今最優先すべきなのは、何をどう考えてもあのジャンクのデカブツどもだ。テイマーだけじゃない、そのために虚空領域の全兵力を挙げているといってもいい。その中でそんなに絞って探すなら首尾など上がるわけもない。
聞き返す声は茶化し半分。
「正規軍は? 聞く限りいかにもそっちの仕事って感じだが」
「これは青花師団本部よりフリーラン――ザザッ――依頼です。
ジャンク財団との交戦、および財団の戦力誇示に巻き込まれて出ている多数の死傷者、および拠点強襲作戦へ大きく兵力を割いた―ザーッ――よる兵員不足のカバーをと」
「へえ。テイマーに声かけるほど人が足りてないって?
グレムリンに勝てるとしたらまずグレムリンだろ、財団にぶつけた方がよっぽど助かる命もあると思うがね」
「承知の上で、フリーランサー協賛者の一人としてお声掛けを――ザーッ――論いつも通り、強制力はありません。
我々は師団の理念に従い、自由意思の元の協力を求めます」
その通り、フリーランサーの姿勢としては何も間違っちゃいない。元から金次第で何でも請けるし、何なら金がなくたって食指が動けば請ける。
そういう意味じゃあ最も青花らしい組織だろう。その意思だってカネで曲がる辺りは最高に皮肉だが。
「詳細について続けますね。
『死の眠りの16時間』以前から摘発に当たっていた正規軍の中心メンバーは残存していますから、依頼するのはあくまでその補助になります。
主に出口を固め、逃亡者が発生した―ザッ――最終確保をと」
「そんな重要な役どころを傭兵に任せるのか、本部は?」
「そうであっても好機は今しかない、という考えのようです。間諜が掴んだ情報も、いつまで正しいか―ザッ―
それに、混乱下の今だからこそこれ以上乗じての犠牲者を出すわけにはいかないと」
いささか語気の強まったオペレータの言葉にふとした違和感。犠牲者? 何の。
密売され、かつ犠牲者が出るようなもの。薬? 火器? 人間? どれもあり得るからこそ絞れない。
「待ってくれ。多分一番重要なトコ飛んでんぞ。『何の』密売摘発だ?」
一瞬の間を置いて、大変失礼しました、と返る声。その中にいくらかの訝しみがある。当たり前だ。何でもっと早く言わなかった、逆なら俺だってそう思っただろう。
だがその答えを聞いた後じゃ、そんな些細なことなど覚えちゃいなかった。
「違法人身売買。
それも、天然臓器摘出用の小児のです」
少しの沈黙の後に、なるほどねえ、と出した声が長く尾を引く。
自然と片眼を押さえるように手が動いたのは、そこがふと熱を持ったように感じたからだ。正確には、眼球を跨ぐように刻まれてなお消えない手術痕が。
そんなはずはない。もしそうならこの体中、燃えるように熱くなっているはずだ。一瞬にして氷獄もかくやと思うほど冷え切ったこの胸にあった熱に代わるように。
「OK、受ける」
「! ありがとうございます」
その胸から出した声も案の定同じ温度で、どこか弾んだ調子の抑え切れない向こうの声と比べればなお冷たい。
「ただし仮返答。
明日にはアネモネで機体のチェックだ。万一引っかかったら話はナシ。足がない」
引っかかるものか、とは思いながらも口に出さざるを得ない矛盾した懸念は、氷獄で俺を呼び止めたエンジニアの言葉が残したものだ。
身体検査における第四種制御識《希望》領域への高負荷値。そんなことは分かっている。元から俺にあそこまで四種を扱う適性はない。どうせアネモネに着けばそんな無茶も終わりだ。
棘のように刺さっているのはもう一つの方。
火器系統の命令伝達回路に、微かではあるが異常兆候が見られる、と。
パーツ自体に問題はない。棺でもない。そうなれば原因はフレームか、あるいはブラックボックスのG.I.F.T.システムそれ自体。
もしもシステムであれば、修正はおろか究明さえも危ういかもしれない。工廠で詳細な検査を行うべきだという。
実際に使って何の差異も感じないものに、その言葉一つで異常を認めるのは難しいだろう。だが物がグレムリンだ。命を預けるものに万が一があれば待つのは死。どっちみち、アネモネに寄る用が消えるわけじゃない。
「了解しました。明日の夜に最終可否についてお伺いしますね」
「頼む。そんじゃ」
いくらか冷静になった向こうの声に被せるようにして、そのまま通話を切る。とんだ長話だ、だが悪くはない。
映されていた通話相手が消えれば改めて現れるのは元通り、後はキーをひとつ押すだけの秘匿通話発信画面。もうそれを妨げるものは何もない。
数コールの後に聞こえるのは、先のそれよりもずっと長く。物心ついたその頃から親しんで、心許した声。
「もしもし、アザミネ?」
「おうラトー、今空いてるか?」
「いつ呼ばれるかわからない。待機時間なんだ」
「じゃ、手短に。
通じたってことはアネモネだな? 明日にはそっち着く。ドック一つ点検で予約を取りたい」
「わかった。話は通しておく」
「で、ここからが本題。土産を持ってけそうだ」
「ふうん? アザミネにそんなこと言われるなんて思わなかったな。何?」
「グレムリンだよ。動くやつな」
瞬間モニタ上に浮かんだ表情は、驚きというよりは疑念のそれだった。
細まった目と同じ声色が、先よりもいくらか低くスピーカーから響く。
「……どこで鹵獲した?」
「これからするんだよ。もう実質してるって言ってもいいか?
真紅の連中の量産型がずっとついてきてるんだが、使い物にならないんだよ。今はこんな状況だろ? そうじゃなくたって、グレムリンは使える奴が乗るべきだ。
お前の腕は信頼してるよ、昔からな。『トリップラーレ』じゃなくたって、また一緒に飛べるならこんなに心強いことはねえ」
口に出せばその姿が脳裏に蘇る。両腕に付属する形で二枚、思念誘導方式で宙に浮かぶ四枚、巨大な六枚の装甲板を備えたグレムリン。傷跡の制御識に長けたあいつに宛がわれた迎撃特化の機体。
返答はない。説明が足りてない、あるいは。
「何も連中を殺ろうってんじゃない。登録内容を書き換えるだけだ、ちょっと大人しくしてもらってる間にな。
工廠の設備なら――」
「アザミネ。それは駄目だ」
反発。原因がそちらにあるのは、表情を見た時から少しは予想できていた。
だが道理はまだこちらにある。動くグレムリンが限られている以上、乗るべきはより強い奴のはずだ。それに揺らぎはない。
予想を外してきたのは、その次。
「駄目だ、が通じないなら、できない、でもいい。
協力できない。テイマー登録の書き換え、それに……グレムリンに乗ることそのものにもだ。
例え『トリップラーレ』が今目覚めても、僕は飛ばない……いや、飛べない、かな」
どういうことだ。
乗れなくなった? 何故。手足が飛ぼうが新生体がある。一度目覚めた制御識は失われない。当たり前に飛んでいた俺たちが今更怖がる理由なんか何もない。
それに、俺たちがグレムリンに乗れなくなって何が残る。
淡々と言葉は続く。二の句の継げない俺を置いて。
「明日には来られるって言ってたよね。着いたらすぐ下りて、そこで待ってて。迎えに行く。
きっと、自分で見た方がわかりやすいと思うから」
繰り返される通信エラーの後に響く、心待ちにしていた人工音声に顔を上げる。あのジャンク野郎どもも随分と面倒なことをしてくれたものだ。
立ち上げるのは多重暗号化された秘匿通話回線。発信先アドレスを打ち込み終えて最後のキーの一押しは、寸前で割り込んできた通常通話の受信許可を出してしまう。まだ発信元も何も見ていないうちから。
ようやく繋がったばかりの回線は未だ不安定らしかった。画面に大写しになる姿ははっきりしているくせに、聞こえてくる声は乱れノイズにまみれている。
「ザザッ――かった、繋がりま―ザッ―たね。
ハイド―ザザザーッ――リーランサーより、『フォールスビーク』アザミネ・トウハさ――ザーッ」
音がいくらか潰れたって分かるお決まりの通信文を耳に入れながら、改めて文字として表示し直した発信元は名乗り口上と同じ。
映るのも見慣れた顔だ。フリーランサーに身を置いた当初から変わらないいつもの窓口役。
「切っていいか? 用あるんでね、終わったらこっちから繋ぎ直す」
「待っ―ザーッ―さい、かなり人員の限られた作戦がありまして。話だけで―ザザザーッ――。
繋ぎ直すって言ったってこの―ザーッ――子です。それにせっ―ザッ―取っていただいたんですし」
取りたくて取ったんじゃねえよ。それに説明もろくに聞こえやしねえだろ。
食い下がるオペレータは反応を待たずもう話を次ぎ始めている。最悪このまま切られても構わないといった風に。
そこまで切羽詰まる何がある、その微かな興味が通話終了ボタンへ伸ばした指を止めさせた。
「フリーランサーでは現在、違法――ザザザーッ――取引の摘発――ザザッ―に協力可能な人員を探しています。
作―ザッー域は辺境海域、北西柱。決行は二日後――ザーッ――交戦可能性あり。
グレムリンな――ザザザ――による戦闘ではなく、目標船に乗り込んでの白兵戦任務となります。
決行期日までに作戦領域へ到達可能かつ、肉体的戦闘技術を習得し―ザッ―方として、アザミネさんに協力を要請したく――ザザザ」
ふうん。漏れたのは自分でも分かるほど興味のなさそうな音。
雑音に紛れた分を聞き飛ばしたって分かる。グレムリンに乗れる奴が今最優先すべきなのは、何をどう考えてもあのジャンクのデカブツどもだ。テイマーだけじゃない、そのために虚空領域の全兵力を挙げているといってもいい。その中でそんなに絞って探すなら首尾など上がるわけもない。
聞き返す声は茶化し半分。
「正規軍は? 聞く限りいかにもそっちの仕事って感じだが」
「これは青花師団本部よりフリーラン――ザザッ――依頼です。
ジャンク財団との交戦、および財団の戦力誇示に巻き込まれて出ている多数の死傷者、および拠点強襲作戦へ大きく兵力を割いた―ザーッ――よる兵員不足のカバーをと」
「へえ。テイマーに声かけるほど人が足りてないって?
グレムリンに勝てるとしたらまずグレムリンだろ、財団にぶつけた方がよっぽど助かる命もあると思うがね」
「承知の上で、フリーランサー協賛者の一人としてお声掛けを――ザーッ――論いつも通り、強制力はありません。
我々は師団の理念に従い、自由意思の元の協力を求めます」
その通り、フリーランサーの姿勢としては何も間違っちゃいない。元から金次第で何でも請けるし、何なら金がなくたって食指が動けば請ける。
そういう意味じゃあ最も青花らしい組織だろう。その意思だってカネで曲がる辺りは最高に皮肉だが。
「詳細について続けますね。
『死の眠りの16時間』以前から摘発に当たっていた正規軍の中心メンバーは残存していますから、依頼するのはあくまでその補助になります。
主に出口を固め、逃亡者が発生した―ザッ――最終確保をと」
「そんな重要な役どころを傭兵に任せるのか、本部は?」
「そうであっても好機は今しかない、という考えのようです。間諜が掴んだ情報も、いつまで正しいか―ザッ―
それに、混乱下の今だからこそこれ以上乗じての犠牲者を出すわけにはいかないと」
いささか語気の強まったオペレータの言葉にふとした違和感。犠牲者? 何の。
密売され、かつ犠牲者が出るようなもの。薬? 火器? 人間? どれもあり得るからこそ絞れない。
「待ってくれ。多分一番重要なトコ飛んでんぞ。『何の』密売摘発だ?」
一瞬の間を置いて、大変失礼しました、と返る声。その中にいくらかの訝しみがある。当たり前だ。何でもっと早く言わなかった、逆なら俺だってそう思っただろう。
だがその答えを聞いた後じゃ、そんな些細なことなど覚えちゃいなかった。
「違法人身売買。
それも、天然臓器摘出用の小児のです」
少しの沈黙の後に、なるほどねえ、と出した声が長く尾を引く。
自然と片眼を押さえるように手が動いたのは、そこがふと熱を持ったように感じたからだ。正確には、眼球を跨ぐように刻まれてなお消えない手術痕が。
そんなはずはない。もしそうならこの体中、燃えるように熱くなっているはずだ。一瞬にして氷獄もかくやと思うほど冷え切ったこの胸にあった熱に代わるように。
「OK、受ける」
「! ありがとうございます」
その胸から出した声も案の定同じ温度で、どこか弾んだ調子の抑え切れない向こうの声と比べればなお冷たい。
「ただし仮返答。
明日にはアネモネで機体のチェックだ。万一引っかかったら話はナシ。足がない」
引っかかるものか、とは思いながらも口に出さざるを得ない矛盾した懸念は、氷獄で俺を呼び止めたエンジニアの言葉が残したものだ。
身体検査における第四種制御識《希望》領域への高負荷値。そんなことは分かっている。元から俺にあそこまで四種を扱う適性はない。どうせアネモネに着けばそんな無茶も終わりだ。
棘のように刺さっているのはもう一つの方。
火器系統の命令伝達回路に、微かではあるが異常兆候が見られる、と。
パーツ自体に問題はない。棺でもない。そうなれば原因はフレームか、あるいはブラックボックスのG.I.F.T.システムそれ自体。
もしもシステムであれば、修正はおろか究明さえも危ういかもしれない。工廠で詳細な検査を行うべきだという。
実際に使って何の差異も感じないものに、その言葉一つで異常を認めるのは難しいだろう。だが物がグレムリンだ。命を預けるものに万が一があれば待つのは死。どっちみち、アネモネに寄る用が消えるわけじゃない。
「了解しました。明日の夜に最終可否についてお伺いしますね」
「頼む。そんじゃ」
いくらか冷静になった向こうの声に被せるようにして、そのまま通話を切る。とんだ長話だ、だが悪くはない。
映されていた通話相手が消えれば改めて現れるのは元通り、後はキーをひとつ押すだけの秘匿通話発信画面。もうそれを妨げるものは何もない。
数コールの後に聞こえるのは、先のそれよりもずっと長く。物心ついたその頃から親しんで、心許した声。
「もしもし、アザミネ?」
「おうラトー、今空いてるか?」
「いつ呼ばれるかわからない。待機時間なんだ」
「じゃ、手短に。
通じたってことはアネモネだな? 明日にはそっち着く。ドック一つ点検で予約を取りたい」
「わかった。話は通しておく」
「で、ここからが本題。土産を持ってけそうだ」
「ふうん? アザミネにそんなこと言われるなんて思わなかったな。何?」
「グレムリンだよ。動くやつな」
瞬間モニタ上に浮かんだ表情は、驚きというよりは疑念のそれだった。
細まった目と同じ声色が、先よりもいくらか低くスピーカーから響く。
「……どこで鹵獲した?」
「これからするんだよ。もう実質してるって言ってもいいか?
真紅の連中の量産型がずっとついてきてるんだが、使い物にならないんだよ。今はこんな状況だろ? そうじゃなくたって、グレムリンは使える奴が乗るべきだ。
お前の腕は信頼してるよ、昔からな。『トリップラーレ』じゃなくたって、また一緒に飛べるならこんなに心強いことはねえ」
口に出せばその姿が脳裏に蘇る。両腕に付属する形で二枚、思念誘導方式で宙に浮かぶ四枚、巨大な六枚の装甲板を備えたグレムリン。傷跡の制御識に長けたあいつに宛がわれた迎撃特化の機体。
返答はない。説明が足りてない、あるいは。
「何も連中を殺ろうってんじゃない。登録内容を書き換えるだけだ、ちょっと大人しくしてもらってる間にな。
工廠の設備なら――」
「アザミネ。それは駄目だ」
反発。原因がそちらにあるのは、表情を見た時から少しは予想できていた。
だが道理はまだこちらにある。動くグレムリンが限られている以上、乗るべきはより強い奴のはずだ。それに揺らぎはない。
予想を外してきたのは、その次。
「駄目だ、が通じないなら、できない、でもいい。
協力できない。テイマー登録の書き換え、それに……グレムリンに乗ることそのものにもだ。
例え『トリップラーレ』が今目覚めても、僕は飛ばない……いや、飛べない、かな」
どういうことだ。
乗れなくなった? 何故。手足が飛ぼうが新生体がある。一度目覚めた制御識は失われない。当たり前に飛んでいた俺たちが今更怖がる理由なんか何もない。
それに、俺たちがグレムリンに乗れなくなって何が残る。
淡々と言葉は続く。二の句の継げない俺を置いて。
「明日には来られるって言ってたよね。着いたらすぐ下りて、そこで待ってて。迎えに行く。
きっと、自分で見た方がわかりやすいと思うから」
◆15回更新の日記ログ
向こうの壁さえ見渡せないほどの大部屋いっぱいに敷き詰められたテーブル席、それを埋め尽くしてなお余るごった返す人波。
来るまででおおむね予想がついていても、目に入った瞬間思わず舌打ちが漏れた。何のために時間をずらしたと思ってる。俺の後ろに続いてレーンへ向かう人間皆、似たようなことは考えているだろう。
青花旗艦船団のうちの一隻、その胃袋を担う大食堂。だが昼時を過ぎてなお席はろくに空きもなく、配膳待ちの列は途切れそうもない。
トレーを取りながら思い返したのは前に工廠船で見た避難民だ。居住船の沈没のあおりに例の作戦もあって、そもそも人が多すぎるんだろう。その前には多少の知恵なんざ絞ったところで無駄らしい。
思考に鈍る足は順繰りに進む列に並ぶには邪魔っけだ。後ろの奴のトレーに背を小突かれながらさっさと歩を進める。
仕切られた配膳板の上、一番大きなエリアにコーンミール。もう少し小さな区切りの中に申し訳程度のバイオベーコンと味付きバイオビーンズ。ドリンクホルダーにコーヒー。流れ作業で盛られていく飯はこんな日でも大して代わり映えはしない。
そんな感想は最後でいきなり裏切られた。普段ならドロが入る一番狭いスペースに下ろされたのは、明らかに瓶から出したままの栄養錠剤。
「ドロは?」
「切れました」
配膳員が返すのは今トレーに乗ったと同じ味も素っ気もない台詞。もう飽きるほど同じことを聞かれてるんだろう。
時間をずらしたのはいよいよ完全に裏目だ。さっさと席を探して食うしかない。
とは言ってもその席さえすぐには見つからない。何せ配膳レーンがまだ続いているかのように、形成された列が落ち着く場もなくそのまま移動しているような状態だ。
遠目に見かけた空席も、向かうまでもなく他のレーンから来た奴が埋めていく。
それでも先頭の方から一人消え、二人消え、気づけば大分列の先の方。部屋の中の位置取りとしてももう中心辺りだろう。
360度のテーブル席を見回す視界に席を立つ一人が映って、間髪入れずにそちらへ足を向ける。幸い他に近づく奴はいない。
空席の向かいへ座る男に声をかけるのは手のトレーをテーブルへ下ろした後。持ってちゃまだ動けると思われる。この中からもう一度探し直すのは骨だ。できればここで決めてしまいたかった。
「ここ、貰――」
言葉が切れたのは、そいつが顔を上げた瞬間に血の気が引いたからだ。
板が手にあったままなら、ひっくり返して酷い音がしたに違いなかった。だが幸か不幸か手は空のまま震えるだけで、鳴るのは息を呑む音程度。それさえ大食堂の喧騒があっちゃ目の前にすら伝わらない。
顔立ちにははっきり覚えがある。老けちゃいるが目の合わせ方も、その次に変ににやける癖も同じだ。間違いない。
そんな内心なんざ気にもしない様子で向こうは驚きもあらわに、喜色まで出して声をかけてくる。
その声色に無神経ささえそのままなモンだから、いよいよ進退窮まった。
「アザミネ君? アザミネ君かい? 生きていてくれたか……!!」
「…………どうも、教官」
「そう言ってくれるのかい? いや、懐かしいな、もう教官じゃあないんだが」
おまえたちがそれを言うのか。その言葉を押し殺し、やっとのことで喉から声を絞り出しながら、指の震えを隠して板を持ち直す。
そりゃ向こうからすれば不審極まりないだろう。だが差し向かいなんて御免だ。それにあの頃から話好きのこいつのこと、先に席を立ってくれるなんざ望み薄。さっさと席を変えるに限る。
「いやいや、待ちなさい!
そりゃあ君たちにとっちゃ、今更僕らと同席なんて思うところもあるだろうけどね。食べていきなさい。席、探し直すとなると大変だろう」
だが振り返った周囲に空席はない。できても後続が次々に埋めていく。丁度さっき俺がしたように、席を立つ奴とほとんど入れ替わるようにして。
出る側から見てみればあのコンベア状の席探しの隊列は壁じみて出る側の動きまで制限していて、出られる方向といえば出口側だけだ。
待とうが状況はさして変わらないだろうし、何よりそんな時間はもうない。腹が減っているのもそうだし、繰り延べた予定は後へつかえないギリギリだ。
喉奥の舌打ちは聞こえないと分かってのことだ。返事は乱雑に、引いた椅子へ腰を下ろしてから。
「みたいスね」
目は合わせないまま、視線は無味乾燥な食事へ向けて。
文字通り道がない以上、残る選択肢はさっさと食べきって出ていくしかない。山盛りに掬い取って啜るコーンミールには案の定味がなかった。
飲み込むより早くスプーンを刺して、向かいの相手など一瞥することもなく。話しかけるなと全身で訴えていることなんか分かっているだろうに、そんなことはお構いなしの調子で向こうはべらべらと楽しげに話しかけてくる。
教官は教官でも色々いたが、せめてこいつじゃない方がよほどマシだったろう。舐めた口を聞けば即座に鉄拳を飛ばす、露骨に駒を見る眼で俺たちを見ていた奴。あの頃は皆が何よりも嫌っていたあいつの方がよほど。
「それにしても大きくなったな。今いくつだい」
「15です」
「3年ぶりか。君くらいの年の3年は本当に大きいからねぇ。背も随分伸びたし……顔つきも、随分良い男になったじゃないか。
眼は替えたのかい? 前は左右、違ったろう」
「はい」
「そうか。つつがなく稼げてるようで何よりだよ、暮らしには問題あるまいね。
これまではどこにいた? ああ、こんなことになる前だよ」
「フリーランサーに」
「ああ、なるほど。君がいるなら彼らも心強かろうね。
君のグレムリン、今でも動いているかい。ケイジが崩壊してから動かなくなったのを随分見たが」
「はい」
「そうかそうか、それは良かった! なるほど、生き残れているわけだ。
ああ、連絡先いるかい? 君は教えてくれって言ったってくれる方じゃないだろうけどね。何かあったら」
顔も上げずに生返事を繰り返す相手に、よくもまあここまで延々と飽きもせずに話し続けられるものだ。会っていないとは言ったって、十中八九耳には入れているだろうに。
それとも聞いた話と今とで、真偽をできる限り照合しようとでもしているのか。探るところが多いのを見れば可能性としてはその線だろう。
そう合点が行けばなお、苛立ちと憎悪が腹から上る。使うと決めれば口を塞がせる口実も話の端緒も、隠しもしない棘の言い訳もいくらだってあった。例えば半端に残ったまま全く減らないトレーの中身に、それを放ったまま紙片に書きつけ始めるペンの動きに。
「食べないんスか? 席、早く空けた方がいいでしょう。こんだけ混んでんだ」
「ああ、すまないね。せっかく会ったものだから。だが、教え子がどうしているかというのは気になるものだよ。
こんな時世なら猶更、次にいつ会えるのかも分からないんだし──」
『西方行き特別艦『オオトビウオ』の乗船券をお持ちの方をお呼び出しいたします、船団空母3番艦デッキへお集まりください。繰り返します……』
こちらの話を聞いたようでいてまったく受け入れないその言葉を止めたのは、割り込んだ船内放送。それがタイムリミットだった。
『大とびうお座星雲を西へ』、あのジャンクのデカブツどもを相手取る作戦の合言葉に関連付けた単語が複数入った放送は、作戦参加者の呼び出し符丁だ。いよいよこうしている時間はない。
幸い、向こうの長口上の間に皿はほとんど空。残る錠剤を乱雑につかんで口に放り込み、そのままコーヒーで流し込んで立ち上がる。
もう顔を見ることもない。そうあってくれ。二度と。
そう思っていたのに。
「死ぬなよ」
俯いたままの立ち姿にかけられた言葉がいやにはっきり聞こえたのと、顔を上げたのは同時だった。
視線の先では奴が真剣そのものの面持ちでこちらを見据えている。さっきまでのへらへらした調子が嘘みたいに、聞こえてきた声色と何ら変わることなく。
トレーを持とうとした手は縛られたように止まって、けれど頭はそれにさえ気が付かない。
気にすることなんかない、きっと演技だ。いや、それにしては。
一瞬が幾分にも引き延ばされたような中での葛藤は、向こうからすれば物も言えずにただ呆然としているだけだ。
それがよっぽどおかしかったか。目の前の顔はすぐ、普段と同じようににっと崩れた。
「どうした。行かないのかい?」
その台詞が耳に届くや否や、全身へ血流が急速に戻ってくる。正気を取り戻した頭は今するべきことを思い出して、さっきまでの重しが取れた手脚を自在に操り人をかき分けるようにして大股にその場を後にする。
もう一瞬だって、同じ時間も空間も共有していたくはなかった。その理由は嫌悪もあれ、第一はといえば羞恥心だったろう。
恥ずかしかったし、何よりも許しがたかった。そう言われるほどに凍りついていたことも、それをわざわざ奴の口から指摘されたことも。
それを思えば蘇ったはずの思考は再びみるみる鈍って、幾度だってあの台詞をひとりでに繰り返す。
何なんだ。どうして。よりによってお前にそんなことを言われる理由がある。そんなに駒が減るのが嫌か。
そう思いながらトレーを回収スペースに投げ込めば、風に乗ってひらり飛ぶものがあった。空中で掴んで広げれば、書かれているのは乱雑な文字。中途の記号から判断すればおそらくメールアドレス。
あの時間でねじ込みやがったのか、そう分かれば一つ鼻が鳴る。読めるかもわからない、普段なら迷わず捨てていたはずのそれをポケットに突っ込んで歩き出す。
「死んでやるモンかよ。言われなくたってな」
来るまででおおむね予想がついていても、目に入った瞬間思わず舌打ちが漏れた。何のために時間をずらしたと思ってる。俺の後ろに続いてレーンへ向かう人間皆、似たようなことは考えているだろう。
青花旗艦船団のうちの一隻、その胃袋を担う大食堂。だが昼時を過ぎてなお席はろくに空きもなく、配膳待ちの列は途切れそうもない。
トレーを取りながら思い返したのは前に工廠船で見た避難民だ。居住船の沈没のあおりに例の作戦もあって、そもそも人が多すぎるんだろう。その前には多少の知恵なんざ絞ったところで無駄らしい。
思考に鈍る足は順繰りに進む列に並ぶには邪魔っけだ。後ろの奴のトレーに背を小突かれながらさっさと歩を進める。
仕切られた配膳板の上、一番大きなエリアにコーンミール。もう少し小さな区切りの中に申し訳程度のバイオベーコンと味付きバイオビーンズ。ドリンクホルダーにコーヒー。流れ作業で盛られていく飯はこんな日でも大して代わり映えはしない。
そんな感想は最後でいきなり裏切られた。普段ならドロが入る一番狭いスペースに下ろされたのは、明らかに瓶から出したままの栄養錠剤。
「ドロは?」
「切れました」
配膳員が返すのは今トレーに乗ったと同じ味も素っ気もない台詞。もう飽きるほど同じことを聞かれてるんだろう。
時間をずらしたのはいよいよ完全に裏目だ。さっさと席を探して食うしかない。
とは言ってもその席さえすぐには見つからない。何せ配膳レーンがまだ続いているかのように、形成された列が落ち着く場もなくそのまま移動しているような状態だ。
遠目に見かけた空席も、向かうまでもなく他のレーンから来た奴が埋めていく。
それでも先頭の方から一人消え、二人消え、気づけば大分列の先の方。部屋の中の位置取りとしてももう中心辺りだろう。
360度のテーブル席を見回す視界に席を立つ一人が映って、間髪入れずにそちらへ足を向ける。幸い他に近づく奴はいない。
空席の向かいへ座る男に声をかけるのは手のトレーをテーブルへ下ろした後。持ってちゃまだ動けると思われる。この中からもう一度探し直すのは骨だ。できればここで決めてしまいたかった。
「ここ、貰――」
言葉が切れたのは、そいつが顔を上げた瞬間に血の気が引いたからだ。
板が手にあったままなら、ひっくり返して酷い音がしたに違いなかった。だが幸か不幸か手は空のまま震えるだけで、鳴るのは息を呑む音程度。それさえ大食堂の喧騒があっちゃ目の前にすら伝わらない。
顔立ちにははっきり覚えがある。老けちゃいるが目の合わせ方も、その次に変ににやける癖も同じだ。間違いない。
そんな内心なんざ気にもしない様子で向こうは驚きもあらわに、喜色まで出して声をかけてくる。
その声色に無神経ささえそのままなモンだから、いよいよ進退窮まった。
「アザミネ君? アザミネ君かい? 生きていてくれたか……!!」
「…………どうも、教官」
「そう言ってくれるのかい? いや、懐かしいな、もう教官じゃあないんだが」
おまえたちがそれを言うのか。その言葉を押し殺し、やっとのことで喉から声を絞り出しながら、指の震えを隠して板を持ち直す。
そりゃ向こうからすれば不審極まりないだろう。だが差し向かいなんて御免だ。それにあの頃から話好きのこいつのこと、先に席を立ってくれるなんざ望み薄。さっさと席を変えるに限る。
「いやいや、待ちなさい!
そりゃあ君たちにとっちゃ、今更僕らと同席なんて思うところもあるだろうけどね。食べていきなさい。席、探し直すとなると大変だろう」
だが振り返った周囲に空席はない。できても後続が次々に埋めていく。丁度さっき俺がしたように、席を立つ奴とほとんど入れ替わるようにして。
出る側から見てみればあのコンベア状の席探しの隊列は壁じみて出る側の動きまで制限していて、出られる方向といえば出口側だけだ。
待とうが状況はさして変わらないだろうし、何よりそんな時間はもうない。腹が減っているのもそうだし、繰り延べた予定は後へつかえないギリギリだ。
喉奥の舌打ちは聞こえないと分かってのことだ。返事は乱雑に、引いた椅子へ腰を下ろしてから。
「みたいスね」
目は合わせないまま、視線は無味乾燥な食事へ向けて。
文字通り道がない以上、残る選択肢はさっさと食べきって出ていくしかない。山盛りに掬い取って啜るコーンミールには案の定味がなかった。
飲み込むより早くスプーンを刺して、向かいの相手など一瞥することもなく。話しかけるなと全身で訴えていることなんか分かっているだろうに、そんなことはお構いなしの調子で向こうはべらべらと楽しげに話しかけてくる。
教官は教官でも色々いたが、せめてこいつじゃない方がよほどマシだったろう。舐めた口を聞けば即座に鉄拳を飛ばす、露骨に駒を見る眼で俺たちを見ていた奴。あの頃は皆が何よりも嫌っていたあいつの方がよほど。
「それにしても大きくなったな。今いくつだい」
「15です」
「3年ぶりか。君くらいの年の3年は本当に大きいからねぇ。背も随分伸びたし……顔つきも、随分良い男になったじゃないか。
眼は替えたのかい? 前は左右、違ったろう」
「はい」
「そうか。つつがなく稼げてるようで何よりだよ、暮らしには問題あるまいね。
これまではどこにいた? ああ、こんなことになる前だよ」
「フリーランサーに」
「ああ、なるほど。君がいるなら彼らも心強かろうね。
君のグレムリン、今でも動いているかい。ケイジが崩壊してから動かなくなったのを随分見たが」
「はい」
「そうかそうか、それは良かった! なるほど、生き残れているわけだ。
ああ、連絡先いるかい? 君は教えてくれって言ったってくれる方じゃないだろうけどね。何かあったら」
顔も上げずに生返事を繰り返す相手に、よくもまあここまで延々と飽きもせずに話し続けられるものだ。会っていないとは言ったって、十中八九耳には入れているだろうに。
それとも聞いた話と今とで、真偽をできる限り照合しようとでもしているのか。探るところが多いのを見れば可能性としてはその線だろう。
そう合点が行けばなお、苛立ちと憎悪が腹から上る。使うと決めれば口を塞がせる口実も話の端緒も、隠しもしない棘の言い訳もいくらだってあった。例えば半端に残ったまま全く減らないトレーの中身に、それを放ったまま紙片に書きつけ始めるペンの動きに。
「食べないんスか? 席、早く空けた方がいいでしょう。こんだけ混んでんだ」
「ああ、すまないね。せっかく会ったものだから。だが、教え子がどうしているかというのは気になるものだよ。
こんな時世なら猶更、次にいつ会えるのかも分からないんだし──」
『西方行き特別艦『オオトビウオ』の乗船券をお持ちの方をお呼び出しいたします、船団空母3番艦デッキへお集まりください。繰り返します……』
こちらの話を聞いたようでいてまったく受け入れないその言葉を止めたのは、割り込んだ船内放送。それがタイムリミットだった。
『大とびうお座星雲を西へ』、あのジャンクのデカブツどもを相手取る作戦の合言葉に関連付けた単語が複数入った放送は、作戦参加者の呼び出し符丁だ。いよいよこうしている時間はない。
幸い、向こうの長口上の間に皿はほとんど空。残る錠剤を乱雑につかんで口に放り込み、そのままコーヒーで流し込んで立ち上がる。
もう顔を見ることもない。そうあってくれ。二度と。
そう思っていたのに。
「死ぬなよ」
俯いたままの立ち姿にかけられた言葉がいやにはっきり聞こえたのと、顔を上げたのは同時だった。
視線の先では奴が真剣そのものの面持ちでこちらを見据えている。さっきまでのへらへらした調子が嘘みたいに、聞こえてきた声色と何ら変わることなく。
トレーを持とうとした手は縛られたように止まって、けれど頭はそれにさえ気が付かない。
気にすることなんかない、きっと演技だ。いや、それにしては。
一瞬が幾分にも引き延ばされたような中での葛藤は、向こうからすれば物も言えずにただ呆然としているだけだ。
それがよっぽどおかしかったか。目の前の顔はすぐ、普段と同じようににっと崩れた。
「どうした。行かないのかい?」
その台詞が耳に届くや否や、全身へ血流が急速に戻ってくる。正気を取り戻した頭は今するべきことを思い出して、さっきまでの重しが取れた手脚を自在に操り人をかき分けるようにして大股にその場を後にする。
もう一瞬だって、同じ時間も空間も共有していたくはなかった。その理由は嫌悪もあれ、第一はといえば羞恥心だったろう。
恥ずかしかったし、何よりも許しがたかった。そう言われるほどに凍りついていたことも、それをわざわざ奴の口から指摘されたことも。
それを思えば蘇ったはずの思考は再びみるみる鈍って、幾度だってあの台詞をひとりでに繰り返す。
何なんだ。どうして。よりによってお前にそんなことを言われる理由がある。そんなに駒が減るのが嫌か。
そう思いながらトレーを回収スペースに投げ込めば、風に乗ってひらり飛ぶものがあった。空中で掴んで広げれば、書かれているのは乱雑な文字。中途の記号から判断すればおそらくメールアドレス。
あの時間でねじ込みやがったのか、そう分かれば一つ鼻が鳴る。読めるかもわからない、普段なら迷わず捨てていたはずのそれをポケットに突っ込んで歩き出す。
「死んでやるモンかよ。言われなくたってな」
◆14回更新の日記ログ
いなくなれ、の意志一つで爆ぜた風船を最後に捕捉敵影は尽きた。機体の中枢に据えたファントムハートは未だ棺内まで響くほどの唸りを上げていて、なお機影があればいつだって飛び掛かれる。
そこから置く一分の間。海面から立ち上る幾筋もの煙の間に動くものは何もない。あるのはただ粉塵舞う、見飽きた赤い空。
広域レーダーへ映る反応もゼロ。高速機および潜水艇による奇襲可能性はごく低い。
02:04、絶滅空域、制圧確認完了。
状況、終了。
「コンテナってより、びっくり箱か。
似たようなモンかね。
しかしやっぱいいねえ、叩けば素直に落ちるってのはよ」
友軍回線へ流すそれは素直な感想だ。べろりと梱包でも剥がすように『生まれ変わる』あの空飛ぶコンテナは、鉄屑になることを拒む亀どもを思い出させて余りある。
殺せば死ぬ。一番シンプルで実感に近い手段を、当たり前の顔で覆してくるあいつらの。
そうしてもう一つは、状況共有だ。
これくらいの軽口を叩ける程度の環境は確保した。計器でも実感でも確認している。何か問題はあるか、あるなら返せ。もちろん、警戒は怠らずに。
そうして案の定、聞いているはずの相手からの応答はなかった。今に始まったことじゃない。最初からごくごく事務的な連絡以上のことはした試しもない。
する気にさえならない飛び方しかできないような連中に、かける言葉なんか見つかるはずもない。あるとすれば揶揄だ。たった今、いよいよデコイだな、なんて嘯いてやりたくなったように。
いてもいなくても戦況としては大差ない。ただ思念の総数に対応しているらしい未識別機動体を呼ぶためだけにここにいる。向こうだってそれが分かっていないはずもないだろう。幸いなのは当初の懸念通りエレクトロフィールドを持ち出すような事態になっていないこと程度。
役割としては弾除けでしかなく、それ以上は期待できない。それ以外の何ができるものか。俺にも、あの未識別機動体どもにも、加速し続ける戦場そのものについてこられない連中に。
幾度も行き着いた結論へ今日も帰着して、鼻を鳴らす一息さえもう出やしない。そうして外へ出ていくものの代わりに、腹の内へひたひたと溜まっていく憎悪の滴もまたいつもと同じだ。
どうしてあんな連中のグレムリンばかりが動いてる。
『サーシオネ』がその代わりに動いたのなら。それだけじゃない。その席に他のアルテアのテイマー、それに似たような生え抜き連中が座れたのなら。
戦況を考えれば、そっちの方がよほどマシな戦果を挙げるに決まっている。
思い出すのは青花工廠『アネモネ』。あらゆる機能を保ったまま、ハンガーに立ち尽くす遺骸と化したグレムリン。未だそれを受け入れられずに、見上げて呆然とするばかりのテイマー。動くグレムリンへ向けられる、疑念と羨望と嫉妬をありありと浮かべた眼。
船そのものが巨大な墓標ででもあるかのような、怖気がするほど陰鬱な空気。グレムリンを受け入れるはずの工廠が無言のうちに、動く乗機を持つテイマーを弾き出すあの異様さ。
あれがあってどうして、のうのうとあいつらが空を与えられたままでいる。答えは出ない。出ないから余計に、その理不尽が癪に障る。
もちろんアネモネであの場にいた全員が、グレムリンを与えれば今いるデコイ以上の働きをするかと言われればそんなわけもない。
ただ、マシな人間は間違いなくいる。例えばラトー。きっとあいつは、俺の他にも生き残りの行き場を知っているはずだ。
待っていろ、そう思ってようやく、口元が吊り上がる感覚が戻ってきた。
もうすぐ戻れる。氷獄での作戦を終えればそうはかからない。ヴォイド・エレベータとやらがなくたって、補給を含めても二昼夜あれば着く。
関心はずっとそこにある。この予定に割り込んできて、グレイヴネットに我が物顔で居座った連中のことよりも前から。
そこから置く一分の間。海面から立ち上る幾筋もの煙の間に動くものは何もない。あるのはただ粉塵舞う、見飽きた赤い空。
広域レーダーへ映る反応もゼロ。高速機および潜水艇による奇襲可能性はごく低い。
02:04、絶滅空域、制圧確認完了。
状況、終了。
「コンテナってより、びっくり箱か。
似たようなモンかね。
しかしやっぱいいねえ、叩けば素直に落ちるってのはよ」
友軍回線へ流すそれは素直な感想だ。べろりと梱包でも剥がすように『生まれ変わる』あの空飛ぶコンテナは、鉄屑になることを拒む亀どもを思い出させて余りある。
殺せば死ぬ。一番シンプルで実感に近い手段を、当たり前の顔で覆してくるあいつらの。
そうしてもう一つは、状況共有だ。
これくらいの軽口を叩ける程度の環境は確保した。計器でも実感でも確認している。何か問題はあるか、あるなら返せ。もちろん、警戒は怠らずに。
そうして案の定、聞いているはずの相手からの応答はなかった。今に始まったことじゃない。最初からごくごく事務的な連絡以上のことはした試しもない。
する気にさえならない飛び方しかできないような連中に、かける言葉なんか見つかるはずもない。あるとすれば揶揄だ。たった今、いよいよデコイだな、なんて嘯いてやりたくなったように。
いてもいなくても戦況としては大差ない。ただ思念の総数に対応しているらしい未識別機動体を呼ぶためだけにここにいる。向こうだってそれが分かっていないはずもないだろう。幸いなのは当初の懸念通りエレクトロフィールドを持ち出すような事態になっていないこと程度。
役割としては弾除けでしかなく、それ以上は期待できない。それ以外の何ができるものか。俺にも、あの未識別機動体どもにも、加速し続ける戦場そのものについてこられない連中に。
幾度も行き着いた結論へ今日も帰着して、鼻を鳴らす一息さえもう出やしない。そうして外へ出ていくものの代わりに、腹の内へひたひたと溜まっていく憎悪の滴もまたいつもと同じだ。
どうしてあんな連中のグレムリンばかりが動いてる。
『サーシオネ』がその代わりに動いたのなら。それだけじゃない。その席に他のアルテアのテイマー、それに似たような生え抜き連中が座れたのなら。
戦況を考えれば、そっちの方がよほどマシな戦果を挙げるに決まっている。
思い出すのは青花工廠『アネモネ』。あらゆる機能を保ったまま、ハンガーに立ち尽くす遺骸と化したグレムリン。未だそれを受け入れられずに、見上げて呆然とするばかりのテイマー。動くグレムリンへ向けられる、疑念と羨望と嫉妬をありありと浮かべた眼。
船そのものが巨大な墓標ででもあるかのような、怖気がするほど陰鬱な空気。グレムリンを受け入れるはずの工廠が無言のうちに、動く乗機を持つテイマーを弾き出すあの異様さ。
あれがあってどうして、のうのうとあいつらが空を与えられたままでいる。答えは出ない。出ないから余計に、その理不尽が癪に障る。
もちろんアネモネであの場にいた全員が、グレムリンを与えれば今いるデコイ以上の働きをするかと言われればそんなわけもない。
ただ、マシな人間は間違いなくいる。例えばラトー。きっとあいつは、俺の他にも生き残りの行き場を知っているはずだ。
待っていろ、そう思ってようやく、口元が吊り上がる感覚が戻ってきた。
もうすぐ戻れる。氷獄での作戦を終えればそうはかからない。ヴォイド・エレベータとやらがなくたって、補給を含めても二昼夜あれば着く。
関心はずっとそこにある。この予定に割り込んできて、グレイヴネットに我が物顔で居座った連中のことよりも前から。
◆13回更新の日記ログ
「おれ、……船外出たんだ。第五教練棟の非常口、錠の電気時々落ちてるだろ。あそこから。非常ボートあるし」
「それは聞いてる。元々無断外出がどうって話だったもんな」
「よっぽどやべえとこでも――」
「違う!!」
「そ、そりゃ、行こうとしてたトコはあったんだ。
だけど皆でぎゃあぎゃあやってるうちに、今どこにいるのかわかんなくなっちゃって。
それで、その、そのときにさ……」
「絡まれたんだ、……気違いみたいな変な女に」
まだ大して話してもいない。むしろ聞いてるこっちからすりゃまだまだ触りに過ぎない。なのにその声はもう震えていた。
真っ暗な布団の中じゃ見えやしないが、どうせ身体だってそうなんだろう。
声の方向に目を向けたってあるのは暗闇だけだ。それでも印象に残ってるものってのは浮かぶもので、ここ最近で見慣れたルームメイトの、真っ青になって怯え切った情けない顔は脳裏にはっきり見えていた。多分実物はそれ以上酷かったんだろうが。
そう思っている間に、続く言葉はなかった。そいつは恐怖のあまりかすっかり口をつぐんでしまって、息をするだけで精一杯と言わんばかり。
そうなったところで、周りは元々上官命令でもなければ大人しく待つなんてろくにできないガキどもだ。そんな沈黙に堪えられるわけもない。
「おい、しっかりしろよ! 話すって言ったのお前だろ!」
「変な女って、実際どう変だったんだよ。見てくれとか言ってたこととかいろいろあるだろ」
しびれを切らして声を張り上げる奴、続く奴。
怯えたように息を呑む音が聞こえた時は駄目かと思ったが、なんとかそれで気を取り直したらしい。
あんな距離でもなければろくに聞こえもしないだろう、空調にさえ負けそうな声。
ただそれでぽつぽつと述べる言葉を、あの場の誰もが耳を澄まして聞いていた。
「変、……で、気色悪、くて……
おれのこと見た瞬間に声上げてさ、駆け寄って抱き着いてきて、
……顔も知らねえ、ずっと上の女だぞ? ワケ分かんねえ、それに、そいつおれの名前も知ってた。何度も呼んでさ、それで、」
最初は促されてやっと、という風を隠しもしなかったその喋り方が次第に勢いづいて、そのまま転んだ。
ただ、先を急かす奴はもういなかった。俺もそうだ。止められはしないが聞きたくもない、そんな気分だった。
伝説のテイマーの戦闘記録。生身の時に現れた自分を狙う機影。恐ろしくも目を離せない、そういうものを見た時に似て。
そいつは何だ。何だってそんなことをする理由がある。どうして知ってる。答えのまるで見えないそれを考えれば嫌な汗ばかりが出てくる。
じっとりと、纏わりつくような気味の悪さ。
それは布団の中にこもったいきれの湿気が大半だったろうが、その時の俺にとっては話についた実体に他ならなかった。
そうぐるぐると いる間に、転んだ話は立ち上がっていたらしい。
続いたのはただ一言。絞り出すような、呻きにも似た声。
「……帰りましょう、って」
「どこにだよ」
聞き返す声は呆然としていた。訳の分からなさがまた別の方向へ飛んでいった。そんな思いを全員が共有していただろう。
帰る。この船以外のどこに帰ればいい。ここの他に持ったこともない居所を、ぽっと出の誰が用意できるものか。
スクールの関係者が連れ戻しに来たわけでもない。俺たちの籍は間違いなくここにあって、他のどこにも行けやしない。
その答えを持っているのは、震えている言い出しっぺしかいなかった。
「……家」
「家」
「家?」
「家だあ?」
返ったその答えを呑み込むまでに、口々の復唱が3回。
無理やりにでもそうして腹に落としてしまえば、消化できなくはない。ギリギリだが、その範疇には収まった。
「……ああ、気違いってそういうことな」
「教官が言う奴だろ」
気の触れた女は珍しくない。特に子供を亡くした女は。
落ち着きのないのがスーツも着ずに弾丸じみて外に飛び出すだけで。あるいは大人の背に合わせて作られた甲板の手すりからするりと外へ出てしまうだけで。それだけで子供ってものは死ぬ。
そうでなくても子供を十全に育ててやれないことは多い。もっと遡れば、産まれないことだって。
てっきり教官たちの恩着せ話だとばかり思っていたそいつに、多少の信憑性はあったらしい。
ようやく答えが見えたと安心しきった俺たちに水を差したのは、相変わらず歯切れの悪い言い出しっぺの声。
「……かもしれない、けど、なんか……」
「なんか?」
「なんか、…………それとも、違って……」
振り払ったはずのあの湿り気が、その言葉一つで音もなく戻ってくる。
誰も口を開けない。沈黙の中で、ただ嫌に響く胸の早鐘の音だけを聞いている。
そいつもまた静かな真っ暗闇の中で、必死で説明する言葉を探しているらしかった。何が「違う」のか。その差異がどういうところから出ているのか。
ただ、まっとうな成果なんて上がらなかったんだろう。もしくは何かの名案があったとして、そいつは俺たちへの何の緩衝材にもならなかった無意味なものだ。
「一番気持ち悪かったの、抱きしめられたことでも、名前のことでも、帰るってのでもなくて……
……ぶつぶつ言ってたんだよ。おれをガッて抱きしめたまま、ずっと。
おれに話してるわけじゃなくて、聞かせたいってんでもなくて、わかんないけど、
『障害なんて嘘だ、病気なんて嘘だ、書類も全部』
『あんな奴に見せるんじゃなかった、誘拐犯どもに』
『そうすれば一緒に暮らせた』
『人殺しになんてならなくて済んだのに』って、ずっと、……ずっと……」
すっかり目が慣れたって、灯のひとつもない中では何が見えるはずもない。
むしろ何も見えないことこそがおそらくは幸せなはずだった。それを聞いて何も思い浮かばないことこそが。
けれど俺たちはその中に、すっかり見慣れた互いの顔を見ることができてしまっていた。全員の面に制服みたいに走った、目頭と目尻を繋ぐみたいな手術痕。左右で違う新生体の目の色。顔だけじゃない。カプセルの溶液に浮かぶ体に走るめちゃくちゃな傷跡だって。
一人でも例外がいれば違ったろう。だが生憎、ここにいるのは全員そういう奴だった。
粉塵性障害、新生体措置により寛解済。
当然に書類へその文字の刻まれた、赤い空の下に産まれた子供。
この間中ろくに喋りもしなかった口へ手が行ったのは、こみ上げた吐き気を堪えるためだ。
気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い。ひどく息苦しい淀みきった空気。訳の分からない女。何が潜むかも分からないこの船。そこで今まで生きてきた俺。何もかも全部。
話はまだ続いていた。だがあのうちのどれだけがそれをきちんと聞いていたのかはわからない。何もなかった。周りを気にする余裕も、聞こえてくる言葉を文字に直す余裕も。
「それは聞いてる。元々無断外出がどうって話だったもんな」
「よっぽどやべえとこでも――」
「違う!!」
「そ、そりゃ、行こうとしてたトコはあったんだ。
だけど皆でぎゃあぎゃあやってるうちに、今どこにいるのかわかんなくなっちゃって。
それで、その、そのときにさ……」
「絡まれたんだ、……気違いみたいな変な女に」
まだ大して話してもいない。むしろ聞いてるこっちからすりゃまだまだ触りに過ぎない。なのにその声はもう震えていた。
真っ暗な布団の中じゃ見えやしないが、どうせ身体だってそうなんだろう。
声の方向に目を向けたってあるのは暗闇だけだ。それでも印象に残ってるものってのは浮かぶもので、ここ最近で見慣れたルームメイトの、真っ青になって怯え切った情けない顔は脳裏にはっきり見えていた。多分実物はそれ以上酷かったんだろうが。
そう思っている間に、続く言葉はなかった。そいつは恐怖のあまりかすっかり口をつぐんでしまって、息をするだけで精一杯と言わんばかり。
そうなったところで、周りは元々上官命令でもなければ大人しく待つなんてろくにできないガキどもだ。そんな沈黙に堪えられるわけもない。
「おい、しっかりしろよ! 話すって言ったのお前だろ!」
「変な女って、実際どう変だったんだよ。見てくれとか言ってたこととかいろいろあるだろ」
しびれを切らして声を張り上げる奴、続く奴。
怯えたように息を呑む音が聞こえた時は駄目かと思ったが、なんとかそれで気を取り直したらしい。
あんな距離でもなければろくに聞こえもしないだろう、空調にさえ負けそうな声。
ただそれでぽつぽつと述べる言葉を、あの場の誰もが耳を澄まして聞いていた。
「変、……で、気色悪、くて……
おれのこと見た瞬間に声上げてさ、駆け寄って抱き着いてきて、
……顔も知らねえ、ずっと上の女だぞ? ワケ分かんねえ、それに、そいつおれの名前も知ってた。何度も呼んでさ、それで、」
最初は促されてやっと、という風を隠しもしなかったその喋り方が次第に勢いづいて、そのまま転んだ。
ただ、先を急かす奴はもういなかった。俺もそうだ。止められはしないが聞きたくもない、そんな気分だった。
伝説のテイマーの戦闘記録。生身の時に現れた自分を狙う機影。恐ろしくも目を離せない、そういうものを見た時に似て。
そいつは何だ。何だってそんなことをする理由がある。どうして知ってる。答えのまるで見えないそれを考えれば嫌な汗ばかりが出てくる。
じっとりと、纏わりつくような気味の悪さ。
それは布団の中にこもったいきれの湿気が大半だったろうが、その時の俺にとっては話についた実体に他ならなかった。
そうぐるぐると いる間に、転んだ話は立ち上がっていたらしい。
続いたのはただ一言。絞り出すような、呻きにも似た声。
「……帰りましょう、って」
「どこにだよ」
聞き返す声は呆然としていた。訳の分からなさがまた別の方向へ飛んでいった。そんな思いを全員が共有していただろう。
帰る。この船以外のどこに帰ればいい。ここの他に持ったこともない居所を、ぽっと出の誰が用意できるものか。
スクールの関係者が連れ戻しに来たわけでもない。俺たちの籍は間違いなくここにあって、他のどこにも行けやしない。
その答えを持っているのは、震えている言い出しっぺしかいなかった。
「……家」
「家」
「家?」
「家だあ?」
返ったその答えを呑み込むまでに、口々の復唱が3回。
無理やりにでもそうして腹に落としてしまえば、消化できなくはない。ギリギリだが、その範疇には収まった。
「……ああ、気違いってそういうことな」
「教官が言う奴だろ」
気の触れた女は珍しくない。特に子供を亡くした女は。
落ち着きのないのがスーツも着ずに弾丸じみて外に飛び出すだけで。あるいは大人の背に合わせて作られた甲板の手すりからするりと外へ出てしまうだけで。それだけで子供ってものは死ぬ。
そうでなくても子供を十全に育ててやれないことは多い。もっと遡れば、産まれないことだって。
てっきり教官たちの恩着せ話だとばかり思っていたそいつに、多少の信憑性はあったらしい。
ようやく答えが見えたと安心しきった俺たちに水を差したのは、相変わらず歯切れの悪い言い出しっぺの声。
「……かもしれない、けど、なんか……」
「なんか?」
「なんか、…………それとも、違って……」
振り払ったはずのあの湿り気が、その言葉一つで音もなく戻ってくる。
誰も口を開けない。沈黙の中で、ただ嫌に響く胸の早鐘の音だけを聞いている。
そいつもまた静かな真っ暗闇の中で、必死で説明する言葉を探しているらしかった。何が「違う」のか。その差異がどういうところから出ているのか。
ただ、まっとうな成果なんて上がらなかったんだろう。もしくは何かの名案があったとして、そいつは俺たちへの何の緩衝材にもならなかった無意味なものだ。
「一番気持ち悪かったの、抱きしめられたことでも、名前のことでも、帰るってのでもなくて……
……ぶつぶつ言ってたんだよ。おれをガッて抱きしめたまま、ずっと。
おれに話してるわけじゃなくて、聞かせたいってんでもなくて、わかんないけど、
『障害なんて嘘だ、病気なんて嘘だ、書類も全部』
『あんな奴に見せるんじゃなかった、誘拐犯どもに』
『そうすれば一緒に暮らせた』
『人殺しになんてならなくて済んだのに』って、ずっと、……ずっと……」
すっかり目が慣れたって、灯のひとつもない中では何が見えるはずもない。
むしろ何も見えないことこそがおそらくは幸せなはずだった。それを聞いて何も思い浮かばないことこそが。
けれど俺たちはその中に、すっかり見慣れた互いの顔を見ることができてしまっていた。全員の面に制服みたいに走った、目頭と目尻を繋ぐみたいな手術痕。左右で違う新生体の目の色。顔だけじゃない。カプセルの溶液に浮かぶ体に走るめちゃくちゃな傷跡だって。
一人でも例外がいれば違ったろう。だが生憎、ここにいるのは全員そういう奴だった。
粉塵性障害、新生体措置により寛解済。
当然に書類へその文字の刻まれた、赤い空の下に産まれた子供。
この間中ろくに喋りもしなかった口へ手が行ったのは、こみ上げた吐き気を堪えるためだ。
気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い。ひどく息苦しい淀みきった空気。訳の分からない女。何が潜むかも分からないこの船。そこで今まで生きてきた俺。何もかも全部。
話はまだ続いていた。だがあのうちのどれだけがそれをきちんと聞いていたのかはわからない。何もなかった。周りを気にする余裕も、聞こえてくる言葉を文字に直す余裕も。
◆12回更新の日記ログ
一番最初に連絡を絶ったのは、傭兵なんかどう見たって向いてない神経の細い奴だった。制御識適性だけは五種どれも飛び抜けて高いくせに、実戦に出て引鉄を引けば帰ってから寝込まない日はない。
なんであんな奴がいるんだろうな、無駄飯喰らいじゃねえか。
俺だってそう嗤ったことを覚えている。テイマー養成施設と言う場ではその通り以外の何物でもないし、変に庇い立てでもしてあんな腰抜けの仲間だと思われる方がよっぽど恥ずかしかった。
何を話すことはなくともこいつが傭兵になるなんて有り得ないと誰もが思っていたし、本人だって乗り気じゃないのは見るからに明らかだった。
だから正確に言えば、誰も連絡を取ろうとしなかった、というのが正しい。少なくとも俺の周りでは。
そいつが死んだんじゃなく失踪したらしいって話になったのは、別の奴から連絡が来てからだ。そいつにとっては唯一の友人といってもいい。
そいつですら知らないことを俺たちが知るわけがない。それは突っぱねる意味でもあったし、文字通りでもある。
そう答えてから、そのダチの方もそれっきり行方が知れない。
その次は、卒業したら真紅へ鞍替えするつもりだと一度だけ漏らした奴だった。
何お前あのだっせえ制服着んの、なんて茶化した奴も、あいつの顔を見ればすぐに黙った。嘘も冗談も入り込みようがない、思い詰めたと言った方がいい表情。普段ふざけてた奴だったからこそ、その面がどんな言葉よりも効いた。
外に真紅の女がいた、『赤い手紙』があいつを注文したんで引き抜かれた、殺った相手の家族に情が移った、そいつを見てやるために真紅の物資や補助が必要だった。
聞こえてくる噂はごまんとあれどれも憶測に過ぎなかったし、結局そいつはそのどれも真実だとは言わないまま、生きている証明さえもできなくなった。
もっとまともなメシが食いたい。そう言い残してシンカプへ行った奴もいた。
コーンミールの供給元の社員ならもうちょっと真っ当なメシが出るだろうなんていかにもガキの発想だが、そいつがそう言い出した時には大真面目に信じた奴が結構いて、そいつについていったのもいくらか。
そのうち何人かが受かったって聞いて、本気で羨んだ奴、自分も行けばよかったなんて漏らす奴。自分が受からなかったんで何かコスい手使ったって言い出す奴。随分いろんな反応があるモンだなと他人事で眺めていたのを覚えている。
だから最初にそいつらと連絡が取れなくなった時は、エリート社員様は忙しいんだろ、くらいの話で終わっていたはずだ。勤め始めの頃から実際に返信は飛び飛びになっていたから、誰もそれを疑う奴なんていなかった。
実際、その状態からちゃんと連絡がついたことが何度かあったから猶更だ。ただ、その間隔はどんどん開いていったが。
返事が一週間開き、二週間開き、ひと月開いた頃に、状況を聞いた奴がいた。送られてきた文面はいかにも無難だった。それが最後になった。
そんなことが続けば続くほど、残りの団結は強くなる。似たように消えた奴がいればすぐに割れる。
その生き残りどもで一度共通点を話し合えば、結論なんてすぐに出た。
離れなかったことだ。青花から。グレムリンから。アルテアで仕込まれたことから。
育てた側から見りゃそいつは当然なんだろう。
手間も金もかけて技術を教え込んだ商品あるいはグレムリンの最終パーツを、操縦棺の外へ出すわけにはいかない。もちろん、他の勢力にも渡せやしない。
誰もはっきり気づいたなんてことは言わなかった。
代わりに行き交ったのは、やっぱり、と言わんばかりの陰気な目配せ。その感じが揃いも揃って同じだったから、何も言わなかろうが同じ結論に行き着いたと知っただけ。
青花師団の組織である以上、その題目としての自由は耳にタコができるほど聞かされてきた。
だがそいつをいくら説いたところで、アルテアにあるのは額面通りの自由じゃあない。
定められたランダムさの間にしかない気まぐれに従って決められた通りの動きをする、画面の向こう側から出てこないプログラムの猫みてえな自由。
何せテイマーの養成施設。将来的に他の勢力の連中とどうしたってぶつかることが約束されている場所に字面通りの自由なんかないってのは、大して考えなくたって知れている。
ただ俺たちの疑いはそれよりも少し違うところにあった。
空っぽのベッドを連日囲んで、残った連中で話していたのを覚えている。
手を出しちゃならないモンに手を出した。別勢力の連中と通じた。『航空者』に連れ去られて体を弄られた。流石にそりゃねえって。いや、どうだろ。
無断外出の懲罰にしたって謹慎一か月は長すぎた。最初は真っ青になって心配するばかりだったガキどもも、次第にその不安をどうにかしたくて必死に理由を考え出す。
つまり格好の噂の的だった。その理由がどんなに切羽詰まっていても、いや切羽詰まっているからこそ話は留まるところを知らないし、憶測でしかないはずのことが事実みたいに広まっていくのにも時間はかからない。
それも戻ってこないのは同室の奴だけじゃなかったから、どうせ学校中で似たような話はされていたんだろう。
そこそこ真実味のあるものから荒唐無稽なものまで話は様々あって、だがいざ帰ってきた連中はそのどれにも答えなかった。
ただ元と変わらずに、謹慎も何もなかったように過ごしていただけだ。
腹の底に収められない何かを押し込めたようなひきつった笑いを、真っ青な顔に浮かべながら。
何があったか知らないが、あんなのが長く続く訳もない。
その思いが裏切られなかったと確信したのは、耐え切れなくなった奴がようやっと口を割った時だ。
絶対外へ聞こえないようにしろと何度も念を押すそいつのベッドへ全員分の掛布団を持ち寄って、その中にガキとはいえぎゅうぎゅうに男が詰まるモンだから狭くてしょうがない。
だが顔を寄せ合って話を聞いているうちに、そんなことさえ忘れるようだった。
「おれ、……船外出たんだ。第五教練棟の非常口、錠の電気時々落ちてるだろ。あそこから。非常ボートあるし」
「それは聞いてる。元々無断外出がどうって話だったもんな」
「よっぽどやべえとこでも――」
「違う!!」
「そ、そりゃ、行こうとしてたトコはあったんだ。
だけど皆でぎゃあぎゃあやってるうちに、今どこにいるのかわかんなくなっちゃって。
それで、その、そのときにさ……」
「絡まれたんだ、……気違いみたいな変な女に」
なんであんな奴がいるんだろうな、無駄飯喰らいじゃねえか。
俺だってそう嗤ったことを覚えている。テイマー養成施設と言う場ではその通り以外の何物でもないし、変に庇い立てでもしてあんな腰抜けの仲間だと思われる方がよっぽど恥ずかしかった。
何を話すことはなくともこいつが傭兵になるなんて有り得ないと誰もが思っていたし、本人だって乗り気じゃないのは見るからに明らかだった。
だから正確に言えば、誰も連絡を取ろうとしなかった、というのが正しい。少なくとも俺の周りでは。
そいつが死んだんじゃなく失踪したらしいって話になったのは、別の奴から連絡が来てからだ。そいつにとっては唯一の友人といってもいい。
そいつですら知らないことを俺たちが知るわけがない。それは突っぱねる意味でもあったし、文字通りでもある。
そう答えてから、そのダチの方もそれっきり行方が知れない。
その次は、卒業したら真紅へ鞍替えするつもりだと一度だけ漏らした奴だった。
何お前あのだっせえ制服着んの、なんて茶化した奴も、あいつの顔を見ればすぐに黙った。嘘も冗談も入り込みようがない、思い詰めたと言った方がいい表情。普段ふざけてた奴だったからこそ、その面がどんな言葉よりも効いた。
外に真紅の女がいた、『赤い手紙』があいつを注文したんで引き抜かれた、殺った相手の家族に情が移った、そいつを見てやるために真紅の物資や補助が必要だった。
聞こえてくる噂はごまんとあれどれも憶測に過ぎなかったし、結局そいつはそのどれも真実だとは言わないまま、生きている証明さえもできなくなった。
もっとまともなメシが食いたい。そう言い残してシンカプへ行った奴もいた。
コーンミールの供給元の社員ならもうちょっと真っ当なメシが出るだろうなんていかにもガキの発想だが、そいつがそう言い出した時には大真面目に信じた奴が結構いて、そいつについていったのもいくらか。
そのうち何人かが受かったって聞いて、本気で羨んだ奴、自分も行けばよかったなんて漏らす奴。自分が受からなかったんで何かコスい手使ったって言い出す奴。随分いろんな反応があるモンだなと他人事で眺めていたのを覚えている。
だから最初にそいつらと連絡が取れなくなった時は、エリート社員様は忙しいんだろ、くらいの話で終わっていたはずだ。勤め始めの頃から実際に返信は飛び飛びになっていたから、誰もそれを疑う奴なんていなかった。
実際、その状態からちゃんと連絡がついたことが何度かあったから猶更だ。ただ、その間隔はどんどん開いていったが。
返事が一週間開き、二週間開き、ひと月開いた頃に、状況を聞いた奴がいた。送られてきた文面はいかにも無難だった。それが最後になった。
そんなことが続けば続くほど、残りの団結は強くなる。似たように消えた奴がいればすぐに割れる。
その生き残りどもで一度共通点を話し合えば、結論なんてすぐに出た。
離れなかったことだ。青花から。グレムリンから。アルテアで仕込まれたことから。
育てた側から見りゃそいつは当然なんだろう。
手間も金もかけて技術を教え込んだ商品あるいはグレムリンの最終パーツを、操縦棺の外へ出すわけにはいかない。もちろん、他の勢力にも渡せやしない。
誰もはっきり気づいたなんてことは言わなかった。
代わりに行き交ったのは、やっぱり、と言わんばかりの陰気な目配せ。その感じが揃いも揃って同じだったから、何も言わなかろうが同じ結論に行き着いたと知っただけ。
青花師団の組織である以上、その題目としての自由は耳にタコができるほど聞かされてきた。
だがそいつをいくら説いたところで、アルテアにあるのは額面通りの自由じゃあない。
定められたランダムさの間にしかない気まぐれに従って決められた通りの動きをする、画面の向こう側から出てこないプログラムの猫みてえな自由。
何せテイマーの養成施設。将来的に他の勢力の連中とどうしたってぶつかることが約束されている場所に字面通りの自由なんかないってのは、大して考えなくたって知れている。
ただ俺たちの疑いはそれよりも少し違うところにあった。
空っぽのベッドを連日囲んで、残った連中で話していたのを覚えている。
手を出しちゃならないモンに手を出した。別勢力の連中と通じた。『航空者』に連れ去られて体を弄られた。流石にそりゃねえって。いや、どうだろ。
無断外出の懲罰にしたって謹慎一か月は長すぎた。最初は真っ青になって心配するばかりだったガキどもも、次第にその不安をどうにかしたくて必死に理由を考え出す。
つまり格好の噂の的だった。その理由がどんなに切羽詰まっていても、いや切羽詰まっているからこそ話は留まるところを知らないし、憶測でしかないはずのことが事実みたいに広まっていくのにも時間はかからない。
それも戻ってこないのは同室の奴だけじゃなかったから、どうせ学校中で似たような話はされていたんだろう。
そこそこ真実味のあるものから荒唐無稽なものまで話は様々あって、だがいざ帰ってきた連中はそのどれにも答えなかった。
ただ元と変わらずに、謹慎も何もなかったように過ごしていただけだ。
腹の底に収められない何かを押し込めたようなひきつった笑いを、真っ青な顔に浮かべながら。
何があったか知らないが、あんなのが長く続く訳もない。
その思いが裏切られなかったと確信したのは、耐え切れなくなった奴がようやっと口を割った時だ。
絶対外へ聞こえないようにしろと何度も念を押すそいつのベッドへ全員分の掛布団を持ち寄って、その中にガキとはいえぎゅうぎゅうに男が詰まるモンだから狭くてしょうがない。
だが顔を寄せ合って話を聞いているうちに、そんなことさえ忘れるようだった。
「おれ、……船外出たんだ。第五教練棟の非常口、錠の電気時々落ちてるだろ。あそこから。非常ボートあるし」
「それは聞いてる。元々無断外出がどうって話だったもんな」
「よっぽどやべえとこでも――」
「違う!!」
「そ、そりゃ、行こうとしてたトコはあったんだ。
だけど皆でぎゃあぎゃあやってるうちに、今どこにいるのかわかんなくなっちゃって。
それで、その、そのときにさ……」
「絡まれたんだ、……気違いみたいな変な女に」
◆11回更新の日記ログ
「目ェつぶって飲んだらぜんぜん普通のクリーチャーじゃん」
「匂いだけはなんかめちゃくちゃっつーか、何味だかわかんねーけど」
「めっちゃ甘ったるい匂いしない? グレープが一番強いんじゃね?」
普段なら俺だって周りから聞こえる声と同じように、目の前のコップに注がれていたクリーチャーを喜んで飲んだだろう。
その色がバケツの中でも覗いているかのようにどす黒く濁っていなければ。
コモン・テイル・ストアを傘下に収め物資不足とは無縁の真紅連理、資金源のルートの多い翡翠経典、それに比べれば青花師団は資金や物資調達力に波があるとはよく言われる話で、その下で創設されたアルテアも例に漏れない。
食堂のコーンミールさえ濃くなるのは週一で、普段は倍ほどに伸ばした薄いコーンミールに今でも何だったのか分からない白い粉をどさどさと注ぎ、薬臭いそれで錠剤栄養を流し込むのが普通だった。
そんな中で嗜好品類として数少ない支給を受けていたのがこのエナジードリンクで、種類すら選べないそれの味を巡って支給日になれば喧嘩が始まるのは日常茶飯事。
オレンジ、グレープ、シトラス、それぞれが何なのかも知らず、せいぜい色の名前だとしか思っていないことは全員が知っているのに。
その真っ只中にどうやってか両手に提げた袋いっぱいの缶を持ち込んだ奴がいたもんだからガキの俺たちはそりゃもうお祭り騒ぎで、その騒ぎが行くトコまで行った時だった。
あのバカの極みみたいな真っ黒いクリーチャーを見たのは。
飲んでも飲んでもなくならない夢みたいな量のドリンクを前にした上しこたま飲んで、多分全員まともじゃなかったんだろう。
『これ全部混ぜてみねえ?』なんてバカの提案を誰が言い出したんだかはもうとっくに覚えていない。
記憶にあるのはコーヒーとも違うオイル汚染水みたいな色をした、やたらに甘ったるい匂いがする泡立つ液体を目の前にして動けなかった俺と、それの入ったコップをひょいと脇から取っていく腕、大して考えもせずそいつに向けて振るった拳の感触と、結局その俺の分の黒いクリーチャーは床が全部飲んだことくらいだ。
そうしてそれもすべて、
翡翠工廠の静養カプセルの中で見た夢に見た、とっくに記憶の底に沈んでいたものに過ぎない。
目が覚めた頃にはいつも通りカプセルの液体はすっかり抜けていて、濡れた身体がひどく肌寒かった。
普段と同じく数度むせるようにして肺までを満たしていた呼吸液を吐き出し、体を外での呼吸に慣らしていく。
脱衣所の鏡に映る身体のそこかしこに走る縫合痕は多少薄くなった気もするが、素人目でさえ分かる雑さはさっぱり直りやしない。
あの頃と変わらないのはその程度で、今じゃそれ以外のすべては違う。
背丈は頭いくつで数えるのもまだるっこしいほど伸びた。横幅だって似たようなものだ。
自分のグレムリンだって持っていて、腹一杯食うには困らない。
そうして自分のクレジットで自販機のクリーチャーを買うことだって。
あの大量の缶ジュースを全部混ぜようなんて言い出したのが誰かは覚えちゃいないが、誰があれを持ち込んだのかははっきり覚えている。
あの頃操縦訓練が一番上手かった奴。実戦へ行ったんだぜ、と誇らしげに語っていた姿。
訓練に打ち込んでグレムリンが動かせれば夢が叶う、俺たち全員にそう教え込んだのは間違いなくあの日、浴びるように飲んだクリーチャーの味で。
押したボタンはグレープ味、同時にゴトンと落下音。
缶を開ければ嗅ぎ慣れた甘ったるい匂いが鼻をつき、口をつければ強炭酸とカフェインが眠気の残滓を払っていく。
そうして考えてなお分からない。
あの真っ黒なクリーチャーを飲んだくれてゲラゲラ笑っていた連中の大半が、今どこでどうしているのかは。
「匂いだけはなんかめちゃくちゃっつーか、何味だかわかんねーけど」
「めっちゃ甘ったるい匂いしない? グレープが一番強いんじゃね?」
普段なら俺だって周りから聞こえる声と同じように、目の前のコップに注がれていたクリーチャーを喜んで飲んだだろう。
その色がバケツの中でも覗いているかのようにどす黒く濁っていなければ。
コモン・テイル・ストアを傘下に収め物資不足とは無縁の真紅連理、資金源のルートの多い翡翠経典、それに比べれば青花師団は資金や物資調達力に波があるとはよく言われる話で、その下で創設されたアルテアも例に漏れない。
食堂のコーンミールさえ濃くなるのは週一で、普段は倍ほどに伸ばした薄いコーンミールに今でも何だったのか分からない白い粉をどさどさと注ぎ、薬臭いそれで錠剤栄養を流し込むのが普通だった。
そんな中で嗜好品類として数少ない支給を受けていたのがこのエナジードリンクで、種類すら選べないそれの味を巡って支給日になれば喧嘩が始まるのは日常茶飯事。
オレンジ、グレープ、シトラス、それぞれが何なのかも知らず、せいぜい色の名前だとしか思っていないことは全員が知っているのに。
その真っ只中にどうやってか両手に提げた袋いっぱいの缶を持ち込んだ奴がいたもんだからガキの俺たちはそりゃもうお祭り騒ぎで、その騒ぎが行くトコまで行った時だった。
あのバカの極みみたいな真っ黒いクリーチャーを見たのは。
飲んでも飲んでもなくならない夢みたいな量のドリンクを前にした上しこたま飲んで、多分全員まともじゃなかったんだろう。
『これ全部混ぜてみねえ?』なんてバカの提案を誰が言い出したんだかはもうとっくに覚えていない。
記憶にあるのはコーヒーとも違うオイル汚染水みたいな色をした、やたらに甘ったるい匂いがする泡立つ液体を目の前にして動けなかった俺と、それの入ったコップをひょいと脇から取っていく腕、大して考えもせずそいつに向けて振るった拳の感触と、結局その俺の分の黒いクリーチャーは床が全部飲んだことくらいだ。
そうしてそれもすべて、
翡翠工廠の静養カプセルの中で見た夢に見た、とっくに記憶の底に沈んでいたものに過ぎない。
目が覚めた頃にはいつも通りカプセルの液体はすっかり抜けていて、濡れた身体がひどく肌寒かった。
普段と同じく数度むせるようにして肺までを満たしていた呼吸液を吐き出し、体を外での呼吸に慣らしていく。
脱衣所の鏡に映る身体のそこかしこに走る縫合痕は多少薄くなった気もするが、素人目でさえ分かる雑さはさっぱり直りやしない。
あの頃と変わらないのはその程度で、今じゃそれ以外のすべては違う。
背丈は頭いくつで数えるのもまだるっこしいほど伸びた。横幅だって似たようなものだ。
自分のグレムリンだって持っていて、腹一杯食うには困らない。
そうして自分のクレジットで自販機のクリーチャーを買うことだって。
あの大量の缶ジュースを全部混ぜようなんて言い出したのが誰かは覚えちゃいないが、誰があれを持ち込んだのかははっきり覚えている。
あの頃操縦訓練が一番上手かった奴。実戦へ行ったんだぜ、と誇らしげに語っていた姿。
訓練に打ち込んでグレムリンが動かせれば夢が叶う、俺たち全員にそう教え込んだのは間違いなくあの日、浴びるように飲んだクリーチャーの味で。
押したボタンはグレープ味、同時にゴトンと落下音。
缶を開ければ嗅ぎ慣れた甘ったるい匂いが鼻をつき、口をつければ強炭酸とカフェインが眠気の残滓を払っていく。
そうして考えてなお分からない。
あの真っ黒なクリーチャーを飲んだくれてゲラゲラ笑っていた連中の大半が、今どこでどうしているのかは。
◆10回更新の日記ログ
『もしも君たちが棺の外で死ぬようなことがあれば、グレムリンはどうなると思う』
教官がいつか聞いたことへ、返すべき模範的な答えは一つだった。
『テイマー登録をフォーマットされ、後輩たちの乗機になります』
いくら生体認証とテイマー登録番号が機械と人を紐づけても、どちらかが没すればそれを呼び戻す手段はない。
そうすればテイマーは新たな機体を求め、グレムリンは初期化された上で新たな乗り手のところへ旅立つ。
グレムリン・フレームへ接続するパーツを交換できるように、テイマーとグレムリンもまた交換可能な『グレムリン』という兵器を構成するための一パーツにすぎない。
授業はそう結ばれたことを覚えている。けど誰だって大して信じちゃいなかった。
きっとアルテアの連中は、俺たちが自分のグレムリンに愛着を持つのに良い気がしていなかったんだろう。
識別名は要るがテイマー自身に付けさせはしなかったのも、きっと。
愛機がもし何らかの理由でテイマーを置いて墜ちたとして、その死を悼むよりも先にテイマーにはすべきことがある。
新たな乗機を見つけることだ。それも可能な限り速やかに。
専門訓練を受けたテイマーはグレムリンがない限りただの人にすぎない。
それも操縦棺の中以外のどこにも生きることのできない、腹の中のガキみたいな生き物だから。
だが命を預けるものへ、
それも自分の体格、指向、クセ、その一つ一つに合わせてカスタムするものに愛着を持つなって方が無茶だ。
よっぽどの冷血野郎じゃない限り誰だって、テイマーはグレムリンへ特別な何かを持っている。
いくら外からそれを遮られたって、内から生えてくるものを止められるはずもない。
今になって思い知るそれはどうしようもなく真実だ。
今も青花工廠のハンガーに屍として押し黙る『サーシオネ』、もう「かつての」と言い切るほかない乗機をまだふと思うことも、
あの今まで見てきたどこよりも色濃い死と、それまで『サーシオネ』と飛んだ空を「ふと」と言うしか思い出せなくなっていくことも、
音もなく遠ざかっていくそれが時折無性にから恐ろしくなることも、
今乗る『フォールスビーク』、ただ動かせたから動かしたというだけの、『サーシオネ』へよく似たそれへ緩やかに傾いでいく心も、
テイマーとグレムリンはどれだけ愛着があろうと替えることができ、その事態に際して愛着とは障害にしかならない、その揺るぎない証明に他ならない。
あの高高度全翼機の主へ答えたテイマーのように、迷いもなくグレムリンを相棒だと言い切れたらどんなに良かったか。
殴りつけたコンソールはただめちゃくちゃに押されたボタンの組み合わせだけを認識して、無機質なビーブ音を返した。
教官がいつか聞いたことへ、返すべき模範的な答えは一つだった。
『テイマー登録をフォーマットされ、後輩たちの乗機になります』
いくら生体認証とテイマー登録番号が機械と人を紐づけても、どちらかが没すればそれを呼び戻す手段はない。
そうすればテイマーは新たな機体を求め、グレムリンは初期化された上で新たな乗り手のところへ旅立つ。
グレムリン・フレームへ接続するパーツを交換できるように、テイマーとグレムリンもまた交換可能な『グレムリン』という兵器を構成するための一パーツにすぎない。
授業はそう結ばれたことを覚えている。けど誰だって大して信じちゃいなかった。
きっとアルテアの連中は、俺たちが自分のグレムリンに愛着を持つのに良い気がしていなかったんだろう。
識別名は要るがテイマー自身に付けさせはしなかったのも、きっと。
愛機がもし何らかの理由でテイマーを置いて墜ちたとして、その死を悼むよりも先にテイマーにはすべきことがある。
新たな乗機を見つけることだ。それも可能な限り速やかに。
専門訓練を受けたテイマーはグレムリンがない限りただの人にすぎない。
それも操縦棺の中以外のどこにも生きることのできない、腹の中のガキみたいな生き物だから。
だが命を預けるものへ、
それも自分の体格、指向、クセ、その一つ一つに合わせてカスタムするものに愛着を持つなって方が無茶だ。
よっぽどの冷血野郎じゃない限り誰だって、テイマーはグレムリンへ特別な何かを持っている。
いくら外からそれを遮られたって、内から生えてくるものを止められるはずもない。
今になって思い知るそれはどうしようもなく真実だ。
今も青花工廠のハンガーに屍として押し黙る『サーシオネ』、もう「かつての」と言い切るほかない乗機をまだふと思うことも、
あの今まで見てきたどこよりも色濃い死と、それまで『サーシオネ』と飛んだ空を「ふと」と言うしか思い出せなくなっていくことも、
音もなく遠ざかっていくそれが時折無性にから恐ろしくなることも、
今乗る『フォールスビーク』、ただ動かせたから動かしたというだけの、『サーシオネ』へよく似たそれへ緩やかに傾いでいく心も、
テイマーとグレムリンはどれだけ愛着があろうと替えることができ、その事態に際して愛着とは障害にしかならない、その揺るぎない証明に他ならない。
あの高高度全翼機の主へ答えたテイマーのように、迷いもなくグレムリンを相棒だと言い切れたらどんなに良かったか。
殴りつけたコンソールはただめちゃくちゃに押されたボタンの組み合わせだけを認識して、無機質なビーブ音を返した。
◆9回更新の日記ログ
操縦棺の中でもとりわけ己一つを守ることに特化し、そこからの思念で希望の通りに外界を歪める。小世界の中心――セントラルの中で、広域レーダーの拾う機影を絶え間なく追う。
すっかりモニタを埋め尽くしていた影は戦線が火蓋を切ると同時にいくつか減り、残りは点滅するように消えては捉え直されることを繰り返す。
敵機のうちの半数を占める、あの倒せば倒すだけ起き上がってくる『世界の不具合』。
来るな。
消えろ。
いなくなれ。
怖気はそのまま破壊の思念に転化して、グレムリンのフレームを伝って全身を満たしてゆく。
一分と経たずに加圧十分のサインを出した大型思念増幅機構から迸った、文字通り光の速さで駆けるはずの一矢が見知らぬ大型機のすれすれを抜ける。
だが場所は掴んだ。それで十分。そのままに右トリガー。
粒子銃から迸る光の雨が視界を埋め尽くし逃亡を許さずに装甲を削り、やがてその最奥へ達する。
それだけは既知機と同じように煙や破砕音を上げ、重力に引かれて海面へ向かうそれの末路は見ない。
・・・
まともに落ちるものを落としきったら、後はそうでないものが残るだけだ。
もはや帯に近いほどに収束させた粒子線の中を、煙と破砕音を立てながら近づいてくるものたち。
最大加圧からそれを消し飛ばす極大の光は心から出でる拒絶そのもので、普通なら装甲一片さえ残らないその中からさえ駆動音は絶えずに。
スクラップから戻って来る度にご丁寧に内部兵装まできっちり再生されるらしいそれが立てるジャミング煙がカメラの前を遮り、鳴り響くのは動作停滞アラート。それを無視して引きっぱなしのトリガーへなお力を込める。
機体を満たしてなおあり余るほどの増幅思念と付属する小型EN供給器は、粒子銃をほとんど自動兵器に変えている。
そのまま目を向けるのはモニタ上の電子時計。どこの戦闘記録でも、これだけの攻撃を受けて12分以上を耐えた機体はいなかった。
時刻は02:03。
それを視認すると同時、まだ消えるはずのない反応がひとつ、ふつりと消えた。
02:11。違えるはずのない予測よりも、交戦終了は2分早かった。
絶句したように応答のない真紅の友軍どもに適当に声をかける。答えを待たずにまだ遠いヒルコ・トリフネ船団への自動操縦をセットして、操縦棺のシートに身を預けて目を伏せる。
まだ眼球の奥底で、どくどくと痛みが熱く脈を打っていた。第四種制御識適正はあったはずとはいえ、流石にこれほど振り回すことまでは支えきれないらしい。
それか旗艦に寄った時に静養カプセルの一つでも借りるべきだったか。
揺れる船団のベッドだろうが操縦棺だろうが問題なく眠れるようにしておけ、とは散々言われたことだが、カプセルの液体の中で受けた全身処置のあとはとりわけ調子が良かった。
ただこうしてどれほど戦ったところで、そうしている間は死にはしない。少なくともグレムリンから放り出されて傷跡の制御識の増幅が切れるまでは。
逆に言えばはっきりと終わりはそこにある。救助船団すら避けて通る死の空域。絶滅戦場を飛び続ける限り。
元より安全装置すら外したこの機体はその救助の機会さえも与えはしない。ただ砕けた操縦棺から生身で宙に投げ出され、粉塵大気の層をくぐり海面に叩きつけられて、死ぬ。
そうなれば泳げるかどうかに差はない、と言いながらきっちり水泳訓練は課しやがった教官の言葉。それだけを覚えていて、理由がすっぽり抜けている。それで十分だった。
死ぬのが嫌でないかと聞かれればそんなはずはない。
ただ生きるための安全装置のスペースより、そこに積めるパーツを取った。
落ちても生きていける海の上より、一度だって落ちないまま飛び続けることを選んだ。それだけの話だ。
そうじゃなきゃ生きていけるものかと思った。グレムリンという力それ一つで虚空を飛んでいくのなら。
青花の言う心の自由なんざ信じる気はなくとも、青花に与えられた力で掴む俺の手の自由だけは確かに今も俺の触れ続ける本物で。
その手で触れて崩せなかったあの不死身の化け物は、他の何かがそれを崩すとしても俺にはどうしようもなくおぞましくて。
それがさっさと消えてくれたことは、理由はどうあれ喜ぶべきで。
そして随分と、安心することだった。
すっかりモニタを埋め尽くしていた影は戦線が火蓋を切ると同時にいくつか減り、残りは点滅するように消えては捉え直されることを繰り返す。
敵機のうちの半数を占める、あの倒せば倒すだけ起き上がってくる『世界の不具合』。
来るな。
消えろ。
いなくなれ。
怖気はそのまま破壊の思念に転化して、グレムリンのフレームを伝って全身を満たしてゆく。
一分と経たずに加圧十分のサインを出した大型思念増幅機構から迸った、文字通り光の速さで駆けるはずの一矢が見知らぬ大型機のすれすれを抜ける。
だが場所は掴んだ。それで十分。そのままに右トリガー。
粒子銃から迸る光の雨が視界を埋め尽くし逃亡を許さずに装甲を削り、やがてその最奥へ達する。
それだけは既知機と同じように煙や破砕音を上げ、重力に引かれて海面へ向かうそれの末路は見ない。
・・・
まともに落ちるものを落としきったら、後はそうでないものが残るだけだ。
もはや帯に近いほどに収束させた粒子線の中を、煙と破砕音を立てながら近づいてくるものたち。
最大加圧からそれを消し飛ばす極大の光は心から出でる拒絶そのもので、普通なら装甲一片さえ残らないその中からさえ駆動音は絶えずに。
スクラップから戻って来る度にご丁寧に内部兵装まできっちり再生されるらしいそれが立てるジャミング煙がカメラの前を遮り、鳴り響くのは動作停滞アラート。それを無視して引きっぱなしのトリガーへなお力を込める。
機体を満たしてなおあり余るほどの増幅思念と付属する小型EN供給器は、粒子銃をほとんど自動兵器に変えている。
そのまま目を向けるのはモニタ上の電子時計。どこの戦闘記録でも、これだけの攻撃を受けて12分以上を耐えた機体はいなかった。
時刻は02:03。
それを視認すると同時、まだ消えるはずのない反応がひとつ、ふつりと消えた。
02:11。違えるはずのない予測よりも、交戦終了は2分早かった。
絶句したように応答のない真紅の友軍どもに適当に声をかける。答えを待たずにまだ遠いヒルコ・トリフネ船団への自動操縦をセットして、操縦棺のシートに身を預けて目を伏せる。
まだ眼球の奥底で、どくどくと痛みが熱く脈を打っていた。第四種制御識適正はあったはずとはいえ、流石にこれほど振り回すことまでは支えきれないらしい。
それか旗艦に寄った時に静養カプセルの一つでも借りるべきだったか。
揺れる船団のベッドだろうが操縦棺だろうが問題なく眠れるようにしておけ、とは散々言われたことだが、カプセルの液体の中で受けた全身処置のあとはとりわけ調子が良かった。
ただこうしてどれほど戦ったところで、そうしている間は死にはしない。少なくともグレムリンから放り出されて傷跡の制御識の増幅が切れるまでは。
逆に言えばはっきりと終わりはそこにある。救助船団すら避けて通る死の空域。絶滅戦場を飛び続ける限り。
元より安全装置すら外したこの機体はその救助の機会さえも与えはしない。ただ砕けた操縦棺から生身で宙に投げ出され、粉塵大気の層をくぐり海面に叩きつけられて、死ぬ。
そうなれば泳げるかどうかに差はない、と言いながらきっちり水泳訓練は課しやがった教官の言葉。それだけを覚えていて、理由がすっぽり抜けている。それで十分だった。
死ぬのが嫌でないかと聞かれればそんなはずはない。
ただ生きるための安全装置のスペースより、そこに積めるパーツを取った。
落ちても生きていける海の上より、一度だって落ちないまま飛び続けることを選んだ。それだけの話だ。
そうじゃなきゃ生きていけるものかと思った。グレムリンという力それ一つで虚空を飛んでいくのなら。
青花の言う心の自由なんざ信じる気はなくとも、青花に与えられた力で掴む俺の手の自由だけは確かに今も俺の触れ続ける本物で。
その手で触れて崩せなかったあの不死身の化け物は、他の何かがそれを崩すとしても俺にはどうしようもなくおぞましくて。
それがさっさと消えてくれたことは、理由はどうあれ喜ぶべきで。
そして随分と、安心することだった。
◆8回更新の日記ログ
「そうだね、私は……グレイヴキーパー。墓所の護り手。死にゆく世界に手向けた花」
そう告げられて浮かぶのは、元よりくすんだ安物の造花。
あるいはグレムリンのエンブレムに描かれた、決して褪せない図画の花。
「この世界は致命的な不具合を持っている」
知っているさ。
年寄りどもはいつでもこんな世界は間違っていると言う。コーンミールに顔をしかめ、水にコーヒーシロップを流し込みながら。
語るだけの正しさに辿り着けないことなんかとっくに知っているくせに。
目の前にいるのがその間違った世界しか知らない人間だとわかっているくせに。
「次会う時は、今度こそ。
『迷わないでね』」
そんなことを求められるのなら、何も言わずに戦場に放り込んでくれればよかった。
俺に関わる誰もがするのと、この錆びきったグレムリンと俺を引き合わせたその時と同じように。
ただ倒すべき敵だと示されれば、それを鉄屑にすることに何の躊躇もない。
そこに迷いが生まれるとすれば。
鳴り響くアラームに薄ら開いた瞼、ぼやけた視界に映るモニターの空。その赤に奇妙な濃淡がある。
画面さえイカれてきたか、あの機体状態から見れば仕方ねえ、なんて寝惚けた頭で考えたことはまったくの見当違いだと気が付いたのはすぐのこと。
雨音列島に降る粉塵交じりの赤い雨粒は静かに降り続いて、絶え間なくカメラを濡らしていた。
そこへ被るように開いたウインドウがでかでかと映す、音に合わせて点滅する真紅連理のマーク。どうやら呼び出しの主はここらしかった。
通信を繋げる。どうせ顔は出ない設定にしているから、欠伸さえ噛み殺せば問題はない。
「やっと繋がったか。
こちら第28真紅連理テイマー隊隊長、巨大未識別融合体に対する合同作戦に伴う要請に応じ――」
モニターに映る顔そのものに見覚えはなかったが、姿はどうにも既視感まみれだ。
真紅のテイマー、特に下っ端ってのは誰も彼もが揃いのヘルメットに統制スーツで、俺から見れば誰が誰だかもわからない。
義務感たっぷりに読み上げられるお決まりの台詞の隠しもしない苦々しさは、呼び出しておいて散々待たせたのがよっぽど堪えているか、あるいは正規軍にありがちな傭兵嫌いか。
どっちだってよかった。せいぜい、後者ならこんな時にまでよくもまあ、と思うくらいだ。
それでわざわざ戦場でまで纏わりついてくる程度にどうしようもなければ、エレクトロフィールドを手配するくらいはするだろうが。
そう告げられて浮かぶのは、元よりくすんだ安物の造花。
あるいはグレムリンのエンブレムに描かれた、決して褪せない図画の花。
「この世界は致命的な不具合を持っている」
知っているさ。
年寄りどもはいつでもこんな世界は間違っていると言う。コーンミールに顔をしかめ、水にコーヒーシロップを流し込みながら。
語るだけの正しさに辿り着けないことなんかとっくに知っているくせに。
目の前にいるのがその間違った世界しか知らない人間だとわかっているくせに。
「次会う時は、今度こそ。
『迷わないでね』」
そんなことを求められるのなら、何も言わずに戦場に放り込んでくれればよかった。
俺に関わる誰もがするのと、この錆びきったグレムリンと俺を引き合わせたその時と同じように。
ただ倒すべき敵だと示されれば、それを鉄屑にすることに何の躊躇もない。
そこに迷いが生まれるとすれば。
鳴り響くアラームに薄ら開いた瞼、ぼやけた視界に映るモニターの空。その赤に奇妙な濃淡がある。
画面さえイカれてきたか、あの機体状態から見れば仕方ねえ、なんて寝惚けた頭で考えたことはまったくの見当違いだと気が付いたのはすぐのこと。
雨音列島に降る粉塵交じりの赤い雨粒は静かに降り続いて、絶え間なくカメラを濡らしていた。
そこへ被るように開いたウインドウがでかでかと映す、音に合わせて点滅する真紅連理のマーク。どうやら呼び出しの主はここらしかった。
通信を繋げる。どうせ顔は出ない設定にしているから、欠伸さえ噛み殺せば問題はない。
「やっと繋がったか。
こちら第28真紅連理テイマー隊隊長、巨大未識別融合体に対する合同作戦に伴う要請に応じ――」
モニターに映る顔そのものに見覚えはなかったが、姿はどうにも既視感まみれだ。
真紅のテイマー、特に下っ端ってのは誰も彼もが揃いのヘルメットに統制スーツで、俺から見れば誰が誰だかもわからない。
義務感たっぷりに読み上げられるお決まりの台詞の隠しもしない苦々しさは、呼び出しておいて散々待たせたのがよっぽど堪えているか、あるいは正規軍にありがちな傭兵嫌いか。
どっちだってよかった。せいぜい、後者ならこんな時にまでよくもまあ、と思うくらいだ。
それでわざわざ戦場でまで纏わりついてくる程度にどうしようもなければ、エレクトロフィールドを手配するくらいはするだろうが。
◆7回更新の日記ログ
壁一枚隔てた向こうから聞こえるのは走り回る軽い足音と高い声。
青花旗艦船団、それも工廠船でこんな声がするなんて昨日までは考えられなかった話だ。
避難民をグレムリン取扱区域、機密区画のこれほど近くまで受け入れなければならないほどに、船そのものが足りていない。
「何隻落ちたって?」
「2割。これでも少ない方だ。工廠船と倉庫船、それとお偉方のは守り切ってるよ」
そう返すエンジニアの手にあるIDカードが行く手の扉を開く。
作業用の軽装動作スーツが幾人も慌ただしく行き交うハンガーは見慣れた光景で、これが普通だ。「アネモネ」で見たあの死んだ工廠が異常なだけ。
脳裏によぎるあの荒廃を思い出す間もなく、作業スーツのうちのひとりがずんずんとこちらへ近づいてくる。
誰だったかと思い出すよりも、向こうが口火を切る方が早い。
「小僧。てめえ何しやがった、あの主兵装入れたばっかだっつってたな」
「何もしてねえ。墜とすまで撃ったんだよ」
「それだけでああなるだと? そんなバケモンがいたらお目にかかってみたいもんだ。
新品の武装が一戦交えただけで耐用限界超えなんざ聞いたこともねえ。それか不良品掴まされたか」
「ああ? 戦闘記録も見てねえで言うか? そのバケモンとやった貴重極まりねえ映像だぞ」
言い返したのはほとんど反射的だ。
こいつの口ぶりが気に食わないのもあれ、今も記憶に生々しいあの戦闘は、俺の踏んだ場数の中でもとりわけ異様で。
それを奴らのせいじゃなく俺やグレムリンのせいにされることは見当違いも見当違い。
そしてあの戦いの間ずっとついて回った不気味さを、いま一度呼び起こされたから。
叩き潰してなお、不可視の手で握り潰されてなお、操縦エミュレータのターゲットじみて元の形を取り戻す。それでいて幾度繰り返してもその機能を失わずに、寸分違わず撃ち返してくる。
間違いなく鋼でできた本物の機体が、捉えられる思念がそこにありながら、いくら払ってもなくならない。
鉄屑に成り果てるのを拒むような、受け入れがたい事実を受け取らずにあるような機体。
未識別機動体。その異常性の粋。
消えるはずが消えずにある『世界の不具合』。
あれはまさしく、そういうものだった。
青花旗艦船団、それも工廠船でこんな声がするなんて昨日までは考えられなかった話だ。
避難民をグレムリン取扱区域、機密区画のこれほど近くまで受け入れなければならないほどに、船そのものが足りていない。
「何隻落ちたって?」
「2割。これでも少ない方だ。工廠船と倉庫船、それとお偉方のは守り切ってるよ」
そう返すエンジニアの手にあるIDカードが行く手の扉を開く。
作業用の軽装動作スーツが幾人も慌ただしく行き交うハンガーは見慣れた光景で、これが普通だ。「アネモネ」で見たあの死んだ工廠が異常なだけ。
脳裏によぎるあの荒廃を思い出す間もなく、作業スーツのうちのひとりがずんずんとこちらへ近づいてくる。
誰だったかと思い出すよりも、向こうが口火を切る方が早い。
「小僧。てめえ何しやがった、あの主兵装入れたばっかだっつってたな」
「何もしてねえ。墜とすまで撃ったんだよ」
「それだけでああなるだと? そんなバケモンがいたらお目にかかってみたいもんだ。
新品の武装が一戦交えただけで耐用限界超えなんざ聞いたこともねえ。それか不良品掴まされたか」
「ああ? 戦闘記録も見てねえで言うか? そのバケモンとやった貴重極まりねえ映像だぞ」
言い返したのはほとんど反射的だ。
こいつの口ぶりが気に食わないのもあれ、今も記憶に生々しいあの戦闘は、俺の踏んだ場数の中でもとりわけ異様で。
それを奴らのせいじゃなく俺やグレムリンのせいにされることは見当違いも見当違い。
そしてあの戦いの間ずっとついて回った不気味さを、いま一度呼び起こされたから。
叩き潰してなお、不可視の手で握り潰されてなお、操縦エミュレータのターゲットじみて元の形を取り戻す。それでいて幾度繰り返してもその機能を失わずに、寸分違わず撃ち返してくる。
間違いなく鋼でできた本物の機体が、捉えられる思念がそこにありながら、いくら払ってもなくならない。
鉄屑に成り果てるのを拒むような、受け入れがたい事実を受け取らずにあるような機体。
未識別機動体。その異常性の粋。
消えるはずが消えずにある『世界の不具合』。
あれはまさしく、そういうものだった。
◆6回更新の日記ログ
いつの間にか音もなく棺の中へ入り込んだ寒気が、光の河の夢から俺を引きずり出した。握ったレバーは鋼の冷たさのまま、そのくせ触れるだけで焼け付くように痛む。
理屈は忘れたが、グレムリンの飛ぶ空はどうしたって地表より寒い。だからこそ棺内に防寒設備は整えてある、はずなんだが。
暖房関連のチェックが必要だ。そのつもりで眼下の青花旗艦を見下ろす。こんなところに停泊してやがるんだからできねえとは言わせない。
そう心を決めたところで赤い空を見上げても、光の奔流はない。
グレムリンの放射光やプラズマの輝きでも、ましてや電源系の明かりとも違うあの現実離れした光。
うっかり、天国なんぞ今時俺より下のガキでも信じない話をちょっとは信じる気になりそうな。
だが夢の続きとかいうものは、少なくともこの辺りにはないようだった。
あれが本当だってんなら、戦闘地点はここよりずっと西のはずだ。だから真面目にあの蛙のエンブレムの機体を探そうって気にはさっぱりならなかった。
『天国か! 文献にもそれらしいものはあるな。
だが役には立たねぇ!
どこからが歴史で、どこからが物語なのか、分からねぇからな!』
代わりに耳に入るのはどうやって生きてるんだか生身で釣り糸垂らしたオッサンの話で、その異様さに反して中身は随分真っ当だ。
どこからが歴史でどこからが物語なのか。それが文章として残ったものでも、誰かの口から聞くものでも、結局のところ聞く側にはさして区別もつかない。
それが目の前にあるものとかけ離れている限り。
青い空。注ぐ光。泳ぐという雲。冠された花。生身で外にいる人間。
いくら現実にあったものとして聞かされようが、結局それはお伽噺に違いなかった。
理屈は忘れたが、グレムリンの飛ぶ空はどうしたって地表より寒い。だからこそ棺内に防寒設備は整えてある、はずなんだが。
暖房関連のチェックが必要だ。そのつもりで眼下の青花旗艦を見下ろす。こんなところに停泊してやがるんだからできねえとは言わせない。
そう心を決めたところで赤い空を見上げても、光の奔流はない。
グレムリンの放射光やプラズマの輝きでも、ましてや電源系の明かりとも違うあの現実離れした光。
うっかり、天国なんぞ今時俺より下のガキでも信じない話をちょっとは信じる気になりそうな。
だが夢の続きとかいうものは、少なくともこの辺りにはないようだった。
あれが本当だってんなら、戦闘地点はここよりずっと西のはずだ。だから真面目にあの蛙のエンブレムの機体を探そうって気にはさっぱりならなかった。
『天国か! 文献にもそれらしいものはあるな。
だが役には立たねぇ!
どこからが歴史で、どこからが物語なのか、分からねぇからな!』
代わりに耳に入るのはどうやって生きてるんだか生身で釣り糸垂らしたオッサンの話で、その異様さに反して中身は随分真っ当だ。
どこからが歴史でどこからが物語なのか。それが文章として残ったものでも、誰かの口から聞くものでも、結局のところ聞く側にはさして区別もつかない。
それが目の前にあるものとかけ離れている限り。
青い空。注ぐ光。泳ぐという雲。冠された花。生身で外にいる人間。
いくら現実にあったものとして聞かされようが、結局それはお伽噺に違いなかった。
◆5回更新の日記ログ
年寄りどもが昔語りしかしないのは今に始まったことじゃない。
ここ数時間通信を送ってくるテイマーどもも、あのリザレクションとかいうグレムリンに乗ってた奴もそうだ。
どれを聞く必要がある。
俺が生きなきゃいけないのはいつだって今で、二度と戻ってきそうにない時間に引きずられた連中に巻き込まれている暇はない。
フリーランサーの連中が置いていった肉の缶詰をレンチで叩き割って中身にありつく。
強い塩気のある液体がどろりと絡んだ合成肉ブロックは、今この状況で食えるものとしては上の上。
あいつらはこれも常通り、ぐだぐだと文句を垂れながら食べるんだろう。
いざ奪われようとなったら全力で守り通すくせに。
ここ数時間通信を送ってくるテイマーどもも、あのリザレクションとかいうグレムリンに乗ってた奴もそうだ。
どれを聞く必要がある。
俺が生きなきゃいけないのはいつだって今で、二度と戻ってきそうにない時間に引きずられた連中に巻き込まれている暇はない。
フリーランサーの連中が置いていった肉の缶詰をレンチで叩き割って中身にありつく。
強い塩気のある液体がどろりと絡んだ合成肉ブロックは、今この状況で食えるものとしては上の上。
あいつらはこれも常通り、ぐだぐだと文句を垂れながら食べるんだろう。
いざ奪われようとなったら全力で守り通すくせに。
◆4回更新の日記ログ
乗り込んだ操縦棺。握ったレバー。押された起動スイッチ。生体情報。入力したライセンス。
どれも『サーシオネ』を呼び起こすには至らなかった。
つい昨日までともに飛んでいたはずの機体がただ鉄の塊になって押し黙っている。
死体のように。
酷く淀んだ空気の中に、ぱらぱらと疲れ切った面の行き交う青花工廠。
見ない顔は大半がこの16時間の間に死んだか行方知れずだという。
工廠ハンガーにずらりと並ぶ青花のグレムリンの中に、一台たりとも動いたものはないらしい。
テイマーが死んだグレムリンが呆然と床を見下ろし、
グレムリンが死んだテイマーが空を奪われて鼠のように地を歩き回っている。
それが今の工廠だった。
そこに現れた動くグレムリンとそのテイマーなんぞ、素直に歓迎できなくて当たり前。むしろ換装ができるだけ余裕のある方か。
身内に刺されることにゃ警戒しろとは言われてきたが、流石にこんな無茶苦茶な事態を想定できるほどじゃない。
「………じゃあ、時間があったら通信して。でも、生き残ることを第一にね」
着いたら話そうという約束なんざそんな状態の前じゃあっという間に反故だ。
それをそう責めることもないのは、向こうでも薄々予想はついていたんだろう。もちろんラトーが元々そういう奴なのもあれ。
おう、と短く返事だけ返して、『フォールスビーク』のエンジンを始動する。棺内モニタの出力メーターは滑らかに動いて発進可能アラートを鳴らす。
いくら睨み合っても『サーシオネ』が到達しなかった段階へ。
加速と強烈なGが強く身体をシートへ押し付ける。握り込んだ手が不意に放されるように、音もなくそれから解放される。
ただいつまでも消えずに纏わりついている。
あの場にあった、これまでに見てきた何よりも強い死の気配が。
どれも『サーシオネ』を呼び起こすには至らなかった。
つい昨日までともに飛んでいたはずの機体がただ鉄の塊になって押し黙っている。
死体のように。
酷く淀んだ空気の中に、ぱらぱらと疲れ切った面の行き交う青花工廠。
見ない顔は大半がこの16時間の間に死んだか行方知れずだという。
工廠ハンガーにずらりと並ぶ青花のグレムリンの中に、一台たりとも動いたものはないらしい。
テイマーが死んだグレムリンが呆然と床を見下ろし、
グレムリンが死んだテイマーが空を奪われて鼠のように地を歩き回っている。
それが今の工廠だった。
そこに現れた動くグレムリンとそのテイマーなんぞ、素直に歓迎できなくて当たり前。むしろ換装ができるだけ余裕のある方か。
身内に刺されることにゃ警戒しろとは言われてきたが、流石にこんな無茶苦茶な事態を想定できるほどじゃない。
「………じゃあ、時間があったら通信して。でも、生き残ることを第一にね」
着いたら話そうという約束なんざそんな状態の前じゃあっという間に反故だ。
それをそう責めることもないのは、向こうでも薄々予想はついていたんだろう。もちろんラトーが元々そういう奴なのもあれ。
おう、と短く返事だけ返して、『フォールスビーク』のエンジンを始動する。棺内モニタの出力メーターは滑らかに動いて発進可能アラートを鳴らす。
いくら睨み合っても『サーシオネ』が到達しなかった段階へ。
加速と強烈なGが強く身体をシートへ押し付ける。握り込んだ手が不意に放されるように、音もなくそれから解放される。
ただいつまでも消えずに纏わりついている。
あの場にあった、これまでに見てきた何よりも強い死の気配が。
◆3回更新の日記ログ
最初の一手で小兵を撃墜。その撃墜から起きる思念を丹念に追う。それがぶつかって揺れたところを目掛けて跳躍。
得手通りの電撃戦が敵陣を殲滅するまでに10分。
『サーシオネ』に乗るのとそう変わらない。逆関節機なら調整次第で近づくはずだとは思ったが、ここまでとは思わなかった。
デジタル表示の時計へ目を向けながら、つくづく長ったらしかった二時間前を思い起こす。
この方がずっと俺の好みだ。
とはいえ、こうして早期にカタをつけて飛び続けてもペンギン諸島到達まではそれなりにかかる。
敵影捕捉を10分おきに3回。そのどれにも何の影も映らないのを確認して、操縦をオートパイロットへ。
この間にやるべきことをやってしまうべきだ。
機体内のデータログを見ての出所解析。それに何より、セキュリティシステムを使った専用機体化――可能なら生体認証とテイマーズ・ケイジ登録番号による二重認証で。
結論から言えば見つかったのはジャンクデータの山、山、山。
まともに運用されていたなら当然あるはずのケイジ登録番号だの、テイマー登録名だのは何一つ見つからない。
未使用品、それか登録逃れのヤミ品か?
そう考えればこの機体状況も通るが、そんなモンを全くの部外者に見つかるような場所に置くものか。
ただ、どんな機体だろうがあるだけでできることは格段に増える――というより、グレムリンのないテイマーほど無力なモンもない。
テイマーを殺すには下りたところを狙うのが定石だ。グレムリンのない人間でも簡単にできる、テイマーにある程度の護身が必要になる理由。
何があろうと手放すわけにもいかない。少なくとも『サーシオネ』がまた飛べるようになるまでは。
提示するのは声紋と虹彩。それとともに、とっくに暗記済みのテイマー登録番号を棺内のタッチパネルへ打ち込む。
誰のことも知らなかったグレムリンはこれで俺のものになった。
こんなことになる前から、動くグレムリンが欲しい連中なんていない方がおかしかった。今なら猶更だ。
人の多い青花工廠へ行けば引く手も数多だろう。その前に捕まえておく必要がある。
青花工廠の連中が手を出そうが、最悪俺がどうにかなろうが、手放せやしない。
ただ、名乗るべき名前も示すものもないのは単純に不便だった。
せめて機体名だけでも、と考えても、さして名前なんてつけたこともない。つける先がないんだから。
『サーシオネ』も俺が付けた名前じゃない。アルテアのグレムリンは、皆名付けられてから俺たちの元へ来る。
そうして悩むのも得意じゃない。悩んで迷っているうちにテイマーは死ぬ。
思い浮かべるのはさっきの10分。その間の動き。
そこに見えるのは墜下する長嘴。
フォールスビーク。
これで十分だ。
時間はまだまだ余っていたからヘタクソなエンブレムを書き足して、一応の体裁を整える。
……これでもし、工廠の『サーシオネ』がけろっと息を吹き返していたら?
それが一番いい。これが全部徒労に終わってくれる方が、よほど。
「こちら『フォールスビーク』、そういうことになった――」
得手通りの電撃戦が敵陣を殲滅するまでに10分。
『サーシオネ』に乗るのとそう変わらない。逆関節機なら調整次第で近づくはずだとは思ったが、ここまでとは思わなかった。
デジタル表示の時計へ目を向けながら、つくづく長ったらしかった二時間前を思い起こす。
この方がずっと俺の好みだ。
とはいえ、こうして早期にカタをつけて飛び続けてもペンギン諸島到達まではそれなりにかかる。
敵影捕捉を10分おきに3回。そのどれにも何の影も映らないのを確認して、操縦をオートパイロットへ。
この間にやるべきことをやってしまうべきだ。
機体内のデータログを見ての出所解析。それに何より、セキュリティシステムを使った専用機体化――可能なら生体認証とテイマーズ・ケイジ登録番号による二重認証で。
結論から言えば見つかったのはジャンクデータの山、山、山。
まともに運用されていたなら当然あるはずのケイジ登録番号だの、テイマー登録名だのは何一つ見つからない。
未使用品、それか登録逃れのヤミ品か?
そう考えればこの機体状況も通るが、そんなモンを全くの部外者に見つかるような場所に置くものか。
ただ、どんな機体だろうがあるだけでできることは格段に増える――というより、グレムリンのないテイマーほど無力なモンもない。
テイマーを殺すには下りたところを狙うのが定石だ。グレムリンのない人間でも簡単にできる、テイマーにある程度の護身が必要になる理由。
何があろうと手放すわけにもいかない。少なくとも『サーシオネ』がまた飛べるようになるまでは。
提示するのは声紋と虹彩。それとともに、とっくに暗記済みのテイマー登録番号を棺内のタッチパネルへ打ち込む。
誰のことも知らなかったグレムリンはこれで俺のものになった。
こんなことになる前から、動くグレムリンが欲しい連中なんていない方がおかしかった。今なら猶更だ。
人の多い青花工廠へ行けば引く手も数多だろう。その前に捕まえておく必要がある。
青花工廠の連中が手を出そうが、最悪俺がどうにかなろうが、手放せやしない。
ただ、名乗るべき名前も示すものもないのは単純に不便だった。
せめて機体名だけでも、と考えても、さして名前なんてつけたこともない。つける先がないんだから。
『サーシオネ』も俺が付けた名前じゃない。アルテアのグレムリンは、皆名付けられてから俺たちの元へ来る。
そうして悩むのも得意じゃない。悩んで迷っているうちにテイマーは死ぬ。
思い浮かべるのはさっきの10分。その間の動き。
そこに見えるのは墜下する長嘴。
フォールスビーク。
これで十分だ。
時間はまだまだ余っていたからヘタクソなエンブレムを書き足して、一応の体裁を整える。
……これでもし、工廠の『サーシオネ』がけろっと息を吹き返していたら?
それが一番いい。これが全部徒労に終わってくれる方が、よほど。
「こちら『フォールスビーク』、そういうことになった――」
◆2回更新の日記ログ
引いてなお無反応のトリガー、一向に粒子が噴き出す様子もない柄だけのブレード。
気づいた瞬間は血の気が引き配した指が震えて感覚がなくなるほどだったそれらも、ひとまず生き延びられないほどの障害じゃあないらしい。
錆びた装甲はその外観からは想像できないほど分厚く、シールドを向け損ねるようなヘマがなければ未識別機動体の銃弾さえ通さない。
付属の零力計は3本のレーダーに助けられて順調に数値を上げていく。零力波発動域まではしばらくかかりそうでも、システムそのものに問題はない。
火器だけは外観通りの整備不良そのものでも、その他は意外なほどマトモだ。
最初に想像したほどヤバい状況じゃない。至る結論はそれ一つ。俺が油断するか、向こうに隠し玉のない限り墜ちはしない。
なら必要なのは余計な疲労の原因を作らないことだ。全周型モニタの中、前のめりになっていた体勢を崩してシートへ体重を預ける。
奇妙に慣れた感触。初めて座るはずの見知らぬ機体の中で出会うそれに思わず肩越しの視線を向けたところで、棺内のホルダーに収めていた端末が鳴った。
次の捕捉までは、これまでからすればいくらか時間があるはずだ。
だがもし、こっちにかまけすぎれば? さっきの通信の奴がそれを狙っているとしたら?
逡巡に答えたのは声ではなく制御識が見せる数秒後の自分。
絶対に嘘をつかないそれに従う。ハンズフリー通話をオン。回線を開く。
「アザミネ! よかったやっと通じた!!」
「ラトーだな? わかってたぜ、今棺内なんで4分以内で頼むわ」
戦闘中の話はハウリングじみて二重三重に聞こえて好きじゃない。
だけどこんな状況の中で、誰より聞き慣れたその声が聞こえてくれば話は別だ。
隣り合うカプセルで眠り起きるたびに顔を合わせ、腐れ縁じみて喜色満面から俺を散々叱り飛ばすところまでいろんな表情を見てきた相手となれば。
「棺っ……、お前、グレムリンに!?」
「おう。誰のだか知らねーけど貰っちまったよ、緊急徴発で通るだろ多分」
端末の向こうで絶句する気配。何度も見たその表情が脳裏にありありと浮かぶ。そりゃ、俺のした無茶の中でもこいつは最大級だろう。
だが向こうがその続きを語るより前に、俺の方がその続きへ違和感を覚える。
「あ?」
「そのグレムリン、動くのか!?」
「だから乗ってんだっての」
「そうか…………」
答えた後に、長い長い溜息。
動作を聞いた時の剣幕とは打って変わって、その吐息に宿る深い落胆。
「こっちは今、『アネモネ』の本拠ガレージ。こっちに残ってるグレムリンは全部停止してる。何度やっても仮設エンジンすら稼働しない。
僕のトリップラーレも、……アザミネのサーシオネも」
挙がる愛機の名前も、微かに聞こえる歯噛みの音も分かっていた。その理由も痛いほどに。
養成機関のテイマーが、今この時に肝心のグレムリンにそっぽ向かれちゃ誰だってそうなるだろう。
オートパイロットじみて意志が見えない見慣れた機体、だがそれより遥かに上を行く戦闘能力。
あの未識別機動体に、グレムリンさえあれば敵わないなんてことはないのに。
……あれ?
「……でも、お前の乗ってるそれは動くんだな。全部のグレムリンがダメって訳じゃないのが分かっただけでも良かった。
他にまだ動くのがあるかもしれないし、何か条件が……」
その言葉も、ほとんど耳に入っていなかった。
俺はどこでこのことを聞いたんだった?
あの、自分でもどことも知れない場所で目覚めてから。あるいはその前に?
「……ごめん、戦闘中だったね。
じゃ、切るよ。『アネモネ』で待ってる」
「……お、おう」
生返事に現れたその動揺を、多分あいつなら端末越しでも分かったろう。
それを裏付けるように、
「着いたら話、聞かせてね。
そのグレムリンも見てみたいし」
そう念を押して、通話は切れた。
それを認識した瞬間に改めて視線を走らせたモニタには、まだ捕捉敵影のサインはない。
零力計は普通の交戦なら明らかに達さない数値を示してこそいるが、零力破の水準にはまだ遠い。
何の混線かそんな時にラジオが鳴り出すものだから、無駄にビビった。
だが聞こえてくるそのアナウンサーの声にも聞き覚えはない。俺はラジオでこの状況のことを聞いたんじゃない。
だがそれ以上のヒントもない。
その思考を打ち切ったのは思念捕捉を示すアラームだ。向けられた銃口に宿る攻撃意志、未識別機動体にも一丁前に存在するらしいそれをレーダーが捉えた証。
予測射線へ向けてシールドを構える動きは初発に比べればずっと滑らかだ。鋼を伝わる衝撃は棺までもをびりびりと揺らして、しかし計器は一切の損傷を伝えない。
戦闘の終わりはまだ遠い。
気づいた瞬間は血の気が引き配した指が震えて感覚がなくなるほどだったそれらも、ひとまず生き延びられないほどの障害じゃあないらしい。
錆びた装甲はその外観からは想像できないほど分厚く、シールドを向け損ねるようなヘマがなければ未識別機動体の銃弾さえ通さない。
付属の零力計は3本のレーダーに助けられて順調に数値を上げていく。零力波発動域まではしばらくかかりそうでも、システムそのものに問題はない。
火器だけは外観通りの整備不良そのものでも、その他は意外なほどマトモだ。
最初に想像したほどヤバい状況じゃない。至る結論はそれ一つ。俺が油断するか、向こうに隠し玉のない限り墜ちはしない。
なら必要なのは余計な疲労の原因を作らないことだ。全周型モニタの中、前のめりになっていた体勢を崩してシートへ体重を預ける。
奇妙に慣れた感触。初めて座るはずの見知らぬ機体の中で出会うそれに思わず肩越しの視線を向けたところで、棺内のホルダーに収めていた端末が鳴った。
次の捕捉までは、これまでからすればいくらか時間があるはずだ。
だがもし、こっちにかまけすぎれば? さっきの通信の奴がそれを狙っているとしたら?
逡巡に答えたのは声ではなく制御識が見せる数秒後の自分。
絶対に嘘をつかないそれに従う。ハンズフリー通話をオン。回線を開く。
「アザミネ! よかったやっと通じた!!」
「ラトーだな? わかってたぜ、今棺内なんで4分以内で頼むわ」
戦闘中の話はハウリングじみて二重三重に聞こえて好きじゃない。
だけどこんな状況の中で、誰より聞き慣れたその声が聞こえてくれば話は別だ。
隣り合うカプセルで眠り起きるたびに顔を合わせ、腐れ縁じみて喜色満面から俺を散々叱り飛ばすところまでいろんな表情を見てきた相手となれば。
「棺っ……、お前、グレムリンに!?」
「おう。誰のだか知らねーけど貰っちまったよ、緊急徴発で通るだろ多分」
端末の向こうで絶句する気配。何度も見たその表情が脳裏にありありと浮かぶ。そりゃ、俺のした無茶の中でもこいつは最大級だろう。
だが向こうがその続きを語るより前に、俺の方がその続きへ違和感を覚える。
「あ?」
「そのグレムリン、動くのか!?」
「だから乗ってんだっての」
「そうか…………」
答えた後に、長い長い溜息。
動作を聞いた時の剣幕とは打って変わって、その吐息に宿る深い落胆。
「こっちは今、『アネモネ』の本拠ガレージ。こっちに残ってるグレムリンは全部停止してる。何度やっても仮設エンジンすら稼働しない。
僕のトリップラーレも、……アザミネのサーシオネも」
挙がる愛機の名前も、微かに聞こえる歯噛みの音も分かっていた。その理由も痛いほどに。
養成機関のテイマーが、今この時に肝心のグレムリンにそっぽ向かれちゃ誰だってそうなるだろう。
オートパイロットじみて意志が見えない見慣れた機体、だがそれより遥かに上を行く戦闘能力。
あの未識別機動体に、グレムリンさえあれば敵わないなんてことはないのに。
……あれ?
「……でも、お前の乗ってるそれは動くんだな。全部のグレムリンがダメって訳じゃないのが分かっただけでも良かった。
他にまだ動くのがあるかもしれないし、何か条件が……」
その言葉も、ほとんど耳に入っていなかった。
俺はどこでこのことを聞いたんだった?
あの、自分でもどことも知れない場所で目覚めてから。あるいはその前に?
「……ごめん、戦闘中だったね。
じゃ、切るよ。『アネモネ』で待ってる」
「……お、おう」
生返事に現れたその動揺を、多分あいつなら端末越しでも分かったろう。
それを裏付けるように、
「着いたら話、聞かせてね。
そのグレムリンも見てみたいし」
そう念を押して、通話は切れた。
それを認識した瞬間に改めて視線を走らせたモニタには、まだ捕捉敵影のサインはない。
零力計は普通の交戦なら明らかに達さない数値を示してこそいるが、零力破の水準にはまだ遠い。
本日のニュースです
昨日、星の海、真紅連理旗艦での連理会議が開かれました
真紅連理は戦力を結集し、系列企業や協力する傭兵に
連帯と結束を呼び掛けています
真紅連理はコモン・テイル・ストアで赤メシ無料配布を行い、人々を鼓舞しています
戦う人々に祝福を……我々は、生き続けるのです
何の混線かそんな時にラジオが鳴り出すものだから、無駄にビビった。
だが聞こえてくるそのアナウンサーの声にも聞き覚えはない。俺はラジオでこの状況のことを聞いたんじゃない。
本日のニュースです
南の島では今、謎の珍獣「カビャプ」が多数目撃されています
人々の気配が消えた町などを横切る姿が確認されています
ピンク色でもふもふしていてかわいいですね。血を吸うそうです
戦火の世にも、人々の連環を。我々はまだ、戦えます
だがそれ以上のヒントもない。
その思考を打ち切ったのは思念捕捉を示すアラームだ。向けられた銃口に宿る攻撃意志、未識別機動体にも一丁前に存在するらしいそれをレーダーが捉えた証。
予測射線へ向けてシールドを構える動きは初発に比べればずっと滑らかだ。鋼を伝わる衝撃は棺までもをびりびりと揺らして、しかし計器は一切の損傷を伝えない。
戦闘の終わりはまだ遠い。
開封コンテナにはもう何も残っていない……
開封コンテナにはもう何も残っていない……
開封コンテナにはもう何も残っていない……
アザミネはカーテンコールドケースを手に入れた!!(フラグメンツ-1)
アザミネは018-B-FIREARM《SNIPER-RIFLE》を手に入れた!!(フラグメンツ-1)
アザミネはラスト・アーマーを手に入れた!!(フラグメンツ-1)
アザミネは022-COFFIN《EXTRA-HEART》を手に入れた!!(フラグメンツ-1)
アザミネはカソワリ拡散火球砲を手に入れた!!(フラグメンツ-1)
アザミネはミサイルを手に入れた!!(フラグメンツ-1)
アザミネはミサイルを手に入れた!!(フラグメンツ-1)
◆アセンブル
◆僚機と合言葉
(c) 霧のひと